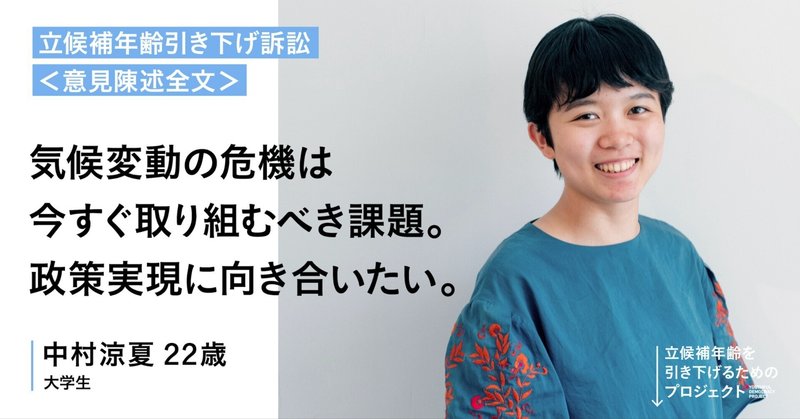
気候変動の危機は今すぐ取り組むべき課題。政策実現に向き合いたい。(中村涼夏)
日本が直面する少子高齢社会、中高年男性が多くを占める政治の場に、より長い未来を生きる若い世代の声はなかなか届いていません。そこで、2023年7月10日、東京地方裁判所に、10代・20代の原告6人が「立候補年齢引き下げ訴訟」を提訴しました。若い世代の声が届く社会に向けて、立候補年齢の引き下げを求めるものです。
提訴にあたっては、全員が、声をあげた理由を意見陳述書にまとめて提出しました。彼ら彼女らのメッセージをぜひご一読ください。
今回は、現在、大学生の中村涼夏さんの意見陳述全文です。
私は今回の立候補年齢引き下げ訴訟の原告の一人です。今回訴訟を提起するに至った経緯をお話しします。
私は三姉妹の長女として鹿児島県指宿市で生まれ、4歳頃まで鹿児島県内で暮らしてから名古屋市に引っ越し、大学から再び鹿児島にやってきました。いまは鹿児島大学で大学生をしています。
現在、私は自然保護関係のアクテイビストとして活動をしていますが、自然保護などに初めて関心を抱いたのは4歳ころだったと思います。
当時私は、種子島の海で毎日のように遊んでいました。海の色は雨が降ってすぐでもエメラルドグリーンに維持され、海の中には豊富な魚が泳いでいました。名古屋に引っ越して、種子島で囲まれていた自然は、決して当たり前のものではなく、とても恵まれた環境だったことを強く感じました。名古屋の海は種子島と同じ海とは思えず、黒く燭ってヘドロなどの臭いがしていました。海という単語としては同じでも、その実態は全く別物でした。この違いはどこから来るのだろうと考えるようになり、漠然とではありますが、次第に将来の夢として環境問題や自然問題に取り組む科学者やNGOの活動家になりたいと思うようになりました。
とはいえ、中学校まではその将来の目標に向けた具体的な活動をしていたということはなく、幼い頃から続けていた競技水泳に熱中する日々でした。自然との触れ合いは、お盆や正月に鹿児島の祖父母の家を訪れるときに限られる生活でした。
高校2年生の夏ころから、かねてから関心のあった、自然保護などの活動に少しずつ携わるようになりました。世界自然保護基金(WWF) などの専門のNGOが企画する自然環境ツアーに参加したり、さらには自分自身が九州の北部の水田めぐりツアーなどを企画するようになりました。フィールドワークのような活動もするようになり、現地を訪れて楽しく学ぶ生活でした。
そのような中高校2年の冬に、SNS経由でスウェーデンの環境活動家であるグレタ・トゥーンベリさんの講演を聞く機会を得ました。それから気候変動に関心を抱くようになったところで、グレタさんが立ち上げたFridays For Futureという活動に共感する人たちが日本で集まる機会がありました。名古屋のレンタルスペースで開かれていたので、参加してみたところ、気候変動危機は本当に差し迫った課題で、すぐに取り組まないと大変なことになると痛感しました。科学者になるまで勉強を続けていたら手遅れになってしまうと感じました。
そこですぐに気候変動に取り組む活動をしようと考え、友人数名で2020年1月にFridays For Futureの日本支部を設立しました。その後、メンバーも20人くらいとなり活動規模も大きくなってきたところで、新型コロナ禍が始まってしまいました。そこからはもっぱらオンラインでの活動となりましたが、提言書や声明を発出したり、グレタさんから送っていただいたビデオメッセージに翻訳をつけて動画サイトで公開するなどしていました。メンバーの多くは高校生から大学生で、海外系の高校やインターナショナルスクールに所属している人が多数です。
2020年4月に鹿児島大学に入学し、鹿児島に引っ越しました。環境への取り組みに専念したいと思っていたところで、国公立で水産系の学部があるということで鹿児島大学を選択しました。
大学進学後は、オンライン上でオーガナイザーという裏方の役割を担うようになりました。その後、当時の環境大臣だった小泉進次郎さんとの意見交換会を企画したことがきっかけで、少しずつ政治とのつながりを持つようになりました。2021年3月ころには、SNS上で「気候危機を止めるために学校を休みます」というプロジェクトが起こり、私もそれに賛同して4月の間は毎週金曜日に大学を休むようになりました。それから少しして、気候変動について社会で議論される機会が増えるようになってきたころ、地方に住んでいて女性で気侯変動に取り組んでいる、ということで推薦を受け、参考人として国会で意見を述べる機会もいただきました。
それ以降、少しずつ裏方にとどまらず人前で発信する役割も担うようになりました。ここ数年で気候変動問題が社会に浸透し、議諭がされるようになってきたと感じますが、他方で気候変動危機を具体的に解決できるような政策実現までには至っておらず、歯痒い思いでいます。
気候危機に関する活動は大変なものなので、数ヶ月以上継続できる人はそれほど多くありません。特に、東京や名古屋といった大都市以外での活動は、孤立しがちで続けにくいという難しさがあります。
2021年の衆議院議員選挙の際には、メンバーも少なくなっており、なんとか盛り上げ直そうとカンフル剤的に「選挙で聞きたい気候危機」というプロジェクトを立ち上げました。これは候補者に気候変動危機についての見解や政策を尋ねるという全国規模のプロジェクトで、70名以上が参加してくれました。同じ頃、テレビ局が自分を含め数名のメンバーに密着するドキュメンタリーを制作してくれており、テレビカメラが同行するということで多くの政治家が誠実に応えてくれました。プロジェクトとして成功を収めたので、次の参議院選挙でも同じ企画を行いました。2023年9月からは、今年4月の統一地方選挙で当選した議員を対象に、「選挙の後も聞きたい気候危機」というプロジェクトを行う予定です。
気候危機の活動をする中で、政治家とのつながりも増えていきました。最初に関わることとなったのは、Fridays For Futureの日本支部を設立した高校3年生のころです。当時は政治について本当に全く分からず、どのような過程でもいいから気候危機について政策に取り込んでほしいと考えていましたが、複雑な段取りを踏まないと入り口にも入れないと知り、とても大変なことだと感じました。
その後、当時の環境大臣だった小泉進次郎さんとのオンラインでの意見交換会などを経て、国会で参考人質疑に参加しましたが、参考人質疑を終えたタイミングで小泉さんと会うことができました。私たちとしては、この間ずっと、2030年までにどれだけの温室効果ガスを下げないといけないか、60%以上にしないと日本の責任を果たしたことにはならないなどと提言をしたり、意見交換会で小泉さんにも直接意見を伝えてきましたが、最終的にその国会では46%という数字が小泉さんから提示されていました。私は参考人質疑を終えて偶然国会で直接会った際に、あの数字ではありえないと強く訴えましたが、小泉さんからは「僕なりに頑張った」との答えが返ってきました。大きな政治の動きや流れがある中で、小泉さん一人の力ではやはり足りないんだ、もっと若い政治家を増やさないといけないと感じました。
大学2年のころには、鹿児島から立候補した自民党の宮路拓馬さんと直接会って話をする機会もありました。比較的若い政治家とされていましたが、気候変動のことはあまり関心がなさそうでした。他方で、同じ選挙区内の対立候補の川内博史さんは若者向けの政策にはほとんど力を入れていないと感じました。結局、どちらが受かろうとも私たちの声は政治の世界には届かない、私たちの危機感は全く通じないと感じました。段々と政治について憤りと悲しさを感じるようになりました。
COP27などの国際会議に参加する機会も何度かありましたが、自分と同じ年代かそれよりも若い人たちが、議員として自己紹介をしている場面に何度も出会いました。他方で、国政であれ地方議会であれ日本の議員が気候変動に関する国際会議に出てくることはほとんどありません。
2022年6月にスウェーデンの国際会議、11月にはエジプトで行われたCOP27、2023年には韓国で緑の党の会議に参加しました。国際会議には当然ですが様々な国の人たちと会うことができます。様々な話をする中で、日本との違いを痛感することがしばしばありました。他国には、自分たちの世代の声を代弁してくれる若い議員が大勢いると感じました。以前は、若者の声を聞いてくれる大人を探せば良いと考えていましたが、数年活動をする中で、与野党問わず、国政・地方政治問わず、自分たちの世代の声を聞いてくれるような政治家は全くいないことを理解しました。
その根本の原因は被選挙権年齢にあるのではないか、被選挙権年齢が25歳や30歳とされている間は、自分たちの世代の代弁者・代表者は生まれないのではないかと感じるようになりました。自分がその代弁者・代表者になろうにも、被選挙権年齢の壁があり、立候補することすらできない現状がありました。そのような気持ちが生まれていたところに、この訴訟の原告の一人で、以前からの友人だった能條さんからこの訴訟のことを聞いて、自分も原告になることを決意しました。
2023年3月30日、自分の住民票がある鹿児島県の鹿児島県議選の選挙管理委員会に立候補届を提出しましたが、年齢要件を理由として受理してもらえませんでした。事前に弁護士などから流れを聞いていたので、当然受理されないとわかっていましたが、やはり自分たちは政治の世界から阻害されているんだなという気持ちが沸き起こりました。
翌日から街中を走る選挙カーを見かけるたびに、自分たちはあのような選挙活動すらできないのか、どの政党も自分たちの声を聞いてすらくれないのに、選挙の間に自分たちで自分たちの考えを訴えることすらできないのかと感じました。参政党などは、気候変動は出任せだという政策を掲げており、それを様々な媒体で選挙期間中に発信していました。メディアは選挙活動の一環ということで、そのままの意見を報道します。他方でその他の政党はどこも気候変動について何も述べませんから、参政党の意見だけがメディアに載ることになっていました。自分たちが選挙に出られたら自分たちの政策として気候変動の問題を発信することができるのに、自分たちはそれすらもできない、という状況でした。立候補できるかどうかというのは、実は声を届けるという点でもすごく大きなことだと感じました。
将来的には自分の生まれた指宿市で地方議員となることなどを考えています。ここ数年の選挙で、尊敬できる女性の政治家が増えていると感じます。
ここ最近の鹿児島では、馬毛島の自衛隊基地の問題や種子島の環境問題など、ワンイシューを重要政策として掲げて地方議員として当選する政治家も出てきている。一つの問題であっても、それを重視する人たちの代弁者・代表者として活動できる人が政治の世界にいることの重要性をひしひしと感じている。例えば私の関心事である気候変動であれば、市民電力の導入などを通じて地域主導で問題に取り組むこともできます。地域から変えていく、という気持ちで気候変動に取り組んでいきたいと考えています。
これまでは年齢要件のために政治家には絶対になれないと思いこんでいて、自分のキャリアの選択肢にすら上がっていませんでしたが、実はその年齢規定は違憲で、自分も選挙に出られるとなれば、政治家というキャリアが現実的な選択肢になってきます。他の議員や首長が自分と同じような問題意識で活動しているのをみるにつけ、早く一緒に活動したいと思うようになりました。
以上
「立候補年齢引き下げ訴訟」サポーターになりませんか!
教育・雇用・福祉・メンタルヘルス・環境問題・気候変動・軍縮・ジェンダー・LGBTQ・多様性。長期的な視点を持った10代・20代の声が届く政治は、日本をもっと持続可能で、生きやすい社会にします。
「立候補年齢引き下げ訴訟」について、詳しく知りたい方や応援くださる方はぜひ下記リンクページへ。クラウドファンディングも実施中です。みなさまの応援をお待ちしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
