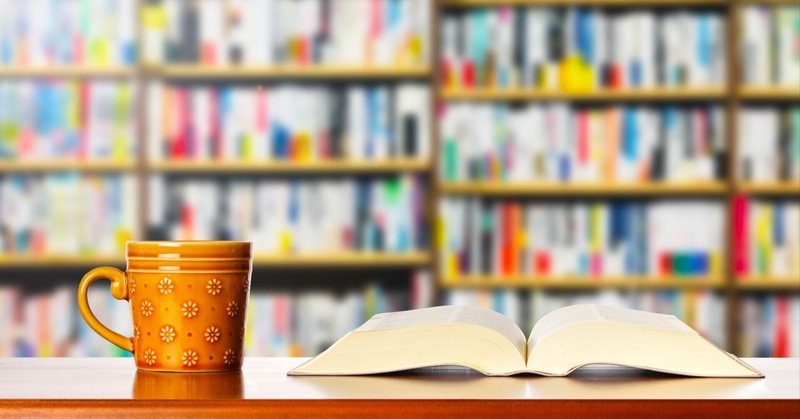
とある本紹介式読書会の記録~2024年1月編~
はじめに
1月21日(日)の朝、学生時代からの知り合いと行っている毎月恒例のオンライン読書会に参加した。
この読書会は月によって、メンバーがそれぞれ好きな本を紹介する形式になったり、決められた課題本を読んでおき感想や考察を話し合う形式になったりする。今回の読書会は前者の本紹介式であった。
読書会のメンバーは、現在のところ6人で実質的に固定されている。この日は1人体調不良で参加できなくなったので、集まったメンバーは5人であった。さらに、そのうちの1人は新幹線に乗っていて声を発することができず、1人は多忙を極めて本を読めていなかったので、実際に本を紹介したメンバーは3人のみであった。
紹介された本は3冊。僕の記憶に間違いがなければ、読書会史上最少記録である。もっとも、紹介の中身はいずれも興味深く、アフタートークも盛り上がっていたので、物足りないという感じは全くなかった。
では、その3冊の本を順番に見ていこう。
——と言いたいところだが、今回はその前にどうしても書いておかなければならないことがある。この日、読書会史上初となるハプニングが発生したのだ。
読書会が始まらない!
1月21日の朝、僕は眠い目をこすりながら、前日の貴船神社詣での記録をnoteに上げる準備をしていた。下書きした文章を貼り付け、一部文言を修正する。ふと時計を見ると、読書会の開始時刻が迫っている。僕は写真のセレクトを諦めてnoteを下書き保存し、Zoomを立ち上げた。そして、前日に読書会の代表・竜王さんから送られてきたミーティングIDとパスワードを打ち込んだ。
待機画面がポップアップされた。読書会ではセキュリティ対策のため、ミーティングルームに待機室を設けているので、待機画面が出ること自体は何ら不思議ではない。
ただ、その待機時間がやたらと長かった。いつもならものの数秒で主催者から入室を許可されるのだが、この日に限り「しばらくお待ちください」の表示がいつまで経っても消えない。そうこうするうち、読書会の開始時刻が過ぎた。
「操作を誤ったのだろうか」そう思って一旦待機画面を閉じ、もう一度IDとパスワードを入力した。しかし、結果は同じだった。待機画面が切り替わらないまま、読書会開始時刻から5分が経過した。
僕はたまりかねて、読書会のライングループを開いた。
〈ミーティングが始まらないのですが、いまどういう状況ですか?〉
程なくメンバーから返事があった。
〈同じく待機中です!〉
〈同じ状況です〉
待機画面から進めずにいるのは僕だけではなかったことに安堵する。同時に、そもそも竜王さんがミーティングを開始していないらしいということが見えてきた。
さらにメンバーからの返事が続く。
〈朝から体調を崩しているためお休みさせていただきます。竜王さんにラインしましたが既読がつきません〉
〈1時間前に遅れて参加しますと竜王さんに伝えたのですが、既読がついていません〉
「なんてこった!」と思った。竜王さんはミーティングを始めていないばかりか、連絡がつかなくなっているのである。
一体どうしたというのだろう。昨夜IDやパスワードと同時に、「明日はよろしくお願いします!」と送ってきていたのだから、読書会を忘れているはずはない。まさか、竜王さんの身に何か良くないことでも起きたのか!?
僕がそうやって物事を大袈裟かつ良くない方向へ考えていると、読書会きっての多読派であるvan_kさんからメッセージが来た。
〈ひじきさん、リンク発行できます?〉
どうやら、別途ミーティングルームを立ち上げて読書会を始めようということらしい。読書会用のミーティングの設定は、今は竜王さんが行っているが、以前は僕が担当していた。Zoomの有料会員は継続していたので、タイムフリーでミーティングを開くことは可能だった。
僕は数ヶ月ぶりにミーティングを予約し、IDとパスワードを発行してラインに通知した。同時に、自分で作ったミーティングルームを立ち上げた。
間もなく、読書会最強のブロガーであるしゅろさんが入ってきた。が、映し出された画面は、どう見ても新幹線の車内であった。後からわかったことだが、しゅろさんは前日姫路へ旅行に行っており、東京へ帰る途中だった。当然ながら喋ることはできない。
参加者が2人になったのに声を出せない状況に困惑していると、van_kさんが入ってきた。van_kさんは自室からの参加だった。僕は漸く喋れるようになった。が——
「2人で本紹介し合ってもしょうがなくないですか?」
「たしかに」
かくして、読書会用に開けたミーティングルームは、僕とvan_kさんの雑談室と化したのだった。
まだまだ読書会は始まらない
「竜王さんはどうしたんですかね?」というところから雑談は始まった。そのうち、しゅろさんがチャットにコメントを投げてくださり、それに誘導される形で、僕らはしゅろさんのブログを覘いた。トップに姫路観光の話が出てきたので、話題はそこから姫路の観光資源のことや、旅先でのお土産の選び方などに移っていった。
そうやって、読書会の本来の開始予定時刻から50分が過ぎた頃、待機室に竜王さんが現れた。僕はすぐさま入室を許可した。そして、画面に竜王さんが現れる頃合いを見計らって、「お話聞きたいですなあ」とわざとらしく言った。
「大変申し訳ありませんでした」竜王さんは言った。「単純に寝坊してしまいました」
僕とvan_kさんは呆気に取られて笑った。
「それだけですか?」
「はい」
「昨日飲み会だったとかでもなく」
「全然ないです」
それから話を聞いたところによると、前の晩に直前連絡を発信したにもかかわらず、竜王さんは読書会の存在をすっかり忘れ、二度寝三度寝を繰り返し、今しがた漸く目を覚ましたのだという。とにかく気が抜けてしまったらしい。余談であるが、竜王さんの休日の起床時間が遅くなったのは、ごく最近のことである。学生時代の頃から9時寝3時起のような生活をしていて、周りから「おじいちゃんか!」とツッコまれていた人とは、とても思えぬ変貌ぶりだ。
何はともあれ、たっぷり睡眠を取り健康体になった竜王さんを迎えたところで、喋れるメンバーが3人になった。最年少メンバーの茶猫星さんから1時間遅れで参加するという連絡が来ていたので、僕らは一旦休憩を取ってから読書会を始めることにした。
休憩が終わった時、茶猫星さんはまだ現れていなかった。竜王さんが「メッセージ送るね」と言い、ラインを更新した。
〈始まってます~〉
「竜王さんなんですかこれ!」僕は直ちにツッコんだ。「誰のせいで今まで始まらなかったと思ってるんですか!?」
「ほんとですよ!」van_kさんが笑いながら加勢してくれた。
「いや、ホント申し訳ない」竜王さんはもう一度頭を下げた。
そこへ茶猫星さんが現れた。そして、「このところずっと忙しくて、本は紹介できないんですけど」と言いながら、聞く姿勢に入っていった。
かくして、予定から1時間10分遅れで、読書会はスタートした。
◇
というわけで、何とか読書会が始まりましたので、ここからはいつも通り会の中で紹介された本について見ていきたいと思います。読書会が予定より大幅に遅れてしまったために、この振り返りも本編が始まるまでに時間がかかってしまいました。「そんなもの追体験させんでええわい」とお怒りの皆さまには、謹んでお詫び申し上げます。
紹介本①『体はゆく』(伊藤亜紗)
ワタクシ・ひじきの紹介本。人間の身体の不思議さを様々な事例からみている研究者・伊藤亜紗さんによる、〈何かが「できる」ようになるとはどういうことか〉をテーマにした一冊です。
この本の面白い点の1つは、「できる」とはどういうことかを探るに当たって、理工学系の研究者の調査や実践を研究対象にしている点です。「こうすればうまくいく」という思い込みを超えていくためのピアノの練習ツールの開発、桑田真澄元投手のピッチングフォームの解析、新たな神経経路を構築するための「ないしっぽをふる」という実験——最新の技術を使って「できる」の仕組みを解明する。新たなテクノロジーを開発して、人々の「できる」をサポートする。そういった、身体とテクノロジーの出会う場面を取り上げて、「できる」の不思議に迫っているのです。
それを通して見えてくる「できる」の諸相は、興味深いものばかりです。人は自分でも意識しないうちに体の動かし方を調整して、最適な動作を実現しているということ。自分の思うベストな状態を作り上げるより、周りの環境に合わせて体の動きを調整できる「ゆらぎ」を持つ方が、パフォーマンスを向上できるということ。VRやスローモーション映像を活用した〈偽の実践〉を通じてでも、現実にそれをやるためのノウハウを獲得できること——
そういった話に触れていると、「できる」はどこまで自分の能力なのか、という疑問が湧いてきます。無意識のうちにやってしまっていることも自分の実力のうちなのか。ケースバイケースで上手くできたりできなかったりすることがある時、それはどこまでが自分の実力によるもので、どこからが環境によるものなのか。テクノロジーの力を使って何かを行う時、どこまでが自分の力だと言えるのか。これらの問いにパッと答えるのは容易なことではないでしょう。
紹介後のアフタートークでも話題になりましたが、この本のポイントは、何かが「できる」理由を個人の能力に還元し、できる/できないを優劣に結び付けるような見方を相対化することにあったのではないかと思います。自分の体の動きを意識的にコントロールすればよいというほど、「できる」は単純ではありません。無意識下での調整、環境やテクノロジーといった他者の存在を通じて、「できる」は初めて可能になる。その複雑さと面白さを見せることで、何かができたりできなかったりする一人ひとりの体の違いを楽しみ理解し合うことを、この本は目指しているのかもしれません。
紹介本②『幸福論』(ラッセル)
読書会きっての多読派・van_kさんからの紹介本。三大幸福論の1つと言われる、20世紀の哲学者ラッセルの『幸福論』です。
この本の原題は”The Conquest of Happiness”、直訳すると「幸福の征服」です。一体なぜ「征服」という語が入っているのか。van_kさんによれば、それはこの本の根底に〈幸福は思考や行動のプロセスによって実現できるものだ〉という考え方があるからだそうです。手短に言ってしまえば、幸福になるためのテクニックを示すことが、この本の目的と言えるでしょう。
ただし、ラッセルはこの本の中で、〈自分は一般論を語っているだけであり、最終的に幸福とは何であるかはそれぞれの判断次第である〉ということも語っているようです。「これさえ実践すれば、あなたもゼッタイ幸福になれる!」という自己啓発本的な書き方ではなく、読者に考える余地を残しているところに、ラッセルの学者としての矜持を感じたと、van_kさんは話していました。
本の内容をもう少し詳しくみていきましょう。ラッセルはまず不幸が生じる原因を分析していきます。挙げられているのは、過度の競争・退屈・終始興奮している状態・自分と他者の比較・嫉妬などです。それらを踏まえたうえで、次に幸福になるためのコツが述べられます。一番のポイントは、〈自分の興味・関心を外の世界に向けていくこと〉です。さらに、〈1つのことに興味を絞らず、幅広く関心を持つこと〉〈偏ったものの見方に陥ることなく、バランスを保つこと〉なども、幸福になるためのポイントとして挙がっているそうです。
van_kさんは本を読み終えて、次のように感じたと言います——不幸の形は昔も今も変わらない。一方で、幸福になるための処方箋は時代性を帯びているように思う。例えば、ラッセルは上で述べたのとは異なる幸福の在り方として、科学の発展や国家の防衛などの大きな目的のために、最大限の努力をしたり自分の全てを捧げたりすることを挙げている。だが、行き過ぎた成果主義のために常に全力を出すことを求められている現代人は、幸福であるどころか、むしろ苦しんでいる。ラッセル自身が述べているように、この本に書かれたことを土台に自分たちで考えを深め、現代版にアップデートされた「幸福論」を作り上げていくことが、大事ではないだろうか——と。
この問いに触発されるように、アフタートークでは、幸福になるための条件や、幸福を考える際のポイントを巡って、かなり長い議論が交わされました。ここで詳細に立ち入るのはやめておきますが、そちらもかなり興味深い内容でした。この本を課題本にして読書会をやってみたいくらいだと、僕は思いました。
紹介本③『手間ひまをかける経営』(高田朝子)
読書会の代表を務める竜王さんからの紹介本。京都信用金庫を扱ったケーススタディの本で、組織論や経営論に関連する一冊です。
会社組織においては、業績を上げて組織を発展させていくために、従業員にノルマや目標を課し、達成状況を見ていくことがよくあります。京都信用金庫は、このノルマを撤廃し、目標についても従業員が自発的に設定する仕組みを設けたことで注目されていた会社だそうです。また、目先の利益を追求するのではなく、長期的な利益を考えた行動を大事にし、その一環としてお客さんとの信頼関係の構築に重きを置く会社でもあるようです。
竜王さんはこの本の中でも特に、ネットワークの構築に関する話が印象に残ったと言います。一般に、人や組織の間にネットワークを築くには、ある程度の時間をかけて何度もやり取りを交わすことが必要です。しかし、ほんの数回やり取りを重ねただけですっかり意気投合し、良好な関係性が生まれることがあるように、やり方次第ではもっとスムーズにネットワークを構築することもできるのではないかと、竜王さんは言います。
京都信用金庫では、ネットワーク構築のための方法として、ビジネスマッチング掲示板を導入しています。信用金庫で培った地域のネットワークを活用して、お客さん同士のニーズと解決策の提案をつなげる仕組みです。市街地に事業者が密集している京都だからこそできる方法という側面はありますが、注目すべき仕組みではないかと話していました。
この振り返りを書く段になって、僕は読書会当日の紹介内容もさることながら、この本のタイトルにある「手間ひまをかける」という言葉にグッときています。それは、普段仕事をしている中で、少なからぬ人が「手間ひまをかける」ことに忌避感を抱いていると感じているからです。
決められた仕事以上のことをしたところで、給料が増えるわけでもなく、ただしんどい思いをするだけ。だったらなるべくラクに仕事をこなしたい。そういう空気を感じることがしばしばあります。僕自身、ちょっと手に負えないと感じた仕事をすぐ上の人に任せようとする節があるので、あまり人のことは言えないのですが、そんな自分のことも含めて「本当にこれでいいのだろうか?」と思うことはしばしばあります。
もちろん、手間ひまをかけるのは簡単なことではありません。きっと、この本に書かれている組織運営や経営のツボは、「言ってることはもっともだけど、実際どうすればできるの?」と思うようなことばかりなのでしょう。その実践を支えているものは何なのか、というところまで見える本だとしたら面白いだろうなと、僕は思いました。
おわりに
以上、読書会で紹介された3冊の本を見てきました。今回は小説・エッセイ・マンガは登場せず、研究書やそれに似た本がズラリと並びました。「はじめに」でも触れたように、冊数こそ少ない回でしたが、それぞれの紹介が濃かったので、自然と振り返りも長くなってしまいました。何はともあれ、気になる本や話題との出会いがありましたら幸いです。
珍事の紹介もあり話がかなり長くなってしまったので、締めの言葉もほどほどに、そろそろ筆を置きたいと思います。読書会は来月も予定されていますので、できれば引き続き振り返りを書きたいと考えております。どうぞご期待ください。それでは。
(第209回 1月24日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
