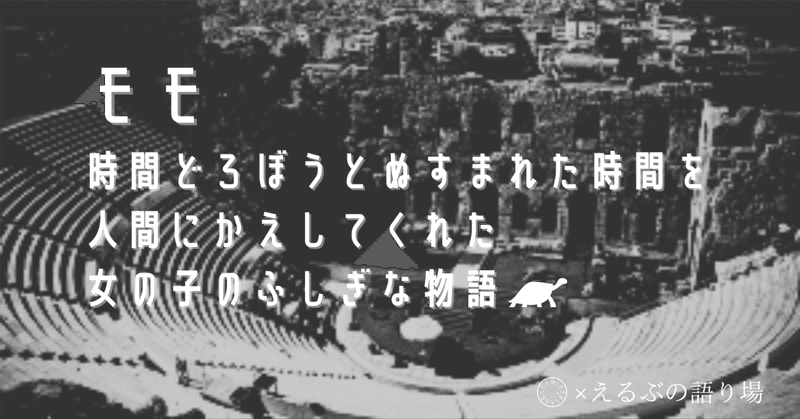
灰色の男たちの正体とは?/ミヒャエル・エンデ『モモ』【×えるぶの語り場】
シュ:灰色の男たちって結局どういう存在だと思う?
一般的には功利主義のメタファーであるとか言われているけれど。
ナチスに対する批判というのも多分に入っていると思うんだよね。
ソ:というのは?
シュ:灰色の男の言動を振り返ってみると分かるのだけど、例えば理髪師のフージーさんという人がいたじゃないですか。
ソ:いたね。物語の中で一番最初に灰色の男の毒牙にかかってしまった人だよね。
シュ:そうそう。灰色の男がフージーさんに対して時間を節約するために
「耳の聞こえない母親と話す時間」「歩けない恋人に会いに行く」
などの行動は控えるように伝えていたよね。
それってナチスの安楽死計画を暗に示しているのかなと思ったり…。
実際に彼は、第二次世界大戦中は召集令状を拒否して逃亡、反ナチス運動をしていたらしいよ。
ソ:それは大いにあると思うな。
一番はやっぱり功利主義に対するアンチテーゼであるとは思うけれど、シュベールが言う通りナチズムに対する批判だとか、色々なものに対する批判を感じるよね。
あと俺はこの灰色の男に対して、ソ連っぽさを感じたんだよね。
街の大人たちが時間を銀行に預けて働き始めた結果、街の建物のデザインが同じものになっていったという記載があったじゃないですか。
ああいうのは実際に戦後のソ連で起きていたことで、競争したり飾り立てる必要がないという社会主義の国だったので、
フルシチョフカなんていう同じデザインの団地が大量に建築されたりしたんだよね。
これの凄いところが、建物だけではなく、家具や日用品なんかも国営工場が作っているから全て同じなところなんだよ。
どの部屋に入っても同じものしか置いていない(笑)
当時のアネクドートで
酔っぱらった独り身のおじさんが自宅で眠りについた。
朝起きたら隣に若い女が寝ていた
というものがあるぐらいだったので(笑)
当時、エンデを取り巻いていたものに対する批判と皮肉を感じるな。

ソ:ホラさんが「人間は自分の時間をどうするのかは自分で決めなければならない」と言っていたじゃない。
要するにこれは自分の時間を銀行に預けることに対する批判だと思うのだけど、
現代人は時間の使い方を他者に依存している感じがしない?
例えば、8時間労働であったり、国が決めた祝日だったり...
そういったものに依存してきた人間がリタイアした後に自由な時間が手に入ったけれども、
何をすれば良いのかわからなくて思考停止になってしまう、みたいな話もある訳じゃないですか。
シュ:確かに。自分の体験としても急に自由な時間を与えられても何をすれば良いのか戸惑った経験はあるな。サルトルに同意する訳ではないけれど、自由というのは難しい問題だよね。
ソ:うん。
話が長くなってしまったけど、灰色の男というのは自分の時間、もっと言うと自由を放棄した現代人が自然と生み出してしまった悲しきモンスターなんだと思うな(笑)
シュ:なるほど。確かに本書にも灰色の男は人間が生み出したと書かれていたもんな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
