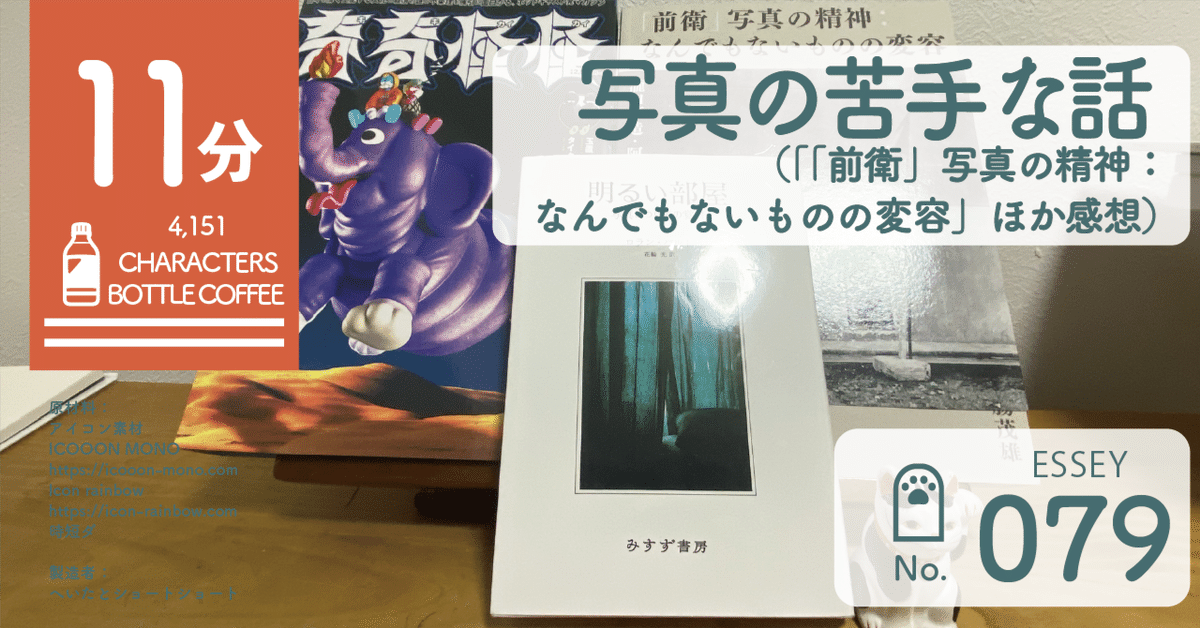
エッセイ 写真の苦手な話(「「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容」ほか感想)
写真を撮るのが下手である。苦手なのだ。
他人に対しては(特に悩みを吐露された場合には)「下手なんて言っちゃいけない」「知識と練習で上手くなるものだよ」などと返事をするが、本当に正直に、私は写真を撮るのが下手だ。
まず、たいてい画面が曲がっている。撮りたいものが中心から外れる。見返した時びっくりするほど被写体を小さくとってしまう。妙に暗かったり明るかったりする。たまに動画になっている。
おおむね、きちんと腹を据えてとっていないから、ということで片付けられそうな気がする。慌て者なのだ。
「売り上げをあげたい…」
最近、そうした悩みを打ち明けられる機会が何回かあり、一念発起することにした。
「SNSで写真や動画でプロモーションするといいですよ」
などと、やったこともないくせに言ってはいかん、と思ったのだ。
ここはひとつフォトジェニック(もう死語だろうか)な写真を撮って、SNSでバズってやる、くらいの勢い(弱気)になってやろう。
参考資料も用意した。日本政策金融公庫の「写真の撮り方ガイド 飲食店編」である。小規模事業者の売り上げ向上のために日本政策金融公庫さんが無料で公開している写真の撮り方ガイドである。
これは結構いいパンフレットで、「新規顧客獲得用」「単価を上げる用」「注文数を増やす用」とちゃんと目的別の撮り方のポイントを教えてくれる。
Xにポストするために、これで学んだ方法で朝食の写真を撮りながら「この朝食の注文数を増やすには…」と謎の思考がかけめぐる。その方向にうまくなったとして、どうする気なんだろう、私は。
「「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容」を読んだ。瀧口修造・阿部展也・大辻清司・牛腸茂雄ら1930年代からの「前衛写真」の系譜にある写真家の写真とその仕事を解説した本である。としたり顔で書いては見たものの、ちょっと怪しい。私は本当にこの手のことに明るくないからだ。
でも、写真をみて、「あ。知ってる」と思った。写真そのものを知っているわけではない。小学生や中学生の頃、美術の本に載っていた写真は確かこんな風だった。今思うと随分違う。今やどこを見てもおしゃれだったり、おいしそうだったり、かわいかったりするフルカラーの写真だ。子供の頃学校や図書館で見た写真は白黒で、ちょっと怖くて、何か訴えていそうな硬派のものだった。広告、というより、芸術だったのである。
写真それぞれに論を重ねるには私の知識はあまりに足りないのだけれど、本の終わりに「学生の頃」という写真家の畠山直哉のエッセイがあり、なんとなく自分が抱えている「写真は変わったなあ」という印象に近いことを言っている。
この「前衛」も、瀧口さんや大辻さんの時代ならば、生き生きとした比喩として成り立っていたのでしょうが、それがそうでもなくなってきた、というのがじつに僕が学生の頃だったんですよね、「新しさ」とか「進歩」とかに疑問符がつくようになったり、芸術資源を手近なものに求めるような傾向が強まったり、個人プレーが増えたり、そもそも革命を遂げた国や人々の雲行きが怪しくなってきている。そうなれば、「前衛」の比喩も空回りするしかなくなるでしょう。「モダン」という言葉と同じように。レトロな用いられ方をするようになったはずです。(後略)
「時代の思想や言葉が、表現者たちのものの見方考え方に影響を与えている」という風に続くのだけれど、素人目にはかなり現実そのものに近い(と、思ってしまう)写真にもそれがあるのは面白いと思う。私が大学生の頃、教授たちは、学生時代に全共闘などで自分たちの大学の先生たちと闘った経験のある人が結構いた。「お前たち授業に出て、まじめだな」としょっちゅう言われた。教授たちが積極的で私たちが消極的だったわけではなく、そういう時代だったんだろうなと思う。保守的なものと芸術と思想で戦う時代、というか。
そういえば、と、昔古本屋さんで買ったロラン・バルトの「明るい部屋 写真についての覚書」を引っ張り出してきた。買ったはいいものの、読んでいる途中で、写真に写っている人はみな死者である、みたいなことを言われ、「そういえばそうだな!」と納得して、それから怖くて読めなかった本だ。
「写真」は思い出を妨害し、すぐに反=思い出となる。ある日、何人かの友人が子供の頃の思い出を語ってくれた。彼らには思い出があったが、しかし私は自分の過去の写真を見たばかりだったので、もはや思い出を持たなかった。それらの写真に取り囲まれると、《思い出のようにやさしく、ミモザの香りが部屋を満たす》というリルケの詩に慰めを見出すことはもはや不可能だった。「写真」は部屋を《満たし》はしない。香りもなければ、音楽もなく、ただ、この世の常ならぬものを示すだけである。「写真」は暴力的である。それは暴力行為を写して見せるからではない。撮影の度に強引に画面を満たすからであり、そのなかでは何ものも身を拒むことができず、姿を変えることができないからである。(ときとして「写真」は心地よいと言われることがあるが、このことはその暴力性と矛盾しない。多くの人が砂糖は心地よいと言う。しかし私はと言えば、砂糖は暴力的であると思う)
これは結構わかる。写真と思い出は違うものだ。もしかしたら写真と思い出をより近づけるために技術を学んだり、編集をしたりするのかもしれない。より現代に近い写真論はどうだろう、と思っているとこんな文章を見つけた。
TaiTan なるほどねぇ。そうだ、今ってすごく不思議な時代というかさ、これは俺もあんまりまとまっていないからたどたどしくなるかもしれないけど、例えば結婚式の話とかも、「写真を撮る」という能動的なアクションも通過してないと、「自分がそこにいた」という記憶が体に付着しないんじゃないか、という意識がある。
周啓 それは飯も同じで、もう今は情報が多すぎて、飯をただ食うだけではそれを経たという実感が沸かない、ヤバい時代に突入してるんじゃないかと。
(中略)
TaiTan (笑)。高速とかでね。ネオンの電灯が秒で過ぎていくときの。でもこれはけっこう正しい気がするな。自分の体験というものを、スマホ越しにしか理解できなくなっている、満足できなくなっている、解釈できなくなっている、咀嚼できなくなっている。
これはラッパーのTaiTanとMONO NO AWARE、MIZのギターボーカル玉置周啓がSpotifyで配信しているpodcast「奇奇怪怪」の対談を収録した「奇奇怪怪」という本の「なぜ人は飯の写真なぞ撮影するのか 2022.07.21」からの抜書きである。1980年のロラン・バルトの「写真は思い出の邪魔をする」感覚から22年が経過して、今や「写真を撮らないと(思い出の)実感がわかない」ということが話の話題になるまで私たちと写真の関係性は変わってしまっているということになる。
少し、考えたのだけれど。
私の歴史認識では、「読み書き」は結構最近まで特殊技能だったと思う。(「代書屋」とかが成立していたように)だから、小説や評論なんかが「芸術」で、とても偉かった時代がある。
けれど、各種の技術革新などの環境の変化で、読んで、書いて、かつ公表するという行為がかなり手軽に、広範囲の人が行えるようになった。結果として、ポストしたり共感したりしてもらわないと、自分の生活の実感が湧かないような現象が起こるような人もいる。こういうの、今まで見てきた写真の系譜に似ていると思う。しかし、ちょっと何かが落ちている。多分、最初にとりあげた「前衛」のところ。「奇奇怪怪」をもう少し引用する。
TaiTan そうだよね。飯なん撮るよりも、「美味っ!」と発話する方が、実は体験としての純度は濃くなるんじゃないか、という。だから山に登って、みんな「空気が美味しいね」とか「水が美味しいね」とかわかったみたいに言うじゃん。それを言うことによって、実はその体験の濃さというものが確定されていく。
これはものすごく個人的な考えだけれど、私は「人間は幸せになるために生きている」と思う。金持ちになるためでも善行を積むためでも芸術を大成させるためでも子孫を残すためでもない。それらはみな個人が幸せになるための手段であって目的ではない。だから、何か書いたり写真を撮ったりというのは、単純に、その人が幸せになるためにやっているんだろうと思う。なぜそれをすると幸せになるのか、多分それで現実をより良く認識できるんじゃないだろうか。「これ、おいしい!」って発話して初めて「おいしいんだな」とちゃんと認識できる、というようなことである。写真を撮ることによって「自分はこういう食事を食べた」ということを認識できるのだ。
前衛の話に戻ると、この世に「おいしい」という意味にあたる言葉がないときに「おいしい」と言う表現を探す、というのが前衛とか芸術とかの行為なのではないかと思う。私たちは何か表現をしないと現実を実感できないくせに、0から何かを表現するのはほとんどの場合かなり困難(あるいは大変)で、なんやかんや毎日忙しいから、とりあえず既存の誰かの表現を借りてお茶を濁している。でも「表現」というのは時代によって変わる。正確には、人は生きて、変化していくから、「表現」側が人間についていけなくなって変化を強いられる。これは非常に都合が悪い。自分のふわふわした現実認識を何らかの「表現」で固定しないと現実の実感が得られないのに。私たちは小説を読み、動画を見て、SNSで写真を眺める。自分が使うぴったりの表現を探すためだ。
表現か……と、微妙に斜めに曲がった自分の朝食写真を眺める。写真の難しいところは、撮った時点で「現実をそのまま写した」ような気がする、という点だろう。たくさん撮ったらうまくなるかな。文章と同じか。
とりとめもない話になってしまった。やっぱり苦手だ、写真は。
エッセイ No.079
埼玉にある本屋さん「つまずく本屋ホォル」さんの「定期便」をとっています。毎月一冊、店の方が選んだ本が小さな紹介文つきで届くしくみです。どんな本が届くのかな、と楽しみにしながら、先月以前に届いた本の感想をこっそり言うエッセイです。
エッセイに登場した本
「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容 瀧口修造・阿部展也・大辻清司・牛腸茂雄
赤々舎(著/文)
美術評論家の瀧口修造(1903-79)、絵画と写真で活躍した阿部展也(1913-71)、写真家大辻清司(1923-2001)と牛腸茂雄(1946-83)の4人から日本写真史の「前衛」の系譜を紹介した巡回展の本です。「なんでもない写真」というのは、「現実とは何か」という問いでもあるんじゃないかあと思います。
明るい部屋 写真についての覚書
ロラン・バルト(著) 花輪光(訳) 1997年 みすず書房
批評家ロラン・バルトの写真論であると同時に、母への思いを書いたエッセイでもあります。写真と実感についてかなり昔から議論があるんだなあ、と思うと同時に、母親の写真があるからこそここに届いた評論なのかな、とも思います。
奇奇怪怪
TaiTan(著) 玉置周啓(著) 2023年 石原書房
「ラッパーのTaiTan(Dos Monos)、音楽家の玉置周啓(MONO NO AWARE / MIZ)の二人が、映画・音楽・小説・漫画などのコンテンツから、生活の中で遭遇する違和感とワンダーの裏に潜む経済の謎まで縦横無尽に語り尽くす、Spotify Podcastチャートで最高順位第1位を記録した、超人気ポッドキャスト番組『奇奇怪怪』。」と、リンク先で紹介があります。面白そうな番組だと思います。聞こうと思ってメモしてあります。疲れが内臓の次に耳や目にくるたちで、特に平日の夜は勢いのあるものが聞けないので(これは元気がよさそうだなあと思うんです)、まだ未視聴。
本は面白いです。ざっくばらんな掛け合いのようで、かなり掘り下げた文化論なんかもしていたりします。昔、こうしたサブカル系の本を読むと知らない話題ばかりで「大人はいろんなことを知っているな」と思ったものでした。今はかなりの話題についていけます。年取ったということなのかなあ。複雑な気持ち。
