
【うちの採用CX】超マーケティング思考!LAPRAS社の“採用広報戦略”を聞いてみました!
採用市場が売り手市場へと変化していることや、様々な採用手法が生まれ続けるなかで、昨今「Candidate Experience(=候補者体験)」の重要さが叫ばれています。
HeaRではCandidate Experience向上に取り組む企業インタビュー企画を連載中です。
第二弾は、LAPRAS株式会社PR責任者の伊藤さんに、採用が順調な秘訣を聞きました!
<プロフィール>
2012年に入社したソーシャルワイヤー株式会社にて、企業のPRサポートサービスを提供する@Press事業を副事業部長として統括。またセミナー・ イベントの開催や登壇、メディアへの記事寄稿を行う。 2015年には東京証券取引所マザーズ市場への新規株式公開を経験。2017年8月にLAPRAS株式会社に参画。 ビジネスサイドの幅広い業務に加えて広報業務を担当する。
1.記事だけが採用広報ではない?企業が発信する全ての情報が採用につながる
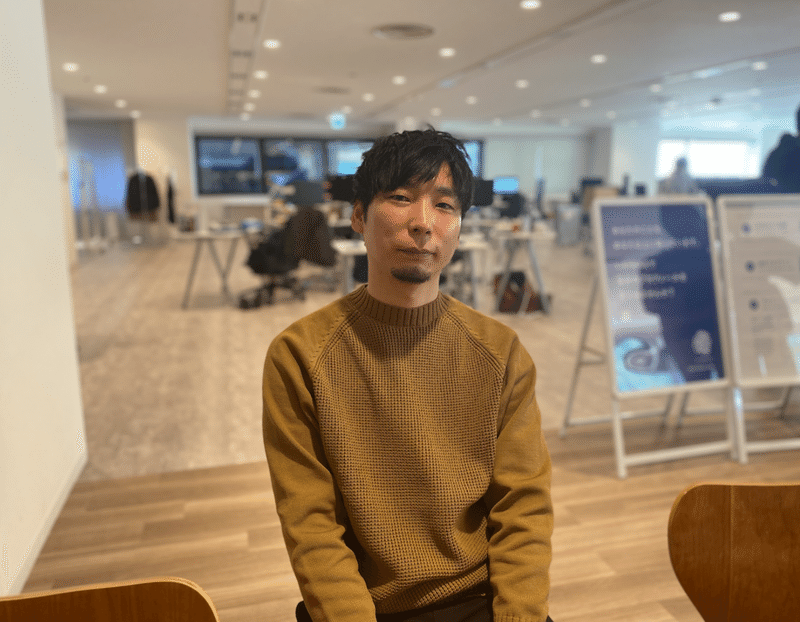
--採用広報に力を入れてないって本当ですか?そう言い切れる理由について教えてください!
そもそも“採用広報”の定義は難しいと感じています。
社外向けに新サービスの情報をリリースしたり、社員が自らSNSで発信することも、広い意味では採用活動につながっていることもあります。
例えば業績や新規事業に興味を持ち応募を検討する人もいるはずです。要するに、企業から発信する全てが採用に繋がっていきます。そのような観点から採用に繋がる広報活動は幅が広い採用に繋がる広報活動。そういった前提を踏まえて、現在LAPRASでは一般的に採用活動を目的としているオウンドメディアの運営や情報発信は行なっていません。
--なぜ採用広報をやっていないのですか?
前提として、採用広報はやった方が良いです。
しかし弊社は、リソースも限られていますし、やりたいことも色々ある中で、今は採用広報の部分はやっていないというよりも、優先順位を下げています。
ただ採用が計画通りにいっているので、“力を入れていない”というのが本音です。
そして、弊社では少数精鋭のチームを作りたいと思っています。今はメンバーが30人くらいですが、これからとにかく人を増やしていくといった採用計画はありません。必要な事業計画から逆算していき、プロフェッショナルな人材を確実に採用していこうとしています。
--今いるメンバーで円滑に業務を回しつつ、優秀な人だけを採用する方針なのですね。
もちろん今後事業計画を逆算し、もっと採用する必要があれば採用します。
会社の考え方としてジュニアクラスの人材をたくさん採用して、その分給料を下げて、馬車馬のごとく働かせて売り上げを作ることはしたくありません。それは効率が悪く、労働集約型になりがちだからです。だからこそ弊社は、少数精鋭のプロフェッショナル集団として事業を展開したいと思っています。
--企業は“個々の力を最大化にする“ことに、より着目しないといけませんね!
そうですね、一人当たりの売上高が頭打ちの組織になると、どこかでハレーションが起きてしまいます。例えば、ある企業で営業マン一人当たりの売上が月500万円とします。大体の企業が100人採用して、5億の売上を作ろうとする方針です。そのような考え方だと一人当たりの売上高や一人当たりにかけられる人件費も変わりません。だから給料は頭打ちになり、人がたくさんいるから昇進もしない。お金を稼ぎ続けるだけのロボットのようになっていくと、非人間的です。だから僕らもなるべく自動化する部分をはっきりさせ、生産性を上げていく必要性があります。
2.“ペルソナだけに刺しにいく”、LAPRASの魅力の打ち出し方は?

--LAPRASの魅力の打ち出し方を教えてださい!
魅力の打ち出し方や、採用広報において重要なことは、欲しいペルソナに刺さるような内容にすることだと考えています。弊社の現状として、スペシャリティがないポテンシャル層の方は基本的には採用しません。僕らとしては、”強い人と働ける”、優秀なメンバーが揃っている部分に魅力を感じる方と一緒に働きたいからです。「LAPRASって給料高いね」、「働きやすそうだから、とりあえず入りたいです」といった方は、来て頂いても簡単に入社はできないですし、もし入って頂いてもミスマッチになります。
例えば、Wantedlyフィードの記事作成においても、ルールがあります。「弊社は仲がいいですよ」とか「お花見に行きました」といった楽しいイベントをやっている内容の記事は出しません。「仲良しだし、楽しそう!」で応募されてもミスマッチになってしまうからです。もちろんそういうコンテンツで興味喚起することが悪いというわけではありません。会社のビジネスモデルや採用したいペルソナ像によってはその方が有効なケースも多くあります。
--結構戦略的ですね。多くの企業でイベントの記事とかを公開してしまいがちです…
そうですね、その都度状況に合わせて、打ち出し方を考えていかなければなりません。
たとえば、弊社セールスメンバーの中島は、統計の資格を保持し、プログラミングもできます。彼は「営業スキルや人間力で売るのではなく、データを活用し、どのように売れるのか再現性を持つ必要がある」と考え営業を行なっています。自分でシステムを組んだりR言語を使って多項分析し、何が課題になっているのかを割り出してるのです。そんな、彼の考えをアウトプットしたWantedlyの記事を見たときに「面白い!」、「この人みたいに自分も働きたい!」と思ってくださる方は優秀な方が多いと考えていますし、カルチャーの面でもLAPRASにマッチする方が多いとも考えています。
こちらの記事▽
--たしかに、「こんな優秀な営業マンがいるなら入りたい!」と思いそうですね!
そうですよね。これを見てセールスメンバーの魅力だけではなく、自社のカルチャーも伝わります。エンジニアであっても「LAPRASのセールスメンバーって面白いな!」と興味付けになるので、弊社にはピッタリな施策です。
また記事のPV数をKPIに置いていないことも一つの特徴です。なぜならPV数を増やしたり、たくさんの方に応募してもらいたいと思っていないからです。むしろPV数はそこまでいらないので、本当に僕らが出会いたい方だけに届けたいと思っています。
--PV数や応募数にKPIを設定するより、ペルソナに伝わる広報記事を発信できているかが重要ですよね。
当たり前のように言われていますが、採用にはマーケティング思考が必要です。マーケティングと同じファネルのように遷移をしていき最終的に採用になります。企業はWantedlyのフィードやブログ記事などの情報発信を行い、求職者がたまたまみつけて、「あ、〇〇って会社があるのね」、「面白そう、ちょっと話聞いてみようかな」といった段階を踏みます。そのため、まずは自社に関する情報発信がないとそもそも候補者にリーチできません。
しかし弊社はこの部分をあまり重視していません。なぜなら僕らは“LAPRAS SCOUT”というサービスを持っているので、そこでスカウトができます。その中で自社にマッチしそうな方にコンタクトをとり、その人に刺さるコンテンツを添えれば、「これ面白いな!この会社知らなかったけど、こんなことやってるのか!」とそのメールを通して思ってもらえます。情報発信による認知というプロセスを飛ばして、スカウトという候補者とのOne to Oneのコミュニケーションの中でいかに興味づけできるかという点を重視しています。
--採用広報記事のコモディティ化が起きているので、もう一度考え直す必要がありますね。
何を目的として採用広報をやるのかといった視点をはじめ、マーケティング観点がない情報発信による認知というプロセスを飛ばして、スカウトという候補者とのOne to Oneのコミュニケーションの中でいかに興味づけできるかという点を重視しています。焦ってとりあえず発信するのではなく、ロジカルなマーケティング視点を持つことが長期的に見ると効率的な採用に繋がるはずです。
3.採用は全社員で!当事者意識を上げるLAPRASの採用活動とは

--採用広報に関する記事は誰が企画して、発信されるのですか?
メンバーが自発的に行なっている場合もあります。
最近ではWEBアプリチームが、新たにエンジニアを採用したいと、自発的に記事を書きました。
弊社では、社員自らが採用の現場に立ち、スカウトメールを自分たちで送ります。その時に、「こんな情報があればもっと興味を持ってくれるかもしれない」と考えるので、記事の発信が自発的になってくるのかもしれません。
--現場のエンジニアさんもスカウトメールを送るんですね!
弊社では定期的にイベントスペースに全員集まって、採用要件をスクリーンに映しながら、スカウトメールを送付します。他には知り合いの中から、現在オープンしている採用要件にマッチしてる人はいないかを洗い出して、人事担当に繋ぐリファラル施策をやっています。
--社員を巻き込んで採用活動を展開することは簡単ではないと思いますが、ここまで協力的な理由はありますか?
まずは僕らが採用のサービス事業を展開しているからです。だからこそメンバー一人ひとりが採用の大切さを分かっています。ただ、社員を巻き込むには考え方や理念がちゃんと浸透しているかが重要です。LAPRASでは採用は“各部門がやるべき”だと考えています。
--それはどういう意味ですか?
各部門がやるべきとは、“各部門が主体的になって動くべき”のことです。採用はHRBPが主要で行いますが、採用要件は現場のメンバーから上がってきます。
こういう人で、こんなスキルを持っていて、大体どの辺りにいて、入社したらやる仕事とかはこういうものがあって…そして、この人が、LAPRASのどこに魅力を感じて入社するのかなど。詳細なところまで落とし込みます。現場のメンバーがどのような人物を採用したいのかを真剣に考えます。だから、メンバーの多くが当事者意識をしっかり持っているのです。
--ペルソナ設定が細かいですね…だいたいの企業が要件ばかり定義しがちですが、どこに魅力を感じて入社するかまで明確にすることが大事ですよね。
たとえば「うちの会社って別に魅力ないし、給料も低くて、残業多いけど残業代も出ないし、仕事も別に面白くないけど、優秀な人に入って欲しい!」といった企業は採用が難しいです。なぜなら求職者が入社する意味がないから。しかしそれをちゃんと現場のメンバーが自社の面白さや業務・仕事のやりがいを採用要件の中で明確化することで、候補者に伝えられます。
あとは詳細な採用要件があることで採用活動を手伝う僕らも、すごくやりやすいです。機械学習エンジニアと話をするときに、どのようなところが面白いのか僕が話せると興味付けになります。仮に僕が「なんかうち機械学習エンジニア募集してて、とりあえず色々話聞いてください」と言っても、全然刺さりません。「何が面白いの?」と求職者に思われてしまいます。
しかし、詳細に落とし込むことで、「LAPRASはSNSなどのオープンデータから取得した膨大なデータを構造化して、綺麗に構造化・統合された状態で機械学習エンジニアが分析できるようにしている。それを活用して生存時間解析や……」と詳細を話せます。そのような会話から実際の業務や魅力をイメージしてもらえるのです。
--すごいですね、ここまで落とし込んでいるならミスマッチとかなさそうです!
そうですね、また変わった施策として、弊社ではカルチャーマッチを確認するための面談をメンバー全員対候補者で行います。
面接後には、メンバーそれぞれが3段階の評価をします。
『-1』は次の選考プロセスに進めるのを待って欲しい
『0』は今すぐ選考プロセスを止めるほどではないが、ちょっと迷っている。判断がつかない。
『+1』はぜひこの人と一緒に働きたい、問題がなさそうなので次の選考プロセスに進めてOKになります。
一人でも『-1』がいたら採用しません。『0』の人がいた場合どういうところが懸念なのか、それを払拭できるのかを話し合います。その結果そのメンバーが『+1』になったら入社してもらいます。
--やはり文化を大切にされてるのですね!
カルチャーフィットや人の部分は大事にしています。弊社がHRサービスを展開していることもありますが、常に個々が力を発揮できる組織なのかを意識しています。カルチャーチェックに重きを置いているのも、優秀なメンバーだけを採用するのも最終的にはLAPRASがビジネスで成功するために必要だからです。組織体制や働きやすさも、そうすることによって優秀なメンバーが採用できたりシナジーが生まれたり、ビジネスにとってプラスになるから選択しています。
文化を大切にする背景にはこういった前提がありますし、どんな人を採用するべきかということを考え抜いて的確にアプローチしていくことは会社の成長にとってとても重要です。
編集後記
戦略的なLAPRAS社の採用活動、いかがでしたか?
採用は、目的ではなく企業が勝つための手段です。
勝つために逆算した採用計画。
その採用計画に基づいたマーケティング思考を持って採用活動を展開していく必要があります。
やみくもに採用する時代は終わりました。
自社の成長のため、今一度採用計画や活動を改めてみましょう!
■LAPRAS社の採用ピッチ資料はこちら!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
