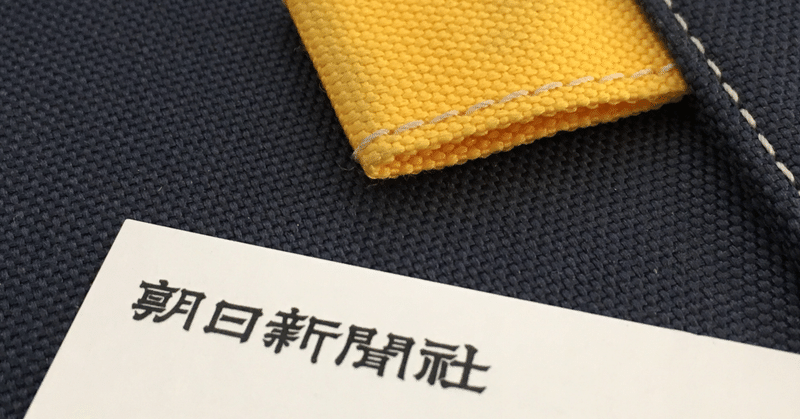
「魂の退社」を読んで
noteでの私の記事は色んなジャンルについて
発信している。
大まかに分けるならば
子育て系、ビジネス系、英語系、昆虫系、繊維系
のような分け方ができるであろうか。
そして、これらの記事に加えて、時々
読んだ本や映画のレビュー記事を書いている。
とはいえ、本はどちらかというと
多読派であるし、映画も洋画限定だが
週に3本は見ている。
これらを全てレビュー記事にしていたら
到底時間が足りないので、
その中でもよほど印象に残ったものや
心が動いたようなものをピックアップして
記事を書くようにしている。
今日は最近読んだ本の中でも
特に心が動いた本を紹介しようと思う。
それは稲垣えみ子さん著の「魂の退社」である。
この本はnoteでよく交流させて頂いている
なんでもやってみる母さんの記事で
ご紹介されていたのをキッカケに手に取ったもので、
ぜひこちらの記事も読んでみて欲しいのだが、
実を言うと私自身この本を購入するかどうか
わずかな躊躇があった。
それは著者の方のプロフィールに
「50歳、夫なし、子なし、無職」と
書かれていたことである。
著書のタイトル通り、この話は筆者の方が
退職をされることがテーマとなった話だが、
独身の方と家族がいる私達では
正直退職に対する見え方は違うのではないか。
そんな風に思い、私はこの本を手に取るのを
躊躇したのである。
だが、何でもやってみる母さんが書かれていた
レビュー記事では
退職はこの本のキーワードではあるものの、
会社社会に対する疑問点が本書の
大きなテーマとして描かれているようである。
それもあり、最終的に私はこの本を購入することにした。
ところが、私のこの疑念はいい意味で
見事なほどに裏切られたのである。
私達は会社員として働き生計を立てているが、
働いている中で「このままでいいのか?」と
疑問を感じる事がしばしばある。
その疑問が明確に言語化されていればいい。
しかし、しばしば言語化ができないまま
何だかモヤモヤしているようなことが
案外多いのではないだろうか。
この本は、そのモヤモヤした感覚が
見事なまでに言語化されているのである。
私はどちらかというと本を多く読むタイプだが、
これまでこんなにも明確に会社社会を
客観的な視点で書き記した本は
見たことがない。
そのぐらいこの本は読んでいて痛快であった。
筆者はもともと朝日新聞の記者として
働かれていたこともあり、
いわば言語化のプロである。
そんな言語化のプロが会社という船から降りて
船の外、否、海を見渡せる陸の上から
その船や船を取り巻く海を見渡した時に
見えた景色を言語化したからこそ
こんなにも明確になっているのであろう。
あまりに感じることが多く、
何を記事に書いていいか悩むほど
色んな部分に心を動かされた本であったが、
その中で最も私が印象に残ったのは
”会社という組織が、実は自己利益のために
弱きものを食い物にしている”
という内容であった。
私は中小のメーカーで仕事をしているが、
ここ数年会社の業績はお世辞にもよくない。
海外から輸入する原材料が尋常じゃなく
値上がりし、商品の原価が上がる一方なのに
私達よりもずっとずっと規模の大きい
大企業は購入価格の交渉に驚くほど応じず、
苦労の末に勝ち取った値上げも
値上げ前に大量に買い込みをされてしまう。
だが、その一方でこの顧客のような大企業は
「春闘で満額回答」のような従業員への
昇給を行っている。
まさにこの構図は私達下請けの中小企業が
大企業に食い物にされていると
言えるだろう。
だが、話はここで終わらない。
このようなシチュエーションに置かれた
私達中小企業は次に何をするかというと、
さらに安い原材料や加工先へ代替しようとする。
私はメーカーの商品開発として
新規商品の開発だけでなく、
既存商品の収益改善に向けた改良なども
手がけることがここ数年とても多いのだが、
この仕事をしながら、
「こうして代替されたメーカーやその中の人たちは
果たしてハッピーなのだろうか?」と
薄々感じていた。
当然ながら彼らも高い値段で仕事を受けることを
望んでいるはずである。
そこで、何らかのアドバンテージを見つけて
高い値段でビジネスができればいいが、
多くの場合はそうはなっていない。
大企業から回ってきたおこぼれのような仕事を
地獄につり下がったニンジンのように
多くの人がそれにすがりつこうとする。
そうなると市場での価格が上がるはずがない。
自分たちの利益はスズメの涙であっても
0よりはマシぐらいの気持ちで
受け入れざるを得ないケースも多々あるだろう。
私達が代替メーカーを探して
そこに注文をするときに、形式上先方は
「ありがとうございます」と言うわけだが、
内心、これがWin-Winなのかというと
現実的にはそうではないと思っていた。
結局、私達中小企業は大企業からの搾取の中で
何とか利益を出そうとするあまり、
次にさらに小規模な企業から搾取をしようと
しているのではないだろうか。
結局、この負の連鎖が行きつくところは
最も弱い人である。
本書の筆者はもともと朝日新聞という
大企業で働いていた。
そこで働いている時には見えなかった
下請けに対するブラックな姿勢が
退職というイベントを経て見えてきた。
そして、私は本書を読むことによって
自分がこの連鎖の被害者だけでなく、
加害者にもなっていたことに気が付いてしまった。
本書は全体を通してエッセイ調の軽めのタッチで
書かれており、とても読みやすいはずである。
私は一般からすると読むのが早いほうだと
周りから言われるので、
エッセイ調の本ならばすぐに読み終わるはずなのに
この本はなぜか読み終わるのにかなり
時間をかけてしまった。
それはここに書かれた内容を
自分に当てはめたときに
咀嚼が必要だったからであろう。
本書の後半に筆者はこの会社社会を
生き抜くために「自立をせよ」という
メッセージを書いている。
会社社会に依存するのではなく、
自分から頭を使って必要なものを取りに行くことが
自立であると筆者は述べている。
会社に対して依存しない生き方を取ると言うことは
給料に対する依存度を下げ、
皆で奪い合わないようにするということである。
一人一人が奪いあうことをやめれば
先ほど例に出した地獄につり下がった人参も
一人一人が譲り合い、
結果として皆が天国に行くことができる。
こうして文字にするととても簡単そうに見えるが、
それはかなり勇気のいる事であろう。
だが、それをしない限り私たちは
この負の連鎖を消すことはできないのだ。
自分にできる事は一体何か。
まだ現時点で私の中ではボヤっとしているが
しっかりとTO DOに落とし込んで、
まずは依存心からの”退社”を目指してみようと思う。
ちなみに私が読んだ文庫版は
今年の5月10日に第一版が出たばかりで
文庫版のあとがきも追記されているので
本書をまだ読まれていない方はぜひ読んでみて欲しい。
ちなみにこの本をリビングで読んでいると
妻から「え?会社辞めるつもりなん?」と
不安そうな声をかけられた。
この手のタイトルの本を読む際には
余計な不安を煽らないように気を付けねば
ならないらしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
