
リーカンキョウのワークショップ!
目指せ日本一安いチラシ・日本一高いチラシ!
2021年5月に世田谷区駒沢にOPENしたDOHSCHOOL(ドースクール)で、
クリエイターズファイル Vol.1
【リーカンキョウのチラシを作るワークショップ】
を2週に渡り開催した!

「情報」とは何か?
今の子供たちにとっては、当たり前のように身の回りにあるもの。
今回は、日々の生活に必要な「情報」が凝縮された「チラシ」を作るワークショップ。
参加者の中には、紙のチラシを初めて見る子もいた。

チラシを作品としている台湾出身のアーティスト リーカンキョウ氏。
日本で初めて住んだ家の一階がスーパーマーケットだった。
夕方になると、チラシを見ながらその日の献立を考える主婦たち。その光景は、台湾にはない日本特有のものだった。
そこにとても興味を持ったという。

チラシというメディアをもう一度考え直してみる。
それが今回のワークショップの要。
■ ワークショップ1回目
「目指せ!日本一高いチラシ」制作。
shufoo.netというサイトで、チラシをくまなく観察し、高い商品を探す。
みんな高級な商品に思いを巡らし、ひたすら検索。

すると参加者の一人のお母さんから、こんな質問が出た。
「さまざまなお店のチラシから、イチゴの情報だけをひっぱり出せないの?」
インターネットを活用して情報を集めるなら、その発想に至るのは当然だろう。
しかし、チラシの情報からは、それはできない。
AIを使えば、できなくは無い。
膨大な量の画像をAIに学習させれば、の話だ。

情報の扱いは、時代によって変化する。
・昨今
献立を決める→必要な食材を買う
・チラシが一般的だった頃
チラシを見て安い食材をチェック→献立を決める
発想が真逆である。
もちろんみんながそうとは限らない。
しかし情報の扱い方により、生活スタイルも変化している、これは事実である。


身の回りにある情報をよく観察し、アイデアを集めて孵化させる。
答えは人の数だけある。
■ ワークショップ2回目
「目指せ!日本一安いチラシ」制作。
前回、近隣のスーパーの情報を調べ、安い商品を探してくる、という宿題が出ていた。
予め準備してきてきた分、初回より作業がスムーズに進む。

仕上がりを見ると、前回の絵よりもはるかに完成度が上がっていた。
塗りの配分、レイアウトの仕方、描き方、一回目を経験し、自分の流儀ができていた。
実際に自分の手で描いてみると、普段意識していない所に目がいくようになる。
(下記は描くことで分かった事の例)
高い商品は「栃木産」と地名がしっかり書いてあるが、安い商品は「国産」と曖昧に記されている
22個入りのチョコレートは、写真で数えると20個しか写っていない。「プレーンチョコレートは2枚重なっています」注意書きをし、クレーム対応している
税込価格に小数点第2位まで表記されている商品がある

コンピューターで情報整理できる時代。
コンピューターで情報処理を学ぶ時代。
だからこそ知るべき、人間がどのように情報を認識するのか。
それがリー氏の視点を通し、浮き上がってきた。



子供の頃、母親に
「今日何食べたい?」と聞かれ、
「なんでもいい」と答えた。
そして夕飯時に
「ハンバーグが食べたかったぁ」というと、
「さっき聞いた時に答えなさい!」
と怒られたものだ。
ご飯には、家族のロマンが詰まっている。
絵を描きながら、食材を見ながら、献立を考えながら、
親子であ〜だの、こ〜だの、たわいの無い話をする。
すごく良い時間だと思った。
とにかく絵を描く子供たちは楽しそう!

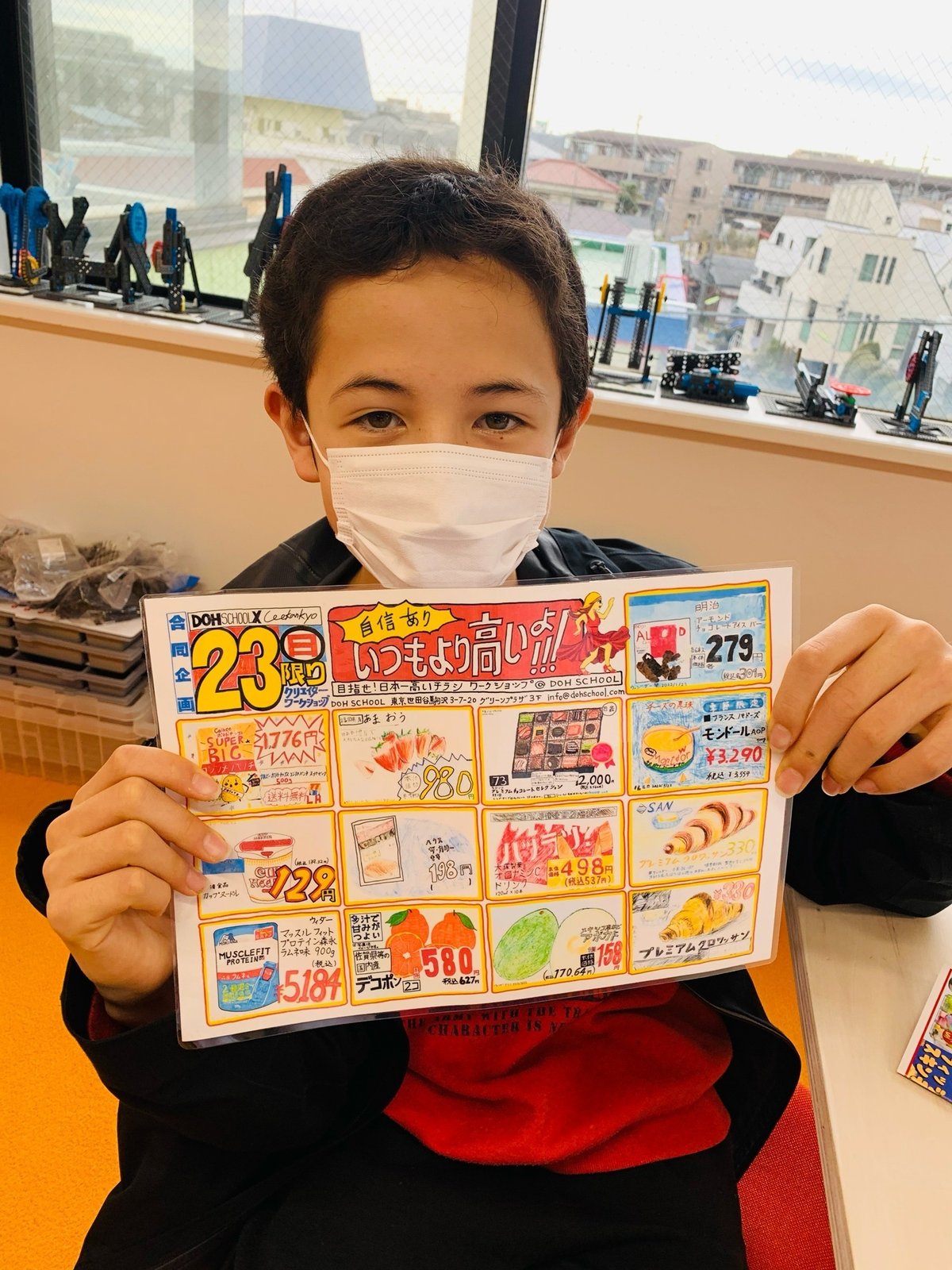


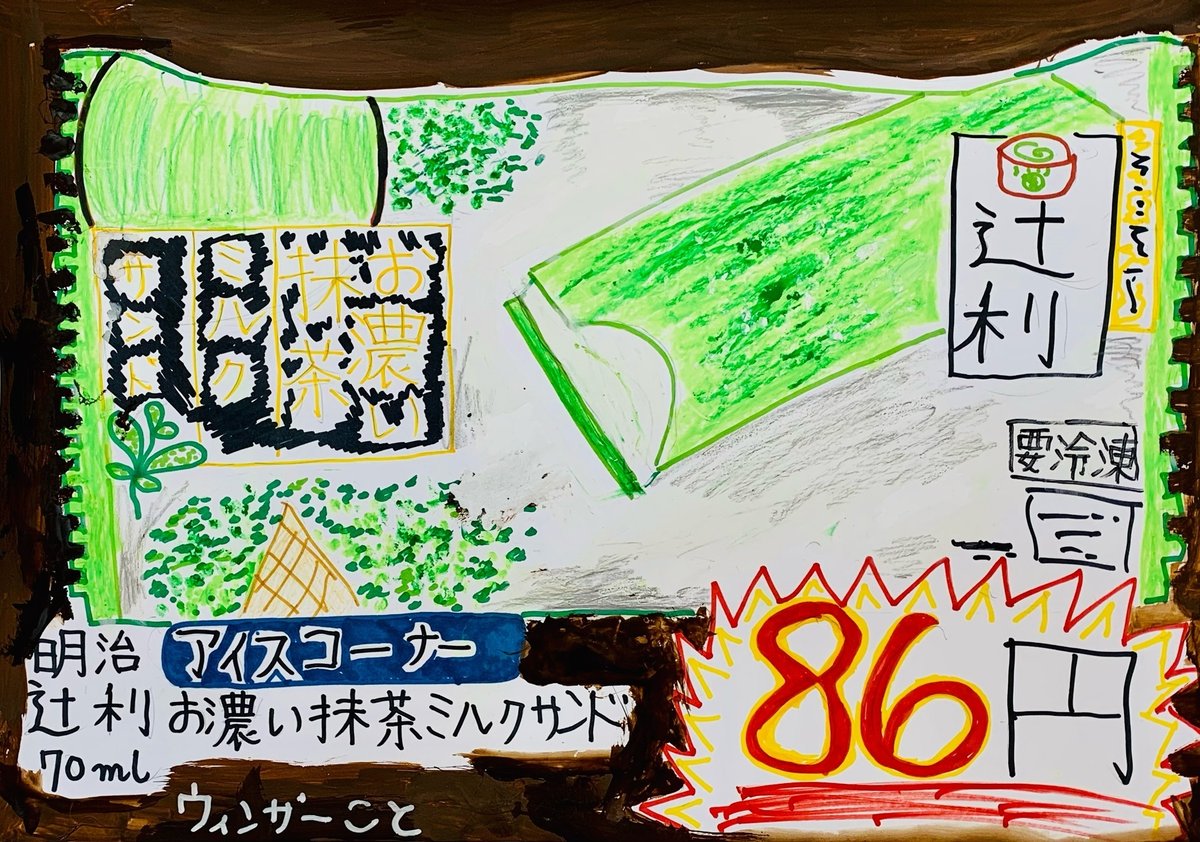



描くことで見えること。
効率が悪くても、人間が認知する情報をたくさん教えてくれる。
楽しさはそんなところからやって来る!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
