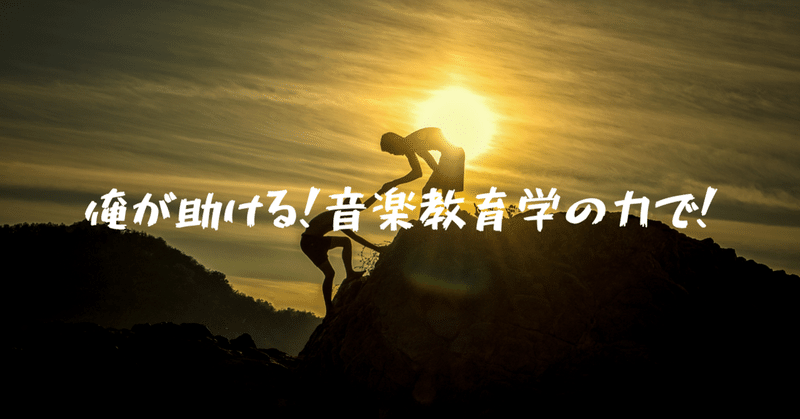
「シャンクスの腕問題」にモヤモヤしている『ONE PIECE』読者を音楽教育学的に救いたい
どうも,音楽教育学者の長谷川です。
これまでのnoteではコンサートにおけるプログラムノートのあり方について論じたが,今回はタイトルどおり,とあるマンガについてのあれこれを語りたい。
「音楽教育学者がなんでマンガの話をしているんだ」と思う人もいるかもしれないが,僕はこの話を大学の講義や高校への出張授業で取り上げるくらいには重要なトピックだと認識している。
理由は至ってシンプルで,このテーマは「表現」「価値」「美」といった音楽教育学の根幹に関わる問題について考察するのに非常に適した題材だからだ。早速語らせてください。
1.『ONE PIECE』の第1話の問題のシーン
マンガ『ONE PIECE』をご存知ない方は今や日本にはいないのではないだろうか。海賊王を目指すゴム人間ルフィが仲間と共に困難を乗り越えてく王道のバトルマンガで,今や日本が世界に誇るマンガ・アニメ文化を牽引する国民的作品である。
その『ONE PIECE』の第1話がちょっとした物議を醸しているのである。第1話についてはジャンプの公式サイトで無料で読めるので是非そちらを読んでいただきたいのだが,念のために以下に概要をまとめておく(ネタバレ注意)。
まだ幼く弱かった頃の主人公ルフィは,なんやかやいろいろあって(雑ですいません),海で溺れてしまう。ルフィは泳げないので(悪魔の身を食べた能力者は泳げない)放っておいても溺死なのに,さらにそこに「近海の主」と呼ばれるでかいサメみたいなやつが現れてもう大ピンチ。サメが巨大な顎で襲いかかってきてもはや絶体絶命か…!というタイミングで,ルフィの村に滞在していた気の良い海賊シャンクスが颯爽と現れルフィを庇うのである。仲間を守る時のシャンクスの迫力は凄まじく,睨みをきかせるだけでサメは撤退,ルフィは無傷で無事救われた。が,なんとシャンクスはルフィを庇った際にサメに片腕を喰われてしまっていたのだ。そんな大怪我を負ったにも関わらず,シャンクスは「安いもんだ腕の一本くらい…無事でよかった」という驚くべきセリフを発する…😭ルフィは,海の過酷さ,普段ヘラヘラしてるシャンクスという男の本当の強さ,そして海賊の偉大さに思いを膨らませ,修行する。そして10年後,鍛えた腕で「近海の主」を軽々とぶっ飛ばし,シャンクスを追いかけて冒険に出る。
これだけ聞けば,別になんの問題もないように思える。僕は初めて読んだ時この第1話でめっちゃ泣いた(アナ雪の序盤でも泣くくらいなのであまり参考にはなりませんが)。
しかし,問題のタネは物語が少し進んだ後に表面化してくる。
実はシャンクスはルフィ達の世界において「四皇(海賊四天王みたいなもの)」の1人に数えられるほどの有名海賊で,その辺のサメなんて目じゃないくらいのとんでもない実力の持ち主だった,という設定が明らかになるのだ。
そうすると,ちょっとおかしなことになる。「あれ,シャンクスって四皇だったの?めっちゃ強いじゃん!ってことはそのシャンクスの腕を食ったサメってそんなに強かったの?でも第1話でルフィが軽くぶっ飛ばしてたよ?強さの序列どうなってんの?」という疑問が湧く。
そして,今や「ワンピース シャンクス 腕」とかで検索すると,まぁいろんな説がまことしやかに語られてるくらいには物議を醸しているのである。中には「ワンピは矛盾だらけwww」とかいってドヤるやつまで出てくる始末。
2.何が問題なのか
確かに,その辺のサメに腕を食われる程度の男が実は四皇だった,というのは話の筋としてちょっとおかしいのかもしれない。なので,この展開を見た読者が「なぜ四皇のシャンクスがサメごときに腕を食われてしまったのか」ということについてあれこれ議論して楽しむこと自体は否定しない(「ONE PIECE考察サイト」なるものもあるくらいだ)。これもSNS時代におけるマンガの楽しみ方なのだろう。
でもね,僕がどう考えてもおかしいと思うのは,「物語に矛盾があるから面白くない(価値がない)」と早計に結論付け,それを他人に発信してネガティブキャンペーンをするネット上のアンチ民である。
そして,この矛盾指摘ネガキャンアンチ民は,私たちの世界を自らの手でどんどん窮屈にしていっている,といことに気付いていない。
アンチコメントをする人間というのは特定のプラットフォームが構造上必然的に抱えている代謝物みたいなもので,コンテンツの質に関わらず絶対に湧いてくるのだから気にしてもしょうがないのだが,一個人として,そして音楽教育学者として,世界を窮屈にされるのは本当に困るのである。
なぜ矛盾指摘ネガキャンアンチ民が私たちの世界を窮屈にしていると言えるのか,このnoteで語らせて欲しい。
3.世界は説明責任に支配されている
まず大前提として,多くの学問は「言葉と数字によって原因・結果・方法・意味・価値等を説明(理解)しようとするもの」であるということを確認しておこう。
物理学は「リンゴが木から落ちる理由を数字で説明(理解)しようとする学問」だし,国語は「日本語を効果的に使用する方法を日本語で説明(理解)しようとする学問」だし,哲学は「私たちが世界を認識する方法や人間が生きている意味等を言葉で説明(理解)しようとする学問」である。
ちなみに音楽教育学は非常に学際的な学問なので(教育学・音楽学・文化人類学・美学・哲学等複数の学問領域を横断する学問なので),「音楽や音楽教育の意義・価値・方法論等について言葉や数字で説明(理解)しようとする学問」というように少し広い定義になる。
こうやって並べてみると,あらゆる学問は,「探求したい何か」こそバラバラだが,その「何か」について言葉や数字の理屈で説明(理解)しようととしているという点においては共通している,ということがわかるだろう。人類が世界を理解しようとする際の主たる武器は,ずっと「言葉や数字で紡がれる理屈」だったというわけだ。
そしてこのような説明主義とでも呼べる考え方は,当然現代社会においても通底している。通したい企画があれば企画書を書いて「なぜこの企画に意義があるのか」「どうやって利益を出すのか」言葉と数字で説明しなければならない(研究費が欲しければ「その研究にどんな価値があるのか」言葉と数字で説明しなければならない…😭)。「どうしてもやりたいから」「なんとなく好きだから」では通用しないのである。私たちの世界は言葉と数字の理屈によってできている,とも言えるわけだ。
当然ながら教育も,そのような「言葉や数字で説明(理解)する力」を育もうとしてきた。上述の学問体系がそのまま学校の教科になっていることからもそれは明らかであろう。
そして,これは教育を提供する側にも求められている。
例えば中学校の音楽科教員は成績をつける時,
「A君の音楽の成績は5段階評価の4です。実技テストが100点,期末テストも100点だったのですが,提出物が出てなかったので4になりました」
のように後から数字の根拠をきちんと説明できるよう,事前にめちゃくちゃ綿密な準備をする(※観点別評価等もあり本当はもっともっと複雑)。もちろんこうすることの理由については,「公平性」「目標に準拠した評価」というポジティブな理由から「クレーマー対策」といった現場の事情までいろいろと語れるのだが,いずれにせよ,教師もあらゆることに対して(授業内容から生徒指導的発言に至るまで全て)言葉と数字による説明を要求されているのだ。
つまるところ,私たちは,学問だろうとビジネスだろうと,そして教育であろうと,言語と数字によって説明責任(accountability)を果たすということを至上命題に掲げる「説明主義」の世界で生きている,ということだ。
4.マンガに説明責任はあるか
説明責任に支配される説明主義の世界では,ロジックの通っていないものは無価値とされ,物事には何か必ず説明されるべき意味が宿っている,とされる。「頭がいい」「仕事ができる」の今日的な意味は,「物事を言葉や数字で説明(理解)する能力が高い」である。では,マンガというメディアにおいても全ての描写に対して説明責任が適用されるべきなのだろうか?
答えは,圧倒的に,完膚なきまでに,ノーである。
なぜなら,ほとんどのマンガは「面白さに価値を見出している」のであり,「何かを言葉や数字で説明(理解)することに価値を見出している」わけではないからだ。したがって「理屈が通らない=価値がない」という評価は的外れにも程がある。
もちろん,
「理屈が通らない→そのことが気になりすぎてその他の描写が頭に入らない→面白くない」
という矢印の連続を経た後,最終的に「面白くない→(自分にとって)価値がない」に辿り着いた,というのであればよく理解できる。でも,「理屈が通らない=このマンガには価値がない」は違うでしょ。ヒールの高い靴を自分で買っておいて「走りにくい=この靴には価値がない」と主張しているようなものだ。そもそも価値の所在を見誤っているとしか言えない。
では芸術はどうだろうか(ここが授業でこの話をする際の本筋だったりする)。
例えばクラシック音楽では「この音型は〇〇を意味する」といった修辞法が用いられることがあるし,現代アートにおいてはコンセプトそのものがその作品の価値を規定する場合もあるので,一概に「美しければ意味が通らなくてもいいのだ」とは言えない。芸術は,部分的に説明主義のフィールドに足を突っ込んでいると言えるだろう。
しかし,芸術は「言葉や数字で何かを説明(理解)する」という目的のために運用するには明らかに非効率的・非客観的すぎる,というこはご理解いただけるだろう。そして,言語や数字に置換不可能な部分に芸術の価値の多くが置かれてることも何となく想像がつく。そのような「言語や数字での説明(理解)」とは一線を画す探求様式を我々は「美」や「芸術」と呼んだりしている訳である(超簡略化をお許しください)。
この辺はいろんな説明の仕方ができるし,議論しだすとキリがないので割愛するが,要するに,芸術もマンガも,世界を支配する説明主義の視点のみでその価値を議論できるものではない,ということを我々は把握しておく必要があるということだ。
5.一部のマンガは説明主義を取り入れ始めている
一方で,近年のネット広告で表示されるマンガを見ていると,キャラクターの能力値やレベルが数値化されていたり,属性が明示されて「勝てる・勝てない」の基準が可視化されていたりしていて,説明主義的な表現が多用されていることに気づく。
そう,まるでゲームの世界だ。
スマホ用ゲームの多くは勝ち負けの要因を数値で説明しており,このルールは絶対に崩れることがない(もし崩れでもしたら運営に重課金ユーザーからの悲痛なクレームが届くことだろう)。ゲームは,ユーザーに感情報酬を与えることを目的にしているという点でマンガや一部の芸術とも共通する部分がある一方で,その根底には明確な言葉と数字のロジックがあるという点で説明主義的であり,非常に興味深い例だと言えるが,いずれにせよ近年のマンガはこのゲーム的な世界観を取り入れていることが多い。
もちろん作家が「ゲームのような世界をマンガで描きたい!」と強く思っているのであれば,それについて僕がとやかく言う筋合いは全くない。また,作家の低年齢化が進み,ゲームに日常的に触れている層が作品を描くようになった,つまり「マンガのゲーム化」には時代的必然性がある,と言うことができるのかもしれない。
しかし,僕が勝手に危惧しているのは,有名マンガに対する矛盾指摘ネガティブキャンペーンを目の当たりにした若手作家が,「矛盾叩きの予防線」として数字の根拠を使わざるを得なくなり,結果的に数字を運用しやすいゲームの世界観が多用されているのではないか,ということである。
若手作家:主人公が無双するマンガ描きたいな,でもいきなり無双させると強さの根拠がないって言われて叩かれそうだ…最近の読者は「努力と根性で勝った」「奇跡が起きた」みたいなの嫌いだし。よし,主人公はとにかく「早く動ける能力」があるという設定にして,それでパワー系を翻弄する物語にしよう!とすると,どうやって「早く動ける能力」を描写するかが問題だな。半端な描写だとアンチが湧くぞ…あ,「素早さ」のステータスが数値的にMaxだという設定にすれば確実に説明できる!こうなったらもう「パワー」も「身の守り」も数値にして,ゲームみたいにすればいいんだ!
という具合である。もちろん数字による根拠付けが全て悪いわけではないし,一周回って「主人公が数字の力で無双する」という部分に面白さがあると捉えることもできるのかもしれないが,この発想がネガキャンアンチによって不可避的にもたらされたものだとしたら,個人的には少し考えさせられるところがある。
僕が個人的に好きなマンガ(スラムダンクとか,あと全部は読んでないけどキングダムとか)は,この「強さの根拠」みたいなものを数字ではなく別の描写(キャラクターが背負っている過去,過去と結びついて発揮される火事場の馬鹿力みたいな必然的奇跡,そして何より有無を言わせない圧倒的な絵の迫力)を複合的に用いて表現していることの方が多かった気がする。作者は言葉の理屈や数字の根拠を超えた形で世界の秩序を独自に描いていたし,読者もいちいちの描写を過度にロジカルな視点で捉えなかった。
もちろん個人的な観測値でしかないのだが,近年では説明責任を果たしているマンガしか市民権を得られない傾向にあるのかな,とマンガ家志望でもないのに勝手に不安になっているのである。
6.世界には余白が必要だ
説明主義は一見すると全ての人に対して平等であるように見える。言葉と数字の理屈の通るものだけが存在を許されるというルールがあり,そのルールを巧みに捉えるという「世界の攻略方法」が明示的なので,万人に開かれている感がある。
だが,説明主義は言語化不可能なものを削ぎ落とすことで矛盾をなくして成立している,ということに私たちはそろそろ気がついた方がいい。そして音楽科教育はまさにこの問題にぶち当たっているといっていいだろう。
例えば音楽の先生が「この子はめちゃくちゃ音楽を愛しているし,何ていうか楽器持ってるときのオーラがもうアーティストそのものなんだよな…今は私より技術的には下手だだけど,絶対本物の表現者になるわ…」と直観的に思ったとしよう。
言うまでもなく,「オーラ」(芸術家性のようなもの)は言語化・数値化して説明(理解)するのが非常に難しい。先生がこの「オーラ」を確かに感じたとしても,現状では言語化・数値化できないので評価できないし,義務教育課程に含めることはできないのである。
一方で,「提出物が出ている・出ていない」という状態は誰にでもわかる形で簡単に説明できる。より教科内容に目を向ければ,「音を間違えずに演奏できている・できていない」というのも同じように説明可能だろう。説明主義の世界において,客観的な評価として採用されるのは「定量的な(数値化可能な)資質」というわけだ。
もちろん僕は「オーラ」を公教育の評価項目に入れろ,と主張しているわけではない。でも,「言葉や数字で説明(理解)できないものは存在しない」と結論付けるのはあまりに短絡的だ。だって私たちはその「オーラ」みたいなものに触れたくて,他の誰でもないアルゲリッチの演奏をわざわざ聴きにいったりしてたわけじゃないですか。特異なアーティストの「素晴らしさ」の本質を定量的な言葉や数値で説明することは難しい。そしてその「素晴らしさ」は,定量的な技術の総和なんかではない。そんなことみんなわかってるはずだ。とんでもない芸術経験って大体そんな感じだろ。
それに,今では言葉と数字で説明されている医療的な行為や燃焼という現象だって,昔は魔法でしかなかったはずだ。もしかしたら「オーラ」だって言葉と数字で説明される未来が訪れるのかもしれない(それを望むかどうかは別として)。落合陽一氏みたいな天才がいつか本当にやっちゃいそうだ。200年後の文化人は,「令和時代の人間って音楽におけるオーラの存在を無視してたらしいよ,何しにコンサートに行ってたんだろねw」と言っているかもしれない。
いや,もっと悪いことに,現代の私たちがあまりに「オーラ」を無視するので200年後には「オーラ」なんて言葉は死後となり,技術的には「オーラ」を数値化・可視化するテクノロジーが確立していたとしても誰も興味を持っていないかもしれない。そして音楽家でさえもコンピュータと争う未来が到来するというわけだ。「切り捨てる」とはそういうことである。
いずれにせよ,「言語化不可能な何か」を直ちに切り捨てるのではなく,また粗雑な言葉で説明してしまうのではなく,「そのままそっと取っておいて静観する」といういわば「認識の余白」のようなものが世界には必要なはずだが,どちらかと言えばその余白はどんどん狭くなっているように感じる。そして,余白のない窮屈な世界を作っているのは,「マンガにさえも根拠を求める」説明主義の我々自身なのである。
7.まとめ:矛盾指摘ネガキャンアンチ様への贈り物
言葉と数字の力は強力だ。人間が世界を言葉と数字で理解しようとする生き物である限り,この力に抗うことはむずかしい。
でも,マンガや芸術は「言葉と数字の世界」に片足を突っ込みながら,「非言語的表現の世界」にも半身を預けている。だからこそ多くの人を夢中にさせてきたのだろう。それを推し量ろうとせず,何のリスペクトももたずに,言葉と数字の力を振りかざして「非言語的表現の世界」を無自覚に侵略しようとするアンチの方々には,僕からDysonの加湿器Hygenic Mistの取扱説明書をささやかながらプレゼントしたい(個人的にお気に入りの加湿器である)。
別にDysonに限った話ではないが,おしなべて取扱説明書という表現媒体は,絵と文章による描写を全くもって客観的・合理的に采配することに成功している。序盤で示された機能やスイッチについての簡易的な説明が後から取りこぼしなく補足される構成になっており,矛盾がないどころか伏線の回収にまで余念がない。ユーザーの理解にエラーが起こらないよう,徹底した配慮がなされている。
僕はこのHygenic Mistという加湿器に一切不満を感じていないが,残念ながらこの商品に対してクレームを言う人は必ずいるだろう(アンチは代謝物)。だが,商品に対するクレーマーはいても,取扱説明書の矛盾を指摘してくるクレーマーはきっといないはずだ。取扱説明書はそれだけ「言葉と数字の世界」の住人に対して最適化された読み物ということだ。
さぁ,このnoteでもそろそろタイトルに張った伏線を回収しておこう。
「シャンクスの腕問題」が気になりすぎて『ONE PIECE』という作品全体の美質を楽しめなかったばかりか,そのモヤモヤをぶつける先が見つからず,最終的に矛盾指摘ネガティブキャンペーンに精を出しているそこのあなた,あなたを救うための画期的な読み物を僕はとうとう見つけた。Dyson Hygenic Mistの取扱説明書だ。あなたの価値判断基準を多角的に検証した結果,この取扱説明書はあなたにとって「面白い」読み物として認識されるだろうと結論された。遠慮せず受け取って欲しい。誰にでも間違いはあるし,全ての人に救いはある。夢中になって読んで欲しい。そしてアンチ発言をする暇がないくらい没頭していただいて,世界の余白を確保するという僕のミッションに消極的に貢献してもらいたい。
僕はというと取扱説明書を読むのがめちゃくちゃ嫌いなので,シャンクスが腕を食われるという描写でしか成し得なかったあの非言語的な感動を味わいながら,もう少しマンガを読むことにする(仕事しろ)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
