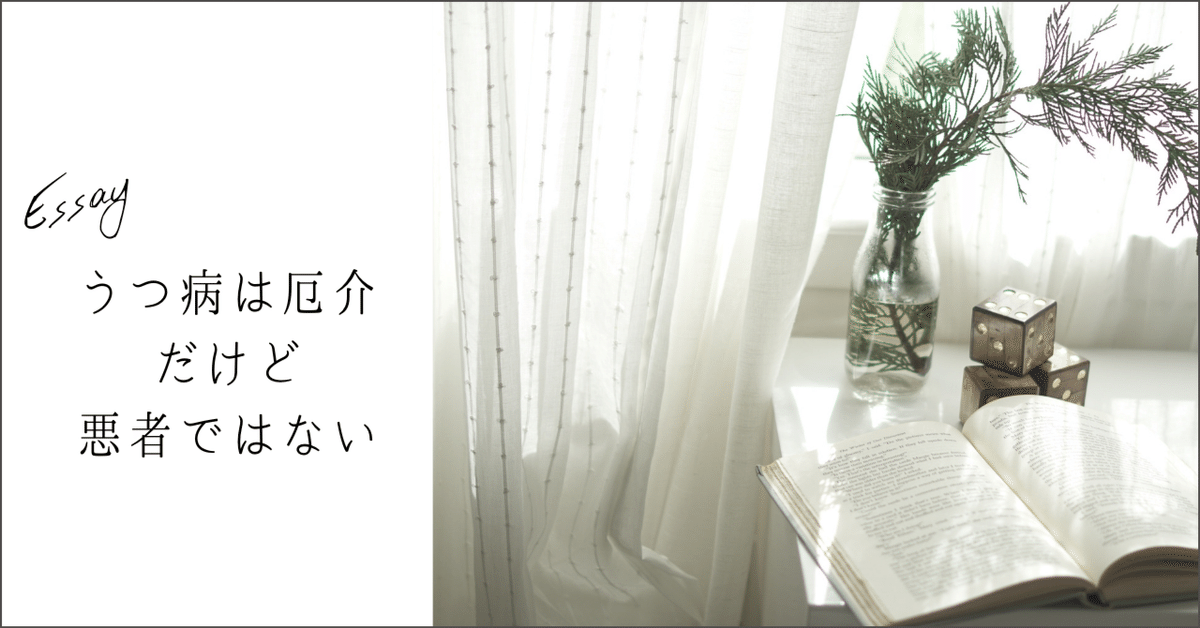
うつ病は厄介だけど悪者ではない
18歳のとき、初めて「うつ病」と診断された。改めて振り返ると「この厄介なやつ」とも、かれこれ約15年の付き合いになる。
この病の第一印象は最悪だった。忘れもしない。あれは約15年前の1月。私が高校2年生のときのこと。
3学期に入り、風邪のような症状で学校を数日休んだ。いつもなら長くても3日程度のんびりすれば復活するところだが、体調は一向に良くならず、そのまま登校できなくなった。
心配した当時の担任が、どうやら私の母に心療内科への受診を進めたらしい。私の意思などお構いなく(というより、うつの症状もあってか意見する気力もなかった)病院に連れて行かれた。
心療内科で病名を告げられた瞬間は、今でも昨日のことのように、はっきり思い出せる。
不自然なくらい清潔感が漂う診察室。椅子や机、壁、カーテン……いろいろなものがやたら白く、どんより気分の私にはまぶしくて居心地が悪かった。
おそらくエリートコースで大人になったであろう、おぼっちゃま風の先生。(人を見かけで判断してはいけないのは分かっていても、当時の私は瞬時に「苦手なタイプ」と感じてしまった)
そんな医師は、感情を持たないAIのようなトーンで「うつ病ですね」と、私に告げた。それは青春真っただ中の高校生にとって、受け入れがたい現実だった。
以前テレビのドキュメンタリー番組で、たまたまうつ病の特集が放送されていたのを一瞬見ただけの私。うつに関する知識はゼロに近かった。
そのため病名を告げられたときは、ただひたすら「うつ病」という言葉が脳内にこだましていた。
どうしてうつ病になってしまったんだろう。
私が弱い人間だから?
これから私はどうなるの?
すぐ良くなって、学校に行けるよね。
そんな不安だらけの私を待っていたのは、思っていた以上に苦しい現実だった。この厄介者は、私の体と心を使って暴れまくったのだ。「生きているのに死んでいる」、そんな感覚だった。
茶碗や箸が100キロを超えるダンベル並みに重たく、思うように持ち上げられない。そのためごはんが食べられず、何十分も掛けてアイスクリームで栄養を採っていた。
お風呂では、湯船の中で体がフリーズして出たくても出られない。誰かを呼ぶ気力もなく、のぼせてフラフラのところを、「えらい遅いわね」と心配した家族に発見されてようやく脱出。
今まで当たり前のようにできていたことが、当たり前のようにできなくなった。
頭の中では知らない誰かが、「おまえなんて消えてしまえ」と繰り返しささやいてくる。あるときは「今日私は誰かに殺されるんだ」という、根拠のない恐怖に震えた。
「とにかく今日一日をやりすごす」それだけが当時の私の目標だった。もちろん学校には行けず休学。ベッドの上で寝たり起きたりして過ごす毎日だった。
私の当たり前の日常を奪ったうつ病は、悪者でしかない。心の底から、うつを呪った。
そんな私が「うつは厄介だけど、別に悪者ではない」と思えるようになったのは、何年もたってからのこと。
高校を休学し、体調が落ち着いたので留年。ひとつ下の学年に混じって登校してみたものの、うつの再発でまた休学することに。結局学校は泣く泣く退学し、「高校卒業程度認定試験」という高卒の資格をとった。
その後はフリーターとしてケーキ屋やアパレル、パン屋、雑貨屋、カフェ、などさまざまな職場を転々とすることになる。
その間もちょっと油断すると、うつ病は存在を猛烈アピールしてきた。
「仕事に慣れてきたし、週6日働いても良いかも」などと私が調子に乗ると、「再発」という形で無理やり休息させてくる。「いったん立ち止まって、冷静に考えろ」と言わんばかりに。
気付けばうつ病は、暴走しやすい私のブレーキ役を担っていた。だいぶこの病気をコントロールできるようになった今も、こいつのやり方は気に入らない。だけどその一方で、憎めないのも事実。
こうして今もうつ病は、「厄介な相棒」として私の一部になっている。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

