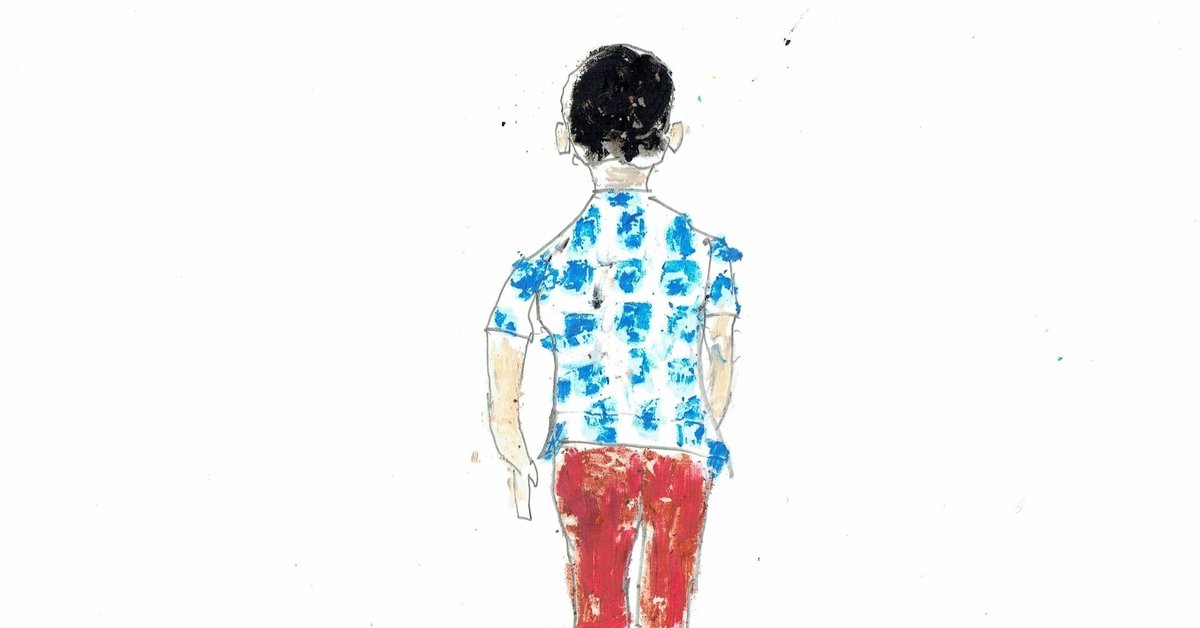
僕が地域マネージャーになる理由
現在私は、富山大学に通う大学生です。富山県高岡市を拠点に、空き家を活かした“地域と大学生”で創る街づくりに励んでいます。
そんな私が一人の社会人との出会いによって、大学生と社会のあるべき関わり方について学んだことを今回の記事では紹介します。
大学生の生態
広いキャンパス内を見渡すと、おしゃれな洋風に身を包み、髪型をバッチリとキメた学生の集団や、勉学に勤しんでいることが見て取れるような風貌の学生がちらほらと目に入ります。そんな大学生たちの生態について、独断と偏見を交えながら数少ない調査結果を基に語ってみたいと思います。
一. バイトでお金を稼ぎ、遊びにお金を使う典型的な陽キャ型
一. バイトの掛け持ちでお金を稼ぎ、学費と生活費にお金を使う苦労型
まずは前者の型について。
バイトでお金を稼ぎ、遊びにお金を使う典型的な陽キャ型に共通してみられる特徴として、まず比較的家が裕福であることが挙げられます。
このタイプは経済的に余裕があるために、バイトでお金を稼がなくては生きていけないという危機感がありません。そのため、勉強は二の次に、遊ぶためにお金を稼ぐという行為を優先し、その循環を繰り返します。また、「とりあえず大学に入っておこう。」と考えて入学した人も多いため、勉学への熱意というものは後述する苦労型の人間と比べると低い傾向にあることも特徴の一つです。
では、次に後者の型について紹介します。
バイトの掛け持ちでお金を稼ぎ、学費と生活費にお金を使う苦労型に共通してみられる特徴として、やりたいと思っていることを実現できていないということが挙げられます。本当はもっと学びたいのに、バイトをしなければ学費を払えないどころか生活にも困窮してしまう状況だったり、趣味に時間をかけたいけれどそこまで体力的、精神的に余裕がなかったりする場合です。また、一つ一つの行為に対する考えが深いことも前述した陽キャ型と比べると高い傾向にあることも特徴の一つだと思います。
今回はあえて極端な二つの例を紹介しましたが、
現大学生は、生産と消費を繰り返す生態を持っていると私は考えています。
そして今回紹介した、一見相反する時間の使い方をしている二つのタイプの学生が、唯一お互いに課題として認識しているものがあります。
それが、就活です。
就職活動への意識
大学生にとっての一大イベントといえば、やはり就活ではないでしょうか。
(かくいう私もつい最近まで就活なんて言葉とは無縁の関係でした。)
大学生なら誰しも、3年生にもなれば就活というビッグイベントに向き合う日がやってきます。幾千もある選択肢の中から、自分に合う就職先を探し出し、エントリーシートと呼ばれる用紙を経験者の指導のもと何度も何度も書き直し、希望の就職先へと提出します。その後一次選考、二次選考と進んでいき、最後の難関である面接の結果によって合否が判断されます。
そんな就活は、先ほど紹介した二種類のタイプの学生が唯一お互いに意識している共通の事柄だと私は考えています。そして私はそんな全ての学生にとって共通である就職活動、厳密いえば就活中に書くエントリーシートの「ガクチカ」および「活動実績」という項目に着目しています。
どんな学生であっても、このガクチカおよび活動実績というものはあって困るものではありません。近年は企業の物事を自分考え主体的に行動する若者のニーズが増加しています。そんな中でこれらガクチカや活動実績が揃っていることは就活において有利になること間違いなしです。
しかし、実はこれまで、ガクチカや活動実績を手に入れるためには、満たすべき知られざるいくつかの必要条件があったのです。
ガクチカを手に入れられる選ばれし者
ガクチカは人を選びます。正式にいえば、ガクチカを手に入れるにはいくつかの必要条件が存在します。そして、昨今その条件によってガクチカを手に入れたくても手に入れられず辛い思いをしてきた学生たちが少なからずいたことをぜひここでは知ってもらいたいと思います。
ガクチカを手に入れるための必要条件
①時間とお金に余裕がある
②精神的に余裕がある
③ガクチカを手に入れる機会に出会う
まず、①の時間とお金の問題について。
これは説明をしなくても大方想像がつくのではないかと思います。最も肝心なところであり、今回「大学生の生態」というコーナーで紹介した二種類の大学生の一番の違いです。時間とお金に余裕があることで、例えばインターンシップに参加できたり、ボランティア活動に参加できたりします。どんなに意欲があったとしても、時間とお金がない限りはそれは実現しません。
次に、②の精神面での問題について。
これは独断と偏見に侵され、限られた少数の方々への調査によって得られた結果に基づく信憑性の低い内容ではあるものの、社会全体をみてもかなり当てはまるのではないかと思ったために条件の一つとして取り上げました。先ほど苦労型として紹介した人の特徴の中に、一つ一つの行為に対する深い思考があると話しましたが、まさにそれが影響していると私は考えています。例えば家族の問題、経済的な問題、恋愛に関する問題などなど、それぞれに対する考えが深いため一つの問題と向き合うだけでも大変なのに、同時に複数もの深刻な問題や悩みを抱え、精神的に疲弊している人が多くみられます。そういった精神状態では、現状維持することの他に新しいことを始める精神的余裕はなかなか生まれないように思えます。
そして、③ガクチカを手に入れる機会と出会うことについて。
これは結局、自分がいかにアンテナを張っているかや身近にガクチカを身につけようと積極的に活動している人がいるかということに帰着します。どんなにガクチカを手に入れたいと思っても、ガクチカを手に入れる機会を探したり、たまたま出会ったりしない限りは、なかなかガクチカを手に入れることは難しいと私は考えます。
結局のところ私が何を言いたいかというと、このガクチカを手に入れるための三か条、およびその必要条件を環境状況の差異によって満たせず悔しい思いをしてきた学生が数多くいること。そして、その反対に条件を満たしいつでもガクチカを手に入れられる環境にいる学生が、その環境のありがたみに気づかずせっかくのチャンスを無駄にしてしまっているというこの2点です。
今の私にできること
ここまで現在の大学生について長々と語ってきたところで、最後は今の私にできることについて話したいと思います。
それは、全ての大学生が公平な機会のもと社会と関わりながら着実にガクチカを築き上げていく環境の整備です。陽キャ型の学生も苦労型の学生も、そのどちらもが公平に取り組むことのできる環境づくり。それこそが私の取り組むべき課題だと感じています。
ここからの文章は、私の尊敬するとある社会人の方から教わったものを、自分なりの解釈と知見を足し合わせて書かせていただこうと思います。
大学生が有益的に関わるための理想環境
①First stage:一部協力でメディアにバストアップ掲載@学生団体
②Second stage:お金を稼ぎながらガクチカをつける@企業
大学生が実績を残す環境の整備として、新聞やテレビといったマスメディアでの活動の掲載や行政との連携といった実績として示す上で非常に信頼度の高いものと連携を図っていくことが非常に重要であると考えています。そのため、地域マネージャーがしっかりとした活動のストーリー設計を行い、問題の分析と課題と役割の明文化をした上で大学生に一部協力を仰ぎ、大学生と連携して活動を推進していくこと。これこそが私の目指す第一段階です。
またそのために、大学生が関わりやすいようにできる限り敷居を低くしたファーストアクションを用意します。そして敷居を低くするヒントには、学生団体という存在が鍵になると考えています。
「就活(ガクチカ)のため何か始めたい。」と思った学生が最初にとる行動として、企業にインターンへ行くことはかなりハードルが高く、逆に全く実績の積めない活動を試しにやってみることは時間の無駄のように思えます。そこで、実績をつけることが保障されている団体である、学生主体の団体(学生団体)の活動に参加することが、これから何か始めたいと考えている学生にとって最適な第一歩になると考えています。
次に、第二段階を紹介したいと思います。
それは、大学生がお金を稼ぎながらガクチカをつけることです。既存にある一番近いものとしては、有給インターンがわかりやすいと思います。スキルを身に付けたい大学生が企業にお金をいただきながら、学び働く。この関係性というのが全ての大学生にとって公平な機会のもとガクチカをつける最善の方法だと私は考えています。
具体的には、大学生のうちから地域マネージャーとして活動することです。それはつまり、お金を稼ぎながらガクチカをつける状態を指します。この段階では、実際に地域の方々との交流を盛んに行い、地域の方のためにも、自分自身のためにも活動するようになります。また、一定の収入も確保できるようになり、生活が担保された状態で気兼ねなく地域に根ざした活動を行えるようになります。
そして、(ここからは大学を卒業した後の話)第三段階です。
この段階というのは、地域マネージャーとして活動に関わる全ての人を幸せにした後(ガクチカも十二分につけた状態)、実際に自分の理想とする就職先に行ったり、もしくは独立して会社をおこしたりと、自分自身の進むべき道に進んだ状態を指します。地域に根ざして活動を行い、多くの人に幸せを届け、またその時に関わった多くの人たちとの親交が残り続けている状態。就職先はその地域とは遠く離れた場所ではあるものの、半年に一度、お世話になった地域の方々の顔を見にきて「変わらずお元気ですか?」と尋ねる、そんな関係性。
もしかしたら、その地域には二人目の両親のような大切な存在ができているかもしれません。
物理的には遠く離れた場所にいても、心はつながり合っているような、私はそんな関係性を第三段階だと思っています。
そして最後の第四段階。
この段階であなたは応援される側から、応援する側にシフトします。若かりし頃の自分を育ててくれた街、応援してくれた街に対して、次は自分が恩返しをする番です。ただ、自分を育ててくれた方々や街に対して恩返しをするのではなく、その想いをバトンのように次の世代へと繋げます。
これから地域に根ざした活動に取り組もうとしている学生に対して、できる限りの支援をする。自身の知識や経験を語り、伝え、一緒に街を創っていく。次は感謝する側から感謝される側へと移っていく。それが私の考える第四段階です。
人はあるべきところで循環する

地域に関わる人々の循環/各段階の役割
①ガクチカをつける/他世代から応援される
②街を活性化する/次の学生を教育する
③自身の夢へと羽ばたく/これまでの経験を活かして社会で活躍する
③街の住民として協力する/新しい世代を支援する
私が何度も言っている「地域」という言葉についてですが、この活動の「肝」は、地域に根ざした活動であるということです。
「地域」とりわけ地方の地域という限定された場所に根ざした活動を行うことに最大のポイントがあります。(ここを明文化すると卑しいように感じるかもしれませんが、今回は素直に話します。)
①口コミによる拡散力
②協力してくれる大人の数(特に高齢者の方々)
③現地メディアの食いつき
④若い世代の活動に協力的な支援者(企業、行政、街の方々etc.)
結局のところ、上記した4つの点において非常に有利であるということが、地域に根付いた活動することの最大のメリットだと私は考えています。
そしてこのメリットというのは、いえ、言葉をあらためて「長所」としましょう。地域に根ざして活動する長所が最も作用するのが、多くの方々を幸せにする時です。そして、活動に関わる全ての人にとってプラスに働くこの循環型の環境を理解し、また整備されているところにこそ、人は集まってくるのだと思います。
最後にあなたに届けたいこと
これまで幾千となく様々な地域で行われてきた活動との最たる差異は、地域マネージャーの存在です。
この地域マネージャーの有無によってこの循環の円滑度は圧倒的に変わります。そして現在各地で謳われている地方創生や地域活性化事業といったものにも、結局のところ企業や行政、地域自治体と、地域住民の方をつなぐハブとなるこの地域マネージャーの存在が必須です。これをわかっていなかったために、これまでの地域活性化事業というものは単発的なもので終わってしまい、継続的な活動へと結びつかなかった事例が数多くあるように思います。
この循環の一連の流れをまとめると、まずは一人の大学生として学生団体に入団し、地域の方々に応援されながらガクチカをつけていきます。そして、そこで学んだり経験したりしたことを活かして、次は地域マネージャーとして活躍する。大学を卒業すると同時に、これまで関わった方々に背中を押されながら次は自身の夢を実現をするために旅に出ます。そして最終的には、その地域の一住民として、次の世代を応援する立場になる。
私は、そんな応援し、応援されるような街づくりこそが今後必要とされていくのではないかと考えています。
私はそんな街づくりに励む一人の大学生兼地域マネージャーとして、今後も誠心誠意取り組んでいきたいと思います。
私の活動する富山県高岡市に住む方も、そうでない方も、温かいご声援をよろしくお願いいたします。
2021年12月吉日
おまけ-大学生と上手く関わる極意

上の図で表したように、大学生の適切な関わり方というのはずばり、地域マネージャーが企業や行政と地域の方々とを結ぶ確固たる土台を作った上で、その一部の明確な役割を大学生に担ってもらうというものです。
(今回は立場上、地域マネージャーという表現を使わせいただきますが、その他の業種においても同様のことが言えるため、自身の立場に置き換えて考えていただけると幸いです。※社会人目線)
多くの社会人が私は大学生を教育のためだ、社会経験だ、などと口を揃え、ただ闇雲に大学生を様々なことに巻き込みます。そして、その結果よくあるのが「失敗も一つの経験だ。」という言葉で全てをまとめようとする。これは、最悪のパターンです。ちなみに大学生をタダで働く駒だと思っている人はそもそも論外です。確実に大学生に、いや誰からも嫌われます。
仮にもあなたが大学生のことを本当に思うのなら、あなたは大学生と共に成功の未来を描くべきではありませんか?もっと言えば、成功のビジョンをあなた自身の背中で語るのが、本当の教育であり大学生のためとなる社会経験だとは思いませんか?
これは私自身に対しても同様に言えることですが、問題とそれに対するニーズがどこなのか?ということが整理できていない状態で人に協力を仰ぐことは非常に問題があります。
例えばその地域や組織が抱えている問題が非常に複雑なために、行き詰まっており、そのためにどうしても若い学生の考えを聞いてみたいといった場合には、具体的に複数ある問題のうちのどこを考えたら良いのか?大学生にどのようなものを求めているのか?を明確にしていただく必要があります。
(地域マネージャー目線)大学生との関わり方の鉄則
①大学生と自分達運営を切り離して考える
②問題の全体像を話した上で大学生に何を求めているのかを明確にする
③そこに関わる大学生がその活動を通して実績を作れる環境を整備する
結局、ここまでの話を聞くと、なんて大学生優位の話なんだとご立腹された方がいらっしゃるかもしれません。しかし、これは大学生にとってだけでなく、大学生と関わろうとする多くの方にとってプラスに働くと確信しているからこそ、私は腹を切る覚悟で訴えかけています。
鉄則を守るメリット
私の経験上、上記の3つの鉄則を守ることで飛躍的に関係性と活動のしやすさが向上します。お互いが全体像を理解し、流れを掴んだ状態で、大学生には具体的に何をどうして欲しいかを明確に説明する。その過程で地域マネージャー側は自分自身の思考の整理ができ、将来の明確な道筋が立ちます。また、お互いに全体像を理解することによって二者間でのコミュニケーションが円滑になり、その先、齟齬が生じる可能性が格段に減ります。
逆にこの3つの鉄則を守らないと、お互いが不信感を持ったまま活動することになり、大学生は何をどうすれば良いかが見えずに悩み、地域マネージャー側も強く言おうにも言えず、お互いがギクシャクした関係になってしまいます。そうなることによって、活動へのモチベーションも減少し、せっかくの機会が全く楽しくない苦痛なものへと変わってしまいます。
つまり、先ほど記した3つの鉄則というのは、お互いにとって必ずプラスに働くということです。今回は割愛しますが、ゲーム理論を用いて説明した際にも、同様のことが言うことができます。
まとめ
現在の大学生というのは、非常に気難しく、良くも悪くもよく物事を考えています。そのため、決して子供だと思って接するのではなく、一人の大人として対等な立場で関わっていくということが何より大切なことなのではないかと、一大学生として強く感じています。
長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。今回は所々感情が溢れ、口調が強くなってしまった部分もあったかと思います。しかし、終始本音の魂のこもった記事になったのではないかと思います。
ぜひ今後の記事もお読みいただけると幸いです。
本当にありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
