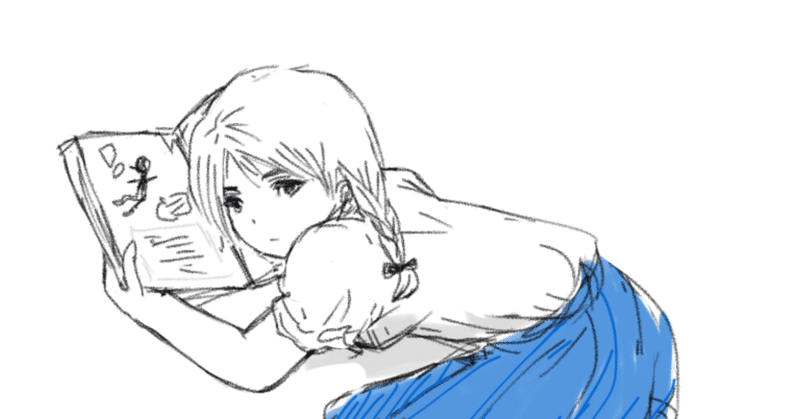
【本の内容がグングン入ってくる⁈】司書直伝の10倍記憶テクニックとは
あなたは本を読むとき、どのように読みますか?
目次を飛ばし、本文をいきなり読み始めるでしょうか。
表紙や目次をじっくり眺めてから読み始めるでしょうか。
時間がない方は、結論から読み始めるかもしれませんね。
わたしがこれまでおすすめしていた方法は「目次を眺めて、本の内容を想像してから読む」というもの。
この読み方をすると、読み進めながら想像していた内容と実際の内容との答え合わせができるので、記憶に残りやすいんですね。メンタリストDaiGoさんもおすすめしていた読書テクニックでした。
おはようございます
— 小夏(こなつ)@元公務員Kindle作家✕Webライター (@konatsu_40) September 26, 2023
もったいないです!「目次」を飛ばす私のような人。色々な読書法を調べて分かったのは、目次は読書の超重要ツールということ。読む前に目次を見て想像する。仮説を立て、読みながら答え合わせをする。忙しいからこそ、記憶に残る効果的な読書をしたいですよね。#nおは戦50927🌊h
しかし、わたしは最近これを上回る(かもしれない)画期的な方法を発見! 実践してみると、面白いほどスルスルと入ってくる実感を得られたので、みなさまにもぜひシェアさせていただきたいと思います。
◆司書直伝の最強読書テクとは⁈(ちなみに一応司書です 汗)
それでは、最強の読書テクをご紹介しましょう。
その方法はズバリ……
「書き手がどうやって読者を納得させようとしているか」を考えながら読むこと
物語や参考書などは別として、1冊の本には書き手が訴えたい「主義主張」や「メッセージ」が込められています。
単にそれを伝えるだけなら、たったの1行でいいかもしれません。でも、それだけでは読者さまに納得してもらうことも、共感してもらうこともできませんよね。
だからこそ書き手は、長い文章にして「あぁそうか~」「なるほどね~」と思ってもらうための工夫を凝らすわけです。たとえば具体例だったり、数値データですね。
ちなみに、わたしの著書『40代 繊細さんの人生がときめく「内向型」を味方につけて自分史上最高のあなたに出会う方法』でも、いろいろな工夫をほどこして、読者のみなさまに納得いただくような「秘密のエッセンス」を盛り込みました。
権威あるかたのお言葉を借りたり、参考文献を引用したり。「繊細は最高の強み」というメッセージをバキバキに補強し、倒れない1本の柱にするためのパーツを、あの手この手で組み合わせたわけです。
(うまくできたかは別の話で……汗)
◆これからの読書方法はコレ!
①書き手が伝えたいメッセージを予想する。
②(できれば目次を見て)どのような方法で伝えようとしているのかを、なんとなく把握する。
③「なるほど、こういう具体例があるわけね~」などと、書き手の理論武装にうなずきながら読み進める。
ぺらりぺらりと、のんびり読み進めるのもよいですが「記憶に残したい」と思ったときは、ぜひ一度お試しください。受け身で読んでいるときよりも、きっと理解が深まり、記憶にも強く残ることでしょう。
人間は忘れやすい生き物。(わたしは「サザエさん並み」に物忘れが激しいアラフォー)
「エビングハウスの忘却曲線」によると、人は20分後に42%忘れ、1時間後には56%忘れ、翌日には74%忘れるといわれています。
命を削った大切な読書の時間。すぐ忘れてしまうのは、もったいなさすぎますよね。
声を大にして言いますが……
「本は読む前が肝心です!」
「本は読む前が肝心です!」
「本は読む前が肝心です!」(←エコー)
読書はページを開く前から始まっているんですね。
【最近の気づき】
編集者 藤原華さんのnoteにも、同じような一文を見つけ万歳三唱!!
おっと……、ここでも権威ある方の裏付けをお借りしてしまいました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
