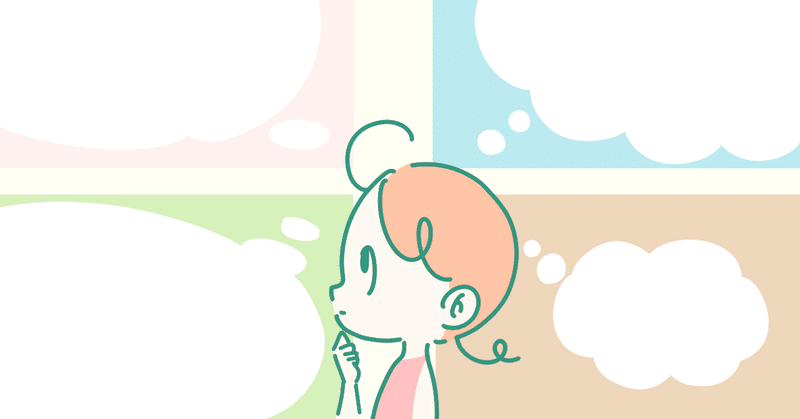
想像力欠如講座①
はじめに
大人は、幼い子どもに芸術的なセンスを求める。親馬鹿はおいておいても、どんな大人も、すべての子どもの発想は新鮮で唯一無二、あらゆるものを無垢な眼差しで見つめることができる、などという幻想を抱いて、そのめちゃくちゃな創作物を褒めちぎる。
断言しよう。「こどもの想像力は素晴らしい」なんて真っ赤な嘘である。なぜなら私に想像力などというものがあった時代は一度もなかったからだ。
幸い想像力に恵まれて生きてきた人間には、これはただの規格外品だと思うかもしれない。しかし、私は私だけが例外だとは思わないし、万が一そうだとしても、それはそれで珍獣として面白がってもらえそうなので共有しておこうと考えた。これは、この世に「想像力」を持ち合わせず生を受けると結構大変だよという実体験である。記憶があいまいな部分はあるが盛ってはいない。
ちなみにこの記事では「想像力」と「創造力」で迷うとき、どちらで表記するかはその時々によって私の内省が判断する。「想像力」という言葉の定義についても一致をみない問題であるので辞書とか引かずにフィーリングで書かせていただく。
粘土でヘビ以外の何を作るっていうんだ
私は保育園に通っていた。ピアノに合わせて歌い、列を作ってお散歩をして、給食を食べて、工作をして母の迎えを待つ日々だった。特になんとも思わず、ぱりんこをかじりながら先生と一緒にアンパンマンとか見てた。
私のパラダイム転換のきっかけは弟だった。当初、3歳年上の私の方が圧倒的に手先は器用だったから、折り紙でも工作でも私の方が上手。そう思っていた。大人は弟の作品を褒めているけど、幼い弟が優遇されてもいいよね。仲のいい姉弟として楽しく遊んでいた。
さて、私が小学校に上がったくらいだろうか。プラレールを一緒にやっていたときに事件は起きる。
私はプラレールの箱に描いてある通りに線路を繋げようとして、パーツがなぜか足りず探し回っていた。ところが弟は「そんなのいいよお姉ちゃん、僕がやるよ」とどんどん繋げていく。
なぜ。プラレールは箱の見本の通りに繋げたいじゃないか。私が茫然と見ていると、弟は私が完璧に作った線路をオリジナルに改変していく。なぜこいつは全然箱を見ず勝手にレールを繋げられるんだ。
「人間は遊ぶ存在である」。ヨハン・ホイジンガは人間を「ホモ・ルーデンス」と表現した。これは弟のためにあるような言葉だった。
私の弟は想像力も創造力も非常にたくましかった。レゴブロックを渡せば何やら見たこともない怪獣を作り戦わせている。一人ぼっちで楽しそうに部屋で野球をしている。どうやら弟の脳内では野球が9人チームで成り立っている。あ、今のはヒットだったんですね。ピッチャーもキャッチャーもいないのに、5才の弟は想像の中で球場に立っていた。架空の動物を作り出すだけでなく空間まで想像力で補う。これがメタバースか……。
私は当時、レゴブロックもレゴ作家さんの作品を丸ごと真似しようと格闘していたし、もしくはひたすら平らな板の上でお弁当を作っていた。日の丸弁当は簡単にできるんだけど唐揚げとか再現しようとするとレゴブロックの色がなくて大変なんですよね……。卵焼きは黄色くてありがたい。
年長のときにけん玉にお絵かきしよう!というイベントでも、絵が上手な子が昔描いていた作品を思い出して真似をした。その子に真似してる!と指摘されなかったのはただ私の絵が下手だったからである。けれどもこの時はかなり罪悪感を感じたし、今でもよく覚えている。
オリジナリティは模倣から始まるなどというが、模倣から一歩も出ない子どもというのも人生が危ぶまれる。
保育園でも小学校でも、粘土だけ渡されるのが一番困った。私の特徴として、現実に見えているものをそっくりそのまま落とし込むことができない道具にぶつかると何も作れない。仕方がないので粘土では永遠に肌がすべすべのヘビを生成していた。母に「粘土でヘビしか作らない子ども初めて見た」と言われた。弟はちゃんと粘土でもすごいの作ってた。
見えないモノを見ようとして――童謡「うみ」で解説する想像力
想像力が豊かな人間が唯一想像できないものは、想像力のない人間の脳内である。私の状態を分かりやすく説明するために、童謡「うみ」の歌詞を引用しよう。
うみ
作詞 林柳波
作曲 井上武士
1.
うみはひろいな おおきいな
つきがのぼるし ひがしずむ
これは正しい。海は広い。大きい。月が上り、陽が沈む。2番に行こう
2.
うみはおおなみ あおいなみ
ゆれてどこまで つづくやら
はいダメ。いや、「海は大波青い波」までは何ら問題はないのだ。海の波は大きいし、青い。同意。
だがここから想像力タイムが始まる。「揺れてどこまで続くやら」。私はこの歌詞を聞いたとき素直に困惑した。海が揺れていてもそこから拡張世界には入らない。どこまで続くか、その終わりを考えるところまで思考が至っているのは童謡で扱うにはいささか難しすぎる問なのではないだろうか。今ここにある海。それだけである。
雲行きが怪しいが3番に入ろう。
3.
うみにおふねをうかばせて
いってみたいな よそのくに
海に船を己が浮かばせる……?そしてよその国に……?そんな無謀なことある……?拡張世界やめてもらっていい……?見えないものを描かないでくれる……?そもそもよその国に行ってみたいという願望はどこから……?ベンザブロック🎵
この事例でどういうことかお判りいただけただろうか。私がいうところの「想像力」の定義もなんとなく分かったかもしれない。目の前にあるものがすべて。目の前にあるものをそのまま描くこと以外、脳内に何もない(だって想像できないから)から、ひたすら真似する、模写する。それは次のステップに繋がるとかではなく、オリジナルを付け加えるでもなく、ただあるものを受け取る。
私には「見えないモノを見ようとして」などという歌詞は一生書けない。ちなみにこの話をしたら漢文の先生に「漢文向いてますよ!」と勧誘されたので漢詩人が天職かもしれない。求人待ってます。
さて、ここまでで私は物心がつき、「想像力がない」とうっすら自覚し始めたころである。受難は続くがすでに2500字なので一旦筆をおこう。
続きはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
