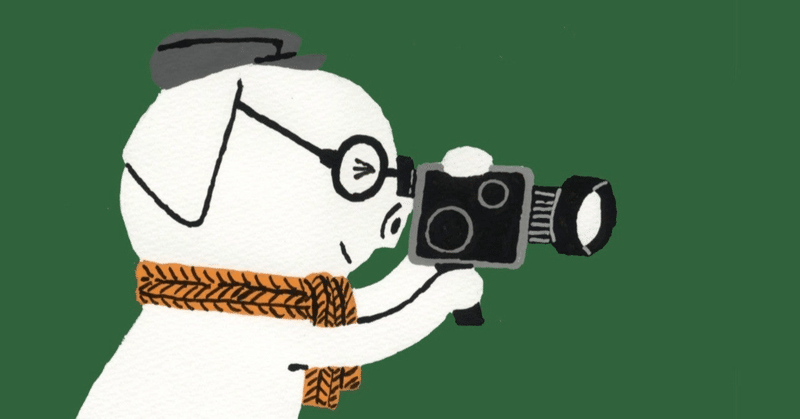
プロジェクト型学習の事例#1 環境問題をテーマにしたSF映画製作。しかも外国語で!
アメリカ合衆国のチャータースクールHigh Tech Hgihのwebサイトに掲載されている実践事例を整理するnoteです。
自分のメモを兼ねて公開します。
¿Dónde Está el Niño?(エルニーニョはどこだ?)
人文科学,数学,科学,世界の言語
11年生(高2)
内容
エルニーニョや異常気象などの自然現象を研究し、SFのショートフィルムを作る。スペイン語と英語のバイリンガル映画にする。
サンディエゴ ラティーノ フィルム フェストの「ユース ショート ナラティブ部門」に出展する。
iMovie と Final Cut Proを使用。
小道具他はリサイクル素材で制作する。
5 ~ 6 人のグループに編成され、そこでアイデアを完成させ、ストーリーを作成した。
映画祭から1 か月後のエキシビジョン(HTHでは、プロジェクトの最後に関係者や保護者らを招いて、交流会を行う)で、生徒は誇りに思っている、面白くて、洞察に満ちた、インパクトのある話をした。
★エキシビジョン=プロジェクトのラストは、映画を上映することではない。それらの活動を通じて、何を学んだか?をPresentationすること。グループと協力して美しい作品を作る。
学習成果
生徒はスペイン語で情報を公開する。
→生徒はライティングとスピーキングで対人コミュニケーションとプレゼンテーション スキルを伸ばす。また、読解力とリスニング力も向上する。生徒は地球のシステムに出入りするエネルギーの流れの変動がどのように気候の変化をもたらすかを説明できるようになる。マクロレベルでの変化をもたらす粒子の動きとしてエネルギーを見ていく。また、環境と生物多様性に対する人間の活動の影響を軽減するためのソリューションを設計する。
生徒は、途中で頻繁に実施されるプレゼンテーションでデジタル メディア (テキスト、グラフィック、オーディオ、ビジュアル、インタラクティブ要素など) を戦略的に使用して、調査結果、考察、エビデンスへの理解を深める。
多様な視点に思慮深く対応する。問題のあらゆる側面についてのコメント、主張、および証拠を総合的に学ぶ。調査を深めたり、プロジェクトを完了したりするために必要な追加情報の調査を自ら行う。
生徒たちは、地球規模の気候とテクノロジーの影響についての疑問を探求するために、何ヶ月にもわたって非常に集中して取り組む。
生徒グループは、映画を通じて情報や意見を他の人に伝える素晴らしい方法を学ぶ。
noteライターのコメント
映画祭に実際に出展するのが面白い。
テーマやジャンルを限定し、さらに言語・文化の要素を入れる(スペイン語)のが面白い。
日本で取り入れるならば、社会科で環境問題やその他社会的な課題、SDGsについて学び、それに関する映画を英語で作る、といったところか。国語でシナリオを書き、英語にする。
SFとジャンルを限定し、しかも制作に相当な創意工夫が要るジャンルにすることで、creativityが活性化される。苦労しそうなジャンルだからこそ面白い。
最後が映画の上映ではないのが良い。映画の上映までのプロセスを振り返り、何を学んだのか?を語る。映画上映のときの高揚感から落ち着いて省察するところまで、プロジェクトに入れているのが学びを落ち着いて自覚し言語化することに繋がる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
