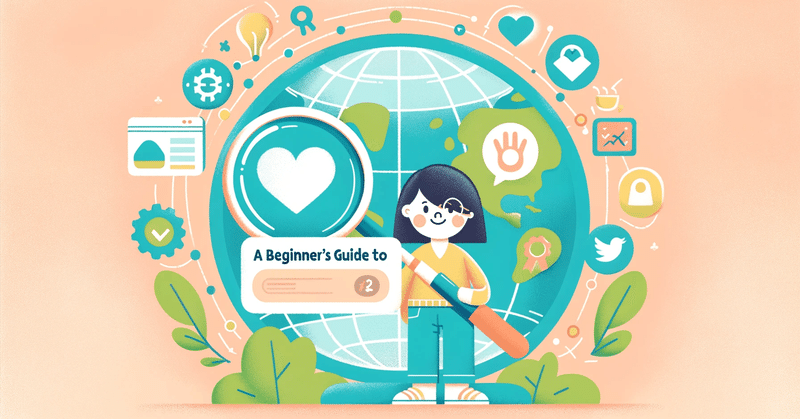
NPO・非営利団体がSEO対策する際にまず読んでほしいガイドライン
初めまして。一般社団法人ペアチル代表理事の南と申します。
僕は新卒でSEOコンサル業界で上位に入る株式会社ウィルゲートに入社し、その後、SEO・SEMを中心にデジタルマーケティング畑で数々の組織のお手伝いをしたり、事業会社でマーケティング責任者を務めたりしてきました。
現在は、ベンチャー企業・NPOを中心にSEO対策などのデジタルマーケティングのお手伝いをしつつ、ひとり親の望まない孤独を解消するべく、シングルマザー・シングルファザー限定のトークアプリ「ペアチル」などの事業を推進しています。
今回、組織内向けにSEO対策のガイドラインを作成したのですが、他のNPO・非営利団体の関係者も読んだ方が良いのではないか?と思い、公開することにしました。
見慣れない言葉があるかもしれませんが、その際はぜひ検索して調べてみてください。よりSEO対策について詳しくなれると思います。
あくまでも初学者向けなので、詳細な内容を一部省略しています。SEO対策の熟練者の方からするとつっこみ万歳かもしれませんが、そこは悪しからず!
では、順をおってSEO対策について説明していきます。
(組織内向けに作成したものなので、本文はだ・である調に切り替わっています)
NPO・非営利団体のSEO顧問もしているので、壁打ち相手など必要な方は気軽にXのDMやFacebookでご連絡ください(^ ^)
・X
https://twitter.com/minami_shiroInc
(そして、正直に言うと、本記事の内容が本記事には適用されておりません!これは甘えです!すみません。ただ、やるぞ!って時に理想論を知っていると知ってないとでは大きな違いが出るかなと思い、恥をさらしますが公開してます。)
1. SEO対策の基本的な考え方
まずSEO(Search Engine Optimization=検索エンジン最適化)対策とは、Googleとユーザー(人間)にとって優良なサイト・ページを制作し、特定のキーワードで検索上位を目指す行い。
Googleに対してはテクニカルな要素もあるが、基本的には特定のキーワードで検索しているユーザーにとって優良なサイト・ページが上位表示すると考える。
「サイト・ページが使いやすく、読みやすく、探しやすい、かつめちゃくちゃためになるサイト・ページ」を上位表示した方が、Googleを使うユーザーが増える。ユーザーが増えると、Google利用者に広告配信したいと考える広告主が増え、Googleの利益になる。
逆に言うと、以下のようなサイトはユーザーのニーズを満たしきれないため、Googleから「ダメなサイト・ページだ」と評価され、上位表示しにくくなってしまう。
文章が読みにくい
サイト・ページの読み込みに時間がめちゃかかる
求めている情報がない。あったとしても足りない
欲しい情報を探しにくい
セキュリティが脆弱で個人情報漏洩の危険性が高い
SEO対策は小難しいテクニカルな話ではなく、以下に制作する読み手にとって良いコンテンツを制作できるかというおもてなし精神が問われる行いである。
とはいえ、業務を遂行する上でテクニカルな要素も必要になるため、以下で諸々説明していく。
2. 検索エンジンの仕組み
まず、Googleは検索エンジンの一つだが、検索エンジンの仕組みについて把握しておく必要がある。
検索エンジンの仕組みは主に3つに別れる。
クロール
インデックス登録
検索結果の表示
街のお巡りさんがチャリンコで色々な住所を巡回して街の情報を把握していることと、同様のことがインターネットの世界でも起きている。
インターネットの世界でも、Googleのロボットがサイト・ページを巡回していて、「こんなサイトがあるのか!このサイトにはこんなページがあるのか!」と発見し、データベースに登録していっている。
データベースに登録したあと、数百以上の指標をもとに「このページはSEO対策について網羅的に解説できているから、"SEO対策とは"と検索している人に優先的に表示してあげれば喜んでもらえるのでは?」といった具合にランクづけしては、調整し続けている。
参考)https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/how-search-works?hl=ja
では、クロールなど一つずつ説明していく。
クロール
クロールとは、検索エンジンのボット(スパイダーともいったりする)が世界中のサイト・ページを巡回し、インターネット上に公開されたサイト・ページを発見すること。
このボットはクローラーとも呼ばれ、GoogleのメインクローラーはGooglebotである。
Googlebotはリンクをもとにあらゆるサイト・ページを巡回している。
まずはGooglebotにサイト・ページを発見してもらえなければ、検索結果に表示されない。
発見してもらうためにすることは主に以下の3つ。
既存ページから新規ページへのリンクを設置する(内部リンクと呼ばれるもの)
XMLサイトマップを送信する
robot.txt でdisallow(拒否)しない
すでにサイトを公開している場合、よく見られているページ(トップページなど)に新規公開したページのリンクを設置しよう。
ドメイン内のユーザー数が多いページにはbotが来てくれる頻度が高いので、botが来てくれた時に新規公開したページを発見してもらいやすくなる。botが来てくれたからといって、ドメイン内の全ページを巡回してくれるわけではないので、発見してもらいやすくする工夫が必要である。
次に、XMLサイトマップという、bot向けに「このドメイン内にはこんなページが500個あるよ!」とドメイン内の全ページ情報を伝えるためのマップがある。このマップを制作して、botに読み込ませることで、抜け漏れなく全ページを発見してもらいやすくするのである。
XMLサイトマップと似た用途として、新規ページを公開したら、Google Search Console(詳細は7章)で「ページを公開したから、クローラー来ておくれ!」ってリクエストもできる。ただし、リクエストしたからといって、数秒後にクローラーが来てくれるわけではない。しかし、ドメイン公開したばかりなら、リクエストしておいた方が良い。
※Google Search Consoleは、SEOに必要な情報をレポートとしてGoogleから受け取れる、Google提供の無料ツールである。SEOに必須のツール。
参考)
https://www.willgate.co.jp/promonista/glossary-sitemapxml/
最後に、robot.txtについて説明する。
robot.txtとは、botに対して「このページには巡回しないで!」と意思表示するためのツールである。つまり、robot.txtにページURLを記載してしまうと、botが来てくれないので、発見されない。そうなると、検索結果ページにも表示されにくくなってしまうため、検索結果に表示させたいページはrobot.txtに記載しないようにする。
参考)
https://wacul-ai.com/blog/seo/internal-seo/seo-robots-txt/
インデックス登録
クロール後はGoogleのデータベースに発見したページ等を登録する。これをインデックス登録と呼ぶ。
ただし、インターネット中のページを全てデータベースに登録してコレクションしたいわけではない。
Googleは「Google の使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすることです。」と掲げており、あくまでも「人間にとって優良なページにアクセスできる状態」を目指しているため、無価値なページ・悪質なページ・全く同じページなどはそもそもインデックスしない。(最近だと生成AIによってつくられたページをインデックスするか否かの調整があった)
ちゃんとインデックスしてもらうための対策は主に4つある。
価値あるコンテンツを生み出す
正規URLを設定する
noindex を設定しない
手動によるペナルティ・セキュリティの問題を解決する
1.価値あるコンテンツを生み出す
前述したように、Googleの使命に反するページはインデックスされず、ユーザーの目にふれる機会が圧倒的になくなる。
そのため、インデックスしてもらうためにもっとも効果的な方法は「価値あるコンテンツを生み出す」である。ただ、「Googleは何をもって価値があるないを判断しているの?」という疑問が出てくるだろう。
ここに対する明確な答えはない!多数の指標をもとに総合評価されるため「●●をすれば、価値あるコンテンツと判断してもらえる」という一つの施策はない。だからこそ、試行錯誤していくしかないのである。
とはいえ、Googleが考える価値あるコンテンツになっているかどうかを問う項目がいくつか開示されている。一旦、以下の項目を流し見してほしい。
コンテンツは、独自の情報、レポート、研究または分析の結果を提示しているものですか。
コンテンツには、特定のトピックに対して実質的な内容を伴う詳細または包括的な説明が記載されていますか。
コンテンツには、自明の事柄だけでなく、洞察に富んだ分析内容や興味深い情報が含まれていますか。
コンテンツが他のソースを参考にしたものである場合は、単なるコピーや書き換えではなく、付加価値とオリジナリティを十分に示すものですか。
メインの見出しやページタイトルは、内容を要約して説明する有用なものですか。
メインの見出しやページタイトルは、コンテンツを誇張している、または読者に強いショックや不快感を与えるものではありませんか。
自分でもブックマークしたい、また友人に教えたりすすめたりしたいと思えるページですか。
コンテンツには、雑誌、百科事典、書籍に掲載または引用されるような価値がありますか。
検索結果に表示された他のページと比較した場合、コンテンツは実質的な価値を提供していますか。
コンテンツに誤字やスタイルに関する問題はありませんか。
上記以外の項目はこちらに全て記載されている。
これらのGoogleからの問いかけをもとに、自問自答しつつ、価値あるコンテンツを生み出せる試行錯誤をするしかない。
次に、「正規URLを設定する」ことについて説明する。
2.正規URLを設定する
類似したコンテンツがサイト内に複数あるとページ単位、あるいはサイト単位で低評価になる可能性がある。つまり、検索上位に表示されにくくなってしまう。
そのため、類似したコンテンツがある場合は、その中でも「このページだけを評価対象にして」とリクエストする方法がある。これが正規URLに設定することである。
例えば、服を扱うECの場合で、3種類のカラー展開している服のページがあるとする。
それぞれのカラーごとに別URLのページがあると、インデックス後、3つのページは類似コンテンツとして判断される可能性が高い。そのため、3カラーのうち、1カラーのページを正規ページ(評価対象ページ)とし、他2カラーのページには「このページは評価対象にしないで」とリクエストする設定を行う。
この事例の設定で用いるのがcanonicalタグと呼ばれるもの。詳細は省くが、他にも301リダイレクト、alternateタグといった設定方法がある。
参考)
canonicalタグについて
https://www.willgate.co.jp/promonista/seo-canonical/
301リダイレクト
https://www.willgate.co.jp/promonista/301redirect/
alternateタグ
https://mieru-ca.com/blog/alternate-tag/
このように、類似コンテンツがある場合は、類似コンテンツのうち一つを評価対象にしてもらい、他は評価対象にならないようにするための設定を行う。
3.noindex を設定しない
インデックス(index)の反対がnoindexであり、意図的にインデックスされないようにするための方法である。
そのため、インデックスしてほしいページに対して必ずnoindex設定しないようにしよう。
めちゃくちゃ時間とお金をかけて、「このコンテンツはめちゃくちゃ価値あるはずだー!!!」と自信満々でコンテンツを公開したけど、インデックスされないケースがある。その場合、何かしらの原因でnoindexに設定されてしまっていたというミスがよくある。。。このミスをしてしまうと、かなり怒られる。。。気をつけよう。。。
参考)https://lucy.ne.jp/bazubu/seo101/how-to-use-noindex-tag
4.手動によるペナルティ・セキュリティの問題を解決する
何かしらのペナルティ(手動によるアクション)やセキュリティの問題があると、インデックスされない可能性がある。
何かしらのペナルティ(手動によるアクション)やセキュリティの問題があるかどうかは、Google Search Console でチェックできる。
参考)
Googleペナルティ
https://lucy.ne.jp/bazubu/penalty-44692.html
Google Search Console のエラーの原因と修正方法
https://lucy.ne.jp/bazubu/how-to-wmt-crawl-errors-29125.html
検索結果の表示
ここまでのプロセスを経て、ようやく検索結果に表示されるステップになる。
ユーザーが特定のキーワードで検索して、検索結果ページが表示されるまでには主に2ステップある。
検索意図の把握
検索意図に合致するページをデータベースから抽出し、検索結果ページを生成する
「SEO対策とは」と検索したユーザーがいた場合に、「SEO対策とは」と調べる人はどういった情報を求めているかを推測し、推測した情報が網羅的に掲載されており、ユーザーを十分に満足させるだろうと考える順番にページが並んだ検索結果を生成するのである。
ちなみに、サイト公開したばかりの時にSEO対策していく場合は、基本、キーワードが詳細なもの(ロングテールキーワードと呼んだりする)から対策していくと、検索上位を狙いやすい。(競合状況など複数の要因によって例外はある)
「SEO対策とは」のキーワードで検索している人のニーズよりも、「SEO対策の失敗事例」のキーワードで検索している人のニーズの方が推測もしやすく、どういった情報をページに記載すればいいか分かりやすいので、価値あるコンテンツを制作しやすいためだ。
参考)
https://www.plan-b.co.jp/blog/seo/37950/
3. SEO対策の種類
SEO対策には主に3つの種類がある。(呼び方は人によって違う)
内部SEO:サイト・ページ評価のマイナスをなくす役割
外部SEO:サイト・ページ評価をプラスにする役割
コンテンツSEO:サイト・ページ評価をプラスにする役割
それぞれの役割は物件の建築・販売で考えると捉えやすいかもしれない。
内部SEOの役割:物件の骨組みを強固にし、耐震性を強くする。あるいは地盤を強固にする行い。どれだけデザインやレイアウトが良い物件でも耐震性が弱いと不人気(低評価)になる。これと同じで、サイトやページでも読み込み速度が遅いといった基礎的な整備がされていないと、どれだけ良い情報を掲載していたとしても低評価となり、上位表示しにくい。そのため、サイトの読み込み速度を高くする、サイト構造を整備するといったことをして、基礎固めをして、高評価を得るための土壌をつくる役割。
外部SEOの役割:物件の骨組み・地盤が強固で耐震性が強くても、似た物件があった時、専門家の評価数や口コミ数で選ばれない可能性がある。これと同じで、サイトの口コミ数(SNS等でのシェア数、他記事等での引用数など)、インターネット上で頻出の専門家からの評価を増やすことで、サイト・ページを高評価にする役割。
コンテンツSEOの役割:物件購入者のニーズを把握し、物件のデザイン・レイアウト(屋上でBBQできるスペースを用意するなど)・立地をより良くし、評価を高めれば、購入してもらえる可能性が高くなる。これと同じで、他のサイト・ページにはないような価値ある情報をサイト・ページに掲載し、特定キーワードで検索する人のニーズに対して120%応えられるようなコンテンツを生み出し、高評価を得る役割。
外部SEOはSNS等でのシェア数なども指標になるため、アンコントローラブルな要素が多い。そのため、「内部SEO→コンテンツSEO→外部SEO」の順で施策を実行していくことが良いと考えている。
それぞれの詳細を以下で説明していく。
4. 内部SEOの詳細
内部SEOは、どのサイト・ページに対しても共通して人間が求めることに応えつつ、botに発見・インデックスしてもらい、適切に評価してもらうための下準備である。
例えば、インデックス登録の箇所で述べた正規URLの設定、noindexの設定などが関係する。
「SEOに答えはない」とよく言われるが、正確にいうと「外部SEOとコンテンツSEOに答えはない」だと考えており、内部SEOには大方の答えがある。
以下のような施策をしていけば、サイト・ページの評価が80点ほどにはなる。しかし、しなければいけないことは多くあり、開発体制などによっては全てクリアできるとは限らない。。
ディレクトリ構造を簡潔にする
パンくずリストで構造を明確にする
ナビゲーションはできるだけテキストにする
クロールが必要のないページはクローラーに見せない
URLの正規化を行って重複ページをなくす
canonicalタグで重複ページを整理する
リンク切れをチェックする
表示スピード上げる
他には「内部SEO チェックリスト」「内部SEO 施策一覧」などで検索して出てくる記事に記載されている。
参考)
https://valueagent.co.jp/blog/27074
https://web-kanji.com/posts/on-page
5. 外部SEOの詳細
外部SEOの目的は被リンクとサイテーション数を増やすことである。
被リンクとは、外部サイトから自社サイトへのリンクのこと。サイテーションとは、サイト名や企業名などが、他サイトに掲載されること。
例えば、自社サービスを紹介するブログ記事があり、その記事に自社サービスサイトへのリンクが貼ってもらっていれば、被リンクを獲得できたことを指し、サービス名が記載されていればサイテーションを獲得できたことを指す。
「被リンク営業」と呼ばれる営業があるくらい、国内外でブロガーさんなどに自社サービスを紹介してもらって、サービス名の記載・自社サイトへのリンク設置を依頼したり、「うちのサイトに貴社サービスのリンクを設置するから、あなたもリンク設置してね」のような相互リンクの依頼をしたりする。
被リンクやサイテーションは選挙でいうところの「票」です。票数が多い人が当選するように、サイト・ページも票数(被リンク数、サイテーション数)が多いと評価が高くなる。
ただし、インターネットの世界では、必ずしも「被リンク数、サイテーション数が多い=高評価」にならない、もしくは「被リンク数、サイテーション数は自社サイトの方が多いのに、競合サイトよりも上位に表示されない」ってこともある。
ドメインパワーという概念があり、ドメインパワーが高いサイトからの被リンク数の方が高評価になりやすい。ドメインパワーが高いサイトは、Yahoo!ニュースなどリアル社会の中でも有名なサイトとかである。
明確な基準はないが、Yahoo!ニュースからの被リンク数が3のサイトと、無名ブログサイトからの被リンク数が10のサイトだと、前者の方が被リンク自体への価値は高いと想定される。
被リンクやサイテーションを獲得する施策は以下の記事を参照。
https://lany.co.jp/blog/backlink/
https://stock-sun.com/column/seo-external/
6. コンテンツSEOの詳細
「コンテンツSEOを制するものは、検索結果ページを制する」と言う人もいるくらい、コンテンツSEOはSEO対策の中でも根源的に重要な行いである。くどいが、ビル・ゲイツが1996年に「コンテンツ・イズ・キング」とも言っているくらい、本当にコンテンツが重要なのである。これはSEOの世界でも同じ。
Googleの使命を振り返ってもわかるように、Googleは全世界の人が有益な情報に簡単にアクセスできる状態を目指しているので、有益な情報を提供しているサイト・ページは当然、評価されて、検索上位に表示されるのである。
コンテンツSEOとは、この「有益な情報・価値ある情報」を提供できるコンテンツを生み出す行いのこと。
例えば、他ページのコピペのようなページなどは評価されず、自分の足を使って調査した一次情報を提供しているページの方が評価されやすい。
前述もしたが、人によってどんな情報に価値を見出すかはさまざま。なので一つの答えがあるわけではないが、価値あるコンテンツを生み出せる可能性を高くするために行っている流れを説明していく。
コンテンツSEOの進め方
コンテンツSEOの進め方は以下の5ステップである。
自社が価値提供できそうで対策した方が良いキーワードを選定する
選定したキーワードの検索意図・ニーズを推測する
推測した検索意図・ニーズに対して120%応えられるようなコンテンツのアウトラインを制作する
ライティングする
コンテンツを調整する(リライト)
一つずつ説明していく。
1.自社が価値提供できそうで対策した方が良いキーワードを選定する
コンテンツSEOは、対策するキーワードを選定することから始まる。
そして、以下のような問いに「Yes!!!」と応えられるキーワードをなるべく選定していく。
事業戦略と合致している分野のキーワードか?
ターゲットが検索しそうなキーワードか?
検索回数・想定流入数が多そうなキーワードか?
自社の専門性が活かせそうなキーワードか?
上位表示しているコンテンツよりも有益なコンテンツがつくれそうなキーワードか?
対策難易度がなるべく低いキーワードか?
そもそも対策でき得るキーワードか?
1,2について、当然の話をすると、「求人掲載サイトに求人を出すことを検討している企業担当者」を獲得するためにコンテンツSEOに取り組もうとしているのに、「求人に応募しようとしている人」が検索するキーワードを対策してもビジネス的な価値は小さい。
3は日本で月間の検索回数が10回程度のキーワードを対策したとしても、ほとんどの場合、ビジネス的な価値は小さい。月間検索回数を調べるためによく使うツールはGoogleが提供するキーワードプランナーである。
キーワードプランナーの使い方は以下の記事を参照。
https://lucy.ne.jp/bazubu/keyword-planner-43113.html
4,5はほぼ同義だが、特定キーワードの検索結果ページに表示されているコンテンツよりも価値あるコンテンツにしなければ、上位表示されることは難しい。そのため、自社の専門性などをもとに他コンテンツよりも価値提供できるコンテンツを生み出せそうかも、キーワード選定の一つの指標である。
ちなみに、競合サイトが獲得しているキーワードを調査するためにもキーワードプランナーは使える。「ウェブサイトから開始」モードで競合サイトURLを入力すると、多様なキーワードと検索回数が分かる。また、Ahrefs、Semrushも競合サイト調査では王道ツールである。
参考)
https://lucy.ne.jp/bazubu/keyword-planner-43113.html
https://semrush.jp/
https://ahrefs.jp/
6について、諸々の条件を満たせるキーワードを見つけられたとしても、対策難易度が高いとコンテンツの力だけでは対策することが困難である。Ahrefs、Semrushなどで難易度をチェックしておく必要がある。ただし、ツールの難易度は参考程度なので目視で検索結果ページを確認し、強力なサイトがないかもチェックしておこう。
強力なサイトは官公庁サイト、特定ジャンルの第一人者・専門家のサイト、有名なサイトなど。
参考)
https://ja.semrush.com/blog/seo-keyword-difficulty/
https://ahrefs.com/ja/keyword-difficulty
これらの問いを考慮しつつ、まずは主軸キーワード(呼び方は人によって違う)を決める。主軸キーワードとは、「人材紹介」「採用戦略」「人手不足」などの単一キーワードを指すことが多い。
主軸キーワードを決めたら、次に掛け合わせキーワード(呼び方は人によって違う)を調査する。「採用戦略」が主軸キーワードの場合、「採用戦略 フレームワーク」「採用戦略 事例」などが掛け合わせキーワードだ。
掛け合わせキーワードを調査する際によく使われるツールはラッコキーワード。上記例だと、ラッコキーワードに「採用戦略」と入力して検索すると、GoogleやYahoo!などの検索エンジンやYouTubeなどごとの掛け合わせキーワードが網羅的に分かる。
使い方)
https://related-keywords.com/knowledge/137/
ラッコキーワードで調べた掛け合わせキーワードをすべてコピーし、キーワードプランナーの「検索のボリュームと予測のデータを確認する」に貼り付けると、すべての掛け合わせキーワードの月間検索回数などが分かる。
2.選定したキーワードの検索意図・ニーズを推測する
検索意図・ニーズを推測する主な方法は以下。
検索結果の1ページ目に表示されているコンテンツをチェックする
サジェストキーワード、関連する質問、関連性の高い検索(再検索キーワード)を確認する
Q&Aサイトの質問文やSNSで確認する
1は選定したキーワードで実際に検索して、1ページ目に表示されているコンテンツ(記事、動画など)をチェックすること。1ページ目に表示されているということは、そのキーワードで検索している人のニーズを満たせるコンテンツだとGoogleが評価しているため(もちろん、例外はある)。
2は検索窓に対策キーワードを入力した際に、対策キーワードと合わせてどのようなキーワードが検索されているかをチェックしよう。

また、現在の検索結果には「関連する質問」「関連性の高い検索」が表示されることもあるので、合わせてチェックし、検索意図を推測しよう。


主軸キーワードに対する関連性の高い検索(再検索キーワード)を調べるには、再検索キーワード(LSIキーワード)調査ツールを使うと、より網羅的な情報を確認できる。
1,2はコンテンツSEOにおいて多くの人やコンサル会社が実施する。意外と抜けているのが3。
主軸キーワード・掛け合わせキーワードでYahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトを検索すると、そのキーワードに関係する質問が大量に表示される。Yahoo!知恵袋であれば、関連度順、最新順で調査すると、検索結果上位のコンテンツやサジェストキーワードだけからでは推測しきれなかった検索意図を発見できることもある。
Xでも同様に検索し、話題順にソートしたり、RT100以上などのコマンドで検索すると、同様に思わぬ検索意図や話題を発見することができ、重要なコンテンツ制作の材料になる。
参考)
X検索コマンド
https://hinakira.com/twitter-x-command-search-method/
3.推測した検索意図・ニーズに対して120%応えられるようなコンテンツのアウトラインを制作する
ここまで準備してきた材料をもとに、コンテンツのアウトラインをつくっていく。
アウトラインの要素は主に以下のようなもの。
タイトル
見出し
本文
結論
(クロージング)
この段階でタイトルまでつくるかは人によるが、仮案でつくっておくと見出し・本文を考えていく際の指針になる。
アウトラインは以下のようなもの。
------------
タイトル:最前線の採用戦略!効率的かつ効果的な人材確保のための実践ガイド
1.採用の新常識:質の高い採用プロセスがもたらす巨大なリターン
1−1.成功企業の採用データ分析
- 成功企業の採用成功率とその影響
- 効果的な採用プロセスの共通点と特徴
1−2.効果的な採用が可能になった背景
- テクノロジーの進化とAIの活用
- 労働市場の変化と求職者の価値観の変動
→ 1−2の結論:市場は変化し、今がチャンスの時。
2.採用成功の分岐点:失敗と成功の要因
2−1.一般的な失敗例とその原因
- 不適切な職務記述と求職者のミスマッチ
- 選考プロセスの非効率性
2−2.採用プロセスの質とスピードがカギ
- スピーディな選考プロセスの実現方法
- 採用の質を保証するためのチェックポイント
2−3.市場と技術の変化に適応する採用戦略
- デジタル化とオンライン化の進行
- 選考基準の透明性と公平性の確保
3.採用戦略の全体構造
3−1.効果的な採用戦略の構築
- 採用目標の設定と戦略的アプローチ
3−2.採用プロセス全体のフローチャート
- フローチャートの具体例
- 使用ツールとテクノロジー
3−3.各ステージで求められる採用の質
- 書類選考、面接、オファーまでの各ステージ
- フィードバックと改善点
4.採用戦略の具体的な方法論
4−0.採用プロセスの設計初期段階
- 目標とするタレントの特定
- 選考基準と評価方法の確立
4−1.効果的な求人広告の作成方法
- ターゲットに合わせたキャッチコピーと内容
- 求人広告の分析と改善ポイント
4−2.面接プロセスの最適化
- 面接官のトレーニングとガイドライン
- 面接の効果を最大化するテクニック
4−3.採用後のオンボーディングとエンゲージメント
- 新入社員の早期適応を支援する方法
- 長期的なエンゲージメントと保持戦略
5.まとめ: 採用の新たな展望
- 採用の効果を最大化するための組織全体の取り組み
- 常に進化する市場と技術に適応する採用戦略の重要性
結論・クロージング:最前線の採用戦略は●●だ。採用戦略策定のご相談は●●社までお問い合わせください。
------------
見出しごとにどのような内容をライティングしていくか分かるように箇条書きなどでメモしておくと良い。
4.ライティングする
アウトラインを作ったら、文章をライティングしていこう。
とにかく読者の目線になって、「どのような文章なら、どのような情報をいれたら、読者にとって役に立てるか」を念頭におきながらライティングしていると、最初に作ったアウトラインよりも「ここはもっと詳しくした方が良いな」「ここはいらないな」「こことここの見出しの順番を変えよう」といった考えが出てくる。
随時、アウトラインを調整しながら、想定読者への思いを馳せてライティングしていこう。
5.コンテンツをセルフ編集する
ライティング後、可能なら自分で以下のような観点で編集してみよう。
(ちなみに本記事はセルフ編集をしてないです。これも現実ですね。。)
誤字脱字がないか?
主語述語が合っているか?
改行した方が読みやすいのではないか?
1文が長すぎないか?
表記が統一されているか?
平易な表現になっているか?
抽象的すぎる表現になっていないか?
読んだ人が実行できるくらいに具体化されているか?
セールス要素ばかりになっていないか?
読者の悩みを解決できているか?
タイトルとずれていないか?
他のコンテンツよりも有益か?
語調は統一されているか?
その後、できれば他の人にも編集してもらおう。自分だけでは発見できないミスや改善点もあるものだ。
ライティングを外注している場合は提出されたコンテンツを上記観点で編集し、外注先にフィードバックしよう。
トピッククラスターモデル
SEO戦略の一つにトピッククラスターモデルと呼ばれるものがある。

(引用:https://lany.co.jp/blog/topic-clusters/)
上記図のように、メイントピックとなるピラーページがあり、その周りにサブトピックとなるクラスターページを配置していくような構造がトピッククラスターモデルである。
つまるところ、ピラーページはまとめ記事で、まとめ記事内で取り上げたテーマを個別に制作したページをクラスターページと呼んでいる。
上記したアウトラインの記事をまとめ記事(ピラーページ)とし、各見出し(「採用の新常識:質の高い採用プロセスがもたらす巨大なリターン」など)ごとにさらに詳細な内容を記載した個別記事をつくっていき、まとめ記事からそれぞれの個別記事(クラスターページ)への内部リンクを設置することで、ピラーページ・クラスターページ双方の評価を高めようって考え方。
このトピッククラスターモデルを実行することで、検索上位を狙いにくいビックキーワードで上位表示できる可能性を高くできる。
キーワード選定する際にも、このトピッククラスターモデルの考え方をもとに、主軸キーワードと掛け合わせキーワードを整理していくのをおすすめする。
より詳細は以下の記事を参照。
https://lany.co.jp/blog/topic-clusters/
ぜひとも読んだ方が良いコンテンツSEOに関する記事(こういう記事がコンテンツSEOの勝者)
ここまで私なりにコンテンツSEOについて述べてきたが、以下の3つの記事はぜひとも読んでほしい。
https://lucy.ne.jp/bazubu/contet-seo-18508.html
https://lucy.ne.jp/bazubu/how-to-create-a-good-content-17943.html
https://lucy.ne.jp/bazubu/good-content-40702.html
余談だが、私にとってめちゃくちゃ価値があると思い、誰かにおすすめしたくなるこの3つの記事は、まさにコンテンツSEOの勝者である記事であり、検索上位表示するような記事。
ただ、「検索1位の記事を読んだけど、いまいちな内容だった。。。」みたいな体験をしたことがある人も少なくないと思う。これらの記事にも記載されているが、「検索上位=価値あるコンテンツ」とは限らないし、「シェア数が多い記事=価値あるコンテンツ」とも限らない。SEOはやっかいな世界なのである。。。最低限の内部SEOはして、より価値あるコンテンツづくりをし続けるしか勝ち目がない。
7.SEO施策でよく使うツール
随時更新
まとめ~非営利法人がSEO対策するのはマジで有効~
NPO・非営利団体の方が寄付者を獲得するため、支援者にアウトリーチするためにSEO対策を実施していくのはかなり有効であると、ペアチルで実践していて思います。
分かりにくい点もあったかもしれませんが、ぜひその点はさらに学習を追求できる点と捉え、検索等で補っていただけますと幸いです。
もしミスがあれば、本当にすみません。
デジタルマーケティングは日本の社会問題を解決するために欠かせないものと考え、これまで人生をかけて実践しつづけてきました。
そんな自分にもし相談してみたいことがあれば、お気軽にご連絡ください。
社会問題×マーケティングが好き / ㍿小さな一歩(前澤ファンド出資先)で養育費の未払い問題にビジネスでトライ→㍿SHIRO創業。社会問題の発見→要因分析→ビジネス考案→実行に必要な資本整備→実行・改善のサイクルが最短で回り社会問題が解決されつづけるインフラを創る。
