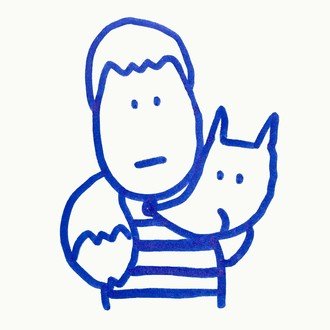2019年11月の記事一覧
適応障害になると、あれもこれもうまくいかないようになり、すごいストレスです。
脳からの指示が身体にうまく届かないので、器用にできなかった子どものころに戻ってるようなもんです。
できる範囲でいいし、本当に完璧にやらなきゃまずいっけ?と自分に問いかけてみてください。
人間の生理的欲求って、それができないと健康を損ねたり、種の維持ができないってことで「食欲」「睡眠欲」「排泄欲」「性欲」とかなんですが、ふつう意識なんかしなくても求めてるものです。
要するにこのへんがめんどくさくなったり、興味がなくなって数週間もたってると「うつ」ですよ。
うつ傾向が強いときって自律神経が乱れてるので、日常的、習慣的なことができなくなったり、コントロールがきかなくなってきますので、目安にしましょう。
具体的には、洗顔、歯磨き、お風呂、着替えなんか、もうめんどくさすぎてできなかったり、過食、小食、過眠、不眠になったりします。
ちょい前から鬱とかパニック障害に関しての私見を投稿してるんですが、いまさらなんですが、パニック障害10年選手でして、またある程度、障害福祉の現場に関わってるんで、なんか参考くらいになったらなと思って書いてってます。結構出尽くしてる感はありますが。
自分でうつの傾向だと認識できる間に、積極的に身体を動かすようにしましょう。
運動でなくても、自転車や、散歩や柔軟体操で十分です。下半身が温まると幾分か楽になり、熟睡できるようになります。
また昼夜逆転しがちですが、夜明け前に寝るより、朝日だけ浴びてから寝るようにしましょう。
鬱と適応障害(パニック障害)はセットになる事が多いです。あらゆる日常生活が不安と怖さになり、何が引き金でパニック発作が起きるかわからず、発作は命には関わりませんが、目眩、動悸、手足の痺れ、周りの目も怖くなり、心が閉じていきます。何も感じないよう感受性を閉じて鬱状態になります。
子どもとワークショップをしていると親御さんが「そうじゃないでしょ!」と口を出してしまうことがあるのですが、そんな時こそスタッフが「これもいいね」「工夫があって面白いね」とこどもと親にむけて声をかけてあげることで、その親子の何かが変わるかもしれません。
「待てない」親が多いんです。
先に答えに導いたり、正解を言ってしまったりして、こどもが自分で思い出したり考えたりする大切な機会を無くしてしまいます。
わかりきったようなことでも、こどもが「うーん」と考える時間の積み重ねが自発的な思考力を鍛えます。
こどもが支度を早く出来なかったり、早く食べられなかったりすることに対して親が怒っているとき、それは、親が子どもに押し付けている理想が実現しないことに腹を立てています。
こどもは自分のペースでできることをやっているだけ。ふざけて手間がかかるのも、それもその子のペースです。