
犯罪者の保身と欺瞞のメカニズム|杉江松恋・日本の犯罪小説 Persona Non Grata【第5回】
▼前回はこちら
文=杉江松恋
権力者からどん底の貧困に喘ぐ者まで。
犯罪という現象を切り口として個人と社会との本質的な対立関係が露わになる状況を描く。そう定義するならば、松本清張ほど社会の全相にわたって犯罪小説を書いた作家はいない。
清張だからこそなしえた、と思わされる作品がこの作家にはいくつもある。『日本の黒い霧』(一九六〇年。文春文庫)はその一つで、一九四五年から五二年の占領期に起きたさまざまな事件をノンフィクションの形で書いた連作である。この中ではGHQという当時の最高権力者が犯罪の主体としてしばしば指弾される。占領体制維持という目的の前には、個人の生命は限りなく無価値なものとなる。そうした非情が描かれた作品なのだ。
そうかと思えばこの世の最底辺を描いた小説がある。追い詰められた人間は人間ではなくなる。自分の身を守るためには他者を排除することを厭わない。そのとき他者は人間ではなく単なるモノになるのだ。そうした倫理観の極限状況を描いたのが殺人の小説である。
「鬼畜」(『張込み』他所収。新潮文庫)は、題名通り人間ではなくなってしまった人物を主人公とする小説である。この作品は一九五七年、『別冊文藝春秋』四月号に発表された。後述するが、清張が推理小説作家としての才能を開花させた年である。竹中宗吉は印刷所を経営して小金を蓄え、菊代という女性を愛人にする。しかし経済状態が破綻すると手当てを払えなくなり、激怒した菊代は自分に産ませた三人の子を宗吉に押しつけていずこかへ去ってしまう。宗吉の妻であるお梅は、三人の存在を許さず、宗吉に非情な行為を促す。棄児である。
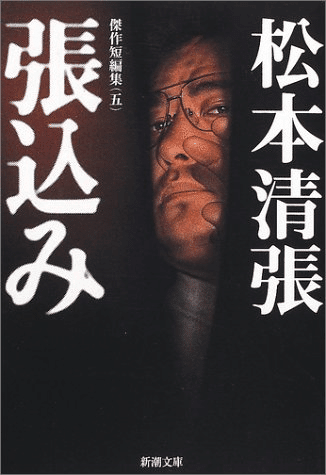
すべての清張作品で「鬼畜」ほど恐ろしい小説はない。本作は清張が親交のあった河井信太郎検事から聞かされた実話が元になっている。こどもが無残に見捨てられる場面が緻密なリアリズムによって描かれていく。たとえば長女である良子を宗吉がデパート屋上に置いてくる場面はこうだ。
――彼はそこを離れた。屋上から下に降りる入口で振りかえってみたとき、どういうつもりか、良子がこっちを向いていた。強い陽射しで顔は真っ白であった。髪の毛だけが燃えるように赤い。彼は少しあわてたが、それなりに後も見ずにエレベーターに乗った。
「あれは、おれの子ではない」と自分に言い聞かせながら帰宅した宗吉をお梅が出迎え、夜は身体を求めてくる。「一人の始末がつくごとに、この女は興奮して燃えてくる」のである。棄児によってこどもの生命を見放すというタナトスがエロスを掻き立てる。無残絵だ。一般家庭で行われる育児放棄や児童虐待に注目が集まり、創作の題材とされるようになるのは「鬼畜」よりもはるか後のことだが、子殺しが性的興奮につながるという非人間性をあからさまに描いている点に感嘆させられる。野村芳太郎監督で一九七八年に映画化されており、緒形拳と岩下志麻の鬼気迫る演技によって迫力ある作品に仕上がっているが、読む者の心を凍りつかせるような非情は小説表現ならではのものだ。
読者の心理を誘導して効果を上げるためには、推理小説作家は文章の彫琢を怠ってはならないと清張は考えていた。一九六〇年に発表した「推理小説の文章」(『松本清張推理評論集1957―1988』所収。中央公論新社)でも「文章は、たんに説明だけではなく、それ以外のいろいろな要素――色彩感情やリズムを読者に与えて、あたかも、さまざまな陰影が、オーケストラにおける各楽器の渾然一体となって一つの演奏をしているようなもの」とし、ただし「異常な事件であるから背景もまた異常でなければならぬというのは間違い」「むしろ、近ごろは内容の異常さに対比して、描写も押さえ、背景もきわめて日常的なものを選んで効果を高める方法が新しいのではないか」と書いている。「鬼畜」における良子遺棄の場面で言えば、デパート屋上を背景としたからこそ、行為の残虐さは際立っているのである。

「鬼畜」についてもう一つ書いておかなければならないのは、宗吉・お梅の犯罪が生きるためのやむにやまれぬ行為ではなく、エゴイズムに起因するということだ。三人の子を残しておいても竹中家が即座に飢えるというわけではない。お梅は夫が他の女に産ませた子が憎いという嫉妬心から宗吉に棄児を強制する。宗吉はお梅に逆らうのが怖いという理由からそれに従うのである。追い詰められるといっても宗吉のそれは単なる無気力のなせる業で、つまり保身のエゴイズムにすぎない。
「鬼畜」と同年の『文學界』一九五七年八月号に清張は「カルネアデスの舟板」(新潮文庫『張込み』他)を発表している。この題名は、自分が助かるために他の者を殺して舟板を独占しようとする遭難者の行為は罪に問われないという、緊急避難の事例を表すものとして用いられる。だが、この作品で描かれるのは緊急避難ではないのだ。ある大学教師が、かつての恩師が自分の地位を脅かす存在になりつつあることを危険視し、策謀をもって排除しようとする。恩師をそのままにしておいても彼の生存自体が脅かされるわけではないのだから、これを緊急避難と呼ぶのはエゴイズムから発した欺瞞だ。犯罪者の心中に存在するこうした欺瞞を書くことが清張犯罪小説においては主題の一つになっている。
大袈裟に言うなら、日本の犯罪小説は松本清張がその原型を準備したと言っていい。
人間が犯罪という極端な行動に走る姿を描くためには、動機の追究が不可欠である。日本の推理小説には動機が十分に描かれていないという欠点があり、そこを深化させていかなければならないと主張したのが松本清張だった。厖大な数の作品を書くことで清張は自ら範を示した。長篇にも数々の名作があるが、短篇執筆によって成し遂げたものはさらに大きいと思う。清張は無数の推理小説短篇を書いた。それらは月刊・週刊の雑誌に掲載され、多くの人に読まれた。そのことは以降に発表される推理小説の質に大きな影響を及ぼしたであろう。人間の中に殺意が生まれて成長していく過程や、自らの中に渦巻く妄執によって破滅していく犯罪者の悲喜劇が作品の主題として成立しうるという可能性を日本の読者に示したことが清張の、推理小説作家としての最大の功績なのである。
清張が推理小説界の旗手と見なされるようになったきっかけを作ったのは、一九五八年に単行本として刊行された『点と線』『眼の壁』(ともに新潮文庫)の二長篇である。これらがベストセラーとなったことが、いわゆる〈社会派推理小説〉ブームを招き寄せる。当人が社会派たることを目指したわけではない。推理小説について清張が考えていたことは、一部マニアのみが喜ぶような作品では「何ら人間性の盛り上がりもなく、奥底に内在する心理描写の追究もなされるわけもない」から「社会性のある熱い動機ととり組み、この動機の主張から人間を描写する手法を勉強しなければならぬ」(「推理小説に知性を」前掲書)ということだった。念のために記せば、清張はトリックによって支えられる推理小説を積極的に肯定しており、風俗小説的な安易さや、題材の煽情性だけを求めるような作品が社会派を名乗ることを否定していた。推理小説の理想を追い求めるならば、現代の小説にふさわしい人間と背景が描かれるべきであるという確固たる信念を持っていたのである。こうした姿勢を持つ作家は、必然的に優れた犯罪者小説、犯罪小説の書き手となるだろう。
清張が本格的に小説執筆を始めた時期は遅い。一九〇九年に福岡県企救郡板櫃村(現・北九州市小倉北区)で生まれた清張は十代で印刷工の職人として働き始め、二十八歳のときに朝日新聞の広告版下を書くようになり、その縁で三十歳で同社に入った。清張が二十歳のとき、友人がプロレタリア文芸誌を購読していたため赤狩りに遭うという事件があり、それに驚いた父親から読書を禁じられた。以降まったく党派的な文学活動とは無縁になる。独立不羈の気風はこうした環境からも養われたものではないかと思われる。
一九五〇年、『週刊朝日』の〈百万人の小説〉に応募した「西郷札」(同題新潮文庫他)が三等に入選し、四十一歳という当時としては遅い年齢でのデビューを果たした。この作品を『三田文学』編集委員であった木々高太郎に送り、推理小説の領域に入るか意見を求めたところ、好評されたという。木々は一九三六年に甲賀三郎との間でいわゆる探偵小説芸術論争を繰り広げた経緯があり、推理小説を文学的に高め、領域を拡大していきたい意志を持っていたのである。清張が木々と接触した時点ではジャンル作家になる意志はなかったが、後の活動につながる素地は既にあったのだろう。この縁が元で『三田文学』に「記憶」(後に「火の記憶」)、「或る『小倉日記』伝」の二篇を寄稿、後者で一九五三年に第二十八回芥川賞を獲得した。
この二篇は清張の資質を示す重要な作品である。「火の記憶」は幼いころに父が失踪した男性の記憶を巡る物語で、彼が母に連れられて見た風景から意外な事実が導かれる。推理小説ではないが、謎の魅力と真相開陳への関心が読者を牽引する構成になっており、現在であればその範疇に入れられてもおかしくない。「或る『小倉日記』伝」は森鴎外の小倉時代を調査することに生涯を捧げた田上耕作という人物が主人公である。田上は生来の障害のために周囲から差別され、母のみが唯一の理解者となる。他人から理解されないところで自分の信念を貫き続けた人間を、清張は好んで題材とした。その嚆矢である。社会と個人の相克という犯罪小説の基盤にもなる重要な主題が、ここに表れている。歌人・杉田久女をモデルとした「菊枕」(一九五三年)、閉鎖的な考古学界を憎悪する在野学者を主人公とする「石の骨」(一九五五年。ここまですべて新潮文庫『或る「小倉日記」伝』所収)など、社会と相容れない生き方をする者の小説が初期には多く書かれている印象がある。
当初は時代小説作家と目されていたためそうした依頼が相次いだが、舞台を過去に取った作品でも執筆の姿勢は現代小説と変わらなかった。泰平の世における戦国武将の不満を描いた「三河物語」(後に「廃物」。光文社文庫『青春の彷徨』)、佐々成政を主人公とする「ひとりの武将」(同)は、社会の中で取り残された個人を描いた小説である。歴史的過去を舞台としても、清張は現代に通じる人間心理描写を主題とした。
清張が推理小説と本格的に向き合う契機となった作品は『小説新潮』一九五五年十二月号に発表した「張込み」である。逃亡中の犯人には三年前に別れた女性がいた。その許に犯人が立ち寄る可能性があるため、柚木刑事が九州まで出張して彼女を監視する。同作は逃亡犯ではなくその別れた情人に焦点を当てた点が卓越であり、別れた男と刹那の邂逅を果たした瞬間を中心として、彼女の人生が鮮やかに浮かび上がる。それを刑事の視点で描いたことにも意味があった。『清張とその時代』(二〇〇九年。双葉社)において郷原宏はこの柚木刑事視点を「推理する眼」と呼び、こうした登場人物の発見が清張のいわゆる〈社会派推理小説〉の道を開いたのだと指摘している。〈社会〉とはこの場合、主人公の備えた濃密な生活感や職業的リアリティを意味するのである。
「張込み」の成功によって清張は時代小説から推理小説へと転じることになる。「張込み」と一九五六年に発表された五作品を収めた短篇集『顔』(講談社ロマン・ブックス)によって一九五七年には第十回日本探偵作家クラブ賞(現・日本推理作家協会賞)を獲得、同年には『点と線』『眼の壁』の連載が開始するのである。前述したように清張が推理作家として名を揚げたのはこの二長篇がきっかけだが、一九五〇年代後半の短篇を改めて読み返すとその質の高さに感嘆させられる。〈推理〉の小説であることはもちろんだが、犯罪者心理を描いたものとしても他に類例のない着想が詰まっているのである。
たとえば、殺人などの重罪を犯した者が、その露見を怖れる状況を描いた作品群がある。「共犯者」(一九五六年。新潮文庫同題他)では、銀行強盗で大金を手にした男が正業を興して成功する。だが心配の種はかつての共犯者で、彼が零落して自暴自棄になっていないか否かを、人を介して監視させる。また、「顔」(一九五六年。新潮文庫『張込み』他)では自分を視認しうる唯一の証人を犯人が誘き寄せて殺害しようとする。これとは別に、初めから策を講じて凶行に臨む犯人を描いたのが「捜査圏外の条件」(新潮文庫『駅路』他)、「一年半待て」(同『張込み』他)などの諸作だ。後者は清張短篇の白眉として名高く、犯人の周到な計画がある一点のみ挫折したことを表す最後の一行が見事だ。
そうした計画的なものではなく、突発的な殺意を描いた作品もある。「発作」(一九五七年。新潮文庫『共犯者』他)がそれで、最後の藁一本が駱駝の背を折る、という英語のことわざにあるように、鬱屈した感情がご些細な出来事によって決壊する。人を犯罪に駆り立てる異常心理が描かれた小説であり、現在であればサイコスリラーに分類されるかもしれない。「二階」(一九五八年。新潮文庫『黒地の絵』他)はある女性が突発的に死を選ぶまでの小説で、非常に屈折した思考によって彼女は自身の愛情を貫こうとするのである。
こうした作品は確かにまとまって書かれてはいるが、「張込み」後の清張がいきなりその路線に転じたというわけではなく、もともと準備されていた引き出しが開けられたのである。その証拠に「張込み」前にも犯罪者心理を描いた作品は書かれている。一九五四年の「恐喝者」(新潮文庫『共犯者』他)「赤いくじ」(新潮文庫『或る「小倉日記」伝』他)は共に、ある経緯から女性を汚す自分を正当化するようになる男の話だ。前者では水害から救った女が自分を強姦者と勘違いしたことから、彼女を恐喝するようになる。後者は戦争の性犯罪を描いた先駆的な作品で、敗戦地でアメリカ兵に女性を慰安婦として差し出すための抽選が行われる。ある婦人が選ばれるのだが、それまで彼女を高嶺の花として見ていた男たちが、一転性欲の対象とするようになり、争奪戦が行われる。こうした人をモノとして見る視線の先に犯罪小説が書かれる土台があることは言うまでもない。
清張の推理小説短篇は一九五八年に『週刊朝日』で始まった『黒い画集』(新潮文庫)連作で完成形に到達する。人を死に追いやった男の視点を用いた「遭難」、エロスとタナトスの融合した過去の犯罪を回想形式で書いた「天城越え」、浮気相手に執着する男が次第に狂を発していく「坂道の家」など、一作ごとに異なる形の犯罪者が主役を務め、その心理があるいは主観で、別の作品では客観的な外形描写で綴られていく。以降の清張推理小説はこのバリエーションなのであり、『週刊文春』に『別冊黒い画集』(一九六二年。文春文庫)、再び『週刊朝日』に『黒の様式』(一九六七年。新潮文庫)と、同様の連載が幾度も行われている。これを読んだ後続作家たちに与えた影響も計り知れないはずである。
以降の短篇から一つを選ぶなら一九七二年の「理外の理」(新潮文庫『巨人の磯』他)を挙げたい。独創的なトリックを出すことに意外なほど拘った清張会心の一作であり、切れ味もいい。物語の中心にいるのは時代から取り残された男なのだが、清張はあえて彼の心情を描かず、幕が閉じられた後で読者が想像するに任せている。読後に浮かび上がるのはなんともねじくれた自我、そして底知れない憎悪なのだ。清張が造形した中でも特に秀抜な犯罪者像だと思う。推理小説の技巧がこうした犯罪者を描くことを可能とした。
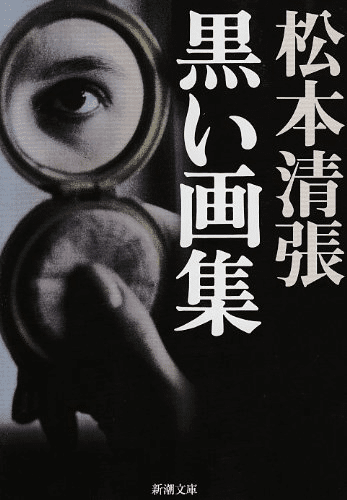
《ジャーロ No.84 2022 SEPTEMBER 掲載》
■ ■ ■
▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
この記事が参加している募集
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
