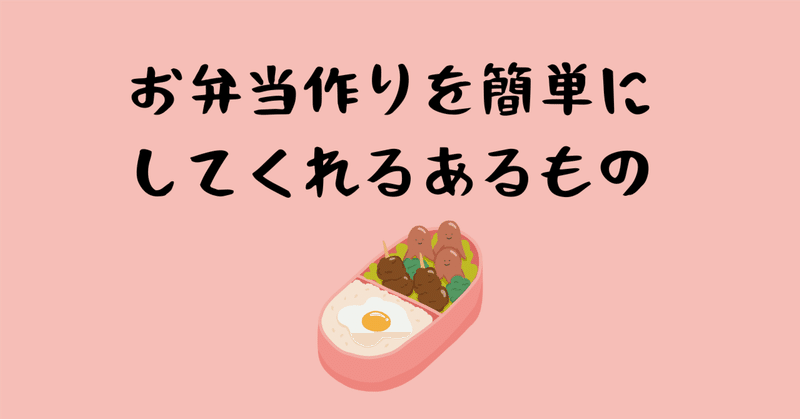
お弁当作りを簡単にしてくれるあるもの
noteでお互いフォローし合って、記事を読み合ったり、時々コメントをし合う仲になる。noteを続けていると、そういう仲間が増えていきます。書くことに付随する、noteの醍醐味の一つですよね。
そんな仲間の一人にhitomiさんという方がいます。実際にお会いしたことはないのですが、勝手に友達みたいな感覚をもっています。
hitomiさんは、定期的に一週間の振り返りを日記形式で綴られています。その中に、お子さんに作られたお弁当の写真がよく載っています。わたしは、その写真をひそかに楽しみにしているのです。
記事の中から写真を抜粋して載せようかとも思ったのですが、無断で写真を引っ張ってくるのも気が引けたので、気になる方はぜひ上の記事に飛んでみてください。
写真をみると、栄養のバランスだけでなく、彩りにも配慮されているのが伝わります。おいしそうな上に、美しい。
なによりわたしが感心してしまうのは、お弁当の四角いスペースの中に、ごはんやおかずをうまく配置していることです。例えるなら、無機質なオフィスの会議室を、手を変え品を変え、毎日趣きの違うモデルルームに仕立てているようです。技を感じます。
栄養のバランス、彩り、ごはんとおかずの配置。これだけでも考えることが十分ありますが、もう一つ大事なことがあります。詰め方です。ただスペースを埋めればいいわけではない。適当な密度で詰める必要があるのです。
詰め方がゆるすぎると、偏ったり、例えばウインナーが違うエリアに侵入してしまったりする。詰め方がきつすぎると、ごはんが固くなったり、柔らかいおかずが潰れたりする。
ごはんとおかずをぽんぽんと並べていっても、スペースがうまく埋まるとは限りません。本当はもうこれ以上いらないんだけど、スペースを埋めるためだけになにかを入れ足さないといけないことがあります(だいたい白ご飯で調整します)。
さらに、温かいものとフルーツを隣り合わせにするとフルーツが温まってしまうとか、味が移っておいしくなくなるなんてことも考えます。なにとなにを隣り合わせにするか。長いもの、短いものをどう組み合わせるか。まるでテトリスのように空間を埋めていくこの作業は、意外に頭を使うし、技術がいります。
わたしには、小学校に通う子どもが2人いて、毎日お弁当を持たせています。わたしは、この空間埋め埋め作業をなんとか回避できないかと考えました。ずぼらな性格なので、技を磨くかわりに、問題を解決してくれるアイテムを探したのです。
そこで見つけたのが、この弁当箱です。というか、アメリカではこの手の弁当箱が広く使われているので、頑張って探さなくてもすぐ見つかりました。

(写真はアマゾンより)
最初からスペースが仕切られているので、一部屋に一つずつ、なにかをぽんぽんと入れていけばいいのです。なにとなにを隣り合わせにすべきかとか、熱いものと冷たいものを離して入れなきゃなどと、考える必要がありません。それぞれがちゃんと仕切られるので、ミートボールの隣にいちごを入れても大丈夫だし、りんごの隣にプレッツェルを詰めても湿気ません。
わたしは、この弁当箱を初めて見たとき、なんて画期的なんだと衝撃を受けました。そうだよ、こういう作りにしたら、弁当作りが何倍も簡単になる。技がなくても、基準を満たすお弁当が作れる。
実際、わたしは、写真にあるような弁当を作って持たせています。主食にサンドイッチかおにぎり、おかずは前日の残りをなにか、それから野菜・フルーツ、部屋があまったらおやつをプラス。
学校のカフェテリアで、子どもたちのお弁当を除いてみたことがあるのですが、おおむね似たような感じです。アメリカでは、朝からお弁当のために火を使って調理する人はごく少数派だと思います。家にあるものを詰めてできあがり。調理するとしても、チキンナゲットを温めるとかそれくらいではないでしょうか。
お弁当作りの救世主。悩みあるところに、解決法あり。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
Xもやっています。繋がってくださると嬉しいです。https://twitter.com/Matsumura_us

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
