
【世代を超えて】 SDGs を学ぶボードゲーム【Z と Y 世代】
最近について更新。
サスティナビリティをテーマとした飲食業界の勉強会に参加したり、最新テクノロジーをつかった事例を調べたり、家族で身近な環境問題について議論してみたり、マイボトルを導入して 500ml ペットボトルの購入機会を減らして、「My Mizu(水がもらえる)」アプリを使ってみたり、スノーピークの ToRain 素材のハット(丈夫で長持ち)を買って、暑い夏に備えたりしています。
さて、またまたボードゲームを使ってのミートアップイベントを実施したので、そのレポートです。
1. 「出会い」は自分で作り、自分で育てる
人間が日々、頭の中で考えていることは、そのまま自分を表現していきます。また、そういった言動を積み重ねていくと、日々、出会う人たちも変わっていくなと感じます。
といっても全体の出会いのパイは世界人口の78億人。日本のコロナ状況ではそれも限定的。制約条件がある出会いもまた相対的に価値があがっているものだと思います。
さて、そういった制約条件について。結構な数の名言を残す我々の恩師でもあるスヌーピー先生に聞いてみましょう。
You play with the cards you're dealt, whatever that means.
配られたカードで勝負するっきゃないのさ、それがどうゆう意味であれね
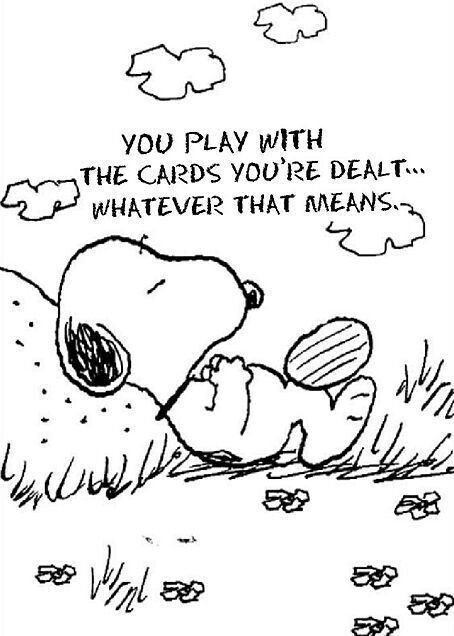
さすがです。スヌーピー先生。そういった条件下の中で、「出会い」をつくって、育てた人がハッピーになるんだぜ!と言わんばかりです。
※ちなみにスヌーピーは「あなたがなぜ犬でいられるのか不思議だわ!」と言われた時にこの名言を放ちます。
2. 日本の歴史にみる「出会い」
日本人の好きな偉人ランキングのトップに必ず入る「坂本龍馬」。彼にも「出会い」がありました。「勝海舟」との出会いです。坂本龍馬の名言は、坂本龍馬が姉に送った現存する手紙の中に書かれています。
「今一度日本を洗濯致し申候」
いまいちど、にほんをせんたくいたしもうしそうろう
これ、ですよね。なんとなく日々の鬱々な政治に関するニュースに対して、霞ヶ関あたりに立って言ってみたいセリフ No.1 ですよね。
そして、他の手紙の中に、下記のような「出会いに関する記述」が残っています。
此頃ハ天下無二の軍学者勝麟太郎という大先生に門人となり、ことの外かわいがられ候て、先きゃくぶんのようなものになり申候。
「(訳)聞いてくれ、姉貴!まじさいっこう!今、日本一の超ホットでクールな勝海舟先生に認めてもらって、一緒に仕事できるようになったよ!ヒャッホーウ!!!」
※ちなみに私が京都で開かれた坂本龍馬展で直筆の龍馬の手紙を見た時はなかなかに感動しました。
すでに、龍馬は土佐藩を脱藩していたため、自由に働ける環境がなかったと思います。
「よっしゃ、あいつ最近有名だし、力を持ってそうだからミーティングしよ(数百キロを自分で走っていくわ)」
と思いたち、他の藩に住む人たちと会合をしたり。手紙を送って、偉い方々や武士たちのもろもろの調整事項をコミュニケーションしたり。
走って会いにいく、といってもそうはできなかったようです。藩、今でいう県的なものをまたぐときには関所があり、通行手形が必要だったようです。
これは、今で言う空港のイミグレを通るためのパスポートが必要だったのですが、脱藩していたので持っていなかったのです(ID 持っていないやべーやつ)。
日本を変革するために、手紙を出したり、縦横無尽にニシヘヒガシヘ移動したりすることも、勝海舟との出会い(勝海舟が色々と裏で調整してくれた)があったからこそ、とされています。またそれに呼応して、坂本龍馬自身も勝海舟のために尽力しています。
彼らの出会いのきっかけは、坂本龍馬自身が勝海舟に会いに招待状を受け取って、「日本をどうするつもりか!?」と突撃訪問インタビュー(仮)しにいったこと、とされているようです。日本を動かした二人の出会いってそういうものだったんですね。

33歳で亡くなった龍馬は地球一周半ほどの距離を走り続けて、仕事をしたそうです
引用:https://ja.m.wikipedia.org/wiki/坂本龍馬
3. ハーバード大の研究にみる「出会い」
1938年に始まったこの超長く継続している研究分野。出会いや人間関係が与える幸福度に対する人間の研究です。TED でもとても話題になりました(動画貼っときます)。
どんな研究なのか。
それは、「比較的経済的な裕福でありつつ、同大学を卒業した学生」と、「ボストンの極貧環境で育った少年たち」に対して何十年もかけて追跡調査しつづけるものです。
毎年、本人たちへの聞き取り調査と健康診断を行いつつ、質問票調査、本人や家族への聞き取り調査、医療記録の確認、血液検査等を行い続けています。殆どの対象者が90以上、亡くなったり、高齢者になりつつも続けてきたもの。
そして、研究成果として、結論付けられたことは、「良い人間関係」こそがその人の幸せを築き、健康的に長生きをするということ(その人の地位や名誉、経済的裕福度について、それらは依存しない)。
ƒそして、動画の最後に本研究の4代目の責任者であるロバート・ウォールディンガー教授が締めくくります。
この TED の公演をみた人たちへ「いますぐ自分たちがなにをすべきか」。そして、マーク・トゥエイン氏(トムソーヤの冒険の著者)の言葉下記のように引用されて、プレゼンを終えています。
“There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that.”
超ざっくり訳すと「とかく人生は短い。人生は愛しあうこと。それは一瞬なのかもしれないが、そのためだけに時間を使いなさい」。
なるほど!やはり「出会い」はとても大切な気がしてきました。
4. 六本木・麻布で出会うボードゲーム
そんな「出会い」が起こせるのか。日々考えながら、いろんなミートアップイベントをプロジェクトにして進めています。
さて、今回の「出会いの場所」は、にぎやかな六本木から閑静な麻布エリアに移動して、そんな素敵な場所に鎮座ましましているグランドデザイン株式会社さんのオフィスです。
そのオシャレなスペースをお借りし、SDGs のボードゲームを通じて、ZとY世代がつながる「場 」を提供してまいりました!

グランドデザイン株式会社さんでサービスの開発をしているエンジニアやデザイナーさん。主に Y世代な方々と、現役の大学生さんたち (Z世代)のプレイの様子です。
このYとZ、隣り合った世代の違い(10年ちょっと)だけでも大きな価値や共感ポイントの格差が広がっていることが参加者された方々も感じた部分があったと思います。

参加した方々は社会問題や環境問題、自分たちの時間の使い方や、何に(時間を)投資していくかという部分については共通項となっている価値観になっています。
間違いなく、2030-2050年頃の日本を作っている世代の張本人になりそうですし、次世代リーダーの方々なんだろうと思います。
大切な時間を使って、この場に、自分の意思と足で駆けつける人たちなのですから。

5. 現役の学生さんのプレゼンと社会と地方創生
現役学生で一緒に事務局をしてくれた小川さん。
彼も次世代リーダーとして、駆け回っています。
学生という忙しい日々。
バイトや友人と遊ぶこと、そして講義やテストなどの学問以外に時間を投資していること。
それは、「日本の地域や地方を少しずつよくしていくこと」。おぉ、まさに現代の坂本龍馬ですよね。

学業の傍らに、みかん農家の方々を支援して、農家が伝えたいメッセージや商品の魅力、事業における課題の解決に取り組む。
「栽培の課題である一次産業」、「加工に関する課題である二次産業」、そして「ウェブやリアル店舗などの三次産業」に亘り、みかん農家を通じて、日本を少しずつ改革していこうと実践しています。
そのような「出会い」を大切にする彼に集まる友人たち。
彼の意思や行動力に共感し、賛同して集まる仲間も、スヌーピー先生がいうように、坂本龍馬がそうであったように、ハーバード大学の研究成果のがいうように、出会いから人生が楽しくなる方向に動いていくんだと思います。
多分ね!(小川くん、また年取って、オッサンになったら教えてください)

6. 今後は自分が主人公
ボードゲームの締めくくりには、グランドデザイン株式会社の村尾さんが、会社のミッションや研究に関する分野のライトニングトークを実施してくれました。
社会課題を解決するための仕組みやサービスの概念。
そして、人間の脳に対するアプローチ、「報酬回路(喜びたいから続けたい)の設計やマリオブラザーズのゲームの勝ち条件に通じるユーザ体験の重要性。
リアルな実ビジネスに直結していくような話に、その場にいる学生さんたちも引き込まれていました。こういった「出会い」を成長させて、長いご縁に昇華していくためには「自分が主人公」になったつもりで動いていく必要があります。

ぜひ、フォローアップの活動や企画を自分たちで作り、周りを巻き込んで、近しい人たちとコミュニケーションをとってください。近い世代だけど、実は遠い世代である Z と Y のギャップがなくなり、世代を超えた面白い取り組みやプロジェクトが生まれていけばと思います。

グランドデザイン株式会社さんのサービス(生活者と店舗・ブランドをつなぐプラットフォーム)はこちら。
それでは!また次回!
YOSHIFUMI OKADA | DIGITAL PROJETISTA
with.generation.2021@gmail.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
