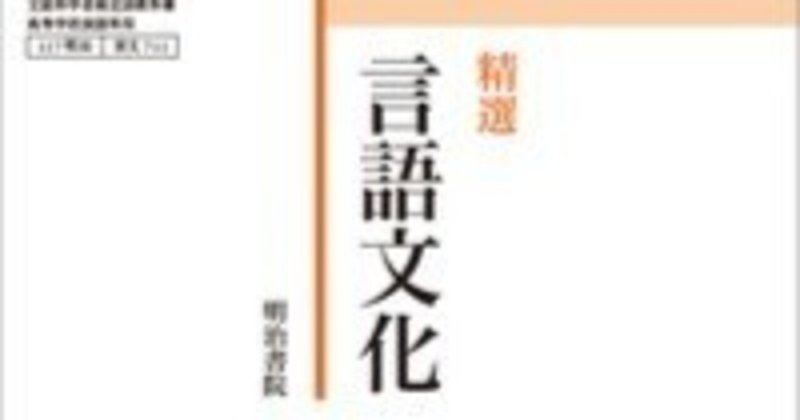
『青が消える』村上春樹をどう読むか‐②‐
『青が消える』村上春樹
科目:高校1年言語文化
教科書:明治書院
前回は、「ポスト・モダン」をキーワードに村上春樹さんの「青が消える」を読んでみました。主に書体に注目した読みで、作品の内容にはほとんど触れていません。
今回は、内容に踏み込んで読みを深めていきたいと思います。
今回のキーワードも「ポスト・モダン」です。
私は徹底して「青が消える」をポスト・モダンの作品として捉えています。
さて、改めてポスト・モダンという用語を考えてみます。
この言葉を広めたのはリオタールというフランスの哲学者です。彼の著した『ポスト・モダンの条件』という書籍が、この言葉のスタートなのです。
リオタールはまず、モダン(近代)という時代を〝大きな物語〟が力をもった時代だった〟と考えます。
大きな物語とは、その時代を生きる人々全員が信じることができるような、力強い物語のことです。
例えば、科学が進歩すればどんどん人の生活はよくなるだろうという物語がありました。あるいは、自由や権利が認められることで、差別や偏見がなくなり、人々はもっと生きやすくなるだろうという物語や、資本主義が発展していけば、世界中の人々が豊かになるという物語もありました。
要するに、近代という時代が前提としていた成長神話のようなものです。産業革命でものすごく効率的な生活を送ることができるようになった先進国の人間が抱いた幻想ですね。
ここで出てきた〝物語〟や〝神話〟という単語は現代文では重要です。
どちらも「根拠がないのに人々が信じ込んでいる何か」というニュアンスをもっています。つまり、あまりいい意味ではないのですね。
そんな感じで、リオタールも「大きな物語」を特に肯定的なニュアンスでは捉えていません。根拠もなく信じられていた価値という点ではむしろ否定的なくらいです。
では、「大きな物語」はどんなところが間違っていたのでしょうか?
この答えとなる事実は、現代では枚挙にいとまがありませんね。
〝科学の発展が環境にいかに深刻なダメージを与えたか〟
〝近代兵器が戦争においてどれほどの被害をもたらしたか〟
〝自由や権利の名のもとにどれほどの人々が争い合ったか〟
〝資本主義がどれほどの格差をもたらしたか〟
近代をいつまでと考えるかは難しいのですが、20世紀後半を近代の終焉と考えれば、そこで起きた様々なトラブルが近代の価値観の崩壊をもたらしたということができるでしょう。
公害問題や戦争は、人々が絶えず成長し続けるという物語の力を無効化したのです。
もはや、「未来はきっと良くなる」という世界の見方を無批判に受け入れることができる人はいないでしょう。
今を生きる私たちはもう「大きな物語」の中で生きることはできないのです。
この「大きな物語」の失墜からポスト・モダンの時代が始まるのだ、とリオタールは語っています。
では、現代はどのような価値観が力をもっている時代なのでしょうか?
それは、「小さな物語」です。
これはまず何よりも、「大きな物語」がもっていたある種の希望に対して、「効率」という価値観が力をもっているという主張です。
社会全体を包み込むのは「平和」とか「豊かさ」といったものではなく、単にいかに「効率的」であるかだけなのです。
かつての「大きな物語」は社会全体を包み込むものでした。例えば、日本は技術大国だという物語を日本人全員が信じていたように。
一方で、「小さな物語」は小さな単位で、あるいは個人で信じられるものです。
〝私は好きなアイドルのグッズを買うために生きる〟
〝私は家族との時間を楽しむために生きる〟
〝私は人生は無意味だと思うから何もしない〟
以上のように、現代の人々はそれぞれの価値観を大事にして生きているし、その権利を他者が奪うことも簡単にはできないでしょう。
人々はそれぞれに、自分にとって「効率的」であるような、「小さな物語」の中で生きているのです。
簡単に言えば、「全体」から「個」へと、物語の重点が移動していったということですね。
この変化は「文学」のテーマにもあてはまります。
近代文学の時代には「人は以下に生きるべきか」といった大きなテーマが意義をもっていましたが、こういった主題は現代ではなかなか効力を発揮できません。
なぜなら、「人それぞれじゃん」と言われたら終わりだからです。
だから、重いテーマを失った現代文学は、ある意味目新しさを追い求めるしかないのですね。あっと驚く仕掛けや、遊び心のある作品、わけがわからないんだけど何だか深そうな作品が喜ばれます。
初期の村上春樹さんの作品などはまさに「新しさ」が目立つものだったのではないでしょうか。
『青が消える』の内容についても、「大きな物語」を失った人々の姿をとらえることができそうです。
「僕」は青が消えたことに焦りを覚え、解決の手段がないかを必死で探し求めます。
しかし、周囲の人々は新しいミレニアムの到来を目前に、楽しいパーティーに夢中なのです。彼らは、新しい千年に殊更大きな意味を与えたりはしません。ただ、楽しいパーティーを開く口実があればそれで良いのだと言わんばかりに、「意味」というものに無関心です。
そんな中で、「僕」だけが、青が消えてしまったことに大きな意味があるのではないか、そして、このままでは良くないことが起こるのではないかと悩み続けるのです。
青が消えたことに思い悩む「僕」とは対照的な、あるいは否定的な考えが文中にはたくさん出てきます。それを、確認しておきましょう。
元ガールフレンドの言葉
「青がなくなって、それがどうだっていうのよ」
駅員の言葉
「私は青のことなんてこれっぽっちも知らないんですよ。私はただ言われたとおりに働いているだけです」
総理大臣の声で語るコンピューター・システムの言葉
「かたちあるものは必ずなくなるのです。」
「それが歴史なのですよ、岡田さん。好き嫌いに関係なく歴史は進むのです。」
「どうして青がなくなってはいけないのですか」
これらの登場人物は誰もみな、青が消えることを深刻な事態だとは捉えていません。
青が消えることは特別なことではないし、他にもっとやるべきことがあるだろうと「僕」以外の人は考えているようです。
ここで1度、「僕」に寄り添うことをやめて考えてみましょう。
青が消えることなんて大したことないという立場に立ってみるのです。
そんなことができるのでしょうか?
多くの人が、色というのは人間の思考から独立した存在であり、客観的な事実としてあるものだと考えているかもしれません。
しかし、そうとも言い切れないのです。
現代哲学の基礎的なところに、記号学という分野があります。
「記号」とは、赤信号=とまれ、青信号=わたれ、のような関係性によって成り立つものです。これは、はっきり言って何の必然性もないルールですよね。
黄色=とまれ、ピンク=わたれ、でも良いはずです。
今の信号機のルールがあるのは、みんながそのルールを守ろうとしているから成立しているのです。
実は、言葉そのものも記号なのだと言ったら意味は通じるでしょうか?
例えば「イヌ」という音声からある動物をイメージしてください。
それは「犬」と呼ばれる動物ですよね。しかし、それは英語では「dog」と呼ばれたり、フランス語では「chien」と呼ばれたりしています。
つまり、「犬」という言葉と、「イヌ」という音声から浮かび上がる動物との間には必然的な結びつきはないのですね。
私が今日から「イヌ」のことを「モイモイ」と呼ぶことにしても良いのです。
ただ、他の誰にも伝わることはありませんが……。
このことは、色を表す言葉にもあてはまります。
以下の図を見てください。

虹が何色に見えるかは文化によって違うということを聞いたことがあるかもしれません。
図のように、日本人が「橙」や「藍」と認識している色は、インドネシアや台湾の一部では認識されていないのです。
図の情報を真実だとするならばですが。(というのも、私が実地で調査したわけではないので確信をもって述べることはできないのです、ネット情報は怖いですね。)
「橙」や「藍」という色が客観的に、人間の認識から独立して存在しているわけではないのです。
「白って200色あんねんな!」というのはアンミカさんの名言ですが、これはあながち馬鹿にできない言葉です。
できる人には、「白」を200種類に分類することが可能なのです。
例えば以下のように……
生成色(きなりいろ) ベージュがかった自然な白
胡粉色(ごふんいろ) 日本画に使われる、黄みがかった白
象牙色(ぞうげいろ) 黄みがかった白
こんな会話を想像してください。
あなた「おっ! 今日はお互い白いTシャツでおそろいだね」
友人「ちがうよ。あなたのは胡粉色だよ。そして、わたしのは象牙色だよ!」
かなりイラっとしますね。
しかしこの時、あなたは胡粉色や象牙色が存在しないと言えますか?
どこで色の区別をするのかというのは、とても難しい問題なのですね。
さて、今までの議論は「青」という色にもあてはまります。
再び上の図に戻って確認すると、どうやら虹の中に「青」という色を認識しない民族もいるようです。
いや、そんなことを確認してみなくても、記号学の見地に立てば「青」が客観的に存在する色でないことはもうわかりますね。
それは文化の違いでしかないのです。青がないと言うこともできるし、青には200色あると言うことだってできるのです。
そうすると、「青が消えた」という小説の展開の違った面が見えてきますね。
多くの読者が(少なくとも私の生徒は)、世界から青が消えるという展開を不条理なものととらえました。
しかし、実際のところ青が消えることは不条理でもなければ、ファンタジーでも、SFでもないのです。
異なる文化をもつ国の人にとって、青は存在しないかもしれないのですから。
そもそも、厳密な意味で言えば、「青」という色は日本語の中にしか存在しません。
もしも「青が消えた」という小説を読んで、英語の「blue」も一緒に消えたはずだと断定するのならば、それは少々浅はかでしょう。
だって、言語が変われば認識する世界も多かれ少なかれ異なるのですから。(この話をこれ以上深めると、違う話になってしまうのでここまで!)
そういうわけで、記号学の見地に立てば、この世からなくならないものなどないのです。
同じようなことを、小説の中では総理大臣(の声で話すシステム)が語っていましたね。
〝石油だってなくなります。ウラニウムだってなくなります。オゾン層だって、二十世紀だって、ジョン・レノンだって、神様だってなくなります。スイング・ジャズだって、LPレコードだって、人力車だってなくなります。岡田さん、どうして青がなくなってはいけないのですか〟
最初に読んだときは、石油やウラニウムといった資源がなくなることと、青がなくなることは同じではないと思った人も多いのではないですか?
そんなことはないのです。青という色も、他のあらゆるものと同様になくなることがあるのです。
こんな時代の特徴を、改めてポスト・モダンの定義に戻って考えます。
リオタールは、ポスト・モダンの時代には絶対的な価値観は存在しないと考えたのでしたね。
永遠に存在し続けるものなどないのです。
小説の中の、「神様だってなくなります」というのはそういった点で象徴的な言葉です。
神道でも、キリスト教でも、神様は不滅の存在です。人間の認識を超越しています。だから、私たち人間ごときが神の存在を感知することなんてできないのです。
神が本当に存在するのなら、きっとそうなのでしょう。
ですが、今の時代、神様を本気で信じている人は少ないですよね。そういう意味で、神様だってなくなるのです。
言い換えれば、「神という絶対的なものを信じなくなった」ということなのです。
かつては人間の一生を支配していた神様でさえいなくなったのがポスト・モダンです。
この時代では、あらゆるものがなくなっていきます。
石油やウラニウムのように、何もかもが「消費」されるのです。。
今、「消費」と書きましたが、これは現代を読み解く重要なキーワードです。
よく、現代は消費社会だなんて言いますよね。それはいったいどういう意味なのでしょうか?
最近、あなたが消費したものは何ですか?
この質問は、簡単に「あなたが購入したものは何ですか?」と書き換えておきましょう。
様々な答えが聞こえてきそうですが、ここでは、実際に私の生徒が答えた「マフラー」を例に考えを進めていきます。
マフラーは何のために買ったのでしょう?
それはもちろん、防寒のためです。
では、防寒の役割を果たす最小限のコストでマフラーを買ったのでしょうか?
答えはノーです。
その生徒は、ノースフェイスというブランドのマフラーを買っていました。(正確には親に買ってもらったのでしょうが。)
そして、そのマフラーはなんと1万円もしたのです。
私は言いました。
「先生のマフラーはユニクロで2千円くらいだったけど、十分温かいよ。こっちの方が欲しくない?」
生徒の答えは聞くまでもないでしょう。
ノースフェイスのマフラーの方がずっとかっこいいし、流行っているし、有名人(スポーツ選手だったかも)も着用していたのだから、ユニクロのマフラーよりも欲しかったのです。
ここで出た理由は大切です。
「カッコいい」、「流行している」、「有名人が着用していた」というこれらの情報は、全てノースフェイスのマフラーが表す意味なのです。
この関係は、「赤信号=とまれ」という記号関係と同じです。
世の中にはいろんなマフラーがあるでしょうが、それぞれが記号のように意味をもっているのです。
・ユニクロのマフラー=コスパ重視の人が着けている
・ノースフェイスのマフラー=おしゃれな人が着けている
・バーバリーのマフラー=お金持ちな人が着けている
あくまで一例ですが、こんなイメージを持つことは珍しくないのではないかなと思います。
そして、大事なのは、「消費社会」ではマフラーそのものの機能よりも、記号的な意味(それを身に着けることでどんなイメージを表すことができるか)の方に価値があるということなのです。
ボードリヤールという哲学者はこう言いました。
〝消費社会においては、欲望の対象になるのはモノではなく、記号である〟
難しい言い回しですが、意味は分かりますね。
現代では、人々が欲しいと思うのは、ものそのものではなく、自分の地位や豊かさ、個性を表してくれる記号的役割の強いものだということです。
人々は、自分自身の好みのイメージを完成させるために次から次へと消費活動を進めていきます。
私にとってはほんの少し前のことですが、AKB48が大流行していました。当時の人気メンバー7名は神セブンと呼ばれたほどに愛されていました。
あれから何年経ったのでしょう。神と呼ばれた7人のアイドルは今、どこで何をしているのかぜんぜんわかりません。
K-POPがはやり始めたとき、音楽に疎い私でさえ少女時代とKARAの2グループは知っていました。
しかし、次から次へとデビューし、大ヒットしていくグループの数々を追いかけることは並みの消費者には難しいほどに、今、たくさんのグループが活動していますね。
少女時代とKARAは今も活動しているのかな?
消費者がどこかで満足するということはありません。
今、あなたは何を欲しいと思っていますか?
どうしてそれを欲しいと思うのでしょうか?
もしかしたら、それを持っていることで表されるイメージの方に魅力を感じているのではありませんか?
私を例に挙げてみます。
私は生活のために車が欲しいと思っています。では、生活の必要を満たす最低限の車で満足かと聞かれると、迷ってしまいます。
ランドクルーザーという大きな車が欲しいと思う自分がいます。
マツダのスポーツカーに乗りたいと思う自分もいます。
アウディという外国産の車も欲しいなー
結局、その車に乗っていることで表されるイメージを考えると、私はどうしても車ならなんでもOKとは思えないのです。
これが消費社会の実態です。
小説の中で、総理大臣の声が語っていたことはこの社会を言い表す事実なのです。
ちょっと長くなりすぎたので、強引にまとめに入ります。(申し訳ありません。)
《まとめ》
ポスト・モダンの現在には絶対的な価値観はありません。すべてが人それぞれでいいじゃんということになります。
すると、人々をつなげる大きなテーマ(=人が生きる意味や宗教)は失われ、人間は孤立していきます。
生きる意味など考えることがなくなった人々は、今度は自分らしさを表現するために消費活動に専念し始めます。
また、今が楽しければいいという考えにもなりやすいでしょう。だって、未来のために自分を犠牲にしたり、過去を反省したりしたって、現代では得るものがほとんどないのですから。
『青が消える』という小説の中で、多くの人々がパーティーに夢中なのは、そういった時代性を表しているからだと私は思います。
多くの人々は、青が消えようが、大好きだったアイドルが引退しようが、いっときの流行ファッションが廃れようが、気にしないのです。すぐに次の流行が生み出されるのですから。あるいは、今を楽しめる何かがあればいいのです。
こういった状況に不安を覚えるのが「僕」です。
変わらないもの、信じられるものが何もない社会の中で生きることへの大きな不安が「僕」の言動から読み取ることができます。
小説の最後に描かれた「僕」の描写はこうです。
〝僕はわけのわからないままどこまでも通りを歩いた〟
彼は、どこかで再び青を発見することができるのでしょうか?
あらゆるものを消費しつくすポスト・モダンの時代の中で、大好きだったものが消えてしまった男の悲しい姿が目に浮かびます。
さて、最後に、これは現代批判の物語なのかという点で考えておきましょう。
村上春樹さんはこの小説を書くことで、現代は間違っているということを主張したかったのでしょうか?
そういった意図を読み取るには、この物語は短すぎますね。
おそらく、現代社会をちょっと誇張して、風刺的に描くというのがこの小説の根本ではないかと思います。別に肯定も否定もしていません。
読者に考えさせる、と言ってしまえば逃げのようですが、私はそういう読み方でいいんじゃないかなと思っています。
以上になります。参考になれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
