
『呪われた詩⼈たち』『アムール・ジョーヌ』刊⾏記念対談(後編)
ルリユール叢書から、ヴェルレーヌ『呪われた詩人たち』とコルビエール『アムール・ジョーヌ』の同時刊行を記念して、2020年2月19日(水)、下北沢のB&Bにて、翻訳者の倉方健作さんと小澤真さんのトークイベントを行いました。そのイベント模様を前編・後編の二回に分けてお伝えいたします。(前編はこちら)

倉方 「前編」で言い忘れたんですが、映画『太陽と月に背いて』は元々イギリス人が書いた戯曲の映画化で、その戯曲を5、6年前に渋谷のシアターコクーンで蜷川幸雄が演出したことがあったんですね。ヴェルレーヌをハゲヅラを被って生瀬勝久が、ランボーは美少年ということで岡田将生が演った(会場笑)。で、たまたま上演パンフレットに文章を書く機会をいただいて、初日に観に行って非常に面白く見たんですけれども、打ち上げにも誘っていただいて。その時ヴェルレーヌの妻役を演っていた中越典子さんにとくとくとヴェルレーヌの人生を語っていた時が、僕のピークだったなと(笑)。ヴェルレーヌを専門にやっていると、たまにそういういいことがあるかな。思い出してせっかくなんでお話ししましたが、コルビエールもそういういいことがあるといいですね(笑)。
「呪われた詩人たち」とは「絶対的詩人たち」ということ
倉方 さて後半は、実際の翻訳についての話をしましょう。今日いらしてる方の中には翻訳の経験が豊富にある方もいらっしゃるわけですが、私にとっては自分個人の名前の翻訳書としては初めてのものです。共訳で社会学者のピエール・ブルデューの本をやった時は、それはそれで違うキツさがあったんですけれども、詩の翻訳、文学作品は初めてだったんです。なので、私が翻訳の蘊奥を語るとかそういうことではまったくなくて、むしろ皆さんにご意見を伺ったりしたいなと。初めて文学の翻訳をやってみた感想みたいな形で聞いていただければありがたいと思います。誤訳の指摘とか……終わった後に、こっそりしていただければありがたく存じます(笑)。
小澤 私は仕事柄、法律だとか行政文書を訳すことが多くて、文学の翻訳をやらせていただくのはすごくスリリングで楽しい作業だった。その分、「いやぁこれでいいのかな……」とずっと迷いながらやってましたね。
倉方 これから作品を紹介しますが、左側に原文があって右側に訳があるとはいえ、そんなに対照して見ていただかなくてもいいかな、と申し上げておきます(笑)。
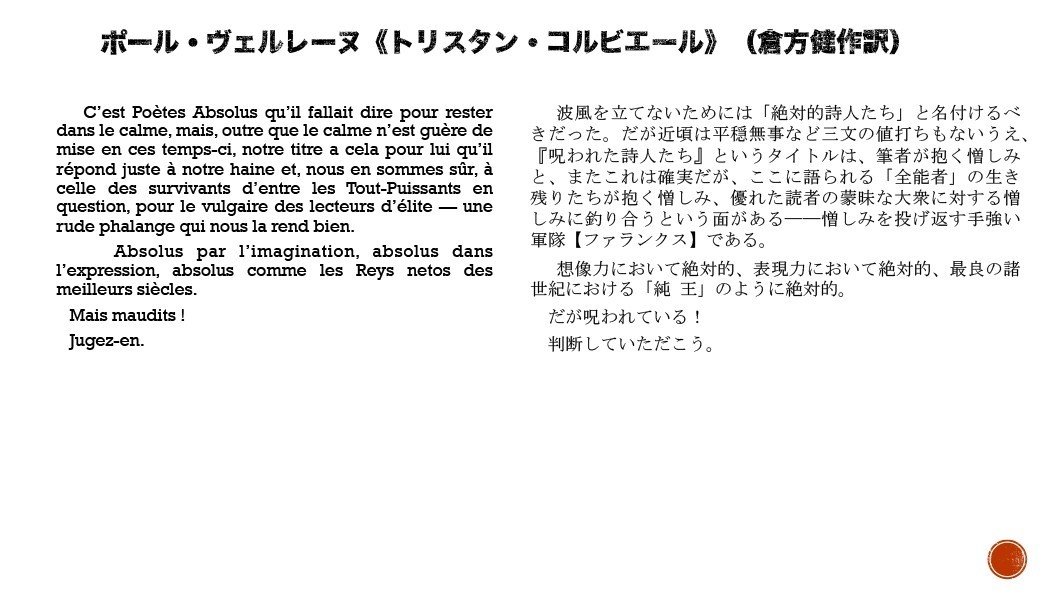
まず、これがどういう本なのか。初版にある口絵の説明の序文を除いた本文の最初の部分、「トリスタン・コルビエール」という最初の章の冒頭に、「呪われた詩人」とは何なのかと説明しています。
波風を立てないためには「絶対的詩人たち」と名付けるべきだった。だが近頃は、平穏無事など三文の値打ちもないうえ、『呪われた詩人たち』というタイトルは、筆者が抱く憎しみと、またこれは確実だが、ここに語られる「全能者」の生き残りたちが抱く憎しみ、優れた読者の蒙昧な大衆に対する憎しみに釣り合うという面がある――憎しみを投げ返す手強い軍隊(ファランクス)である。
想像力において絶対的、表現力において絶対的、最良の諸世紀における「純王(レイス・ネトス)」のように絶対的。
だが呪われている!
判断していただこう。
つまり「呪われた詩人たち」と言ってるけれども、それは「絶対的詩人たち」なんだということと、大衆に理解されないということを言ってるわけなんですね。新版の方ではこの部分が「トリスタン・コルビエール」の章から独立して序文のような扱いを受けたんですが、実際、ここ以外で「呪われた詩人たち」という言葉の定義はしてなくて、「絶対的詩人たち」の定義もしていないので、「呪われた詩人たち」は曖昧なままなんです。どうして「呪われた詩人たち」なのかということを、特に深く掘り下げていくわけではない。ただ「呪われた詩人たち」って、日本語にしてもそうなんですけど、なんかカッコいいんですね。ヴェルレーヌがこの「ポエット・モディ」という言葉を作ったことがすごく大事で、この言葉がそのあと人口に膾炙したからこそ、今でも「呪われた詩人誰々」みたいな感じで言えるんですね。そういう一つの詩人のタイプというものを打ち出したということで、非常に大きな価値があるんだと思います。ただヴェルレーヌ自身は、そんなに深く定義はしていない。
コルビエールの紹介をどのようにしているか。コルビエールの章の書き出しですが、

トリスタン・コルビエールは、ブルターニュ人で、船乗りで、かつ横柄この上ないという「三重の銅」だった。おさおさカトリックのミサにあずからぬが、悪魔は信ずるブルターニュ人である。船乗りだが、彼が乗るのは軍艦でもなければ商船ではなおさらなく、海への愛に狂い、この世界一の奔馬が極限にまで猛り狂う嵐のなかでなければ海に出なかった(無鉄砲極まる逸話の数々が今なお語られている)。「成功」だの「栄達」だのといった間抜けの親玉を心底から軽蔑し、俺の眉一つでも動かせるものならやってみろ、と挑戦するような調子であった!
高潔な人格についてはこのくらいにして、「詩人」について語ることにしよう。
押韻家としても韻律家としても、彼には完全無欠なところ、つまりうんざりするようなところがまるでない。彼を含む「偉人」たちに、完全無欠なものなど一人もいない。才気がたびたび居眠りするホメロスにはじまり、非常に人間味があるゲーテまで、とまれかくまれ、その間にはきわめて不規則なシェイクスピアもいる。完全無欠なやつらというのは、つまり…あいつらやあいつらである。どこまでも木材で出来ているような朴念仁。コルビエールは、ごく単純に、肉と骨でできていた。
これがコルビエールの紹介です。まずコルビエールの紹介をして、その後にゲーテ、ホメロス、シェイクスピアも詩人としては完全無欠なところがなくて人間味があるということを言うんですね。それに対して《あいつらやあいつら》って何かと簡単に言うと、これは自分が追放された元のルメール書店に集っている奴らだとかのことを言ってるんですね。当時の流れとして、その頃の詩人たちというのは、作品としての詩をいかに彫琢するかに命を懸けていたところがあって、文学史的には「高踏派」と言われたりするんですけれども、その人たちが社会的な評価を受けているのに対して、自分たちは「呪われた詩人たち」なんだ、という。
『呪われた詩人たち』は評論というより、紹介集である
『呪われた詩人たち』という本は実を言うと、これから読まれる方がいらっしゃることを期待して言いますが、意外と拍子抜けするところがあるかもしれないのは、これを「評論集」とするのは少し言い過ぎかなっていう感じがするんですね。簡単に言うと「紹介集」です。ヴェルレーヌはコルビエールとかランボーを紹介することが一番の意義だと思っていて、ひたすら引用がつづく。引用文に対して分析すると言うよりは褒め称えるコメントを置いてるくらいで、時々言葉はカッコいいんですけれども、それほど「文学論」だとか、深みがあるとかいうことではない。それがヴェルレーヌという詩人、作家の特徴の一つなんですけれども、ヴェルレーヌ自身、引用して紹介することを大事にしていたと言えると思います。
小澤 《完全無欠なものなど一人もいない》っていうのは、〈アール・ポエティック(詩法)〉で言われていたこととちょっと近いのかなという感じがします。
倉方 ヴェルレーヌは〈 Art poétique 〉という、“De la musique avant toute chose(まず何よりも音楽を)” から始まる詩を書いていて、この後の詩集に収められますけれど、あれも「詩法」とは言いながら、思想の深みから出たとか彼の詩がそれに従って書かれている、というよりは、覚書みたいなところがある。ヴェルレーヌという詩人は文章もそこそこ面白いですし、カッコいいんですけれども、それほど思想性を人に伝えようとする印象ではないかな、という感じですかね。
ランボーを〝美少年〟と讃えるのはヴェルレーヌだけ?!
次に、彼が恐らく一番紹介したがってたのはやっぱりランボーだと思うんですけども、そのランボーの紹介がどういうふうになっているか。これは「ランボー」の章の最初のところです。

筆者はアルチュール・ランボー氏と、知り合う栄誉に浴した。今日では諸々の事情が筆者を彼から遠ざけているが、言わずもがな、彼の天才に対する深い畏敬の念を欠いたことはない。
われわれの親密な交際の比較的初期には、アルチュール・ランボー氏は十六、十七歳の子供だったが、詩のあらゆる蘊奥〔うんのう〕をすでに身に備えていた。真の読者が知るに足るそれらを、筆者は可能な限り引用しながら分析を試みるつもりである。
彼は背が高く、がっしりとして、筋骨逞しいほどであり、流謫(るたく)の身にある天使のごとく見事な卵型の顔に、明るい栗色の乱れた髪と、人を不安にさせるライトブルーの眼を持っていた。アルデンヌ出身の彼が持っていた郷土の美しいアクセントはすぐに失われたが、この土地の人らしく、即座に同化する天与の才を持っていた。それがためにパリの愚かな太陽の下、彼の霊感はたちまち枯渇した。霊感、というのはまったくわれらがご先祖の物言いだが、彼の直截で正確な言葉遣いは、つまるところ、常に間違っていたわけでもないのだ!
面白いのは、ランボーに対する愛情が滲み出ている感じなんですね。未だにランボーというのは美少年、簡単に言うとディカプリオだとか岡田将生だっていう話がある。さっきの写真、鮮明な方の写真を見て、美しいと思うかどうかというのは人それぞれなんですけれども、

当時の証言で、ランボーがカッコよかっただとか天使だとか言っているのって、ヴェルレーヌだけなんですね(会場笑)。夫を盗られた形になっているヴェルレーヌの妻のマチルドは、あとの回想で「陰険な顔をしていた」だとか、ヴェルレーヌの古くからの友人で、ランボーのせいでヴェルレーヌが身を誤ったと思ってる人たちは「殺人鬼みたいな顔をしていた」とか、そういうことを言っていて、ヴェルレーヌと違うところがすごく面白いな感じがする。だからいまだにランボーが美少年だと見ている人っていうのは、ある意味で、この時の紹介の、ヴェルレーヌの眼を通して見ている部分がないわけではない、とは言えると思います。
当時、ランボーという詩人を初めて紹介するのがこの文章です。つまりこれがいかにインパクトを与えたのか。さっきの写真から作った肖像画と一緒にこの文章を読んでインパクトがあるように、かつ、ヴェルレーヌの愛情が滲み出るような感じで訳さなければいけないな、と思ったんですけれども。
あとこれを新訳しなきゃいけないなと思ったのは、既訳がちょっと古くなってるなと感じたんですね。「彼は背が高くて……」のところを鈴木信太郎がどう訳しているかというと、
人としては丈が高く、頑丈で、ほとんど力士の如くであった
(会場笑)力士にも色々ありますけれど、半世紀前だと今で言う力士の大型化の前ですから、栃若とかだと思うんですけれども(笑)、それにしたってちょっと受けるインパクトは違いますし、ランボーという詩人をこれで初めて知って思い描く時のインパクトってありますから、まあ、やっぱり訳し直さなければいけないなっていう意義を多少感じたところもありますし、やっぱり訳語というのはどうしても古くなっていくところがあると思うんですね。
あと今回の翻訳に意義があるとすると、初版の方は『呪われた詩人たち』の肖像に関する序文があったんですけれども、

こんな感じで、これはフランスの国立図書館のサイトからとってきたものなんですけれども、初版には、先ほどみたいな肖像に関する注記みたいのがあって、その感想が書いてあるんですね。どういうことを書いているかというと、ランボーのところに、こんなことを書いている。
「緒言 掲載の肖像について」のランボーに関する部分ですけれども、

エティエンヌ・カルジャは、一八七一年十月にアルチュール・ランボー氏を撮影した。読者諸氏が目の当たりにしているのがまさにその見事な写真であり、コルビエールのものと同様、現物から写真製版によって複製されている。
まさしくこれが「高邁なる子供」であることは、シャトーブリアンも強くは否認しないだろうが、この呼び名には、色気を帯びて久しいその唇と、早熟な夢想よりも大昔の思い出に浸っているその両眼が抗議するのではないだろうか? 若いながらも色恋沙汰に手慣れたカサノヴァ小僧は、不敵に鼻で笑い、ごつごつした美しい顎は、つい今しがた、微塵も揺るぐことのない意志にとっては存在する価値のない幻想に向かい「とっとと失せろ」と、口にしたばかりのようではないか? つまるところ、筆者が思うに、尊大なもじゃもじゃ髪がこれほど広い有様を呈しているのは、ほかなならぬ学術の枕のせいであり、その枕もそもそも皇帝(スルタン)じみた純粋な気まぐれで肘の下に押しつぶされたのだ。文字通りの悪魔の美しさにとって無用の身繕いに対する、実に雄々しい侮蔑である!
ということで、こっちもかなり愛情が滲み出ているんですけど(笑)、面白いのは、新版の時には、ゲラ刷りにかなり書き込みを加えているんですね。でもその書き込みは、実は新版の方には結局収められなかったんです。新版の方では初版にあった肖像画を他の絵に置き換えてしまったので、無用になって、なくなってしまったんですね。だからこれも日本語に訳されるのは初めてです。フランスの方でもこの書き込みというのが、最近フランス国立図書館が所有したので、ようやく研究者が目にすることができるようになった。だからこれはたぶん文字起こしもされてないと思うんですけれども、これを註の部分ではちゃんと、どういうふうに新版の時には書き換えるつもりだったかということを含めて紹介しました。たとえば「ランボー氏」の「氏」を取ったりだとか、「悪魔」を大文字にしてインパクトを強めたりしてるっていうのに加えて、たとえばこんなことが書き込まれていました。
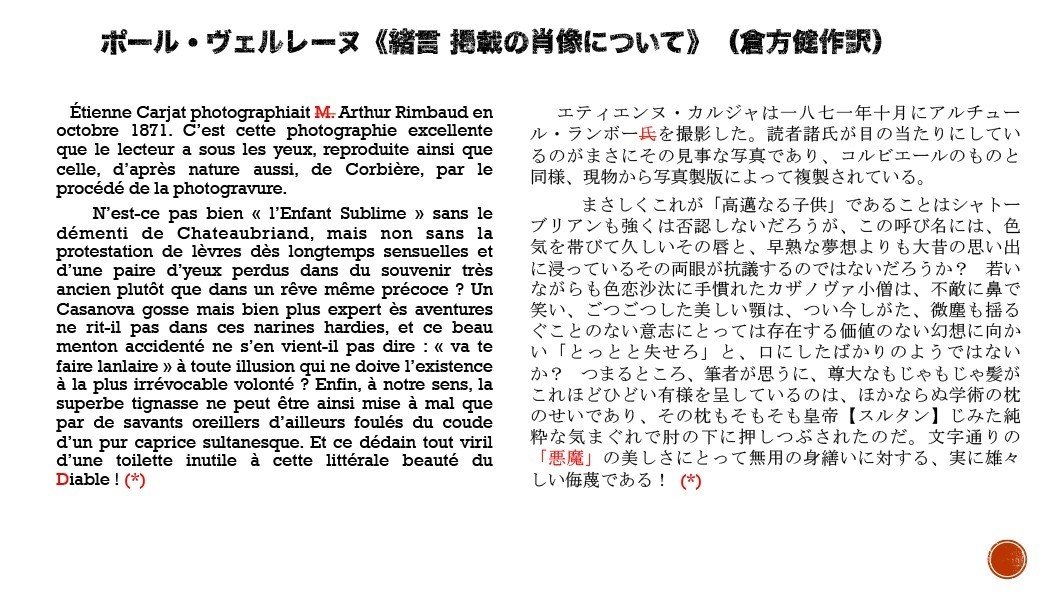
ヴェルレーヌは冷静になって見直したんですね、たぶん。

実のところ、この写真の複製はモデルの美しさ以上に荒々しさを示しており、そもそも縦の長さに欠点がある。他日また別の複製を期したい。
と。言われてみると、たしかにちょっと間延びしてるんですね(会場笑)。

これだとランボーの美しさが伝わらない、というヴェルレーヌの言葉から、ランボーに対する思いが非常に透けて見えるのが面白い感じがしますね。
こういう、初版の掲載の肖像画に関する文章だとか、フランスでも文字起こしがされていない註記というのを、翻訳できて、註に書けたことは、今回ある程度意義があったことだし、よかったなと思っております。それが「翻訳の意義」という点で言えることだと思います。
既訳があるときの、新訳の悩ましさ
翻訳に関してですけれど、先に言ってしまうと、何がきつかったっていうのは、私の方で言うと、既訳があるという話をしましたけれど、ヴェルレーヌの既訳はいいとして、中に引用されている詩篇ですね、たとえばランボーとかマラルメっていうのは、その後ものすごく研究が進んで、日本でもありとあらゆるとは言わないけど、幾つも翻訳がある。だからヴェルレーヌの地の文を訳すのは、まあ、それほどでもないんですけれど、なにしろ引用されているランボーやマラルメを訳すほうがよっぽど辛かったという気はしますね。それは僕が彼らの専門でないからという言い方だとよくないんですけども、もっと詳しい人が見て、「これはちょっと違う」と思われるんじゃないかというので、詩篇が怖かった部分はありますね。
小澤 怖いですよね。
倉方 ですよね。ランボーの分、マラルメの分は、研究者の友人に見てもらって、おかしいところがないか一応きいたんですけれど、やっぱり一回人に見てもらうって大事だなと、当たり前のことなんですけど(笑)、気がついたりしましたね。
ランボーの訳が一番きつかったと思うのは、大学院の時からの指導教師がランボーの専門家だったということもあって、ランボーの作品を訳すときにそれがちらちら浮かぶんですよね。その中に「Le Bateau ivre(バトー・イーヴル)」という有名な詩があります。「酔いどれ船」だとか「酩酊船」と訳されたりするんですが、私の先生は、このivreはお酒に酔ってるわけじゃないんだから、そういうのは訳として間違ってるんじゃないか、「酔いしれた船」だなんて話をしていて、非常に説得力があったので、私も「酔いしれた船」と訳してたんです。で、この訳が終わった頃、先生が新しく翻訳に関する論集に寄稿していて、そこでは「陶酔の船」と訳されていた(笑)。やっぱり訳って変わったりするんですね。堀口大學の名前が出ましたけれども、堀口大學もヴェルレーヌなんかでも翻訳する度に意外と手を加えたりするんですね。やっぱり文芸、文学の翻訳って、解釈もそうですし、自分の感覚もそうで、全然これで決まりというわけではなくて、今も今回のために用意してる時に、なんかこれ違うんじゃないかと自分で思ったりするってことがあって。ただ人間、そんなに何度も訳す機会はないので、一回で仕留めなきゃいけない、という気は、特にややマイナーな作家をやってるとします。そういう緊張感は翻訳する時に常にあったなという感じがしますね。
小澤 たとえば「酔いしれた船」と訳されたやつなんかは、小林秀雄が、文語訳で見事なやつがありますよね。韻文なので、僕なんかも文語で訳しちゃおうかな、でもその力はないしなとか、いろいろ考えたりはしましたけど、どうでしょう?
倉方 問題は、当時の読者は引用で初めて知るわけじゃないですか。ランボーにしろコルビエールにしろマラルメにしろ、初めて読者たちが知るっていうなら、歴史的な意義なので、本来そこで引用された詩人たちの魅力が伝わらなきゃいけない、ということがあると思うんですね。そこが非常に難しいのと、一方で、できるだけ読みやすいようにはした。だから文語調にはしない、という。ランボー、マラルメにしても既訳のイメージってどうしてもあって、ランボーだと小林秀雄の翻訳で読んでる方には、「俺、俺」と言ってないとランボーじゃない、って思ってる方もいらっしゃるんですよね(会場笑)。ランボーが「わたし」とか「僕」とか言ってるとムズムズするって言う方もいらっしゃるんですけれども、やっぱり「俺」ってどうしても訳せないんですよ。どうしてかというと、当時ランボーのことはそれほど知られていない、この肖像画と引用された詩篇で初めて知るわけで、前情報はほとんどないわけだから、それで「俺」と訳してしまったら、いろんな色が付きすぎてしまうと思うんですね。だから比較的ニュートラルな「私」で訳すのがこの場合は正しいと思うし、まあそれでいいんじゃないか。そもそも詩の中に書いてある「私」と、作者の「私」はイコールじゃないわけですから、それを「俺」と訳すのはちょっと行き過ぎだなと、少なくとも思ったんです。
小澤 日本語は一人称の数が多いので、そのへんはやっぱり考えどころというか、翻訳の時にけっこう考えますね。
倉方 そうそう。あとマラルメもすごく翻訳が進んでいて、いろいろとあったんですけれども、やっぱり読みづらいというか、引用しているヴェルレーヌの地の文と、マラルメの詩篇の翻訳の調子があんまり違ったりすると、同じフランス語で書いてるわけではあるんですから、何か全然ちがう国から来たみたいな翻訳になってしまってもまずいので、そんなに齟齬がないようにしなきゃいけないっていうのはありましたね。
というのが、私のほうから言えることです。つづいてコルビエールの詩の紹介を小澤さんにしていただきます。
コルビエールの詩の〈諧謔〉をどう訳したか
小澤 では、コルビエールの詩を紹介しながら、ちょっと読んでみたいと思います。

始まりつつある、あるいは終わりつつある恋人たち、彼らは終わりから始めようとしているのであるが、こうした恋人たちを除き、始まりによって終わる多くの事どもがあり、そのため終わりであることによって始まりは終わり始める、してその終わりとはすなわち恋人や他の者がこの始まりより始める、あるいは再び始めることによって終えるだろうということであり、この始まりは回帰した終わり以外の何物でもないことによってすでに終わっているはずである、このことは終わりも始まりもなき永遠と同義であることから始まり、最終的にまた地球の自転に等しいことによって終わるだろうが、そこにおいてはどこで終わりが始まるのか、どこから始まりが終わるのかを最早区別できぬであろう状態によって終わっているであろう、これこそ全き始まりの全的な終わりであり、あらゆる始まりのすべての終わりに等しい、これは際限なきものによって定義される無限の最終的な始まりである――してこれは墓碑銘に等しく、また序文に等しく、また相互に等しい。
(会場笑)これが詩の頭についているものなんです。これは詩の本文じゃないんです。
倉方 エピグラフってやつですね。よく作品の最初に他の人の引用をしますが、その引用の形で置かれているんですね。
小澤 そうですね。倉方さんがエピグラフについて書いた論文を興味深く読ませていただきましたが、面白いですよね。コルビエールなんかは確かに詩のタイトルの後に、エピグラフですごく工夫して、嘘とか書いてたりするんですよね。
倉方 わざとらしく訊きますが、このエピグラフはどこからとられているんですか。
小澤 はい(笑)、当時流行ったヘーゲル哲学を当てこすってるという感じらしいんですね。
倉方 エピグラフの形をしていながら、本当はコルビエールの創作なんですね。では、詩の本篇のほうをお願いします。


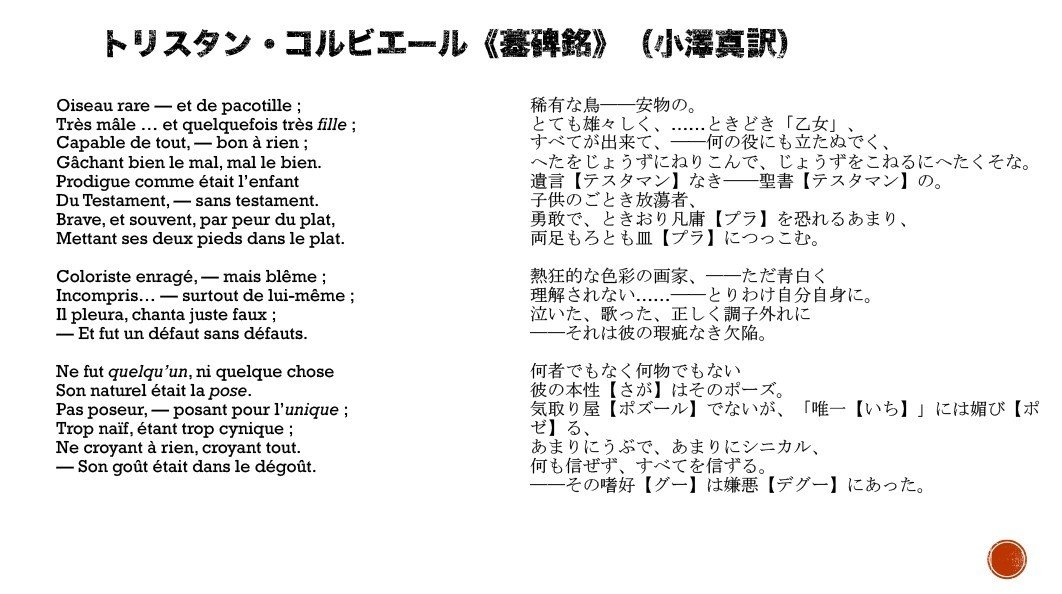

熱情によってみずから殺し、怠惰によっておのずから死んだ。
もし生きていたらそれは忘却によってだろう、これこそ彼が自らに言い残し
たもの。
――彼の唯一の後悔は、彼が自分の愛人でなかったことだ。――
どのような端緒(おわり)からも彼は生まれなかった、
いつも果ての風(むかいかぜ)に背中を押され、
まるで残飯(アルルカン)シチューのよう、
あらゆる姦通の混合だ。
「曰く言い難いもの」の。――どこであるかは分からぬが、
黄金の、――ビタ一文とてありはせぬが、
神経(ネール)の――軍資金(ネール)なく。力なき精力だ、
飛躍の――捻挫してはいるが、
魂柱(たましい)の、――ヴァイオリンもありはしないが、
愛の、――劣性の種馬。
――名指すにはあまりに多くの名がありて。――
理想的な「走者」――理想もなく、
豊かな韻、――決して踏まれることのない、
存在したこともなく、――収入だ、
いたるところ失って見いだされる。
韻文にもかかわらず「詩人」、
芸術なきアーティスト、――あべこべに、
哲学者、――でたらめに。
マジメにおかしなやつ、――面白くはない。
役割を知らない役者、
ミュゼットを吹く画家、
パレットをとる音楽家。
頭領だ! ――しかし頭はない、
狂いすぎてて馬鹿にはなれない、
「とても(トレ)」を削除線(トレ)と思い込む。
――偽の詩行だけがただ真実(ほんとう)で。
稀有な「鳥」――安物の。
とても雄々しく、……ときどき「乙女」、
すべてが出来て、――何の役にも立たぬでく、
へたをじょうずにねりこんで、じょうずをこねるにへたくそな。
遺言(テスタマン)なき――聖書(テスタマン)の。
子供のごとき放蕩者、
勇敢で、ときおり凡庸(プラ)。を恐れるあまり、
両足もろとも皿(プラ)につっこむ。
熱狂的な色彩の画家、――ただ青白く、
理解されない……――とりわけ自分自身に。
泣いた、歌った、正しく調子外れに
――それは彼の瑕疵なき欠陥。
何者でもなく何物でもない
彼の本性(さが)はそのポーズ。
気取り屋(ポズール)でないが、――「唯一(いち)」には媚び
(ポゼ)る、
あまりにうぶで、あまりにシニカル、
何も信ぜず、すべてを信じずる。
――その嗜好(グー)は嫌悪(デグー)にあった。
あまりに生、――焼きすぎたせい、
自分に似るより何にも似てない、
倦怠(けだい)を楽しみ、
徹夜をするほど。
沖での散歩、――漂流する、
辿りつかざる漂流物……
苦しみうるにはあまりに「自己」で、
干された精神(こころ)と酔った頭、
終わっているが、終われない、
生きる覚悟で死んでしまい、
死ぬる覚悟で生きていた。
「ここに眠る」、――情(こころ)なき心、根無し草、
あまりに成功したせいで、――ほとんど「失敗」の。
倉方 これは「墓碑銘(epitaph)」という詩ですが、自分の戯画みたいな形なんですかね。
小澤 そうですね。最初のエピグラフにある、矛盾したものを置いているんですよね。《あまりに生、――焼きすぎたせい、》とか。何を言っているかよくわからない、矛盾の塊。《生きる覚悟で死んでしまい、死ぬる覚悟で生きていた。》と。その矛盾の姿勢がコルビエールっぽいところかなと思いますね。
倉方 コルビエールって諧謔が豊かな詩人ですよね。
小澤 そうですね。中原中也も諧謔というか、おふざけというか、そういったものが好きな詩人だったので、そういうところが共通するのかなと思います。ヴェルレーヌもわりとふざけたものが好きですよね。
倉方 そうですね。コルビエールを読んでいて一番近いなと思うのは、歌手のジョルジュ・ブラッサンス(Georges Brassens 1921–81)ってわかります? それが比較的近くて、真面目な顔でふざけたことを歌ったりアナーキーなことを言ったりするのが面白いなっていうのがあります。
難しいのは、この詩も、ヴェルレーヌが引用しているんですね。専門家じゃないって言うのはさっきからずっと言い訳なんですけど、引用されている詩を翻訳しなきゃいけないというのは非常に辛くて、私は自分の分を訳す前に、小澤さんの訳を見る機会がなかったんですね(笑)。同じ詩なんですけども、訳者が違えば雰囲気も違う。私がどう訳したかについて言うと、ヴェルレーヌが引用を間違えたり、途中飛ばしているところがあったりするんです。そこは当時の文学的な意義、価値を考えて、引用が間違ったまま訳しているところもあります。


この者は野心から自殺した、あるいは怠惰で死んだ。
彼は生きたが、うっかり生きた。されるにまかせた事柄は以下のとおり。
彼の唯一の心残りは、自分自身の愛人ではなかったこと。
この者は頭からも尻からも生まれず、
常に逆風に吹かれたり。
そしてあらゆるものを混ぜ込んだ
残飯煮込みなりき。
「なんだかわからぬ」人であった――だが全てをわかっていた。
黄金の如き人――だが一銭もなかった。
肝が座っていた――体はひょろひょろ。気力充実、だが力なし。
躍動していた――捻挫もしたが。
魂があった――だがヴァイオリンは持たぬ。
愛があった――だが種馬としては最低。
――名を残すには呼び名が多過ぎた――
――――――――――――――――
気取り屋ではなかった――気取るのは「唯一の人」のため。
あまりに純情、あまりに皮肉屋。
なにも信ぜず、すべてを信ず。
――彼の趣味は不愉快のなかにありき。
――――――――――――――――
我慢するには「自分」でありすぎ、
英気はからから、頭脳はぐだぐだ、
落ち目だったが落としどころを知らず、
生きることを期待しながら死に、
死ぬことを期待しながら生きた。
植え損ねの、心なき心、ここに眠る。
失敗における、大いなる成功者。
本当にそれぞれ違いますし、お互いに、自分のほうがいいだろうと思ってなきゃやってられないんですけど(笑)。
小澤 でも、勉強になりますねえ。
倉方 非常に辛かったですんですけども、私も小澤さんの訳は拝見してないから、既訳はなかったわけです。そういう時どうするかというと、注釈付きのテキストを読んだりだとか、あと英訳はけっこう見たんですけれども。篠田一士がちょっと訳してますよね。
小澤 抄訳ですね、筑摩の文學大系で。
倉方 平凡社の世界名詩集大成の収録分も抄訳だから、全体の既訳はないんですよね。既訳ってまがりなりにもあれば、なんだかんだでミスを防げたりとか、こういう意味なのかって分かったりしますし、あと英訳はあるといい。コルビエールはちょっとは英訳はあるんですよね。
小澤 イタリア語の研究者がけっこう多いので、イタリア語訳が二つ三つありますし、英語訳も二つくらいあった気がします。ただ僕は英語あまりできないので、ほとんど参照しなかったんですけど。
倉方 英語の訳だと、英語で韻を踏もうとしたり、イングリッシュ・ヴァースにしようとする訳がけっこうあって、それだとどうしても余計なものが入ってくるんですよね。だから、それよりは、逐語訳というと変だけれども、韻とか考えずに訳してもらったほうが、他国語の人としてはありがたいというところは逆にある。
韻文を、文語調や五七五調で訳してみる
もう一つ、コルビエールの有名な詩篇、これは長い詩篇なんですけれども、ちょっと小澤さんに訳したものを読んでもらいます。
小澤 これはコルビエールの「縁日の吟遊詩人 La rapsode foraine」という詩で、フランスの詩人、文学者なんかはわりとこれを好きな人が多いというか、コルビエールの「白鳥の歌」的なものの一つかなという感じです。長い詩なので、前半がどういった感じかを説明させて頂いてもいいでしょうか。
これはブルターニュの風景、パルドン祭という聖アンヌを祭るお祭りの風景を描いています。最初にブルターニュの風景の描写があって、吟遊詩人という歌を歌って小銭をもらう仕事をしている人の語りが入ってくるわけですね。たとえば、
「善良なるまた堅固なる樫の真っ芯より、
斧でかち割り出でましたるおッ母さん、
あんた様の黄金(きん)のローブの下にゃあ隠れてる
粉々(バラバラ)ではありまするが、真っ当なブルターニュ人の魂が!
と香具師(やし)のような口上のイメージなんですね。そこから、蝋燭を買わせたりするために、ありがたい古いお話をしたり、それを歌っていく。その後にまたブルターニュの風景があって、たとえば当時癩病と言った人々だとか、目が見えない人だとか、病気の子供に傷をこしらえておまんまの種にする、みたいな描写とかがあって、最後、詩人が吟遊詩人に対して語りかける部分の詩になります。



けれど喘ぐような調子で、
風に鈴の音を木霊させながら
この巡業する煉獄の
めえ啼く人々の喧騒に水を打つ。
人の姿をしたものがわあわあわめきながら
十字(カルヴァリー)の丘に相対す。
彼女は半分盲のよう、
片目で犬も連れていない……
縁日の吟遊詩人だ
一リヤールで人々に聞かせてやる
幕垂野真理弥(まぐだらのまりや)のお話だの、
ユダヤの彷徨者、また阿部井良晴(あべいらある)のお話だの。
嘆きのように、
飢えの嘆きのように、
パンなき日の長く、
悲しく哀歌を曳いていく……
――息するように、そは歌う、
羽も巣もない悲しい鳥のごとく
本能に惹かれるままさまよう、
御影石のよき神のあたりを……
たぶん、そは話すこともできよう。
そは目で見るように考えることができる。
いつも目の前には大道がある……
――もし二銭(スー)もあろうものなら……そはそれを飲んでしまう。
――女。嗚呼どうもそうらしい――ぼろ着が
ぶら下がり、襦袢(ジュポン)ごと紐で巻かれている。
黒い歯は火の消えたパイプを
噛みしめている……――おお、良きこともある哉人生! ――
彼女の名前……そは貧困(ミゼール)という。
たまさか生まれてあったもの。
倒れて踏まれて死にゆくもの……
同じことだ――どこかは知らず。
――兵士の古い鞄を携えた、
彼女にもし会ったなら、「詩人」よ、
それは我らのきょうだいだ……やってくれ――祭りなのだから――
彼女のパイプに、ほんの少し煙草の葉を!
彼女の虚(くぼ)んだ顔に
木に刻んだような、
微笑みが浮かぶだろう。そうして瘡疵の手をして
ほんとうの十字を切ってくれる。
こんな詩なんですが、さっきのものもそうなんですが、フランス語の韻文は、日本語の五七五のように音節数をそろえるわけなんですね。これであれば八音節でずっと書いています。八音節で、脚韻(rime)を合わせる。この二つの要素が、フランス詩の中心軸になっているのが、フランス語の韻文です。基本的にはこうなります。韻文ですので、ある種、歌なんですね。節(ふし)というのがあるので、私自身が韻文の訳の時にいくつか迷ったのは、まず文語訳でするか。できるだけ五七五を基本にして、大事にしていった方がいいのかな、というのを心がけてやったりしました。やっぱりリズムというのがありますので。
特にこの最後のフレーズが面白いんですね。たとえば、
Tu verras dans sa face creuse
Se creuser, comme dans du bois,
Un sourire ; et sa main galeuse
Te faire un vrai signe de croix.△
「君は彼女の窪んだ顔の中に微笑みが刻まれるのが見えるだろう」
この脚韻は、「du bois(デュボワ) 木」というのと「 croix(クロワ) 十字」のところです。で、「cruese(クルーズ) 窪んだ」という形容詞と、「galeuse(ガルーズ)」。これは「瘡痂(そうか)の手」と訳しましたが、人間にかかる場合には疥癬(かいせん)、木にかかる場合には、木のゴツゴツした部分のことを言います。で、ここに折りよく「du bois 木」という単語があるんで、これは多分、木のゴツゴツした部分=瘡痂というイメージでつながっている感じです。
ついでに言いますと、boisとcroixというのは、コルビエールの最後の手紙を見ますと、ちょっと面白いんですね。どういう手紙かと言うと、死の病に罹っている時に母親に向かって手紙を書くんですが、「私はデュボワにいて、私のために棺が作られている」という内容を母親に送るんですね。デュボワというのはパリにある医療施設らしいんですけれども、ちょっと予言しているような感じがある。デュボワで、クロワ。個人的にはちょっとグッとくるところで、偶然なんですけれどもね。
韻文なので、そこは気をつけながら訳してみました。
翻訳でルビを使う方法、使わないやり方
倉方 テンポよく訳すのは大変だな、と思います。私はどこかで諦めちゃったようなところがあって(笑)、あんまり考えないところがあるんですね。読んでみて、あまりに不格好だなと思ったら直したりはしますけど。特に気がつくのは、小澤さんは今回すごくルビを使ってますよね。ルビは意識して使ってらっしゃいました?
小澤 はい。ルビに関してはすごく意識をして使っていました。中原中也とか小林秀雄が、けっこう面白い形でルビを使うことが多いんですけれども、ルビっていうのは元々は読めない漢字に対して振るという形だったと思うんですが、中也とか小林秀雄になると、ダブル・ミーニング、別の意味を付けてきたりだとか、色々使ってるんですね。で、コルビエールという詩人は、ほとんど駄洒落になっちゃうくらい、2つの意味を1つの単語に付けていくようなところがある。時にそれは、言葉は悪いけれど、うるさい感じになっちゃうこともあるような、そういった文章です。なので、そういったものも含めてルビを多用することで、コルビエールのコテコテした感じを表現できたらいいかなと思って、ルビは多用しています。
倉方 フランス文学業界だとルビに足を向けて寝られない歴史というのがあります。鈴木信太郎と辰野隆(ゆたか)――一番最初の東京大学のフランス文学科の教授で、辰野金吾の息子――が一緒に訳した、『シラノ・ド・ベルジュラック』といういまだに岩波文庫に生きてると思いますけれども、あれの一番最後、シラノが死んでいくところで、自分の羽飾りだけは傷つけずに天国に持っていくという話をしていて、それが象徴的なんですが、「羽飾り」と書いて、ルビで「こころいき」と振ってるんですね。当時からそういうことをやっている。小林秀雄の師匠の世代なわけですから、アカデミズムの方でも、自由なルビを付けてもいいんだというふうな意識は比較的あったんじゃないかなと思うんですよね。こういうルビのおかげでけっこう創造的なことができると思うんですけど。
逆に、今みたいに口頭で読む場合ってけっこう苦しくないですか。
小澤 苦しいですね。確かにおっしゃる通りです。あと、あまりこれに頼りすぎるとうるさくなっちゃうんで、コルビエールだから出来たかもしれないってところはあります。他の詩人にこれと同じことをしてしまうと、ちょっと……となる部分が多いかなという気がします。
倉方 私はルビを使わないというか、原語を示す時だけには使うけれども、それ以外のダブル・ミーニングの時には基本的には使わないですね。どうしてかと言われても、別に理由はないんですけども(笑)、原語を示す意味で、つまり口頭で言う時にそういうふうに読むんだ、と。原語を示すだけの意味には使うけども、それ以外には使わない。でもそういうのでうまくやっていかないといけない、その方がやっぱり意味が伝わりやすくなる作品があるのだとは思います。
この『アムール・ジョーヌ』の表紙でも、「闇」と書いて「よる」とルビがあるのは、ダブル・ミーニングというよりは、イメージの感じですか。

小澤 そうですね、イメージですね。これは
Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !
Il n’est plus de nuits, il n’est plus de jours ; (Rondel)
というところなんですけども、
闇(よる)が来る、子供よ、火花を盗む者!
もう夜もなく、昼もない、
言っていることは、一行目の「夜」と二行目の「夜」は同じような感じなんですけども、noirとnuit、表現がちょっと違うので、漢字としては「闇」を当てるけれど、音としては「夜」がほしいっていう、リズム的な問題で迷ったところなんですね。
倉方 そこらへんの感覚はもちろん私も固まっているわけじゃなくて、これからも変わっていくと思いますけれども、やはり人それぞれ違うところがあって、私はたぶん、同じようにはできないと思います。あと非常に面白いなと思ったのは、全体のタイトルを、「アムール・ジョーヌ」と片仮名にしましたね。その辺の判断というのも、僕は一貫して「黄色い恋」と訳しているんですね。だから、フランス人に意味が通じるものとして「アムール・ジョーヌ」という言葉に幾つかのミーニングがあろうとも、やっぱり日本人として日本語に訳すんだったら、日本語にあるものにしなきゃいけないんじゃないかという思いがどこかにあって、そうしてるんですけど、片仮名にすることによって、フランス語がわかる人には伝わるようにはなるわけですよね。そこに何かお考えはありますか。
小澤 意味としては、「アムール」が「愛」あるいは「恋」で、「ジョーヌ」が「黄色い」という形容詞です。「黄色い恋」というのは一応決まっている訳。あるいは「黄色い愛」とか、色々考えたんですけれども、まず一つには、中原中也が、これを「アムール・ジョーヌ」と呼んでいたということ。あと響きとして「黄色い恋」というのが、なにかダサい感じがしてしまって……
倉方 (笑)
小澤 どうしても許容できなかったんですよね(会場笑)。なので、ちょっとカッコいい感じでやってしまったんです。
倉方 鹿島茂先生が、バルザックの『ゴリオ爺さん』を訳す時に、「ペール・ゴリオ」と訳したんですよね。「ゴリオ爺さん」だと、「なんだ、爺さんの話か」と読まれないからと(笑)。ああ、そういう考え方もあるかと思ったことがありました。
小澤 ちょっとわがままを言わせていただきました。「黄色い恋」の方がわかりやすかったと思うんですが。
倉方 私はせいぜい、「愛」と「恋」、どっちを使うか悩んだくらいの話ですね。そこはやっぱりそれぞれで。研究とかしていると、逆にその語にどれだけ意味が籠もっているのか、ということもありますし、あとやっぱりどうしても既訳のイメージが強すぎて変えられないというのがあって、どんな人でも、ボードレールの『悪の華』が「悪の〝花〟」ではいけない、中華の〝華〟でなければいけないような雰囲気ってあるじゃないですか(笑)。だから既訳といかに戦うかはけっこう難しい。さっきの「酔いどれ船」の話もそうですし、僕の先生は頑なに、『地獄の〝一〟季節』と訳してるんですけれど(笑)、そこらへんは本当に判断が難しいですし、それはでも、しょうがないかなってところはありますね。
あと、日本語に移す時に、言葉の順番はどうしてます? 詩で一番困るのが順番なんですよね。
小澤 基本的には原文の順番を尊重しつつなんですけれども、でも時にはそれだと意味がうまくわからなくなることがやっぱりあるんですよね。その場合には入れ換えたりしますけれども、極力順番はいじらない感じで、まず考えます。ただやっぱり、頭の中で一回もうちょっとグローバルに見て、動かす時には躊躇なく動かすこともあります。
倉方 僕はけっこう諦めてる部分があって、順番通りが理想なんだけれども、やっぱり意味が通じるかどうかってところがあるんですね。諦めざるを得ない経験というのは、たとえばヴェルレーヌの場合、いわゆる「秋の日のヴィオロンの ためいきの……」(上田敏)という訳がありますね。あの原文は、
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
最初に「長いため息」ときて「ヴァイオリン」、「秋の」と順番がちがうじゃないですか。でも短い詩篇だから、逆にしようがないんですよね。つまり、「Les sanglots longs」から訳すのは非常にきついので、逆にせざるを得ない。あと、「秋の日のヴィオロンの」って名訳だってことになってるし、もちろんいい訳だとは思うんですが、実際は「秋」なだけで「日の」とは言ってないんですね。語調を合わせるために入れたので、原文に「日の」は入っていない。「ヴィオロン」って本当に日本語だろうかっていう問題もあって、当時ヴァイオリンという日本語がどれくらい定着していたかも微妙なところです。「ため息の」はまだいいにしても、この訳だと、あの詩って、実際にヴァイオリンがあると思ってるんじゃないですかね、皆さん。おそらくはあれは風の音の比喩なんですけれども、「日の」ヴィオロンと言ってしまうと、本当にそこにヴァイオリンを弾いている人がいるような感じになってしまう、ということがある。
かといって、堀口大學は、わかりやすく「秋風のヴィオロンの」と訳したんですが、それは「風の」と言ってしまうことによって、逆に隠されていた比喩が消えてしまうというのがあったりして、解釈を入れたりするのは本当に難しい。判断が難しいですね。
小澤 やっぱり聞いた時に、耳に心地いい部分は大事ですよね。「秋の日のヴィオロンの」が誤訳ギリギリのところであったとしても。
倉方 もちろん、その訳が誰に向けているものなのか、という点で、こっちも意訳している部分もあります。『呪われた詩人たち』に関して言えば、プレオリジナルと初版と新版というのがあって、それは学術的には肯定する。一方でこれを日本語で読む人というのは、フランス語の原文と対照して読むわけではないことを前提として、フランス語で自然な原文なら、日本語としても自然にやるべきなんじゃないか。それだからこそ、引用された作家の魅力が伝わったわけだから、っていうのが一応あって、だからなるべく自然に読めるようにした、という感じの方が強かったですね。もちろん自分自身がマラルメとかランボーを読むのに苦労しているからっていうのもあるんですけども(笑)。そこが大変だったなという思いがいたします。
小澤 『呪われた詩人たち』にはマラルメ、ランボーとか色んな詩人の詩篇が本文中に引用として入ってるじゃないですか。別の詩人の詩を訳す時に、ちょっと文体を変えたりとかって意識してますか?
倉方 あんまりしてないかな。基本的にはしない。もちろん翻訳なさってる方はそれぞれ色々あると思うんですが、僕が結局いちばん気にするのは、出てくる名詞とか、名詞と形容詞の関わりとかの頻度が実際にどれくらいなのかっていうことで、突飛な結びつきだったら日本語でも突飛に、あまりそうでないなら近いように訳さないといけないな、と。もちろん標準値の文章なんてないわけなんですが、その詩人たちの個性が、どれくらいずれてるのか、それを把握しないといけない。ただ、前もって、「こういう詩人だからこう訳す」みたいな意識はない気がします。その詩人によってもいろんな詩があるわけですし、さっき言ったように「私」と書いてあっても常に詩人自身ではないわけですから。
せっかく皆さんいらしているので、質問をしていただけると非常にありがたいです。どうぞ。
――先ほど「コルビエールのコテコテ」とおっしゃっていたんですけれども、マグダラのマリアのところに漢字を当てていたのも、何か面白みと重みを出す効果だったのかと思いながら聞いていました。
小澤 そうですね、原文は、
L’Istoyre de la Magdalayne,
Du Jvif-Errant ou d’Abaylar.
ですけれども、「istoyre(イストワール) 物語」という単語と「Magdalayne(マグダレーヌ)」この部分ですね。それから「Abaylar(アベイラール)」これは人の名前ですけれども、フランス語の正しい綴りではまったくなくて、この部分は古仏語を模した形なんですね。古フランス語、昔の中世フランス語っぽい感じで、でも探すとない、というコルビエール独創の、ちょっと古文じみた感じで書いている部分なので、吟遊詩人が昔の話をありがたいようにちょっと古文風に「マグダレーヌ」という。現代フランス語では「マドレーヌ(Madelaine)」です。なので、これはちょっとやりすぎかもしれませんが、「幕垂野真理弥(まぐだらのまりや)」「阿部井良晴(あべいらある)」と当て字にして訳させていただきました。
――この漢字で頑張られた感じがしました(笑)。
小澤 そうですね、面白いところなんで、伝わればいいのかなと。
倉方 「仏恥義理(ぶっちぎり)」とか、そういう感じですね(笑)。他に質問でもご意見でも……ないようですね。
小澤 僕の方から質問を一つしてもいいですか。倉方さんの本、エディション・クリティーク、批評版として本当に価値のあるものを作られて、すごいな、僕にはできない仕事だなというふうにびっくりというか敬服しました。やっぱり、特にランボーの部分が、倉方さんの訳で読んでみると本当に感動的なんですよね。というのはやっぱり、ヴェルレーヌはランボーを紹介したかった。それがまず第一で、だから『呪われた詩人たち』の中心には、やっぱりランボーが想定としてあって、おそらくちょっと似てるというんで、コルビエールだとか他の詩人が並ぶ。ただそうすると、デボルド・ヴァルモール、マラルメ、ヴィリエ・ド・リラダンはちょっと異質な感じというか、「呪われた詩人」というには、ヴァルモールはわりと名声のある人だったりするし、なんでこの人たちが選ばれたんだっていう疑問が単純にありますよね。
倉方 解説にそういうことを書いているんですけども、やっぱりこの中にコルビエールの存在がどうしてもなきゃいけなかったのは、コルビエールは、ヴェルレーヌにとっても呪われた詩人だった、初めて知った喜びがあるんです。同時に、もしもこれが初版から、つまりいきなりランボーとマラルメと自分自身であったとしたら、これは本当にルサンチマンとしか受け取られないんですよね(会場笑)。だから「呪われた詩人」という存在をちゃんと普遍化する意味で、コルビエールの存在は全く不可欠だったというのがあると思うんですね。もちろんランボーのことはどこかで紹介したかったと思うんですけども、そこにコルビエールが都合よく現れたと言うよりは、コルビエールを紹介することによって、このシリーズのままでランボーを紹介できるな、というふうな感じの方が強いんじゃないかなって気はするんですよね。
小澤 なるほど。ありがとうございます。
倉方 解説にも書きましたけども、新版のほうのデヴォルド・ヴァルモールは、すでにボードレールや他の批評家によっていくつも批評が出てましたし、そんなに手に入らない詩人でもなかったわけですよね。実際に刊行された詩集から引いてるわけで。ところがランボーやマラルメは、当時はここでしか読めなかったわけで、コルビエールだって手に入らない。だから、それでしか読めないものを示すことに意義があったわけですけれども、新版の時には、そういう意義はほとんどなくなってるんですね。だから、初版の時にはそういうモチベーションにものすごく満ちていたという感じがするんですけども、新版のほうはやや惰性みたいなところがある。そもそもヴィリエ・ド・リラダンが本当に詩人かってところもありますし、そんなに手に入らなかったわけでもないし。解説を読まれた方は、私が冷めてるなと思われるかもしれないけれども、それが正直なところで、新版の方は少し意義が薄いだとか、ヴェルレーヌの紹介の仕方、対応がどうかと思うとまでは言わないけども、ちょっと熱が冷めてきた部分、おざなりの部分はあるなっていうことは感じざるを得ないですね。
――小澤さんがコルビエールにどう惹かれたのか、翻訳するまでの過程の前に、どう受け止めたのかを聞かせてください。
小澤 やっぱり『アムール・ジョーヌ』の中では、最後の章がすごく叙情的な、いい詩なんですね。ラフォルグとかトリスタン・ツァラが指摘してるんですけど、コルビエールの中には散文的な詩と、すごく小唄的な詩というのがありまして、僕が好きなのは最後の小唄的な章「RONDELS POUR APRÈS のちのためのロンデル」。「この詩はなんかいいなあ」と単純に。音の話なんですけどもね、中原中也のようなイメージもあったりして、それがやっぱりコルビエールを訳そうと思ったいちばんのきっかけだと思います。
――本当にいい訳だと思って。いまの若い世代だと、ヒップホップが好きな子たちもいるから、詩が好きな、いわゆる中原中也を好きな子たちだけじゃなくて、語感とかリズムとかで出会う可能性が一つあるかなって思ったのと、もう一つは今おっしゃった、小唄っぽい感じ、暗誦できたり記憶できたり、フランス語でもたぶん先生は口ずさんだりするんじゃないかなと思うんですけども、そういう詩の魅力が伝えられたらいいなって思いながら伺いました。
小澤 ありがとうございます。
倉方 コルビエールは〝海の詩人〟だとか〝ブルターニュ〟だっていうことがありますけれど、実際に小澤さんは海はお好きですか?
小澤 個人的には好きです(会場笑)。
倉方 海とか、もちろんブルターニュに行ったりした経験っていうのは、訳詩に生きている感じはしますか?
小澤 やっぱり現場を見ているのは、イメージがつきやすいっていう意味ではありますね。たとえばお墓のシーンで、ブルターニュの人だったらたぶん、お墓はただの十字ではなくて、輪っかがついてるケルト十字っていうのが思い浮かぶんですよ。だから、墓場を見ると丸い映像が浮かぶんですよね。そういうのもたぶん、ブルターニュに行ってないとイメージとしてなかったところかなという気がします。現地に行って実際に触れて見る、聞くっていうのは、翻訳にとってはすごくあります。
倉方 それは実際にあると思います。行ったからわかるというわけではないかもしれないけれど、行ったことによって情報は非常にわかってくるなという感じはありますよね。
小澤 そうですね。僕からもう一ついいですか。ランボーの章の中で、最後、コルビエールの詩が引用されてますよね。これ、なんでですかね?
倉方 しかも引用が間違ってるんですよ(笑)。なんでですかね。あんまり深い理由はないと思うけれども、もちろん「呪われた詩人たち」ということで、ヴェルレーヌが自分のことを書いた「ポーヴル・ルリアン」の章でも、いきなり関係なく突然ランボーの詩を引用したりしてるんですね。だから、これから読まれる方にとってはほとんど言い訳みたいになるんですけども、ヴェルレーヌが文章を書く時の脈絡だとか、文章だとかというのが、必ずしも理想的なものだとか、美文とかでは全くないというのがあって、あんまりそこは理由とか追ってもしょうがない部分があるんです。訳者解題にも書きましたけれど、批評家のレミ・ド・グールモンという人が、19世紀末から20世紀にかけての批評家がヴェルレーヌの散文について、こんなことを言ってるんですね。
ヴェルレーヌは仲間うちで話すときには機知に富み、ときにやや意地悪くもあった。しかし筆を執ると、その意地の悪さを引っ込めて、残念ながら大抵の場合は機知までもなくしてしまう。独特さを保ち続けているので、散文作家として凡庸ではないのだが、不器用であるし、軽妙さに欠ける。そして彼は文章を書くのが嫌になる。とっとと終わらせようと、思いついたことはなんでも、ゆがんだ、緩慢な、ちぐはぐな文章にぶちこんでしまう。
実際、そう感じる時があるんですね(笑)。これ、本当に埋め草みたいな感じで、晩年ヴェルレーヌはお金がなくて、何行いくら、とかだったので、もう本当に、池波正太郎みたいな話で、がんがん改行して行数を稼ぐみたいなところがあったりするんですよね。引用ってある意味すごく便利で、自分で書かなくていいじゃないですか。そういうのもあるんじゃないかな(笑)。そこらへんはそんなに深く考えない感じかな(笑)。
小澤 マラルメの章なんて、けっこう引用ばっかりでしたもんね。
倉方 だから最初から、ヴェルレーヌのそういう意味での誠実さはけっこう疑ってかかってるというのが僕のスタンスで、それは変な話、人間としてなんかわかるというところもあるんです。神格化しないというのは、そんなに間違った態度でもなかったんじゃないかなと自分では思うんですけども(笑)。
他に質問はないでしょうか。では時間になりましたので、終わりにしましょう。
(終わり)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。本篇はぜひ、『呪われた詩人たち』『アムール・ジョーヌ』でお楽しみください。
