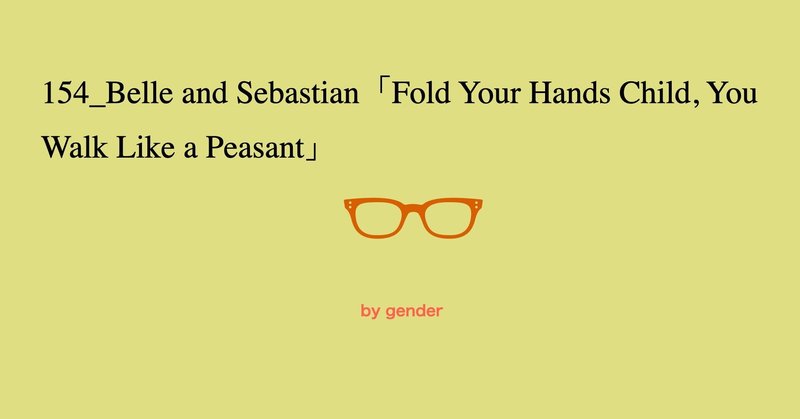
154_Belle and Sebastian「Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant」
父は、単身赴任中の山口で一人で死んでしまった。
朝、出勤中の電車の中で本を読んでいたら、母親からLINEがきていた。「なんかお父さんの様子がおかしいらしい」という断片的なメッセージだった。私は内容を一瞥して、少し針を刺されたように、ギクリとして、まあでも大したことないんだろう、と読んでいる本に集中しようとした。しかし、虫の知らせのように言い知れない悪い予感は止まらない。
その後に、母から電話が来た。たぶん、この母からの電話を取れば、私のこの嫌な予感はおそらく本物になる。このまま電話を取らないでおきたかったが、そんなことも言ってられないというように、携帯は乳飲み児が喚くように鳴り続ける。私は慌てて電車を降りた。発車する電車のけたたましい音や駅から流れるメロディに片耳を抑えながら、母の辿々しい言葉を聞き取ろうとした。
「お父さんが、お父さんが」
「ねえ、お父さんがどうしたのよ」
「朝、職場に出勤してこないから、それで、同僚の人がお父さんに電話かけても応答しないからって」
「そう、それで」
母を急かしているわけではないのに、詰問しているように口調がキツくなってしまう。ただただ、私は真相を早く知りたいだけなのに。
「それで、官舎まで見に行ってくれたら、お父さん、寝たままでそのまま」
「そのまま」
「死んじゃってたって、息してないって」
「うん、うん、ちょっと待って」
「たぶん、たぶんお父さん、血圧高いから、そのまま脳梗塞とかそんな」
「わかった。わかったから、待ってて、すぐにそっちいくから。すぐに、すぐにお父さんのとこ行こう」
だめだ、早く早くお父さんのところに行こう。でも、もうお父さんは息をしていないの?最後にお父さんの声を聞いたの、いつだろう、もしかしたら、昨年の夏の帰省のタイミングくらい?そんなに、お父さんと会って話していなかったっけ?それで、お父さん、何も私も話さない間に今朝死んじゃったの?
私は混乱する意識のままで、職場に急いで電話をして、家族の具合が悪いから休暇を欲しいと伝えた。主任の対応は優しかった。「早くご家族のところに行ってあげなさい」と言ってくれた。私は下りの電車に乗りこみ、まずは自分の家にUターンした。
電車の中で渉にもLINEしておいた。「お父さんがもしかしたら死んじゃったかもしれない。山口に行く」自分でメッセージ書いておいて、いかにもあっさりとした送信履歴の文面に愕然とした。何を飄々と書いているんだ、私は。渉からは「そうか、わかった、大丈夫?無理しないで」と数秒で返ってきた。急を要するということを、察したのだろう。無理をしないで、という文面にお腹の中でコクンと脈打つものを感じる。
そして、口の中に何かザラっとした気持ち悪い違和感を覚える。こんな時に。自分の体が自分のものではないように感じる。お父さんのことに関係しているのか、そうじゃなくて、私の体のことだけなのか。ただ、今はそんなこと考えられなかった。
1週間くらいの着替えをキャリーケースに詰め込んで、私は母のいる埼玉のマンションの実家のベルを鳴らした。母親は少し涙をにじませながら、部屋の中で明らかに狼狽えていた。動転しても仕方ないことだった。私は母の顔を見て少し安心したが、やらなければいけないことがたくさんある。
「すぐに山口に行く準備して、ね、お父さんのところ行かなかきゃ」
「うん、うん、わかってる」
母の声がうわずっている。猫のミドリが私たち2人の平常ではない様子を察してか、部屋の中で甲高い鳴き声をあげている。
「ねえ、ミドリ、咲ちゃんの家に預けなきゃ」
「電話した?」
「それが、電話出ないの」
「もう!こんな時に、咲恵おばちゃん、何しているの」
叔母の咲恵おばちゃんにすぐにミドリを預ける算段をつけて、母親に山口行きの準備をさせて、すぐにお父さんのところに向かわなきゃいけない。頭の中でやることだけはいっぱい並べてある。ただ、状況はそうはいかない。私は私として立っているだけで必死だった。
「服、服、何を着たらいいの、喪服とか」
「とりあえず適当でいいから!喪服なんて、まだ着ないよ」
私も感情が昂ってきて、だんだん泣きそうになった。とりあえず、一刻も早くお父さんの元へ行かないと。咲恵おばちゃんにもなんとかつながった。(毎朝の行事ごとく、家の前で近所のおばちゃんとおしゃべりしていたらしい)ミドリの面倒を見てもらえるように話をして、家の鍵を郵便受けの下に入れて、私と母は早足で駅へと向かった。
山口行きの新幹線の中で、私と母は手を握りしめあっていた。景色を見ればいいのか、どこを見ていいのか、正直よくわからない。新幹線の中って、こんな息の詰まる場所だったっけ。母とも会話は少ない。「朝ごはん食べたの?」と聞かれて、「通勤前にパン食べたよ」とそっけなく返しておいた。なかなか父の容体のことなどを話す気にもなれない。
途中で同僚の方から母の携帯に電話があった。救急車に運ばれて、今は父は病院にいるらしい。父の状況を知りたかった。だが、救急隊員が部屋で寝ている父の様子を確認した時には、もうすでに父がこと切れていることだけは変えようのない事実だった。私と母は改めてその事実を確認し、絞られるようにお互いの目に涙がにじんだ。母の肩を抱き寄せて、父のことを思った。
父は小学校の教師をしていて定年まで後残り3年というところだった。最後のこの山口での単身赴任を終えて、実家のマンションに帰ってこられれば、もうあとは母と猫のミドリとゆっくりと過ごすのみだったのに。
それが、それがこんなタイミングで。たったひとりで朝、家族の誰にも見つからずに、すでに冷たくなってたなんて。最後に父は一体どんなことを考えていたのだろう。何を言いたかっただろう。最後くらい、私たち家族に会いたかったんじゃないかな。人って、なんでこんな急に逝っちゃうんだろう、なんでそれが今日なんだろう、なんでそれが私のお父さんなんだろう。さよならなんて言いたくないのに、それも言わせてもらえないなんて。
私は新幹線の中で朦朧とする意識の中で、父の背中を追いつづけていた。思い出す姿はいつも実家のソファで猫のミドリを膝の上に乗せて、頭を撫で付けているところだった。
「自分の機嫌くらいは、自分で取れるようにしないとな」父は何かにつけて、こう言い添えた。事実、父は自分で自分の機嫌を取れる「気のいい人」だった。いつもどこか鼻歌を歌って、何かよくわからないけど楽しいことを考えているように、振る舞うのが常だった。
小学校の教師だから、少しばかり教条的な部分もなくはなかったが、それでもとても鷹揚な人だった。中学から高校にかけて反抗期だった私には、そんな父の態度が気に食わなかったのだが、大人になった今では、父の言う自分で自分の機嫌を取れるということのその大事さがよくわかった。
駅からタクシーで乗りつけ、山口の地元の病院に駆けつけ、看護婦に父のいる部屋に通された。死後からすでに数時間経っているが、まだ頬には温かみが残っているかのようだった。確かに寝ているだけの、そのままの父だった。ただ息だけしていない。
母が父の頬を探る。私もぶにっとした鈍い肉を触ってみるが、確かに冷たかった。父の顔をまざまざと見る。あれ、こんな顔していたっけな。父は裸眼では何も見えないくらい目が弱く、度の強い眼鏡をしていたから、眼鏡をつけていない父の顔をここまでじっくりと眺めたことがない気がする。そして、確かに刻まれた顔の皺とたるみが、父という人間のこれまでの歩みを表しているようだった。いつ間にか、こんなに老けてしまって。それでそのまま、この顔で死んじゃうなんて。
「お父さん、お父さん」
「お父さん、康子も来てくれたのよ、ねえ、お父さん」
私の母の声に涙が混じる。ふいに私は、涙でしゃくり上げられた拍子に、同時にこれまで味わったことのない言いようのない吐き気を覚えた。無意識にそれを隣の母に悟られまいとする。何週間か前から続いている「それ」には、私は身に覚えがある。ただ、今はすごく反応している。動揺しているのかしら、この子も。
私の中に新しい命が芽生えたのに、同時に私の目の前で古い命が消えていった。
お父さん、どうしてもあなたにそれを見せたかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
