
TDL二次創作「A twinkle of Mouse」10.百万の夢
Rose&Crown Pub &Dining Roomは、エプコットのワールドショーケースのうち、イギリス・パビリオンの通りの角に建てられた、伝統的な佇まいのチェーン・パブである。重厚感に溢れた赤煉瓦と深緑の柱の店構えに、優雅な蔦模様を装飾したガラスを嵌め込んだ、金文字でレストラン名を掲げる建物のドアを押してゆくと、まるで水飴で艶を出したかのように滑らかなオーク材の卓と椅子、複雑な木目を露わにするフローリング、とりわけ巨大な棚にはスコットランドやアイルランドを始めとする各地の美しい酒瓶が並べられ、橙色に吊り下がる灯火を、ベテルギウスの如く反射させていた。窓に隔てられた先、通りに面するテラス席では、ハーバーで行われるナイト・ショーを一望できる一方、店内ではピアノ奏者の演じる軽快なジャズに酔うことができ、まさに店名に相応しく、富裕層から庶民まで、幅広い客層に愛されていた。もちろん実際の東京ディズニーランドにあるわけではない。
「へええ、割と雰囲気の良いところじゃないか。ザ・ブリティッシュパブ! って感じ」
デイビスは椅子を軋ませて席につきながら、嬉々としてメニューをめくった。最もこの酒場を楽しみにしていたエディは、着いて早々、早速水を流し込み、バーテンダーを呼び寄せる。
「マッカランのストレート、ダブルだ。頼むぜ」
「はい」
「ベイゼルヘンデン、トワイスアップ、シングルで」
「はい」
「ペプシコーラをお願いね」
「はい」
「えーっと、フィッシュ&チップスと、ムール貝の白ワイン蒸しと、ローストビーフにオイルサーディンだろ。それから、ハギス&マッシュ、リブステーキと、シェパーズパイ」
「チーズも、チーズも!」
「あと追加で、スモークしたカマンベールと、ナチョスと、サマーブルーカクテルね」
「はい」
横槍を入れてきたミッキーの声を拾いあげ、一通り注文を終えてから、デイビスは満足げにメニューを返却する。
「随分と頼んだな。この小さい丸テーブルに、全部収まるのか?」
「片っ端から平らげてゆけば、何とかなるだろー」
「つーか坊主ども、そんなに食えんのかよ」
「へーきへーき、男四人いるんだろ? それに若ェんだもん、スコットやエディとは違うって」
いらぬ火種を蒔いてゆくデイビスに、かちんと青筋を立てるスコットとエディ。ミッキーは慣れてきたのか、じゅるるる、と素知らぬ顔でペプシを吸っていた。
「しかしもう夜中だとはなあ、随分歩いたもんだよなー。クリッターカントリーまで、あとどのくらいかな?」
「はい、公式のMAP」

オレンジ:1日目の道のり
赤:2日目の道のり
「おいおい、こんなに苦労して、まだここまでしか来てねえってえのかい。牛歩の歩みじゃねえか」
「実際のTDLだったら、歩いて一分もかからないだろうけど、これはストーリーに起伏を作らなきゃいけない二次創作だからね」
「やれやれ。クリッターカントリーに辿り着くまで、あと何話かけないといけないのやら」
「先が思いやられるよなあぁ」
ずうぅん、と重い空気を漂わせる三人に向かって、ミッキーは自信満々に、シャンデリアの下でピーンと片腕をあげた。
「でも僕、ほんのちょっぴりだけ、魔法が使えるようになったんだよ!」
「おお、そいつは良いニュースだな。やるじゃねえか、ミッキー」
「ほら、見ていてね!」
蝋燭の如く立てたミッキーの人差し指に、全員がワクワクと拳を握りしめながら注目していると、やがて、しょわわ〜……という細かい音をとともに、せいぜいバースデーケーキ用の花火程度に噴きあがった火花が、店内の片隅を照らし出した。
「ハハッ。まだほんの、爪の先くらいだけど……」
自分でもなんとなく物寂しくなったのか、作り笑いを浮かべて取り繕うミッキー。しかしスコットは身を乗り出すと、無理に大きな背を屈めて、ミッキーの魔法の指へと咥えた煙草を近づけた。威力の弱すぎる火種に、随分と苦労していたようだが、ようやくふっと火がつくと、静かに笑みを引く。
「ありがとう。旨いよ」
その言葉を受けて、ぱっ、と輝いたミッキーのその笑顔は、子ども部屋のベッドサイドの灯りのように晴れ晴れしく見えた。
(くっそー、スコットの奴、いいとこばっか持ってきやがって)
というわけでデイビスは、壁に向かって、自分のライターで咥え煙草に火をつける。こいつ、何考えているか丸わかりだな、とエディは半目になってその様子を眺めていた。
「ま、雨降って地固まるってやつだな、坊主。あの狐の詐欺師の野郎に捕まった時にゃハラハラしたが、一歩前進したようで何よりだぜ」
「そういやさ。なんでディズニーランドに呼んだのが、俺たちストームライダーのパイロットだったんだ? ジーニーとかの魔法を使える奴の方が、強力な味方になってくれそうじゃん」
素朴なデイビスの問いに、ミッキーは、それまで啜っていたストローから、ぴん、とコーラの雫を飛ばしながら、さらりと言った。
「だって、ジーニーはマジックランプシアターがあるんだもの。忙しい彼を、TDL側に呼ぶわけにはいかないよ」
「ストームライダーはクローズしてるから暇だっていうのかよ!?」
「そ、そんなセンシティブなことは、僕の口からはとても」
「ほとんどYESって言ってるようなもんだろーがっ!!」
「もうやめてくれ、デイビス。お前がストームライダーのクローズに言及するたびに、俺の心はどんどん荒んでゆくんだ」
スコットは、はあ、と溜め息を吐き、遠い目を虚空へと向けた。
「時代は流れた。ストームライダー2(注、ストームライダーIIじゃない)の企画は立ち消えになり、もしかすればソアリンにちらっと出られるかもという、最後の儚い希望も、粉々に粉砕された。ポート・ディスカバリーのBGSから消え、公式の買い物袋からも消え、そしてストームライダーの名は伝説へ——」
「あんた、いったい何言ってるんだ?」
「クソッ、一度くらい、ストームライダーIの活躍するストーリーがあっても良かったのに。雷がなければ、雷がなければ」
「大の大人がよせよ、兄ちゃん。みっともねえなあ」
顔を覆って歔欷し、肩を震わせるスコットに、エディは呆れながら溜め息をついた。
「しっかしおめえたち、向こうのパークじゃ、そんなに人気者だったのか? 俺はどうもトゥーンタウンに引っ込んでいたから、TDS事情には疎くてよ」
「いやまあ、そりゃ熱狂的なファンも多かったけど、ぶっちゃけた話すれば、待ち時間の安定したスリルライドがストームライダーくらいしかなかったから、未だに語り草になってるってのもあるんじゃねえのか?」
「そうだな、回転率は良いし、間口は広く、ストーリーや体感はTDSに合っていた。が、システムは老朽化し始めていたので、クローズが検討されたのは仕方ない」
「ってなわけで、ストームライダーは眠りにつきました、と。ま、この小説じゃ、あんまり関係ねえことになってるけど」
「いや、この先も、クローズネタはちょくちょくいじるよ」
「あ、はい、そうですか」
となると、スコットはこの先もちょくちょく落ち込むことになるのだろうか、めんどくせえなあ、とげんなりするデイビス。さくさくとペプシの中の氷をかき混ぜていたミッキーは、何気なく言葉を切って、
「それにね。君たちは、東京ディズニーリゾートの中で唯一——」
「ん?」
片眉をあげて訊き返すデイビスに、ミッキーは少し黙ってから、微笑んで首を振った。
「でも今のところ、僕たちパーティの内訳はいい感じじゃないかな? 一応、魔法を使える僕に、身体能力なら負けなしのスコット、ずる賢さは飛び抜けてるデイビス、情報収集が本業のエディ。バランスは取れているはずだよ」
「なるほど、確かにな」
「今、俺のこと、ずる賢いっつったか?」
「けれどもこのままじゃ、あまりに手堅すぎて、ヴィランズの不意をつくことはできない。だから僕らには、TDL最強のトリックスター、ロジャー・ラビットが必要なんだ」
「はあー。何だかんだで、お前も色々と考えていたんだな」
感心しながら、デイビスはぱくりとムール貝の身を頬張り、満足げな笑みをこぼした。
「ま、当分ヴィランズとの対決は先だろうけどなー。今はこうして、旨いモンに旨い酒をかっ喰らって、クリッターカントリーに行くまでの英気を養って、」
「ん。このアトラクションはなんだ?」
その隣で、のんびりとマップを見つめていたスコットは、太い指先でファンタジーランドの一角を指差す。
「"怖いキャラクターが登場"……となっているが」
途端に、ミッキーは両手で顔を覆い、重々しい影に打ちひしがれた。
「それはTDL最恐アトラクションだよ——」
「えっ、なんで? スリルライドでも、お化け屋敷なわけでもねえんだろ?」
ミッキーはちらっとデイビスに目を配ると、聞こえるか聞こえないかの声で言った。
「……こ……恐ーいヴィランのお婆さんが……出てくる、から……」
一瞬の静寂。
そして次の瞬間、破裂するような大笑いをしながら、デイビスはハギスにぶすりとナイフを突き立て、存分に胸を張った。
「ヴィランっつっても、萎びた婆さんだろ? ゴリラみたいにリンゴをぶつけてくんならともかく、そんな脅威的な存在になるわけねえだろうが!」
「ほ、本当なんだよー! 侮ったら死んじゃうよ!」
「おい、坊主、婆さんを甘く見てると怪我するぜ」
「リンゴだけに、甘く見たら酸っぱい目に遭うってか? アッハッハ、流石だぜ、エディ!」
「だって、だって……」
ミッキーは震える手を握りしめて拳を作ると、ドン、とテーブルを叩いて言い放った。
「だって映画開始八分で、継娘の心臓を抉り出してこいって命令するんだよ!? デイビスはそんなことを本気で言っている人、今までに会ったことがあるのかい!?」
ふたたび、しーん、と落ちる沈黙。デイビスはすっすっと長い前髪を直し、慎重に目の前で手を組み、その眼光を鋭く煌めかせた。
「よし。心構えを変えよう」
「お前以外はみんな真面目に聞いているんだよ」
「だいたい、娘の心臓なんかどうすんだよ。日がな一日、ぼーっと眺めているのか?」
「食べるんじゃない?」
「えっ?」
「だから、食べるんじゃない? 白雪姫の心臓を」
首を傾げたミッキーの言葉に、しばらく沈黙の続いた挙句、天使のような顔でデイビスは微笑する。
「えーと、それは。文化だの環境だのを抜きにして、食人嗜好をお持ちのご婦人、ってわけじゃねえんだよな?」
「どうだろう。ディズニー映画じゃ、そんな描写はなかったけど」
「よかった。それじゃあ、何とか——」
「でも童話だと、心臓を塩茹でにして、食べてた」
溶けかかったチーズを十センチ以上伸ばしながら語るミッキー。デイビスはムンクの叫びの如く耳に手を当てたまま、ガタッ、と椅子から立ちあがった。
「どうするーーーーー!?!?!?!?」
「だから、それを今から話し合うとこなんだろーがッ!! 行儀が悪いな、席につけ!」
「TDLは恐ろしく治安の悪い場所だ。TDSじゃ考えらんねーよ」
「それはどうだろうな。確かロストリバー・デルタの神殿にも、生贄の心臓を取り出すための祭壇が——」
「馬鹿、スコット、思い出させんなよーっ!」
ハムスターの如く震えるデイビスをよそに、職業柄、そういったグロ話題に慣れているエディは、腕を組んだまま神妙に頷き、
「まあ、元々は遠い昔の民話でえ。現代から見れば残酷に思える臭いがこびりついているのは、間違いねえだろうな」
「うん。死体愛好とか、児童労働とか、魔女裁判とかね」
「やめろーっ! せっかくの飯の時間中に、そんなエグい話をするなーっ!!」
ブンブンと激しく首を振るデイビス。目の前にあるハギスだのステーキだのが、徐々に違う食べものに見えてくる。
「とにかく、これで分かったでしょ? 最恐アトラクションと呼ばれる理由」
「ううう、分かりたくないのに、分かっちまった」
さく、と頬張ったシェパーズパイを、エディはスコッチで喉の奥に流し込みながら、
「しっかし、どう対抗するつもりでえ? 俺らは魔法もなんにも使えねえ、一般人だぞ」
「大丈夫! 心強い味方がいるから。魔女討伐隊のギルドに登録している、七人のこびとたちに依頼しよう」
「また適当な設定を持ち出して、展開を誤魔化そうとしているな」
「まあ、それでヴィランズを倒せるなら、文句はないよ」
空になったグラスを脇に置いて、ミッキーは静かにうつむく。霧のふいたような磨りガラスからは、うっすらと、シンデレラ城の光が透けていた。
「ミニーを早く助けに行かなくっちゃいけないのは分かってる。だけど、焦っちゃ駄目なんだ。ちゃんと、ヴィランズに対抗する術を身につけなくちゃ——」
内に秘めた熱を滾らせながら呟かれた言葉は、まるで暖炉の中に揺らめく炎と同じ。それでいてその目には、もはや逼迫したような息苦しさはなく、燃え盛るのは、覚悟と情熱だけ。その気迫を受けて、スコットは、隣のデイビスにこそっと耳打ちした。
「ミッキーの奴、随分前向きになってきてるじゃないか。お前、何を言ったんだ?」
「べっつにー? ただちょっと、二人で旅行に出かけただけだよ」
というわけでデイビスは、優越感に浸りながら、これ見よがしに酒を煽る。うぜえなあ、とスコットは眉を顰めながら、切り分けたシェパーズパイをミッキーによそってやった。
と、その時、ミッキーのポケットが振動した。おもむろに引っ張り出すと、彼の魔法の無線機である。事前にセットしていた転送設定により、留守番電話の音声がそのまま流れてきたのだ。
「よお、ドロレス、エディは事務所にいないぜ。仕事中だ!」
《仕事ですって? あの人、今は何をやってるの?》
「最近のエディは——ヘッヘッ、口には出せねえ大物とつるんでるぜえ。臭う、臭う、とんでもねえ犯罪の匂いだ。ディズニーランドをひっくり返す大事件の予感がするぜえ」
だくだくと正直すぎる会話を廃水の如く垂れ流す電話に、さすがのミッキーも呆れ返った。
「ねえ、エディの留守番電話、さすがに変えた方がいいんじゃないの? 案件情報を垂れ流しすぎだよ」
「糞ッ、トゥーンタウンの一番安い留守電サービスと契約したのがまずかったぜ」
言いながら無線機を引ったくり、残りの三人に手を振られながら、店の外へと出るエディ。扉を開いた途端、すっと一気に暗がる秋の夜空、虫の音のうずたかく鳴る枯葉の匂いの中で、そうまで長く離れてはいないはずなのに、今は懐かしく思えるアルトが、電話越しの不機嫌な声で応答した。
「ドロレス、悪いな。なんか用か」
《あらエディ、明日は金曜日よ。この店じゃ何やるか分かってる?》
「花金商法——」
《もう! ボスが帳簿をチェックする日よ。貸したお金を返してくれなかったら、あたしクビになっちゃうわ》
「へっ、心配するな、ドロレス。今、大口の仕事を抱えてるんでえ」
《あらそうなの。いくら?》
少しの間、言葉に詰まるエディ。スコットとの商談の際には、金などいらない、と啖呵を切ったが、よく考えてみれば、そんなことを言ってのける金銭的余裕など、とても残されてはいないのだった。
《ほらご覧なさい。アテなどないんでしょ》
「アテはある、アテはあるんだ。ただちょっと——額面で交渉しているだけだ」
《もう、とにかく、明日の夜までに五十ドルを振り込んでおいてちょうだい。残りの五十ドルは再来週までよ、期限を延ばすのはこれっきりなんだから。本当にツケも払わずに、あなたったら、いったいどこへ行っているのよ?》
ほとんどその内容を心に留めることなく、ぼんやりとドロレスの声を聞きながら、少し声色は枯れたが、その分、深みは増したな、と思った。そして、あの痩せた手、薄く小さく、白蝋を塗ったようにつやのあるあの指が、今、自宅から電話に触れているのだ、と思い浮かべた。それから、寸の詰まった指が赤らんで並んでいる、事務仕事で荒れてしまった自分の手のひらに目を落とした。
やがて、ウイスキーでやや掠れ気味になった声が、ゆっくりと言葉を紡いだ。
「ああ、ロジャーを捜しに行く。あの野郎、インスタント穴に落ちて、クリッターカントリーの方にまで流されちまってよ」
《まあ——行方不明になっていたの? また、あなたのクローゼットの中にでも隠れているんじゃ——》
「それだったら、苦労しねえよ。とにかく、ロジャーを連れて帰る。んでもって、帰ってきた暁には、ターミナル・バーで一杯奢らせるさ。大丈夫、お前が案じるようなことは何もねえんだ」
《冗談言わないでよ。私があなたの身の上を心配するわけないでしょ?》
「そうか、悪いな。……どうもお前は、昔から、心配性だった気がしてよ」
鼻でくぐもるように軽く息を吹き散らしながら、安心させるように低く囁く声。それはドロレスが十年以上に渡って耳にし続けた、一番懐かしくて、一番嫌いな声だ。その笑い混じりの言葉を聞くたび、胸が詰まって、何も言えなくなる。
エディはいつだって、大丈夫だとしか言ってくれない、とドロレスは思う。彼の口癖ときたら、背も低いし腹も出てる、そんな男が自慢できるものと言えば、丈夫な体だけなんだ、とおどけたように自嘲するばかり。俺の頑丈さときたらトゥーン並みだぜ、インスタント穴に落っこちたって、頭にピアノを落としたって、大丈夫、きっと死にゃしねえよ。
そんなことはない、あなたは危険も厭わずに難事件に飛び込んでゆくし、そのことで深く傷つきもする。実際、テディが死んだ時だって、あなたは感情を押し隠して、一度も涙を見せはしなかった。けれどもあなたは笑わなくなったし、おどけもしなくなった。時々、私の眼差しに気づくと、そっとちいさく、疲れたように頬を緩めてみせるだけ——まるで、心が欠けてしまったのを、たったひとりで背負おうとするかのように。
けれども、何を言ったらいいの?
それが弟へと捧げる悼みなら、どうやって私があなたを癒せるというの?
そこまで考えて——結局、自分も何ひとつ言葉にできない人間だ、ということに気づいたドロレスは、思い悩むのを打ち切り、菫のような声をさらにか細くして、早口で囁いた。
《無事に戻ってきなさいよ。借金を返してもらわなくちゃ》
「ああ、もちろん。それからな、ドロレス」
ふっと、まるで眼差しすらも同時に投げられたかのような沈黙に、息が詰まった。エディは少し言葉を切って、
「——いい男を見つけろよ」
《あなたって、本当に最低な男ね!》
電話を切る音が、乱暴に耳元で響く錯覚を受け、溜め息をついて無線を切ると、ちょうど、ベルを鳴らしながら店を出てきたスコットが、店内の黄色い明かりを人影の形に切り取りながら、こちらを見出したところだった。ああ、という低い声に、エディは首を振りながら立ちあがった。
「通話は終わったのか、エディ」
「ああ。昔馴染みからの野暮用だった」
「そうかね。もう使わないなら、私にも無線機を貸してもらいたい。こちらも野暮用があってね」
「へえ、奥さんへのラブコールかい」
「まあ、そんなところだ」
エディのからかいを軽く流しつつ、無線機を受け取った彼は、なぜかすぐにはかけず、何やら厳しい顔をしながら、星の散開する夜空を見あげていた。インク壺を覗き込んだかのような闇は、星がなければ、立っている地平さえも見失ってしまいそうだった。それを仰ぎ見ている広い背中へ、
「スコット」
とエディは初めて、その名を呼んだ。スコットは真っ直ぐに振り返り、星の中を彷徨っていた眼を地上へ向けた。
「言いにくいことだが……やっぱり、金を貸してくれねえか。その……あの時言った気持ちは、嘘じゃない。だけど、急に必要になっちまったんだ。言っとくが、ウイスキーに費やすわけじゃねえ。返さなくちゃならねえアテがあってな」
口にすると、酷く惨めな気分になったが、スコットは顔色ひとつ変えずにネクタイの位置を直し、懐をまさぐった。次の瞬間には、その漆を思わせるような手は革の財布を開き、エディに数枚の紙幣を握らせていた。
「元々、報酬は支払うつもりだった。君は金などいらないと言ったが、何日もかかる旅に同行させて、タダ働きで収まるはずがない」
「……ありがとうよ」
「礼を言うのはこちらの方だ。これは君の受け取るべき、当然の対価なのだからな。ロジャーを発見するまで、よろしく頼む」
微かなオリーブがかったそのヘーゼル色の瞳の底へ、スコットが平然とした面持ちで、彼の肩を優しく叩く姿が映る。そして、手に持った無線機のボタンを親指で押し込むと、
「サラ? 私だ。うん、すまなかった、ちょっと変なことに巻き込まれてしまって。……ああ、そうそう。それより、体調は? ……うん、うん。……ああ、そうか——」
と言いながら、ほつほつと街明かりの点じるばかりの、淋しい闇の奥へ吸い込まれていった。
耳に痛いほどに鳴り響く鈴虫の声が、頭上に覆い被さる紅葉の帷に響いて、急に肌身に滲みてきた。気づけば、大きな夜空に包まれて、狂おしいほどにひとりきりだった。頬に明るさを投げかけてくる、光溢れるドアをこじ開けると、艶をよく反射する遠くのテーブルで、機嫌よく飲酒していたデイビスが気づいて、ぶんぶんとこちらに手を振ってきた。
「よーお、エディ! 待ってたぜえ、ぜひともあんたに聞いてもらいたいことがあってよ」
「あぁん? なんだ坊主、俺にかよ?」
「そーそー、俺たち、カウンターにいたこの人と仲良くなっちゃってさ。さ、自己紹介をよろしく」
ニヤニヤしながら、ジンで満たしたグラスを煽るデイビスに、馴れ馴れしく肩を叩かれた男も、負けず劣らずニヤニヤとして、カンカン帽をちょっとあげるなり、その赤とオレンジの縦縞が入った派手なジャケットの襟を、少しばかり気取って整えてみせた。イギリス紳士——とはとても見えない。大きな眉に、羽ばたくほどに軽妙な微笑み、それに白いフランネルのズボンと、目を惹くスカイブルーの蝶ネクタイは、陽気なコメディアンを思わせる。彼とエディは、固い握手を交わした。
「やあ。君も、彼の友達? 僕は、バートっていうんだ」
「エディ・バリアントだ。……で、坊主。この兄ちゃんが、いったいなんだってんだ?」
「おいおい、エディったら、気づかねえのかよ? 吹き替えCVが、あんたのとこのロジャーと同じ、山ちゃんなんだよ!」
ああ、そんなことかい。かくっ、とよれたジャケットを載せた肩を落とすエディ。バートは相変わらずお調子者らしく眉をあげ、実に自信たっぷりにニヤニヤとしていた。
「あのなあ、坊主、山寺宏一の声なんて、TDLを歩けばそこらじゅうから聞こえてくるんだよ。レアでもなんともねえだろうが」
「つまんない人だなあ、エディったら」
「いいかい、ミッキー君、こんな大人になってしまっては駄目だよ。君たちが声優に関心を払うだけで、アニメも、洋画も、テーマパークも、もっともっと豊かに楽しめるものなんだ」
「パークのウッディやバズの声が映画と違いすぎて、一瞬、誰だか分からなくなるとか?」
「TDSのメインナレーション担当が、タワー・オブ・テラーの記者に紛れているだとか」
「もう、そのへんにしてちょうだい、バート!」
その時、くるりとカウンターのハイチェアを回して、紺青の眼を煌めかせる女性が振り返る。デイビスも、ミッキーも、エディも、思わずそちらを向いた。大変な美人だった。少し高慢ちきに見えたが、夜の窓辺から風に舞い込んでくる桜の花の、ひとひら、ふたひらを思わせる風貌で、凛々しい眉に、鮮やかに染まった小さな唇、そして珍しい青紫の瞳が、ぴりっとしたスパイスのようにバートを見据えている。衣装もまた独特で、さながら花嫁の如く繊細な純白のレースを重ねた、ふんわりとしたワンピースを纏い、アクセントとして取り入れられたポピーレッドのステッチやリボン、そして彼女を何よりもスタイル良く見せるコルセット・ベルトは、その背の高さを、より鮮烈に強調させた。スタイルも服装も姿勢もかっちりとしていて、シニョンに結いあげた黒髪の上から、真っ白なつば広の、マーガレットにも似たミリネリーを被り、その帽子を高貴な淑女らしく、純白のレースのチュールで、きゅっと顎下へ結んでいる。
「バート、あなたって、いつだって簡単なことを難しくするんだから」
「そう怒らないでくれよ、メリー」
「メリー? わあ、君って、まさか!」
まるできびきびとした校長のように、人を惹きつける身振りで首を傾げるその姿を見て、ミッキーは目を丸くした。
「そうとも、まさに君の考えている通りだよ、ミッキー君! この素敵なシルエットを見れば、一発で分かるさ——メリー・ポピンズ!」
バートからの熱烈な紹介にも、つんと澄ましたまま、彼女はバーテンダーからショートグラスを受け取って、さくらんぼのように紅い艶を放つ唇で、一口ふくむと、魔法の液体の香りを吸い込んだ。
「ラム・パンチね」
気取った、堂々とした発音で、巻き舌を込めたRの音を強く鳴らしながら、
「結構イケるわ。ひっく」
と、ちいさなしゃっくりをこぼす。
「メリー・ポピンズは、君たちが夢にも思わないような場所へ連れて行ってくれるよ。メリーがパチンと指を鳴らすと——」
バートは声をひそめて、まるで宝箱に隠されていた世界の秘密を打ち明けるように、ニヤリと微笑んだ。
「——たちまち、不思議なことが起こるんだ」
「残念だけど私、そんなつもりは全然ないの」
「本当に? こんな素敵な秋の夜に、君が何にもせずにじっとしていられるわけがあるかい?」
「また、そんなことを言って、人をそそのかそうとするんだから!」
美しく涼やかな声で、けんもほろろに鼻を上に向けるメリーと、悪戯そうに眉を動かすバートのそばへ、ミッキーは矢も盾もたまらない様子で駆け寄ると、軽く背伸びをして、顔を覗き込んだ。
「君があの有名な、メリー・ポピンズだね! お会いできて光栄だよ。僕はミッキー」
「ミッキー・マウスさん、お噂はかねがね。私にとっても、スーパースタアとの謁見は、大変な名誉でございますわ」
メリーはようやく、スカートの裾をつまんで立ちあがると、その白い布に包まれた腰をコンパスのように正確に折って、美しいレースの飾りをひらりと顎の下に垂らしながら、深いお辞儀をした。ミッキーは感動のあまり、すっかり真っ赤になって、声を震わせた。
「あの——あの。これ、プレゼントです」
「あら。どうもありがと」
「花束じゃねーか。どこから出してきたんだよ」
「真心から……」
「どういうことだ?」
デイビスのツッコミにも動じず、ミッキーの手渡してくるピンクの十数本の薔薇を受け取りながら、まるで雲の上の存在のように澄ました顔で、メリーは立ちのぼる花の匂いを嗅ぎ、溜め息をついた。
「美しいものは、永遠の喜びね」
「それで——もしよかったら、あの——僕と一緒に、写真を撮ってもらえますか?」
「ええ、もちろん」
「お前、意外とミーハーなんだなあ」
「だって、ずっとファンだったんだもの。この千載一遇のチャンスを逃すわけにはいかないよ」
ミッキーは、持参してきた一眼レフをいそいそとバートに渡して、輝くばかりのメリーとともに、紅潮した笑みを浮かべてポーズを取った。
「はい、ミッキー」
パシャッ。
「サインも入れてあげるわ」

「わあ、凄く良い写真だ!」
「存分にグリを楽しんでるなー」
「ありがとう、宝物にするよ!」
「喜んでいただけてとても嬉しいですわ」
「僕——僕、映画を観て以来、ずっと君に会ってみたかったんだ! メリー・ポピンズは、いつだって完璧——この世で最も完璧に近い乳母なのでしょう? ああ、今日はなんて素晴らしい日なんだろう! 本当に、言葉ではとても言い表せない気持ちだよ!」
するとメリーはいきなり、レースに包まれた細い片腕をすっとあげて、その言葉を制するように、にっこりと笑った。
「いえいえいえ、そんなことはありませんわ! こんな時にぴったりの言葉があります。そうよね、バート?」
すると、カウンターにもたれかかり、それまでつやつやとしたキャンディー・アップルを齧っていた彼は、丸い果実の上を垂れてゆく最後の果汁を舐め取りながら、おどけたように肩をすくめた。
「教えてやれよ」
「それじゃ」
白砂糖のように透ける肌、そして薔薇色の頬を紅潮させて、美しい眉を傘の柄の如くくいっとあげると、帽子を取り、そのさくらんぼのように潤った唇は一気に、舌の噛みそうなほど長々しい言葉を、完璧な滑舌で歌い始めるのだつた。
♪It's ——……
supercalifragilisticexpialidocious!
Even though the sound of it is something quite atrocious
If you say it loud enough you'll always sound precocious:
Supercalifragilisticexpialidocious!
それは——
"スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス"!
オソロシイ呪文に聞こえるかもしれないけれど
大きな声で言えたらぐんと大人になれるわ
スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス!
Um diddle diddle diddle, um diddle ay!
Um diddle diddle diddle, um diddle ay!
アンディリディリディリ アンディディライ!
アンディリディリディリ アンディディライ!
すると、そばで見ていたバートも、ぽんとハイチェアから飛び降りると、メリーの隣へ颯爽と踊りに加わってきた。
♪Because I was afraid to speak when I was just a lad
Me father gave me nose a tweak and told me I was bad
But then one day I learned a word that saved me achin' nose
The biggest word you ever heard, and this is how it goes:
僕が喋るのにビクビクしていた子どもの頃は
父さんが鼻をつねって悪い子だって叱るんだ
でもある日鼻のじくじくから守ってくれる言葉に出会った
こんな長大な言葉は聞いたことないだろ? こうやって口にするのさ!
するとメリーは桜の花びらがこぼれるように屈託なく笑うと、その真っ白なレースのスカートを大っぴらに翻しながら、まるでビデオの早回しのように奇妙で軽快なダンスを披露した。バートと合わせれば、まるで鏡合わせの双子のよう——先ほどまでの冷ややかな表情はどこへやら、今は少女の如くいたいけのない笑みを浮かべ、その眼からは、楽しくて仕方のないほどの煌めきが飛び散っていた。
♪Oh, supercalifragilisticexpialidocious!
Even though the sound of it is something quite atrocious
If you say it loud enough you'll always sound precocious
Supercalifragilisticexpialidocious!
おお!
スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス!
オソロシイ呪文に聞こえるかもしれないけれど
大きな声で言えたらぐんと成長した気分!
スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス!
He traveled all around the world and everywhere he went
He'd use his word and all would say, "There goes a clever gent!"
彼は世界中どこへだって旅したの
この言葉を使うといつも驚かれたものよ、「なんと偉大なる紳士なのだ!」
When Dukes or Maharajas pass the time of day with me
I say me special word and then they ask me out to tea
公爵やマハラジャと一緒に過ごした時には
この特別な言葉を口にしたら たちまちお茶に招かれたものさ!
Oh, supercalifragilisticexpialidocious!
Even though the sound of it is something quite atrocious
If you say it loud enough you'll always sound precocious
Supercalifragilisticexpialidocious!
おお!
スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス!
オソロシイ呪文に聞こえるかもしれないけれど
大きな声で言えたらぐんと成長した気分!
スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス!
So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay
Just summon up this word and then you've got a lot to say
But better use it carefully or it could change your life!
言葉が見つからなくたってうろたえることはないわ
この言葉を口にしたらスラスラ出てくるの
でも用心して、人生が変わるかもしれないんだから——
Supercalifragilisticexpialidocious!
Supercalifragilisticexpialidocious!
Supercalifragilisticexpialidocious——
Supercalifragilisticexpialidocious!
見事なハーモニーでその騒がしい曲が締め括られると同時、遠い稲妻が鳴り響き、パラパラパラ、と拍手のような音をばら撒いてゆく雨——かと思ったら、酒場に降りそそいできたのは、なんと、細かくきらきらとした金平糖だった。その真下で、メリーは優雅に傘をさしながら、元通りのつんとした表情に戻って、彫刻めいた長身を見事に伸ばしつつ、その金平糖を、傘布の上にぱちぱちと跳ねさせていた。
「な、何の騒ぎだ、これは」
ようやく外からパブへと戻ってきたスコットは、あたり一面に降ってくる金平糖にぎょっとして、おかしな夢でも見ているのだろうかと自分の精神状態を疑った。バートは意気揚々と両手を広げて、楽しそうに糖分の雨を見あげた。
「どうだい、これこそまさに、"お菓子な"夢!メリー・ポピンズは、とっても素敵な魔法が使えるんだよ!」
「まったく、お冗談が上手だこと」
まるで子猫のように尖った鼻を持ちあげ、ぷいっ、と明後日の方を向いてしまうメリー。バートは苦笑して、ミッキーに向かって大袈裟に肩をすくめた。
「実写キャラクター組は、現実の俳優にしか出せない、人間味が魅力だね。どちらかというと、君たちもこっち側に近い人間なんじゃないかい、キャプテン・デイビス君に、エディ・バリアント君?」
「あれ、どこで俺の名前……」
「口の中でモゴモゴ言わないの! さーあ、ここからはミュージカル・タイムだ。次は誰が歌うんだ? あなた? それとも、君?」
「俺たちゃ、ミュージカル俳優じゃないぜ」
「なんだって? ミュージカルの曲を歌わないなんて、そいつはなんともったいないことだ!」
バートは目を丸くして、持っていた杖をくるくる回し、うっとりとした瞳で囁いた。
「ミュージカル、それは世界を素晴らしいものの中に巻き込む力。現実を夢に引っ張り込み、素敵な物語に書き換え、またたく間にみんなを踊らせてしまう力。
良いミュージカルに出会えた時、人はこんなことに気づくんだ。幸せはすぐそこにある。宝箱の中に眠っているばかりじゃない、人の形をして、ノックをし、ドアを開けて——思いがけないやり方で、僕たちと出会うこともあるんだって」
「そうですわ、思いもよらない不思議なことも、時にはきちんと身なりを整えて、品の良い形でやってくることがありますの。例えば、こんな風に」
ぱちん——
バートの熱の籠もった演説も、メリーが指を鳴らすその瞬間までだった。カランカラン、と鐘が鳴り、その時分に店に入ってきたのは、漆黒の修道服を纏った、大柄の中年女性——ご自慢の、羊のように膨れたパンチパーマも、張りのあるふくよかな谷間も、今はトゥニカやベール、伝統的なウィンプルの下に完璧に隠し、代わりに強調されてくるのは、その力強さを秘めた、明るい目だった。美しい栗色の肌とのコントラストを描いて、その白眼はくっきりと浮かびあがり、自信を湛えた瞳孔が素早く動いて、眉も唇も、まだ何も言っていないのに、異様な存在感に満ちている。そして注意深い眼差しが、ぐるりと店内を一周したかと思うと、突然、虎ののぼるような声を腹から響かせ、
「ハイハイ、どいたどいた! そこ、道空けて!」
と叱りつける声量は、デイビスが床からぴょんと跳ねあがるくらいだった。女はその様子を、大きな二重瞼で一瞥すると、妙にからっとした濁声で、ふたたび、彼をどやしつける。
「あんたがそこにぼーっと突っ立っているから、踊れないじゃないのよさ! それともあんた、まさかこんなちっぽけなステージで、このデロリス様に満足しろっていうわけ? あたしゃねえ、ネオンがぴかぴか光ったリノの街で、ゴージャスな金ピカの衣装を着て、クラブを席巻した女よ。そりゃ、ちょっとは売れない時期もあったけど……でも、これまでの人生には感謝してる。毎夜、ちゃーんと神様にも祈ってんのよ。天に召します主よ、明日も、明後日も、最高にイカしてて、男をたらしこみまくる声を授けてください、ってね」
「よく喋る修道女だな。一人で何行分の台詞を使うつもりだ」
物凄い勢いと迫力で繰り広げられる女の説教に、呆気に取られているデイビスを後ろに庇って、スコットはうんざりとした声で嘯く。デロリスは不審げに眉を吊りあげた。
「なんだい、あんたは?」
「妙な言いがかりをつけて、私の同僚を威圧するのはやめていただきたい」
「兄ちゃん、どんなハードボイルドを気取ってるのか知らないけど、過保護だねえ。そんな甘やかし方をしてるんじゃ、女だって、スタコラ逃げちまうよ!」
「なんだと?」
「あんた、既婚者かい? 指輪してるもんね。余計なお世話かもしんないけど、家庭のイザコザに気をつけた方がいいよ」
かちんっと頭の血管を切らせたスコットを、デイビスが慌てて羽交い締めにして押し止めた。
「よせよー、スコット! 酒場で姉ちゃんと喧嘩なんて、みっともないぜ!」
「この——この破戒僧め! ディズニーで宗教色を撒き散らして良いと思っているのか!」
「そのまま縄でもつけて、しっかり兄ちゃんを捕まえておいてよ、坊や! マスター、コーラ・フロートを!」
言うなり、シャーッ、とカウンターを滑って飛び込んでくるグラスを、ぱしり、とデロリスの手のひらが受け止めた。分厚い唇がストローを咥えるなり、彼女はくるりと振り向いて、修道服に包まれた豊満な腰に手をあてる。
「ま、気分を害したなら悪かったね。あたしゃ別に、喧嘩を売りにきたつもりはないんだよ」
「コーラ・フロートを飲みにきただけか?」
「そりゃそうさ。本当は酒をかっくらいたいけど、この格好じゃあね」
「やっぱり破戒僧じゃないか」
「なんか文句でもあんの?」
するとふたたび、店の入り口が開いて、隙間からおずおずとした人影が顔を出した。まだ修道女の修練期間中なのであろう、その豊かな服を完全にウィンプルには収めてはおらず、人参色の赤毛を黒いコルネットから覗かせた、ひょろりと背の高い、痩せっぽちの若い女だった。それまで何にも臆さず、余裕たっぷりの姿勢を崩さなかったデロリスは、その女を見るなり、急に顔色を変えて、慌てふためきながらグラスを置く。女は、やっとの思いで追いかけてきたデロリスを見つけると、嬉しそうに顔を綻ばせ、遠慮がちに手を振った。デロリスは猪の如くすっ飛んでゆき、他の連中の眼差しから庇うように、彼女に向かってちいさく叱咤した。
「ちょっと——なんでこんなところに来たのさ! さっさと帰んなきゃだめだよ!」
「あ、あなたがリノにいた時のように、酔っ払いに奉仕するなら、お手伝いしたいと思ったんです——」
「いけないに決まってるじゃないのさ! 特にあんたは、まだ修練者なんだから!」
慌てて叱りつけてくるデロリスにしゅんとなり、彼女から目を外したその女性は、デイビスを目にした瞬間、はっと大きく息を呑みながら、稲妻に打たれたように立ち止まった。それからみるみるうちに、ぽっと、そのそばかすの浮いた頬を桜色に染めると、最後に見事、花開くような笑顔が咲くにいたった。
「ん?」
その射抜くような眼差しを受けて、デイビスはきょとんと目を瞬かせる。
「ねえ、デロリス、私——」
「おやめ、メアリー・ロバート。ここではあたしは、シスター・マリー・クラレンスだ」
「失礼、シスター・クラレンス。あの……でも……ようく、あの人を見て。彼ったら、……じゃありませんこと?」
こそこそと耳打ちするメアリー・ロバートに、デロリスは大げさに肩を竦め、眉を歪めてみせた。
「なに。あんた、ああいうチャラチャラしたのがタイプなの? あたしゃ止めないけどね。気になるんなら、口説き落としてきたらどうだい」
「いやだわ、そんなこと、神様がお許しになるはずもないのに!」
くすくすっ、と笑いをこぼすメアリー・ロバートを見て、うう、こういう女子校じみた空気は苦手だ、とデイビスは身震いした。デロリスは、突き出しのトルティーヤ・チップスをつまみながら、どこ吹く風、といった調子で、
「そんじゃ、口説くまでいかなくても、踊ったら? 酒場なんだから、何もそのくらい、不思議なことじゃないでしょ」
「あら! でも——でも、一人じゃ流石に——」
「じゃ、あたしも踊るよ。それでいいだろ」
デロリスは早速、袖元に入れてきた手持ちを漁ると、
「そこの兄ちゃん!」
と、ぴいんと銀のコインをはじき、円を描いて飛んでゆくそれが、見事にスコットの手元に収まった。
「なんか適当に、ジュークボックスの曲を選んでよ。あんたのセンスでいいからさ、ひとつ、踊りやすいのを頼むよ」
「私の?」
「そうさ。ダサい音楽はかけないでよね」
一方のメアリー・ロバートは、おずおずとデイビスのそばに近寄ろうとしたが、ぱちっ、と火花が散ったように彼と目線の合うなり、きゃっ、と両手の中に顔を隠してしまった。
「なんなんだよー?」
「ウブなのよ。だけどね、忠告しとくけど、あんた、修道女を粗末に扱ったら、神様からバチが当たるよ」
「い、いや俺、まだ何もしてねえんだけど」
「何かしでかしそうな顔をしているから、こうやって事前に話しているんだよ」
すると、修道女たちの様子をカウンターに凭れて見守っていたバートが立ちあがり、
「それじゃ、彼の代わりに、僕とダンスはどうだい? ハンサムとは言えないけど、踊りのステップには自信があるよ」
「まあ……いいの!? 私、私、ダンスなんて——遠い昔に、プロムで踊ったくらい!」
目をキラキラとさせて喜ぶメアリー・ロバートの無邪気さを見る限り、デイビスに対する感情など、初恋とすらも言えぬ希薄なもので、まあ実質、ダンスの相手など誰でも良かったのだろう。デロリスが下品な口笛を吹いて、大きな掌で打ち鳴らす拍手を、真っ黒に頭を覆うベールの上まで掲げる。
「よう、男前! そうでなくちゃってんだ!」
「いいだろう、メリー?」
「勝手にしてちょうだい」
口ではバートを冷たく突き放したメリー・ポピンズだったが、その焦茶の美しい眉はぴくりと動き、サファイア色の瞳には好奇心と、お手並み拝見、という悪戯心に満ち溢れ、その顔色は薄暗いパブの中で、夜桜のように煌々と輝いていた。
「さてと、あたしは、と——」
と、店中を見回すデロリス。彼女と目が合ったスコットは、僅かばかり微笑んだ。
「踊りたいのか?」
「ド下手と踊る気はないのよ」
一言でバッサリ切り捨てられたスコットに、デイビスは笑い転げて、椅子の上で腹を抱え、
「だっせー、フラれてやんの!」
「デイビス、てめえ、いい加減にしろよ——」
「そんじゃ、そこでゲラゲラ笑っている坊や、あんたでいいや。若いから踊れるだろ、イケるかい?」
「おっ、望むところだぜ。ナイトクラブで遊びまくった経験を活かす時!」
デイビスは朗らかに笑って、高く組んでいた脚を戻して地面に降り立つと、デロリスの手招きに従い、店の中央に躍り出た。
一方のミッキーは、頻りにジュークボックスの前でぴょんぴょんとジャンプしながら、コインをボックスに投じるスコットと手を繋いで、
「どうしよう、スコット。どの曲にしたらいいんだろう?」
「うんと踊りにくい曲にしてやれ」
「意地悪だなあ。あっ、これがいいや」
ミッキーが選んだのは、C+C Music Factoryの『Just A Touch Of Love』。すぐにポップな電子音のイントロが流れると同時に、くすくすっ、とあの女学生らしい笑いをこぼして、メアリー・ロバートは愉快で堪らないように叫んだ。
「この曲、大好き!」
「それはよかった。楽しいかい?」
「もちろん! こんな特別な夜は、生まれて初めてよ!」
♪Just a touch of love, just a touch of love
Just a touch of love, just a touch of love
Just a touch of love, just a touch of love
Just a touch of love, just a touch of love
Love has been on my mind for some time now
But you've been the missing link
Of all that whats happened all the stuff made me
Think that love is not for kids...
「へええ、踊れるじゃないか、おばさん!」
「あんたねえ、気軽におばさんなんて言うんじゃないよ。シスター・クラレンスって呼びな!」
「はいはい、シスター・クラレンス」
♪All I want is your touch
(So come a little closer)
What's his memory
(Open up your heart and let me in)
Like the bird in the sky
(Love has got me flying in)
And the stars in the night
(Beautiful)
すれ違いざま、メアリー・ロバートに向けて、デロリスが大声を出した。
「どおーだい、来てよかったろ?」
「ええ、とっても!」
「バーっていうのはね、特別な場所なんだよ、分かるかい? 人が生きてゆくのに必要なことはね、みーんな、ここにあるんだ」
「おいおい、神に仕えるシスターが、そんなこと言っていいのかよ」
「修道院に閉じこもって尼さんの格好したって、あたしゃ、音楽とセックスは捨てらんないよ!」
デイビスは唇を歪め、ニッ、と笑って、
「あんた面白いね、シスター・クラレンス?」
「そりゃどーも。そう言うあんたも、なかなか食えない野郎に見えるね」
♪All I need is a touch of your love
All I want is the touch of your love
Give me just a touch
All I need is give me just a touch of love yeah
Touch——……
はあ、と全員のうっすら汗ばんだ吐息でもって、ようやくハウスミュージックが終わった。するとその時、止まった音楽を継ぐように、たったひとつ、盛んな拍手の音が聞こえてきた。その場にいた全員が、店の隅に身を寄せ合う人影を振り向く。しかしそれは、彼らに捧げられたものではなかった。目の前のテーブルには、大きなマルゲリータや、ミニトマトのサラダ、たっぷりのバケットの盛られた皿が載っていたが、美味そうに湯気を立てるそれらには目もくれず、チャコールグレーのネクタイを締め、かっちりとした背広を着こなして穏和に笑う男性のそばには、華やかな水色のドレスを身に纏った娘が、彼の手元に熱心に目をそそいでいるのだった。
「ああ、そうだ、いい? 見てて。よく見てるんだぞ。こっちの手でこうやって持つよ——」
男は、テーブルの上の塩入れの頭を、片手で隠したかと思うと、瞬く間に、娘の片側の耳の中からそれを取り出してみせた。
「まあ!」
娘は、すっかり感激して息を呑み、夢中になって、ふたたび手を叩いた。豊かなアンバーの巻き髪がふわりと揺れ、二人分のワイングラスに、逆さになった影を映し込んだ。
「もう一度やってみせて! 本当に凄いわ、もう一度やって!」
「分かった、これで最後、行くぞ。ほら見て——」
「あなた、魔法使いね!」
無邪気に笑いあう二人のテーブルの下から、ぴょこん、と大きく丸い二つの耳が覗く。
「あら?」
娘も男も、思わずそちらに眼差しを向けた。やがてその下からさらに、真っ黒な愛らしい目が覗くと、大層興味深そうにぱちぱちと瞬きをしながら、こんな風に感嘆してくるのだった。
「凄いや! 君も魔法が使えるのかい?」
「いや、僕は——」
「まあ、あなたにも分かるの? そうなのよ。ロバートは、とっても素晴らしい魔法が使えるの!」
自分の感動を分かち合ってくれる者を見つけて嬉しいのか、きゃっきゃと、無邪気にはしゃぐ娘。しかし隣にいる男は、不思議そうに首を傾げるミッキーを見て、あんぐりと口を開けたまま、
「どうしたの?」
「ネズミが……喋ってる」
「ネズミだって、話したい時は話すわ。ねえ?」
「ジゼル、この子は、君の例のおとぎ話の……お友だちかい?」
「いいえ。でも、これからお友だちになるところよ」
しかしそれには構わず、ミッキーは不思議そうに彼らを交互に見つめると、ゆっくりと、言い含めるように話しかけた。
「ここは、素敵な場所だよね」
「? ああ」
「二人でお食事してる」
「ああ……」
するとミッキーは、ぱちんと指を鳴らして、合点の入ったというようにロバートを指さした。
「デートなんだね!」
「ああ!」
爽やかな歯切れの良さで答えたロバートは、一瞬、自分の覚えた違和感に気づくと、取り乱した様子で苦笑を浮かべ、否定した。
「いやあ、違うよ、違う違う! 違うんだ、僕たちは……ただの友だち。それに普通、デートにネズミは乱入してこない」
「ネズミにだって、名前はあるよ」
「そいつは失礼。それじゃ……自己紹介といこうか」
ロバートは咳払いをして、ネクタイの位置を整えた。三十代半ばくらいだろうか、焦茶色の髪をかきあげた、彫りの深く人の良い、実に甘い顔立ちをしていて、文句のつけようのない美男子とまでは言えないが、くすんだミント色の瞳のそばに浮かぶ、柔らかな目尻の皺と、にこやかに下がりがちの眉尻が、不思議に親しみやすい存在に思わせている。そして、隣にいる娘は、豪奢な滝のように垂れ落ちる見事な栗色の巻き髪から、春の曙と朝焼け色のリボンを流して、つんと尖った鼻に、あんず色の頬。何よりも、吸い込まれるように輝く大きなセルリアンブルーの瞳が、その純真さに溢れた魂を象徴しているかのようだった。
「ロバート・フィリップだよ。離婚専門の弁護士をしているんだ」
「あの、私、アンダレーシアのジゼルです」
「二人とも、よろしくね! 僕、ミッキー・マウスっていうんだ」
かくして、彼を熱心に見つめてくるメンバーは、純真爛漫な瞳を向けるジゼルに、ちょろちょろと尻尾を動かして目をそそぐ鼠が加わった。
「そんなに見つめられると、困るな……」
ロバートは恥ずかしそうに笑って、はにかみの中に相好をくずした。
「ねえ、早く、さっきの魔法の続きをやってよ!」
「い、いや、君があんまり見つめるから、魔法が照れて、逃げちまったよ」
「魔法って、逃げるのかい?」
「そうだね。だからもう、魔法は使えない。今夜は、これでおしまいだ」
ところがジゼルは、体よく言って、穏やかな笑みで済ませようとしたロバートの傍から、毅然として首を振った。
「あら、そんなことはないのよ。誰にだって使える魔法があるわ」
「それって、真実の愛のキスのこと?」
「この世で一番強い魔法なのよ」
手に手を合わせて、うっとり、のんびり、はんなりと謳うジゼル、隣でおののくロバート。ミッキーは目をキラキラとさせて、
「素敵だね! 僕にも、その魔法はしてもらえるの?」
「うふふ。それじゃ」
ジゼルはふんわりと微笑むと、ミッキーの額に、軽く、小鳥のように口付けた。まるで母親にキスをしてもらったように、彼はたまらなく嬉しそうな笑いをこぼしてみせたが、横からデイビスが煙草をふかしながら、からかうように茶々を入れる。
「おーい、ミッキー。今の、ミニーに言いつけんぞー?」
「だめだよ、デイビス! 僕、ミニーに簀巻きにされて、東京湾に投げ込まれちゃうよ!」
「なあ、お前ら、本当に恋人同士なんだよな?」
「うん。上下関係が、決定的なだけで……」
「あっははは——」
ロバートは朗らかな笑い声を放った。甘いマスクが解きほぐれ、ようやく元来のユーモアが、何の隠れもなしに覗いてきた。
「新しいお友だちも、いいものよね」
嬉しそうに、陶然として言うジゼル。
「私たち、お互いに運命の相手がいて——ロバートは、愛することについて、たくさんのことを教えてくれたの。彼に出会えて、本当によかった」
「じゃ、僕ら、みんな愛する人がいるんだね?」
「そう……だね。本当にそうだ」
「なんて素敵なんだろう!」
ミッキーはにこにことして、喜びのあまり、上に突き出した鼻をピクピクさせた。ジゼルは、その鼻先にケチャップがついているのを見つけて、綺麗にナプキンで拭ってやった。
「あなたたちも、お城に向かっているの?」
「うん! シンデレラ城へ——あそこで、僕の恋人が待っているんだ」
「まあ……早く辿り着けるといいわね」
「そうだね。でも、もう大丈夫。僕には、心強い仲間がいるんだから」
磨いてもらった鼻をぴかぴかに照明で光らせながら、ミッキーは得意げに眉を蠢かせて、端から指を差した。
「右から順に、キャプテン・デイビス、キャプテン・スコット、エディ・バリアント、メリー・ポピンズ、バート、デロリス・ヴァン・カルティエ(シスター・マリー・クラレンス)、シスター・メアリー・ロバート」
「キツイキツイキツイキツイ」
「たった一話に、詰め込みすぎじゃないかしら」
「でも、一人も欠かせないんだよ。彼らがいれば、僕はきっと、シンデレラ城まで辿り着ける」
と、ミッキーは一人前に胸を張る。
「そいつは素敵だ。……だけどね、そうだな、何かを手伝ってもらうなら、きちんと誓約書を書いてもらった方がいいよ。例えば、対応可能範囲の線引きだとか、謝礼だとか、手切金だとかね」
「まあ、本当にその通りだわ!」←何も理解していないジゼル
「テギレキン? どうしてだい?」
「その——」
ロバートは言葉を切って、人好きのする曖昧な笑みを浮かべたまま、少し考えた。どうやら彼は、喜び以外の時にこそ、その穏やかな顔に笑みを湛える癖があるらしかった。そしてよく見ていると、七色の笑みとでもいうべきか、疲れていたり、少し悪戯そうだったり、取り繕うためだったり——それに、心の傷を誤魔化すために、微笑みを絞りだしたりもするのだった。
「過去に……色々あってね。それ以来、あまり他人のことは信用しない方がいいって、学んだんだ」
ふっ、とジゼルが眼差しを差し向けた。何の企みもなく、何の思いもなく、それは不思議に純粋な眼差しだった。
「モーガンのお母様のこと? ああ——無理に聞く気はないの、ごめんなさい——」
「いやいやいや、いいんだ、ただその……彼女の話はしないんだ。モーガンとも……他の誰ともね」
「哀しいお話だから?」
「始めは違った」
「愛していたのね?」
「ああ——」
ロバートは眉をあげ、懐かしい、子どものように素直な幸福を滲ませて大きく頷くと、遠い目をしながら、徐々にその表情を強張らせてゆき、最後に、瞳に諦めたような笑みの残骸を漂わせた。
「そう。……それが問題だ」
「どうしてそれが問題なの?」
「だって愛っていうのは……君が言う、甘い純粋なやつね……あれは幻想。ある日はっきりと目が覚める。——現実はこうなんだって」
ロバートの声は掠れ、語尾は吐息混じりに震えていた。
「なぜ、目が覚めてしまったの?」
「ああ……」
ロバートは手を組んだまま、長らくの沈黙を置いた後で、まるで腹を括ったような、あの特徴的で淋しい笑みとともに、
「妻が出ていった」
とだけ呟いた。
かなり繊細なプライベート話のはずだが、いつのまにか、酒場にいる全員がホロリと涙を浮かべ、熱心に聞き入っている。メアリー・ロバートなどは、ハンカチで目尻を拭い、絞れば涙の滴るほどになっていた。
「二人とも、辛かったのね」
遠慮がちに、ジゼルが慰めを口にする。ロバートは元の甘い微笑みを取り戻すと、曖昧に微笑んだ唇の合間から、白い歯をこぼして囁いた。
「大丈夫、僕は大人だからね。
心配なのは娘——引っ込み思案で、友だちも多くない。もっと、強くなってほしいんだ。現実の世界に立ち向かえるように……
だから、おとぎ話は聞かせない。あの子には、"夢は叶うもの"だなんていう戯言は、信じてほしくないんだ」
「娘?」
ぴくり、とアンテナに電波を受信したように眉をあげる人影。この現実に疲れ切った父親の、ほんの風にも消えてしまいそうな呟きは、釣り糸を垂らして、思わぬ人物を引きあげてきたのだった。
「まだ幼いのかね? 年は?」
「えっ。いったい誰だい、君は」
「失礼、私はキャプテン・スコットという者で、同じく女児を育てている父親だ」
サッと名刺を取り出して乱入するスコット。その後ろで、うわ、とデイビスが明らかにその生真面目さにヒいていた。もちろん無頼漢である彼は、名刺入れなどまるで携帯していない。
「ねえ、デイビス。もしかしてスコットって、天然なのかな?」
「だんだん分かってきたろ、あいつは生真面目の皮を被ったアホだってこと?」
「うん。まあいい感じにウェットな空気が吹き飛んで、結果オーライだけど」
半目になって肩をすくめてみせるミッキーとデイビスをよそに、ロバートとスコットは、共通の話題を通じて、次第に距離を縮めていった。
「ええっと。この名刺に印刷されている女の子が、あなたの娘さんかな。可愛いね」
「そう、クレアといって、まだ五つになったばかりの、可愛い盛りだ。あなたの娘さんの年齢は——」
「六つだよ。人見知りだが、頭はよくてね」
「ほう、クレアの一つ上か、参考になるな。子どもには、どんな YouTube の動画を見せている?」
「アルファベットの綴り方と、偉人たちの生涯さ。ほら見て、このチャンネルの動画が、特に保護者からの評判が良くて——」
「酒場でパパ友の輪を作るのはやめろーっ!」
ようやく二人の間に割って入ったデイビスが、素早い手刀でもって、スパァンと話題を分断させた。
「いーか、スコット、あんたの娘が可愛いのは分かったよ。でもわざわざこんなところまで、親バカを爆発させんなよ!」
「ウォルト・ディズニーは言った。『大切なのは家族だ。家族が仲良く一緒にいることこそが我々のビジネスの根幹であり、我々が望んでいることだ』」
「それとこれとはちげーんだよ。独身の肩身が狭くなるような会話は、酒場の外でやってくれ」
「こほん、僭越ながら。これでは、子どもの関心は引けませんわね」
と突然、ひょこっ、と後ろから顔を覗かせて話題に混じってくるメリー・ポピンズに、スコットもロバートも、ぎょっとして身を引いた。
「ええと。貴女は……どなたかな?」
「乳母ですの」
「メリーは完璧さ。この世で最も完璧に近い乳母なんだ」
「そうですわ、専門家の立場から一言いわせていただきますけれども、これでは、子どもたちに一番必要なものが、まるで足りていませんの」
目に見えぬ教鞭を振るうかの如く、きびきびと語って咳払いをするメリー。さすがに本業を前にしては、ロバートも怖気付き、脅えながら尋ね返した。
「ここで紹介されている人物たちは、どれも、歴史上偉大な人間だ。いったい、何が足りないというんだ?」
メリーはその問いに、澄ました顔でひょいと片眉を持ちあげ、
「イマジネーションですわ」
ときっぱり言った。
「イマジネーションだって?」
「あら、子どもの創意性や空想を見くびってはなりませんのよ。大人のクリエイティブな力を何倍も超える、素晴らしい能力を持っていますの」
「僕は——そんなものを、娘には——」
「まあ、どうしていけませんの?」
メリーは無垢な白鳩のように小首を傾げ、その青紫の瞳を瞬かせる。そこへ、動画一覧をチェックしていたデロリスが、錚々として並んでいる輝かしい偉人の名に、呻き声をあげた。
「あんた、お堅い動画が好きなんだねえ、もっとイカした偉人の生涯はないの? グラディス・ナイトとか、ライオネル・リッチーとか、アラン・メンケンとかさ!」
「ない。そういうのは、見せないようにしているんだ」
「なんてこった、好きなミュージシャンもいないの? それじゃあ、あんたの好きな音楽って何さ?」
首を突っ込んできたデロリスからの率直すぎる問いに、ロバートは少し考え、頭の中から消去法で出てきた答えを口にする。
「そうだね。落ち着いた静かな曲なんかは、あまり意識を乱されなくて、いいかな。それに、Loveとかいう単語が、歌詞に入っていないやつ」
「まいったな。こいつは、筋金入りの堅物だ」
カンカン帽を押さえながら、あちゃー、と軽く肩をすくめるバート。
「あんたねー。今時、天使だってラブソングを聞くもんだよ」
「Loveが入っていない歌なんて、この世の音楽の1%にも満たないんじゃないかしら」
「本当かなあ」
ミッキーは半目になって、デロリスと一緒に怪しい情報をうそぶくメアリー・ロバートに視線を送る。それはともかく、ロバートに対して、周囲からは非難轟々で、すっかり彼は落ち込み、困った笑いを浮かべていた。
「何を好き勝手言っているんでえ、おめえら、ズケズケと人の領分に入るもんじゃねえぜ」
「や、やっと、僕の仲間になってくれる人が現れた」
「真実の愛なんつうのは、おとぎ話の紋切り型だぜ。第一、そんな目先のことに眩んでくっついたって——」
「王子様とお姫様の幸せな結婚なんて——」
「「うまくいきっこない!!!!」」
そこで、エディとロバートの眼差しがぱっちりと合い、改めて互いをまじまじと見た。外見の雰囲気は真逆といえるのに、なぜだろう、この運命を感じさせる強烈なシンパシーは。
「なんか俺とおめえ、似てるなあ」
「奇遇だね。僕もそう思っていたところだよ」
「キャラのモデルにしたんじゃね?」
グビグビと海賊のようにラムをラッパ飲みしながら、デイビスが横槍を入れる。ジゼルは心配そうに、少し首を傾げて、真正面から手を握り締め、ロバートを見つめた。
「でも、夢は本当に叶うわ。とても素晴らしいことが、いつか起こるのよ」
「話してる相手が、君だって忘れてた」
「お願い、忘れないで。私は、あなたとお話がしたいのよ」
切々と訴えて、じっと下から見あげてくるジゼル。そのブルートパーズのような瞳に見つめられると、もしかすれば、本当にこの世に美しいものはあるのかもしれない、と思えるほど、それは純粋さに満ちた眼だった。一瞬、元妻の面影が浮かんだ。そして次に、幼いモーガンの顔を思い浮かべた。けれどもやはり、そのブルーの瞳は、ゆっくりと睫毛を瞬かせながら、輝いていた。
「ロバートが好きなのは、例えば、こんな曲?」
ミッキーは、店の隅に置いてあるグランドピアノの前に腰掛けると、ポキポキと指の体操をした後で、おもむろに、心地良さそうに酔い痴れた顔で爪弾いた。反響板で響きを膨らませた、些細なアルペジオ——けれどもその途端、まるで魔法の走り抜けるように、鍵盤を自由自在に動きながら始まる音楽は、メロディに付された歌詞をなくした今、真っ直ぐに心の奥底まで入り込んでくるようだった。素晴らしい夢想に満ちたメロディだった。音それ自体が生きて、心と同じ旋律を奏で始め、まるで開け放たれた城の庭園から、まばゆい花が咲き乱れ、清らかな水が溢れて、小鳥さえも羽ばたいてゆきそうな奔放さに絡みとられてゆく。ジゼルが歌っていた曲だ——彼女はなんと口ずさんでいたっけ? しかしその意味をはっきりと思い出せることもなく、ただ、ミッキーの奏でる繊細な音だけが、みるみるうちに店内を満たしていった。
「ミッキーの奴、何でもできるなあ」
「主人公属性を全部詰め込んだようなキャラクターだからな」
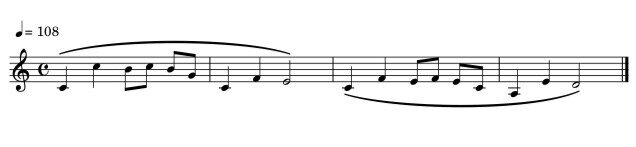


甘く夢見るメロディが、記憶を揺さぶる。出会った翌日のセントラル・パークでは、彼女が幸せそうに歌い踊るのを、遠巻きに見つめているだけだった——極彩色の風船や花々、大道芸人、歌や踊り、そして笑顔に満ちた人々。百万もの夢に囲まれながら、幸福いっぱいに身を染めるジゼルは、遠い昔、やがて訪れる別離も知らず、妻との愛に酔っていた自分と重なり合う。これが永遠に続くのだと信じ、人並みに夢を見ていられた期間は、たった数年間だけだった。
そんな幸せに近づくのは、もう恐ろしかった。それに、もう幸せを望んではならない——自分が考えるべきは、モーガンの幸せであって、僕が何を望むかじゃない。もう二度と、僕のようにだめな父親のせいで、あの子を泣かせてはならない。
なのになぜ——心が疼くのだろう?
傷つかずに済むことをしているはずなのに、なぜ、胸が死んでゆくように痛むのだろう?
「ロバート」
ジゼルはそっと、彼の膝に手を置いて、その顔を覗き込んだ。
「無理をしなくていいのよ。あなたはあなた。頑張って何かを演じなくても、きっとそれは、素晴らしいことなのよ」
彼女の言葉に、そっと、ロバートの眼差しが持ちあがり、二人の間に、沈黙が満ちた。それは感情を絶した沈黙ではなく、限りない言語に満ちた沈黙だった。しかしロバートは、その痛切な言葉の波に堪え続け、ジゼルもまた、何も言わなかった。
音楽は流れ、硬質な音の綴るメロディに、微かな歌を交わらせ、フレーズを躍らせた。
「踊っちまいなよ」
デロリスが顎でスペースを示し、分厚く艶めく唇で、青春を懐かしむように笑ってみせた。
「あたしらのダンスは、もう終わった。今度は、あんたたちの番だ」
ロバートは、ジゼルを振り返った。彼女は、微かな期待にざわめくような、けれども大部分は、不安と諦めに満ちたような目で、ロバートを見つめていた。
そしてロバートもまた、眩しく、寂しそうに彼女を見つめていた。その口角に浮かぶ静かな微笑は、もはや何の意味もなく、形骸化した手癖のかけらが貼りついているだけだった。穏やかな笑みの下に隠され続けてきた、その繊細さ、脆さ、そしてあまりに自己犠牲的にすり減らされてきた優しさが、今、絹の滑り落ちるかの如く、ジゼルの前で鎧を脱ぎ、瞳の奥深くに瞬いていた。
ロバートは静かに立ちあがると、身を屈めて手を取り、そのちいさな耳許に囁きかけた。
「踊ろう」
想いを秘めた胸を高鳴らせながら、ジゼルがおずおずと、はにかむようにうなずく。その時初めて、彼女が一人の女性として、悩みを持ち、温もりを持ち、限りない憧れを持ちながら、震える思いで彼の前に立っているのだということが伝わってきた。
そして唐突に、分かる。この踊りが、彼らの関係を、魔法にかけられたかの如く変えてしまうのだと。静かに、その細い指を並べた手を引くと、薄闇の中から目の前に現れるのは、彫刻のように整った女性の、光と翳を帯びた顔だった。ロバートはためらいながら、最後の笑みを消して、そっと、青いライトに照らし出された彼女の額のふちに触れた。そして今、夢や空想を掻き消し、自分に真剣な眼差しをそそぎ続ける彼女の、その深い瞳だけしか、この世に真摯なものはないのだと思った。二人は、何も口にはしなかった。間近に彼女を引き寄せ、瞳と瞳が結ばれ合うと、もう、いかなる言葉も必要でなくなった。
「お前、良い仕事したなあ」
「分かる?」
「見てみろよ。あの二人、きっと今に恋に落ちるぞ」
ぽわん、と宙に指でハートを描くデイビスに、ピアノの椅子から飛び降りて、ふふん、と鼻を高くするミッキー。
「今夜は、愛を感じるね」
「Can you feel -」
「 - the love tonight?」
「ギャンブルにはおあつらえ向きの夜になりそうだな。おい、スコット」
「なんだ?」
「今日こそ、決着つけようぜ」
指で手招きしながらニヤリとするデイビスに、スコットも無言で席につき、二人は慣れた手つきで懐中をまさぐった。
「キスするに十ドル」
「しないに十ドル。あの二人は奥手だ」
「今しなきゃいつするっつーんだよ、野暮だなー」
「君たちって、本当に考え方が俗だよね」
額を突き合わせ、十ドル紙幣を並べてあーだこーだと言い合うデイビスとスコットに、ミッキーは呆れ返って、溜め息を吐いた。
「大人の醜いところは見ちゃなんねえ。ミッキー、あいつらは無視しろよ」
「なんというか、駄目な大人のお手本みたいだよね、あの二人」
「おう、お前もだんだん分かってきたな。すぐ賭け事に持ち込もうとする奴は、みんなろくでもねえぞ。よく覚えとけ」
「なるほどね。で、エディは?」
「…………」
「やっぱり、ギャンブラーしかいないじゃないか」
呆れ返るミッキー。どうやら真っ当な大人は、彼の周りにはまるでいないらしかった。
「へん、儲けを期待してやるんじゃねえ、単なる暇つぶしだ。大人になってまで、幸運を掴む夢を見てんのは、成長し切れてねえ馬鹿だってこった」
「本当に、そうかな。大人は、夢を見ちゃいけないのかな」
ミッキーは首を傾げた。
「大人こそ、魔法にかけられる瞬間が必要なのかもしれないよ。現実の中で必死に闘っているあいだは、自分が本当に望んでいたことを忘れてしまうもの」
「そうかねえ、俺にはさっぱり分かんねえな」
「エディは、それでもいいよ」
ミッキーはにっこりとして、
「僕、分かっているんだ。ロジャーが君のことを、心から笑顔にしてくれるって。だから僕は、彼に会えるのを楽しみにしているんだ」
エディの睫毛が震えたが、それをけして、表情にまであらわすことはなかった。グランドピアノの前の椅子に、今度は修道服を払って腰掛けるデロリスを見て、メアリー・ロバートは目を丸くした。
「あら、あなた、ピアノを弾けるの?」
「あたしを舐めちゃいけないよ。なんたって、それなりに実力のあるミュージシャンだったんだからね」
デロリスの指がそっと、ライトを浴びて黒と白に光る鍵盤を撫でてゆく。徐々に照明を落とされてゆく部屋の隅に、ポッとサスライトが当たり、マイクを握り締めたバートが佇む。
「十八番、バート。歌います」
「お前が歌うのかよ」
「二人の間に必要なのは、ほんのひとさじのお砂糖。そして、甘いラブ・ソングさ」
「けっ、どうだかねえ」
顎をシャクレさせて背を向けるエディをよそに、情緒豊かなデロリスの指で、ピアノは絹の如く奏でられ始めた。スコットは深く引き結んだ唇の前で、乳白色に濁った煙を吸い殻から漂わせ、メアリー・ロバートは、フロートのてっぺんに飾られていたさくらんぼを、ミッキーの口にぱくりと咥えさせてやっていた。二人が互いの肩に手を添えて、その瞳の底に沈む、ちらちらと噴きあがるような青い光芒に目を奪われるうちに、王子様でなくとも、この夢に溢れた純粋な瞳を見つめ続け、手を握り締めることはできるのだ、と思い知る。ジゼルは、目の前の優しい顔が、微かに傷ついたように歪むのを、じっと見つめていた。そして店内は静寂に満ちて、互いの瞳に互いの姿を映したまま、バートの歌声だけが、ドラマチックに流れ込んできた。
♪You're in my arms
And all the world is calm
The music playing on for only two
君が腕の中にいれば
世界はとても静か
音楽が二人のために流れてくる
So close together
And when I'm with you
So close to feeling alive
こんなにも近くで二人きり
君と一緒にいるときは
生きていると感じられそうなんだ
A life goes by
Romantic dreams must die
So I bid my goodbye
And never knew
人生は過ぎゆき
甘い夢も死んでしまう
だからさよならを告げたのさ
ずっと知ろうともせずに
So close, was waiting
Waiting here with you
And now, forever, I know
こんなにも近く 待っていた
君とここで待ってくれていたんだ
そして今 永遠に分かったよ
All that I wanted
To hold you so close
求めていたのはただ
君を抱き寄せることだったのだと
ジゼルは、熱っぽいバートの歌声に紛れて、微かな低い声で、ロバートが同じ歌詞をちいさく口ずさんでいるのに気づいた。突然、彼女の胸に、抑え切れない悲痛が射した。そして、その大きく吸い込まれそうな瞳が、哀しみのあまり、大きく見開かれた。唐突にやってきた痛みは、何かに気づいてしまったからなのだろうか、目をわななかせ、万感の思いを込めて、ジゼルはロバートを瞳に映し続けた。もはや何もかもが手遅れで、何もかもが遠ざかっていってしまい、そっと彼の腕に抱き寄せられた時、このまま二人で死んでしまえたら、と思った。しかし彼女は、彼の温かい肩に縋りつき、溺れるように顔を埋ずめて、ただ黙ったまま、瞼を伏せた。間近に迫る彼の穏やかな顔が、彼女のターンによって優しく口角を緩めたり、ふっと、何かの熱に憑かれたように霞んだりするたび、胸の中の鼓動も、思いも大きくなり、ますます音楽の高まりに紛れて、自分が消えてゆくように思われた。しかし何も消えはしなかった、何も。……繋いだ手は暖かく、見つめる瞳は優しく、二人の鼓動は静かに、流れる歌とともに脈打ち続けているのだった。
♪So close to reaching
That famous happy end
Almost believing
This one's not pretend
もうすぐ届くのかな
あのお馴染みの幸せな結末に
信じかかっていたんだ
今度こそ嘘じゃないって
And now you're beside me
And look how far we've come
So far we are, so close
今はそばにいる
こんなにも遠くへ来たんだね
とても遠く そして近いんだ……
柔らかなピアノの旋律が、沈黙へ消えてゆき、ようやく踊り終わっても、いつまでも二人の眼差しは見つめ合い、精神の奥底に触れたように頑なに結ばれていた。無性な哀しみを覚えながら、それでもロバートは、美しく印象的な瞳から目を離せなかった。ゆらめく瞳が、何かを訴え、そして音楽の最後の余韻に、それを木霊の如く響かせていた。二人とも動けず、そして何も話せなかった。
(キス!)
デイビスは念じた。
(キス!)
ミッキーも念じた。
(キス!)
デロリスも念じた。
(キスキスキスキスキスキスキスキスキス!)
バートの念じ方が、一番狂気じみていた。
しかしロバートは、そっと身を離すと、触れてはいけない神聖なものを導くように、静かに手を引き、彼女を椅子へ座らせた。そして、その瞳に何か、語りたいけど語れない、崖に縛りつけられたような苦みが漂い、もはや笑わず、笑みのかけらすらも貼りつけず、ただ、自分の中の何かに納得したように、誰にも気づかれぬ小ささで頷いているのだった。
(この……この……腰抜けがああああああああああああああああああああああああああああ)
デイビスの怒りは頂点に達した。これほどの好機を不意にする男など、見たことがない。しかしロバートは、ただただ慮るように、俯いているジゼルを父親の如き眼差しで見守っていた。
「ねえ、どうして二人は、真実の愛のキスをしないんだい? 誰にだってできる魔法なんでしょう? こんな時にしないで、どうするの?」
——こんな時、空気を読まずに真理の爆弾を投げるのは、子どもに与えられた特権なのだろう。ジゼルとロバートはぴしりと凍りつき、その場に石化した。
「ロバート。やっぱりこれは、恋人とのデートなんでしょう? どうして僕に嘘をついたんだい?」
「えっ。えっと、僕たちは——」
「ジゼル。僕にはキスできて、ロバートにはできないのかい?」
「えっ。あ、あの、そんなことは——」
「すればいいじゃないかあ。二人とも、そんなに愛しあっているのなら」
次々と爆弾発言を投じてゆくミッキーは、最強の戦闘機の如き攻撃力を見せつけながら、きょとんと瞬きを繰り返す。周囲の大人は、泣いたらいいのか、笑ったらいいのか、何とも言いかねる顔で、声なき言葉を叫んでいた。
気まずい発言はあったが、ロバートはなぜだか背中を押されたらしく、落ち着き払った様子で、
「ジゼル。——僕の方を向いて」
と誘いかけ、そっ、と不安そうに彼の顔を仰ぐ彼女へ、静かに寄り添う犬のように頬擦りすると、次いでゆっくりと、その柔らかい頬に唇を寄せた。青く剃りあげた顎から、ほんの僅かだけ生えてきた髭がこすれ、ジゼルの顔はたちまち真っ赤になったが、やがて、かすかにくすぐったそうに微笑むロバートの顔を見ているうちに、彼女の方にも、ふわりと優しい微笑がこぼれてきた。
「これは……賭けは、どっちになるんだ?」
「おめえら、ギャンブルのことしか頭にねえのかよ」
「賭博に溺れているわけじゃない。一度取りつけた約束は守りたいだけだ」
妙な方向に真面目なスコットは、公平な判断に努めながら、口直しにごくりと水を煽って、
「しようがない、キスはしたんだし、五ドル渡すか。……デイビス? どこだ?」
「僕も探すよ。デイビス。デイビス?」
彼は部屋の隅にいた。いつのまに移動したのか、熱心に暖炉の前にうずくまっているのだが、なぜだろう、その丸まった背中に、ミッキーは不思議な哀愁を覚える。
「ええっと。デイビス、お店の暖炉で勝手に、何してるの?」
「おう、ミッキー。マシュマロを暖炉の火で焼いてるんだよ。こーやって、フォークに刺してな、じっくり、表面が溶け始めるまで炙るんだ」
「ねえ、自分が恥ずかしくならないのかい?」
「何言ってんだ、マシュマロは子ども向けのおやつじゃねえんだぞ。こうしてチョコレートを添えれば、立派な酒のツマミになる。最高の大人の食いもんだ」
「そういうことを言ってるんじゃないんだけど。......まあ、いいや。美味しそうだね」
ミッキーはそう言いながら、どこまでも続いてゆく煙突の先を、何気なく見あげた。まるで上へ向かって掘られた、底無しのトンネルのようだ。
「わあ。上は暗くて、怖いんだね……」
「いやいや、全然違うよ。ここは、魔法の国まで続いている、入り口みたいなものなんだよ」
バートは、デイビスとミッキーの後ろから、ともに煙突へと続く暗闇を見あげると、摩訶不思議な妖しい旋律を、そっと、想像力を揺り動かすように歌いかけた。
♪上には煙が渦巻いて
空と屋根が僕の世界
昼間もなけりゃ夜もない
光と影が混じり合う
見下ろせばロンドン———
「ああ、なんて良い眺め!」そこまで歌って、バートは溜め息をつき、陶然と呟いた。その目には、限りない大空への空想と憧れがひしめいている。
メリー・ポピンズは、ご自慢の美しいレースの手袋を嵌めながら、彼らの背後から声をかけた。
「デイビス、気をつけて。暖炉では、色んなことが起こるのよ」
「色んなことって?」
その途端、しゅぽんっ、と景気の良い音がして、見る間にデイビスは凄まじい吸引力の餌食となり、呆気なく煙突の彼方へと姿を消した。そして当人も唖然としたまま、一気に煤煙がキノコ雲状に噴きあがると、その気流に乗ってフワフワと漂い、無事に屋上に着地するのだった。
唖然としている見物人たちにも構わず、メリーは溜め息を吐きながら、その細い肩をすくめた。
「言ったでしょ?」
ミッキーは大慌てで、恐ろしく木霊を響かせるその真っ暗な煙突に向かって、懸命に名前を呼んだ。
「デイビス! デイビス、どこにいるんだい? お願い、戻ってきて! デイビス!」
「ちょっと、まずかったかな——」
「しょうがない考えばかり吹き込まないで!」
頭をかくバートと、彼を手厳しく叱るメリー。すると彼方から、まるで天の声の如く、颯爽としたテノールが降ってくる。
「スコットー!」
「なんだ、デイビス?」
「俺のグラスと、酒持ってきて! あと、あったかい料理ー!」
自分をパシリ扱いするデイビスに、スコットはついにキレて、煙突の彼方に向かって、鬼のような声で怒鳴りつけた。
「てめえが降りてこい、デイビス! 私はウーバーイーツの配達員じゃないんだぞ!」
「ケチだなー、グダグダ言ってねえで、早く来いよ! すっげー夕焼け空だぞ、あと少しで日が暮れちまうからなあ!」
デイビスのその台詞が響くにつれて、夕焼け空、という鮮やかな想像に、不思議な余韻が広がった。暖炉は、真っ黒に煤けた時空に、未だに炎を燻らせ、その薪に散る微かな火花の色は、哀愁を秘めて暮れゆく夕暉を思わせた。ソワソワと好奇心を堪え切れなかったミッキーが、覚悟を決めて、真っ先に暖炉に飛び込んだ。
「僕も行こう!」
「あ、こらっ、ミッキー!」
「私も行くわ!」
「ジゼル、よせ!」
「なんだか、楽しそうね」
「どこに行くってのさ、メアリー・ロバート!」
しゅぽしゅぽしゅぽんっ、と爽やかな吸引音が続き、まるでダイ○ンの掃除機に吸われたように、跡形もなく人影が消え去った。
「三人ほど行ったわ」とメリー。
常識的な人物ばかりが取り残された店内に、ポカーン、と呆気に取られたような沈黙が広がる。事の発端となったバートが、気まずそうに言った。
「追いかけようか?」
「子どもたちがカンガルーみたいに跳ね回るのを放っておける?」
「三名ほど、成人済みと思われる奴が混じっているんだが?」
「残念ね。全員、おつむは子どもよ」
メリーからのツッコミに、頭を抱えるスコット。なぜだか、自分のことのように恥ずかしかった。
「ま、今日くらい、みんな童心に帰ってもいいのかもね。行きましょ、バート」
「光栄だよ。君と一緒に、素晴らしい空の上へ飛んでゆけるなんて」
「もう、口がうまいんだから」
ようやく、メリーは優しく口角をあげて、雪のようなちいささで微笑んだ。そのたったひとつの微笑みで、メリーがどれほどバートを大切に思っているかということが、鮮烈に伝わってくるようだった。バートもまた、にっこりと相好をくずして、彼女の差し出す手を握り、まるで舞踏会に向かうように優雅に歩き出した二人は、瞬きひとつ終わらない間に、もう姿を掻き消していた。そしてどこかで遠く、ぱさりと傘の広げられる音。
確かに、それは魔法のようだった。例え手品にしても、こんな不思議なことは見たことがない。けれども、普通に生きていても、魔法はある日突然、自分の身に起こるのかもしれなかった。それはこんな風に唐突な始まりで、ほんのキスや、ダンスや、玄関のチャイムの音で、不意に誰かの肩を揺さぶってくるのかもしれなかった。
「どういう仕掛けなんだ?」
「これは——危険じゃないのか」
こわごわ、といった様子で暖炉を検分する、残された大人たち。エディは、あんまり近寄らない方がいいぜ、と言いかけて、あの機関銃のようにまくし立てるロジャーの言葉が、ふと、耳によみがえってきた。
(そっちこそ何だい、この映画館で笑っていないのは、あんた一人だけだぜ! いないいない、ベロベロベロベロ——嘘、じょーだん! いったい何があって、そんなにいつもぶすーっとした顔ができるようになったワケェ?)
あのキンキンとした声——そういえば彼は、あちこちの映画でフライパンに焼かれたり、頭に棚を落とされたりしても、ちっとも気に介さなかった——まるでそれが、自分の人生なのだというように。そして、石鹸箱の上に立ちながら、まるで自らの存在を問うように彼に訴えた、ロジャーには珍しいほどの、あの切実な言葉。
(笑わせるってことには、すんごい力があるんだ。僕たちアニメが持ってる、唯一の武器になることもある)
エディはふっと口元に微笑を浮かばせると、袖を捲りあげて、暖炉に近づいた。
「よーし、俺も行くぜえ。夕陽を肴に、酒を呑んでやる」
「エディ——」
「ははあん、どうやらパーティ会場は、屋上へと移ったようだね。あたしゃ、メアリー・ロバートの面倒を見なくちゃ。兄ちゃんたち、いつまでもそんな風に気取っててもいいけど、ずっとその調子じゃ、損するよ」
と、デロリスも去り際にクールな台詞をひとつ残して、またたく間に修道服の裾をさばき、上へのぼってしまった。
「君はどうするんだ。屋根の上には行かないのか?」
スコットからの問いかけに、ロバートは強固に首を振った。
「僕は、ここで待ってる。これ以上、彼女のそばにいるのは——」
「本当にいいのか?」
「何がだい?」
「同僚だから分かるがな、最初に吸い込まれていったチャラ男は、とんでもない下半身見境なし野郎だぞ。恋に恋するふわふわの箱入り娘がやってきたら、どんなことになるか——」
ロバートは、ゾッ、と鳥肌を立たせて、上着の襟をぴんと張った。
「やっぱり行こう!」
「それがいいと思う」
げんなりとしたスコットを連れて、バートも暖炉に飛び込み、かくしてついに全員が、しゅぽんっ、と煙突に呑み込まれた。
パチンコ玉になった気分だった。つむじから伸びてゆく糸を辿るように、勢いよく天上へと吸い込まれ、その加速度のままに、キュポンッという気持ちのよい射出音を立てて、暗闇の外へと飛び出すと、最後に、どたりという情けない音と同時に、腰に痺れるような痛みが襲いかかった。
何度尻餅をつけば気が済むんだ、と苛々しながら煤を払い、ようやく顔をあげると、爽やかな夜風が鼻先をさらってゆき、月の光が静かに織り乱れていた。目の前に広がるのは、高級な雰囲気に閉ざされたパブとは、まるで別世界だった。空闊と天に解き放たれた屋上、西側は茜と黄金の薄明に染まり、溢れんばかりの残照が空気を炙るのに対し、東側はすでにとっぷりと日が暮れ、遠い街の数々の灯りや、きららかな星が輝いている。その激しい隔絶の両極端の色を、量り知れぬほど壮大な空が繋いでいた。まるで、世界の喜びも哀しみも、あらゆる感情のすべてがそこにあって、空に包まれた流れる時間の中で、鮮やかに色彩を変えてゆくように思われた。
屋上はすっかり暗がっていて、冴え渡る月の光を集めるベッドシーツが、何枚も干されてはたはたと波打っており、そのぼんやりとした清潔な白さと、屋根の周囲に設けられたエッジを、夕陽が微かに橙色に燃やしている以外は、すべてが、どこか懐かしい影の海に沈められていた。群青色の大空を切り取って、遠くで蠢いているあの人影は、デイビスだろう。彼は地べたに座りながら、腹を抱えて、
「見ろよー、ミッキーの奴、煙突の煤で真っ黒焦げだぜ!」
「それはデイビスもでしょー!」
「ははっ、みんなで真っ黒になってりゃ、世話ねえや!」
とげらげら笑い転げていた。風の切れ切れに、パンや暖かい石鹸の匂いがし、枯れ葉が地を転がり、虫の声もした。数々の人影が、そうして群青色の夕闇の中に、曖昧な輪郭をひるがえして生きていた。
メリー・ポピンズは、すっかりピクニックの手筈を整え、まるで休日に公園を訪れた貴婦人のように、屋上へ優雅にピクニック・シートを広げた。そして、ぱちんと指を鳴らすと、たちまち、煙突を通り抜けてきた酒や食べものが、次々に黄昏の宙へと舞いあがって、夜風を切ってそのシートの上に行儀よく並び、まるで王侯貴族の食事のように豪華に、黄昏の最後の陽を浴びていた。その様子に満足したのか、彼女はフフンと鼻を鳴らすと、たっぷりと木イチゴ・ジャムを煌めかせた、頬っぺたの落ちるようなケーキを一口だけ、誰にも見られないようにこっそりとつまみ食いをした。
「やあ、みんな無事みたいだな。知ってるかい、今みたいな状況を、願ってもない幸運っていうんだ。見てごらん」
とバートは、昂奮を抑えきれないように輝かしい声で言う。その言葉に、その場にいた全員が振り返り、西に広がる光景を見た。
煙突掃除夫しかのぼれない、屋根の上の世界。そこから見えるのは、黄昏と夜との間の、最後の移ろう輝きをとどめ、まさしく深紅と藍色の、人間では理解できないほどに不可解で眩ゆい結託だった。雨に濡れたような窓ガラスは一面、建物の輪郭を四角に切り取る、濃い橙に反射して、遠く、壮大に、英国の工場から天へと還ってゆく煤煙は、その懐かしい夕暉を荘厳に霞ませ、ずらりと並ぶ煙突の煉瓦は、西陽の方角を、艶めくように次々と熱くした。一面が琥珀に閉じ込められたかのよう、そして永遠の過去へ、ねっとりとしたオレンジ色の煤けた雫を滴らせながら、夕陽は濃く、鮮やかに、時空の底に照り映え、無数の煉瓦の表面を輝かせていた。
「———道なき、ジャングルだ。冒険家が来るのを、待っている」
そのどこまでも素晴らしく開けてゆく目の前の光景に、スコットはおもむろに首を傾げ、意味が分からないというようにバートに訊いた。
「ちょっと待て。今は確か、夜中だったろう?どうして夕陽が見えているんだ?」
「ちょっとだけ時間を戻したんだ、君たちに夕暮れの景色を見せたくてね。ああ、ロマンティックなバートさん、ハンサムじゃなくても、とっても素敵な魔法を使える」
「…………」
「徐々にツッコミに、疲れが出てきたね」
もぐもぐとマシュマロを頬張るミッキーが、他人事のようにスコットに言った。
「まあ! なんて綺麗なの、凄いわ!」
「ジゼル、危ないよ。足元に気をつけて」
「ああっ!」
言うが早いか、屋上からの素晴らしい眺めに昂奮したジゼルが、つまずいてバランスを崩し、間一髪でロバートに腕を支えられる。
「ね、言った通りだろ?」
「まあ! うっふふふ——」
二人は顔を見合わせ、一瞬、微笑みあったが、すぐに彼女は駆け出して、ふたたび、踊るように自由に、まるでバレエを思わせる身振りで、その魂を大都市の夕陽と夕闇のさなかに舞いあがらせた。あまりにもたやすく腕をすり抜けていってしまうその暖かさに、ロバートは微かに頬を染め、逸る鼓動を隠すように拳で押さえつけた。
「ねえ、ミッキー。あれがシンデレラ城?」
ジゼルはドレスをひるがえしながら、夜風に靡く髪を押さえつつ、出会ったばかりのちいさな友人に訊ねる。
「そうだよ。あれが、僕の目指すべきお城だ」
月明かりの下、真っ白なライトの中に幾万もの色を溶け込ませて、城は王国の中心で照らされていた。機関車が吐きつらねる蒸気や、煙突の吹き散らしてゆく煤煙、無数に立ち並ぶ煉瓦造りの彼方に、幾億もの夢で創りあげたかのように、それはある。
————あそこで、ミニーが待ってる。
あとどのくらいの時間をかければ、彼女を助け出せるのだろう。敵はどのくらい強いのだろう。どうすれば勝てるのだろう。凛々しく口を引き結び、風の中へ耳を揺らしながら城を見つめ続けるミッキーの肩へ、とん、と優しく手を置くデイビス。
「一人じゃない、って言っただろ?」
その若々しい緑の瞳に勇気づけられたように、ミッキーはしばらくその目を見つめ返し、確信をもってうなずいた。そう、立ち向かうのは一人じゃない。いつだって大切な仲間が、僕を助けてくれるのだから。
ジゼルもまた、夜空の下に青く聳え立つそのおとぎ話の城を指差して、夜風を浴びながら、どこか夢のような声色で囁いた。
「ほおら、ロバート。魔法のお城は、あったでしょ。私、嘘なんかついていなかったでしょ?」
「はいはい。君の言う通りだね」
「嬉しいわ。お城を見ていると、なんだか元気が出てくるの」
「そうかい。僕は君の世話で、一苦労だよ」
「あなたは私と一緒にいても、楽しくないの?」
そしてその時、ふっと、二人の間には何もなくなり——そう、互いの培ってきた年月さえも——ずっと彼女に出会うのを待っていたのだ、という気がした。最も奥底に秘めて封じてきた、それゆえに、最も純粋なまま保存されてきた夢。それは彼が、"プリンセス"と落ち合い、うっとりとするようなおとぎ話を繰り広げる、ということだった。
まるで少年が、お姫様の童話に入り込むところを空想するような憧れ。ずっと昔に封印して、親にすらも打ち明けたことはない——そしてスーツに身を包んで働くうちに、いつしか、そんな"恥ずかしい"幼稚な想い出をも、教育や、ニューヨークでの忙しない生活、素晴らしく理性的な弁舌の中に忘れ去り、まるでそのことによって、 この巨大な街の一部に溶け込み、何者でもなくなり、自らの恥部を掻き消して、一人前の大人になれるかのように感じていたのだ。
ジゼルは———
そんなさなかに、彼の目の前に現れた。幻想の物語から抜け出してきたかのようだった。大したトラブルメーカーで、ちっとも現代の生活に馴致せずに、精神は雲の上、周囲から浮きまくって、後ろ指を差されて、瞳をキラキラとさせて。けれども彼女は、生きるために、その純粋な魂を包み隠さない。どれほど周りに呆れられても、不思議な言動を繰り返して、驚くばかりに素直である。そして、窓際に揺れるカーテンのように、どこか儚く、朝の光に紛れながら、この騒がしいお喋りとクラクションに溢れる大都市の景観を、鳩のように美しい、慈愛に満ちた目で見晴るかすのである。
人は、夢を抱えたまま、生きていけるのだろうか?
それは分からない。少なくとも自分は傷ついたし、もう夢は見ないと誓った。でも、自分の大切な人だけは。
ジゼルとモーガンだけは、夢と現実との狭間で擦り切れてしまわないように——守りたい。
「ロバート?」
夜空の中で眉をあげ、ジゼルは柔和に目を細めてみせた。月が眩しく、彼女の髪を映えさせた。ロバートはまるで甘えるように、彼女を後ろから腕の中へ閉じ込め、その肩口に顔を埋ずめた。
「まあ、いったいどうしたの、ロバート?」
いつになく子どものような振る舞いに、ジゼルは、静かだが華やかな笑い声をこぼした。それにつられて、ロバートも薄く笑みを引きながら、抱きしめる腕に力を込め、貝殻のように小さな耳へと囁いた。
「いや。……楽しいさ」
屋上の中央では、ふわりと生暖かい夜風に包まれて、どんちゃん騒ぎが繰り広げられていた。宴もたけなわ、と言うべきか、呆れ果てるエディにも構わず、ガンガンに酒に溺れながらはっちゃけているのは、やはりデイビスだった。
「坊主、おめえ、今回の章は呑んだり食ったりしてるばかりじゃねえか」
「それの何が悪いんだよー? だーって、せっかくの飲み会だぜ、飲み会! 呑んだり食ったりしなきゃ、なーんも話になんねえって!」
朗らかに笑いながら、デイビスは茫漠たる風を浴びて、気持ちよさそうに鼻歌を歌っていた。これは彼が上機嫌の時の癖で、ゆっくりとした低音は、温度のない風に吹き散らされ、まるで自然の奥底から湧きあがる幻聴の如く、切れ切れに聞こえてくるのだった。
ミッキーも浮き浮きとしながら、空のグラスを取りあげ、
「マゼランズのスペシャル・ドリンクを作ろう!」
と、宵闇の空の下で主張した。
「グレープフルーツジュースと、トニックウォーターと、ゼリーを混ぜたやつ! 甘くて、とっても美味しいんだよ」
「へええ、美味そうだなー! それは?」
「チーズの盛り合わせ!」
「はは、即席のラウンジだな。あー、ローレンス・ジュバーの優雅なアコギを聴きながら、マヌエル様式の巨大地球儀を眺めて、牛頬肉の赤ワイン煮込みを食いてー!」
「銘柄鶏のポワレ、タプナードソース!」
「鴨胸肉のロースト!」
「クレームブリュレ!」
「ちょ、ちょ、ちょっと落ち着け。そんなの、ディズニーランドにあるわけないだろうが」
「何言ってんだスコット、あんだろーが、目の前によー! さ、俺が腕を振るって作ってやったんだ、腹いっぱい食えよー!」
コイツはいったい、何を言っているのだ? ハテナマークを浮かべるスコットのネクタイをぐいと引っ張り、デイビスは大いに酒臭い息を吹きかけ、ヘラヘラと笑った。その目の光はどう見ても虚ろで、上半身も危なっかしくふらついている。
「酔ってるな……だからあれほど、ハイペースで飲むなと「うるへー! いい月夜だろうが、もっと酒を寄越せー!」
煩わしそうに眉間に皺を寄せるスコットへ、デイビスの絡み酒は止まらない。エディはぎょ、と一歩引いて、久々にこんな面倒な奴を見た、と言わんばかりに、近寄るのを回避した。
「おいおい、なんだよ、この酔い方は。始末が悪ィな」
「いや、こうまで酔っ払っているのは初めて見たんだが……まさか、こんなに面倒くさいとは」
「おめえの相棒なんだろう? 何とかしてやれ」
「ただの仕事の同僚だぞ!」
「そうかい。じゃ、この中で、一番親しいな」
すたすたと歩み去ってゆくエディに見捨てられ、スコットはすっかり困惑して、横を見た。そばには、ぱちぱちと炭酸の泡をのぼらせているように酔ったデイビスの姿がある。
「デイビス。あの、私はな、」
「いいって、いいって。俺とあんたの仲だろー?」
「いや、私は、そんなに酒量は」
「いけるいける、あんた、ウイスキーが好きなんだっけ? ほーら、ワイルドターキーだ! ここはどーんと、トリプルでいっちまおうぜー」
ヘラヘラ笑って肩を組もうとするデイビスの手を払ったにも関わらず、なみなみと注がれてゆくストレートの蒸留酒に、スコットは舌打ちしたい気分でいっぱいだった。くそっ、私はゆっくりと嗜む方が好きなのに——それにはっきり言って、ここまで酔っ払った野郎のお相手なんぞ、少しも面白くないんだが?
「デイビス。ほら、管巻いていないで、しゃんとしろ」
「ハッハッ、あんたの方こそしゃんとしろよー、スコット! タコみたくぐねぐねしてんじゃねーか、アッハッハ!」
「まるで手に負えないアホだな」
一日に一回は面倒事を起こさないと気が済まない体質なのか? と大いに脱力して頭痛を堪えるスコットは、そういえば、こいつが交際相手に振られた時は、いつだって酒に逃げていたな、と思い出し、慎重にその顔を覗き込んだ。
「何か、私に言いたいことがあるのか?」
「んー」
デイビスは、ふら、と首を危なっかしく振ると、月の光に睫毛を照らされながら、囁くほどに小さな声で言った。
「なあ、スコット。お前って、誰か大切な人を亡くしたことはある?」
ぽつりと。
月夜の下で呟かれたその言葉に、グラスの中の水面は揺れ動き、風が微かな漣を立てた。いつも緩く目にかかっている彼の長めの前髪も、ひそやかな音を撒き散らして、風の中に持ちあがった。
そのまま、コオロギのように笑い転げ、いきなり地面を叩き始めるデイビスの不気味さに、エディも、スコットも、ゾッと肌を粟立たせて、思わず距離を取る。
「笑い上戸かよ」
「もういい、こいつは放っておく。これ以上構っていられん」
「スコットぉ! 血も涙もねーのかよ! 同じ釜の飯食った仲だろーがよー!」
月の光の下、まだ何かうだうだと言って足首を掴もうとするデイビスを振りほどき、冷酷にその場に置いてきぼりにした。あああ、こいつの横にいると、なぜこうもどっと疲れるのか。そのうちに、ウイスキーの匂いがぐっ、と鼻にのぼってきたかと思うと、次第に焦点は合いにくくなって、うとうとと眠気が襲ってきた。徐々に立っていられなくなったスコットは、物陰を見つけると、崩れ落ちるように座り込んだ。限界だ。疲労しているところに酒を流し込んだものだから、体の自由が効かない。そばにいた人影が、心配そうに顔を覗き込んでくる。
「ちょっと兄ちゃん、大丈夫かい」
「……少し、じっとさせてくれないか。あのバカの相手をしたせいで、酔いが回ってきた」
「ったく、だらしねえ兄ちゃんだねえ」
デロリスは、ぐったりと給水塔に寄りかかるるスコットのネクタイを緩め、両のカフスボタンを外してやった。その間もスコットは、力を萎えさせたまま、デロリスの介抱のされるがままになる。
「シスター・クラレンス。救急車を呼ばなくて大丈夫かしら?」
「あん? 平気だよ、少し夜風にあてていれば。リノでは、こんな風に泥酔した野郎は、星の数ほど見てきたからねえ。ほら、兄ちゃん。朝がくるまで、寝ちまいな」
「……すまない。恩に着る」
「あっちの坊やも、また随分と飲んでいるもんだね。あんたよりはましそうだが」
その言葉に半ばほっとしながら、片膝を立てて、天に顔を向けた。もう中年だ、酒量はとっくに弁えていたのに、こうして立てなくなるまで酔い潰れるのは久々だった。こんな醜態を晒して、サラに怒られるかな、という考えがちらりと脳を掠めたが、考えてみれば、自分が妻に叱られた経験など、一度もないのだった。
「ミッキー。そこにいるのか?」
返事はなかった。スコットはもう一度、その名を呼んだ。
「ミッキー?」
酩酊した大人の対処に慣れないミッキーは、尻尾を盛んにチョロつかせてオロオロとした。
「大丈夫かい、スコット? お水、持ってきた方がいいのかい?」
「いや……」
首も振らずに、小さく、呻くように呟くスコット。
「いいんだ。ここにいてくれ」
ミッキーは相変わらず困惑していたが、その声の切迫感に引きずられて、仕方なしに、彼の隣に体育座りになる。
「まいったなあ。デイビスはともかく、スコットまで、こんなことになるなんて」
「私のせいやない。あいつら、いつもしょあくのこんれんらから」
「もう。何を言ってるのか、さっぱり分からないよう」
屋上に吹き込んでくる風に乗った楓を拾いあげ、その軸をくるくると回しながら、ミッキーは小さな声をこぼし、肩をすくめた。
とはいえ、酩酊している最中は、脳は滲み出るように冴えているもので、心地よい夜風と月にうとうととしながらも、確かに理性は働いていて、狂わされた外界を過ぎてゆく感覚は、何もかもが柔らかく、胸を引きこむほどにみずみずしい。
その波紋の中から、キイ、とドアの軋むような音が揺らめくと、
「おっと……こいつは、先客かな」
と人影が二の足を踏んだ。けれどもデイビスはすぐにそれを認識すると、両手を広げ、彼らをこの大宴会へと誘って、
「おー、新しいゲストじゃねえか! せっかくの月見酒だ。別嬪さんに色男さんよ、俺たちに加わって、飲んじまえよ! ここで出会ったのも、何かの縁だろうが!」
「ありがとう——チャリティ、おいで。僕らを歓迎してくれるそうだ」
階段をのぼって現れたのは、裕福ではない労働者なのだろう、二人とも、みすぼらしい服を着ていたが、それでも二人の燃える眼差しは、力強く、意志に溢れていた。妻の柔らかな金髪も、夫の大きなカーブを描く眉も、月明かりに鮮烈に映えた。まだ若く、二十代も半ばだろうと思われた。
「あんたたち、夫婦かい」
中折れ帽のつばを、夜風に微かに震わせながら、エディが尋ねた。
「ついこの間、結婚したばかりなんです。お金はほとんど持っていませんけれども——」
「それでも、私たちは今、最高に幸せなんです」
まるで夜の風を噛み締めるように、その薔薇色の頬を火照らせ、寄り添い合う男女。エディはどこか遠い眼差しを送り、その若い夫婦を眺めている。
「へええ、新婚たあ、めでたいねえ! Cheers! 二人の門出に、冒険に、人生の旅路に!」
ぐでんぐでんに酔ったデイビスが、月の光へ突き出すようにグラスをあげると、それに合わせて、柔らかな液体を湛えた盃が集まり、屋上に次々と祝杯の手があがった。
「ロマンスに!」とジゼル、ロバート。
「生きる喜びに」とメリー・ポピンズ、バート。
「神のご加護がありますように!」とデロリス、メアリー・ロバート。
「これから君たちの味わう、百万の夢に!」とミッキー。
各々のもつグラスは光り輝き、まるで月の光の眩しさを、一滴一滴に溶かし込んだかのようだった。人生は寄り集まり、喜びを祝する。それが人々の交差路となり、これからの道を変えてゆく。
自分も献杯しなくては、とスコットは思いかけ、もはや指一本、酔いの重さで動かせそうにはないことに気づいた。代わりに、薄目を開けて、ぼんやりと目の前の光景を見透かすと、霞んだ視界に溶けて、ふっ、とぬるい人影が動き回っているのだった。まるで万華鏡のようにシルエットが移り変わり、夜の光の中に交錯してゆくのを、綺麗だな、と感じた。
降りそそぐ月影が滲んだのか、屋上に干されたベッドシーツが、夜の中でしらじらと冴え渡るのか。暗いのに明るく、闇それ自体を皓々と照らす光がある。そして人影は、その光芒のうちに集い、あたかも影遊びの如く、それぞれに話し、めぐり、戯れる。彼らが半透明の神秘的な暈輪に包まれ、庇護されていると感じれば感じるほど、その生命は脆く、鮮やかに、変幻の物語を繰り返すのだった。
夜露に濡れる、甘く、清新な花の香りが漂い、そしてその中で、人々の高低とりどりの声は潤い、波紋のように散り散りに揺れ動いた。彼らの笑いや、身じろぎや、物音。スコットにはそれが、天上に満ちる音楽のように感じられた。一人の柔らかな男の声が、その中から朗々と響いて、感謝の言葉を紡ぐ。
「ああ、みなさん、ありがとうございます。僕らの結婚を祝福してくれる人がいるなんて、本当に嬉しくて……なんと言ったら良いのか……胸が詰まって、分からない」
「ま、ま、ま、駆けつけに一杯! めでたいことに、言葉なんていらねえだろー?」
「飲めるかい、チャリティ?」
「ええ、いただくわ。ここはとても優しい方々のいるところなのね」
「二人は、遠いところからやってきたの?」
「そうさ。ご両親に結婚を反対されて——」
「私たち、駆け落ちしたのよ」
駆け落ち、という言葉に、デイビスはぴくりと目を細めたが、次の瞬間には、その顔をだらしなくくずして、
「へえ、それでお二人で逃げてきたってわけか? やるじゃねえか! 随分な勇気が要っただろ〜?」
と、呂律の回らない舌で言祝いだ。
「いいえ。確かに私たちは新しい世界に出発したけれど、でも、何も怖くありませんわ」
きっぱりとチャリティは告げて、隣にいる夫——月の下で微笑みかけてくるフィリアスを見つめた。
「彼がいるんですもの。私には彼がいる。そしてこれから先も永遠に、彼と一緒にいられるのだから。そのためなら、何を捨てたって構わないの」
はにかむように、けれども凛と芯の通った声が語り、その言葉に誘われて、スコットは思い出す。十数年も前の、自分がサラと恋に落ちた頃。親に反発し、学生結婚を経て、ともに家を飛び出して外へ駆けたあの頃。
(サラと二人暮らしを始めた頃も、あんな風に、毎日がまぶしくて仕方なかったな)
あの当時は、毎日金に困っていたが、明るく笑い飛ばして、心は次々と夢を追っていた。あの時の、世界にふたりきりだ、というはち切れそうな喜び。自分には、彼女しかいないのだ、とむきだしの魂で信じる際の、凄まじくも痛切な甘さ。世界は無性に鮮やぎ、無性に情念を掻き立てられるようで、そして胸は、いつでも空へと浮き立っていた。サラは美しかった。どうして愛せずにいられるだろうと思うほど、心の美しい人間だった。このような女性と知り合い、愛し合い、婚姻を結べること、それ自体が何か、奇蹟的な力で導かれている気がした。
そして月日を経て、子をなし、子が話し、子が走り、子が重くなり、力を入れて抱きあげるようになって、ふたたび、新しい命が宿り、また小さな子どもが生まれようとしている。それはスコットとサラだけが辿る物語で、そのページ一枚一枚の愛おしさは、彼らしか知らないインクの熱で灼きついている。他の誰にも譲り渡せない、彼らの時間は、彼らだけのもの。この地上でそれを分かち合えるのは、彼女ただ一人なのである。
この月の光の下のどこかに、スコットと同じ夜の空気を浴びて、彼らはいるはずだった。甘えたがりの娘、まだ見ぬ我が子、そしてその子を孕み、人生を分かち合うと約束した自らの伴侶が。年月をかけて、世界は静かに変わり続けてきた、そしてどの一瞬も、月明かりに照らされる砂糖菓子のように光り輝いている。すべてに祝福されたように、デイビスたちからの歓声を受けて微笑む新婚の夫妻は、今まさに、その頂点を極めているかのようである。
(ああ。今、目の前ではしゃいでいる夫妻たちは、あの頃の私たちの幸福を、もう一度繰り返しているようなものなのか——)
ふと、スコットはそのように思い当たる。それはサラとスコットにとっては、もはや過ぎ去った日々の夢幻。けれども、今まさにその絶頂を迎えようとする若者たちがいて、喜ばしい出来事は世に繰り返されるのだということに、感銘を隠すことはできなかった。人は生き、恋をし、世界の果てでめぐり逢う。それらは、自分が主人公ではない物語のはずなのに、この世に物語が繰り広げられるたび、すべては美しいと思う。すべては肯定されていると思う。例え、その喜びが自分のものではないとしても、それは極限の美しさを放っているのだ。
「あの二人は、本当に、お互いのことが好きなんだね」
幸せに満ち足りたように微笑み、そして少しばかりの羨望を織り交ぜて、ミッキーは呟いた。
「僕のパパとママも、あんな風に愛しあっていたのかな?」
スコットは彼の方を見ず、ぼんやりと月明かりに目を細めていたのだが、やがて強い酒に枯れた喉で、呻き声を引きずり出すように、ミッキーに低く囁いた。
「ああ、そうだな。きっと、愛しあっていたはずだぞ」
「スコット、君には分かるのかい?」
「ああ。もちろん、大人には分かる」
酩酊に半ば沈み込みながら、スコットはしわがれた喉を鳴らして呟いた。
「でなければ、お前のように優しい子が生まれてくるはずがない。……だから、誰よりも愛しあっていたに決まっているんだ」
そのスコットの肩に、ミッキーはそっと、ちいさな頭をもたれさせた。スコットは何も言わず、ただ深く瞼を伏せたまま、すやすやと、安らかな寝息を漏らしていた。
ずいぶんと無茶苦茶な論理を言うんだね、スコット、とミッキーは心の中で話しかける。僕のパパやママが、どうして姉は残して、僕だけを孤児として手放したのか、分からない。僕にはウォルトと、ミニーだけしかいないと思った。僕を必要としてくれる人なんて、他に、誰もいないと思っていた。
でも、今は。
(守るんだ、僕の大切な人たちを。
何が美しくて、何が素晴らしいのか、もう僕には分かっているから。
————世界一素敵な魔法を、彼らにかけにゆくんだ)
たったひとつでいい、そのように信じるかけらがあるなら、何度でも立ちあがり、夢を見ることができる。捨てられたと感じても、前進する力を拾いあげて、前を向くことができる。何度でも、何度でも。
それは、彼らの生きる力、心の奥底に燃える、希望の灯火だった。先日、新妻を迎えたばかりのフィニアスもまた、貧しい生まれのまま、幼くして労働に就かねばならなかった。寒い冬の夜に、育ての親を看病し続け、曇り空の下で枯れ葉の揺れる共同墓地に埋葬してからは、誰も彼を守ってくれる者はなくなった。身を切るような視線の冷たさ、世間の残酷さ、絶えず脳を占めるひもじさ、自分は痩せっぽちで、惨めで、どうしようもない人間なのだということ。ごみ箱を漁っては新聞を転売し、パンをくすねようとしては蹴りあげられ、雪の中で雇用主に頬を打たれた時は、唇から滴る血とともに、涙が滲んだ。けれども彼は、吐き捨てる唾にも、雨あられと降りそそぐ罵声にも、一度も心を譲り渡したことはなかった。朝陽がのぼるたび、何かが着実に彼を強くし、彼の味方になってくれるのだということを、フィニアスは知っていたのだった。
だって毎夜、彼がベッドに入ると、彼の頭には、あまりに眩しすぎる色彩で溢れかえって、その明るさに昂奮し、まるで眠れなくなってしまうのだから。百万の夢。それが彼を、この世に繋ぎ止めてくれていたのだった。夜の中で輝き、弾け、炸裂し、スパークし、爆発し、増殖し、すべてを照らしながら、無限の世界を駆け抜けてゆく、あまりに高邁な光、太陽よりも鮮烈な光。それはいったい何だったのだろう。孤独の中で垣間見る幻想だったのか、それとも霊感だったのか。まるで大量の彗星が押し寄せてくるよう、彼は心臓の飛び出るほどにドキドキとして、何が現実で、何が妄想で、何が夢なのか、少しも分からなくなってしまうのだ。色は、なおも眩暈の渦となって襲いかかり、何百、何千、何万にも分裂し、素晴らしい軌道を描いて閃光を降りそそがせ、純粋な光だけが支配する、天まで突き抜けるように躍りあがる。そのあまりに不可思議な体験に、ぞっとするほどの鳥肌が走り、わななく手を透明な輝きに伸ばすと、彼さえもが光の一部と化してしまった。彼は叫んだが、叫びすらもが光となった。光は彼を魅し、見たこともない次元へと運んだ。すべては躍り、すべては皓々と輝いた。そして、そのめくるめく洪水と一体化して天翔けるたび、生きたい、という思いが噴きあがり、何よりも強く、明日を求めるようになれるのだ。
この眩ゆさを分かち合えるのは、この世でただ一人、チャリティだけだった。身分など関係ない。何に目を輝かせるか、何を望んでいるか、何に想像力を膨らませるかが、遠い距離の彼方から彼らの魂を繋げる、ただひとつのよすがだった。
やがて彼らが成長し、チャリティが学校に連れ去られ、一人で生きてゆかねばならない時期がやってきても、けして途切れることなく交わされる膨大な書簡の中で、彼らは夢を語りあった。風が舞いあがるように、花びらの躍るように、別々に引き裂かれた人生の中にも喜びは満ち、年月は過ぎてゆく。幾つも月に照らされた煙突は、雲に溶け込むような煙を吐きつらね、最も高所から、地上の全面へと射してくる月の光は、世界を雲隠れさせるその真っ白な煙を、夜の虚空にくずし広げながら冷やしていった。そこは、満月の暈だけが行方を知る、神秘的な世界だった。雲霞の中では、すべてが幻影であり、騒がしかった。高らかな汽笛、まるで英国のシルクハットを被ったような機関車も、高架線も、労働者たちのお喋りと影法師も超えて、限りない自由、削ぎ落とされたかのような自由、安い薄手の服では世界が肌寒いほどに感じる自由の中に、家を飛び出してきた彼らは、無限の夢を躍らせるのだった。十にも満たない持ち物を片手に、世界をぐるりと見渡すと、果てしない孤立と引き換えに、眩暈がしてくるほどの解放を味わった。愛する人間と孤立しているということは、喜びだった。そして新たな世界が幕を開け、新たな扉が彼らを迎え入れた。労働すること——新しい、幾万もの生活を携えて前進する、この街で。ここから、二人のすべてが始まってゆく。
若いバーナム夫妻は、ときめきで胸をいっぱいに膨らませ、新天地に目を見開いた。夕暮れに、労働者たちが汗を拭い、最後の工具の片付けをしていたのはいつだったか。煉瓦造りのビルの窓ガラスに、燃えるような琥珀の夕暉が反射していたのを見たのは、どこでだったか。薔薇と蠟燭を窓辺のテーブルに立てかけ、暖かく波打つ食堂の燈の中で、記念日に乾杯する恋人たち。重たいシャベルで石炭を掬い、真っ赤な焰に照らされ続けてきた火夫たちは眠る。それが、彼らが生きることを選んだ世界。眩しいものと驚くべきことが一体化し、何もかもが真新しく目に飛び込んでくるのだった。
あまりに見切り発車すぎる新婚生活だと、彼女の両親は鼻で笑った。けれども、それで良いのだと思った。切符は片道しかなくて、荷物はぼろぼろのトランクケースしかなくて、身ひとつあれば、どこにでも行ける。彼らは空っぽの新居のドアを叩いて、テーブルクロスを絨毯代わりに敷き、まだ家具も置いていないその部屋に、たった二人、古びた床に赤い蠟燭を煌めかせて座り込む。どこにも故郷はなく、還るべき場所もなく、それゆえに、これから旅をすべき世界だけが広がっていた。誰も知らないこの世で、誰も足跡を残さないこの街で、すべてが夕陽と影だけになってゆく、ちいさなアパルトマンの片隅で、彼らはその煤けた窓ガラスに映る、眩ゆいばかりの夕陽を瞳に映し、たった今、この地球に起こっている、壮大な事変を知るのである。遠くから聞こえてくる機関車は、前進の匂いがした。規則的な蒸気音も、長い長い汽笛も、誰もいない世界に招き入れられ、初めてのアダムとイブの生活を呼び起こすかのようである。ここから始まるのだ、何もかも。地面が震えた。月は蒼かった。翳が判然と躍動していた。何もかもが初めてで、未知だった。すべては永続するものであり、誰にも破壊することはできず、完璧な二十四時間、三百六十五日、何十年もの人生が与えられた。そしてそれを、余すことなく躍り尽くして、昂然と生き続ける人々。この世をばたばたと、屋上に干してあるシーツが高らかに裾をはためかせた時、目が眩んだ。すべてはゆるされていた。すべては自由であった。
「チャリティ、僕は、この地上で一番素晴らしいショーを開きたいんだ。それはもう最高のショーで、誰もが興奮で眠れなくなって、ひとめ見ただけで、めくるめく無数の夢が、全身を駆けめぐる」
「待ちきれないわ」
「そうだろう?」
「あなたはいつだって、ここにはないものを見据えてる。まるで、永遠の子どもみたいに」
「そうさ、チャリティ。僕は、夢を見ずにはいられないんだよ」
愛する妻の手を握り締め、やがて、世界で最も偉大なショーマンになる男——P. T. バーナムは語る。
「そこはね、色鮮やかな光で埋め尽くされて、爪弾きにされていた者たちが、素晴らしい夜を支配しているんだ。どんな不可能も叶えられて、君を虜にさせる。今までの世界なんか、すべてすべて、遠くへ吹っ飛んでしまうんだ」
この人間が夢を語る時の、熱っぽい口調と、絶え間ない煌めきに満たされた眼差しが好きだった。どんなに大きくても、小さくてもいい、とチャリティは思う——私もそこへ行って、同じ夢を担いたい。
初めて出逢った時から、ずっと彼と同じ夢に浸かっていた。私が大切に育てられた令嬢で、彼がまだほんの幼い使用人だった頃でさえ、目に見えるものをたちまち、見たこともないものへと塗り変えてしまう彼の才能は、私を夢中にさせた。手に手を取り合い、深い森に抱かれて廃墟となった洋館を探検し、暗闇に蔓延る蜘蛛の巣や階段に震える私に、たったひとつのランプをつけるだけで、彼はたちどころに、見える世界を、めくるめく光と翳のおとぎ話へと一変させてくれた——あの時から、眩しさを追い求める彼の心は変わっていない。けれども、さらにたくましく、現実を生き抜いてゆく力を身につけ、私は彼の妻になった。この日をどんなに待ち望んでいたことだろう。そうだ、初めて逢った時からずっと、彼と結婚したかった——この人のことを、誰よりも愛していた。そうして、欲しいものを手に入れた今、沸き返る幻想に胸は無限に高鳴り、けたたましい汽笛に心臓が震えるかの如く、未知の領域へと向かって走り出してしまうのだった。
♪Every night I lie in bed
毎夜 ベッドに横たわると
The brightest colors fill my head
眩ゆい色でいっぱいになって
A million dreams are keeping me awake
百万もの夢で眠れなくなるの——
A million dreams, a million dreams
百万の夢 無限の夢が!
張り裂けるように脈打つ夜の風とともに、彼らは満月の夜の屋上を駆けた。月は、吼えるように明るく、この世のすべての事物が、宇宙の光に照らされていた。何もかもがくっきりと見え、そして彼らの目には、幼い頃から思い描き続けた幻の、十数年に渡って交わし合い続けた手紙の、さらにその先の道すじが、ありありと見えたのだった。
♪I think of what the world could be
世界はきっと変わってゆく——
———広い広い屋上で、笑い声をあげながら駆けてゆく二人を、
♪A vision of the one I see
僕の/私の見た方向へと進むんだ!
———誰がこの世で最も貧しい、自由でない人種だと言えるだろう?
♪A million dreams is all it's gonna take
百万もの夢がすべてを導いてくれる
———すべては創造されていた、一瞬ごとに、一秒ごとに。世界は、命の前に解放されていた。
月明かりに照らされ、踊るようにはためく無数のベッドシーツは、真っ白な映画のスクリーンの如く、幾多もの影像が動き出すのを待っていた。冷ややかなまでにみずみずしい思いが、幾つも胸に迫りあがっては、彼らの夢を満たしゆく。彼らは一点の曇りもなく完成されていて、今この瞬間は、例え神であろうとも、否定することなどできない。
♪A million dreams for the world we're gonna make
百万の夢で世界を創るんだ——!
二人の声は交わりながらどこまでも伸びてゆき、歌は満月へと飛翔し、見たこともない高所まで到達していった。めくるめく月の表面に触れ、皓々と眩しい月明かりが睫毛に滲むように、恍惚として近づいてくるこの至純の絶頂を、誰も押しとどめることなどできない。フィニアスもチャリティも思う——どんなに貧しいさなかだって、素晴らしい瞬間はやってくる。今だってそうであり、今まさに、自分たちはその只中に息衝いているのだ。
恋人の温かい腕に抱かれると、人肌の温度と愛する人の匂いが、夜風とともにそっとチャリティを押し包む。そして、その温もりの中で、この世にまたひとつ、命が宿り、とくとくとちいさな鼓動を放ち始めた。フィニアスは彼女の腹に優しく手を添え、彼女とともに築きあげる、新しい家族の夢を見る。
♪For the world we're gonna make...
僕らの思い描く世界を......
夢は、数えきれない小さな波のように押しては引いて、百万ものきららかな反射を撒き散らしてゆく。
真っ白なベッドシーツの彼方に、煙の彼方に、雲の彼方に。それは眠ることなく、懐かしい形の影を落として、隠れていた。はたはた——と微かな音を立ててうち靡くシーツが、夢の名残のように響いた。そして人々の影は、現か、幻か、あまりに淡く、あまりに芒洋とたゆたいながら、その糊の利いた清潔な白紙の上に、ちいさな物語を描き続けるのだった。ランプを灯しながら——ひそひそ話を交わしながら——火種に瞳を煌めかせながら——この深い宵闇の中で。
「この世に素敵なことがある限り、人は夢を見続けるのよ」
ぽつりと、ジゼルが呟く。小花模様の散ったカーテンドレスが、夜風に煽られ、眩しく踊るように揺れ動いた。背後に、シンデレラ城の水色の明かりが灯され、数枚の紅葉が風に流れた。
デロリスは、大の字に横たわるデイビスと、壁にもたれて眠るスコットを見つめ、肩をすくめながらエディに話しかけた。
「この兄ちゃんたちは、ここらへんに転がしておこうかね」
「まったく、情けねえ奴らだぜ。どいつもこいつも、酒に溺れやがって」
呆れながら、けれども俺も、人のことを言えないか、とふと最近までの我が身を振り返ったエディへ、ミッキーは軽く後ろから背広の裾を引っ張って、彼に無線機を手渡した。
「なんだ、ミッキー?」
「君に電話だよ」
「俺にかい?」
「ターミナル・バーの、ドロレスから」
その名前に、ふっ、と一瞬、素顔をさらしたようなエディに対して、ミッキーは、
「愛人じゃないのかい?」
と白い歯を並べ、ニヤッとしてみせた。
「馬鹿。大人の周辺を嗅ぎ回るんじゃねえよ」
「そんなことを言うなら、無線機を貸してあげないよ!」
「おい、ミッキー!」
ぷいっとそっぽを向くミッキーに弱り果てたように、エディは彼の頭をおざなりに撫で、機嫌を取った。
「分かった、わぁるかったよ。——だから、ドロレスと話をさせてくれ。頼む」
「そうだよ。最初から素直になればいいのに」
憎まれ口を叩きながら無線機を受け渡すと、それから、ミッキーの眉毛が不意にあがり、へへっ、と子どもらしく、久方ぶりに悪戯そうに微笑んだ。
その月の光に照らされた、薄闇の中の幼い笑顔を見ているうちに、胸の奥底に、一番純粋で、一番暖かい思いが湧きあがってきた。夜風や、星々や、街のランプの光の輪と共鳴するように、その思いは酷く外界に馴染み、そして溶け広がっていった。気づけば、エディの顔には、微笑が浮かんでいた。それはふと月に透ける花びらのように静かで、自然で、それでいて清冽な笑みだった。人間の浮かべる中で数少ない、完全なる善意に満たされた表情の如く、それは彼を慰め、彼を導き、そして彼を安らぎで満たした。
エディは、それまで被っていた中折れ帽を、ぽすりとミッキーの頭の上に被せてやった。ミッキーはくすぐったそうに笑い、少しばかり、鼻先をエディのスラックスに擦りつけて挨拶すると、階段を駆け降りてゆくその後ろ姿を見送った。
一方のバートとメリー・ポピンズは、床に伸びているデイビスとスコットを見て、揃った溜め息をつく。
「やれやれ。こっちの大人たちは、いつまで経っても子どもなんだから」
「まったく呆れてしまうわ、浴びるようにお酒を飲むだなんて。ひっく」
「メリー。もしかして君も、ラム・パンチで酔ってる?」
「私のように上品な女性が酩酊を? どこからそんな話」
「はいはい、分かりましたよ。誇り高い女王様」
屋上で繰り広げられる饗宴から一人離れ、とん、とん、と階段を降りていったエディは、今にも降るような星空の下で、店の外に吊り下がったランプの下に腰を下ろし、そこでようやく、頭上から照りつける光芒を眼に滲ませながら、無線機の先の声に応じた。
「なんでえ、ドロレス。もう床に就いたんじゃなかったのか」
《さっきのこと、やっぱり文句を言ってからベッドに入ろうと思ったの。変な夢でも見たら困るでしょ?》
「なんだよ、その変な夢ってのは」
《私がろくでもない成金男と結婚して、借金だらけのあなたを、肩代わりにこき使っている夢よ》
クックックッ、と喉の奥で笑いを噛み潰して、エディは肩を震わせた。皓々たる月が、霧のような薄雲に翳り、また微かに現れた。虫の声が響いていた。
「俺はよっぽど、おめえに恨まれてるらしいな」
《当たり前よ。帰ってきたら耳を揃えて、キッチリ返してちょうだい。今度こそ、延長はなしよ》
「ああ、分かった、分かったよ。それからな、ドロレス、……」
《何?》
彼は少しの間迷ったが、もう恥じらうような関係でもないか、と思った。会話するたびに胸を過ぎっていたその感情は、目の前にある地面を、地面だと、そう口にするようなことだったのかもしれない。
「愛してるぜ、ドロレス。たぶんな」
《とんだ臆病者ね。電話でしか言えないの?》
間髪入れず、低い燕のように切り返すドロレスに、エディはふっと唇を緩めて、葉巻を指で弄りながら、煙を吐いた。
「ああ。電話でしか、言えねえんだ」
《私は、あなたなんか嫌いだわ》
「そうか、残念だな。……それでもいいさ」
NEXT→https://note.com/gegegeno6/n/nb36da92abbf2
一覧→https://note.com/gegegeno6/m/m8c160062f22e
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
