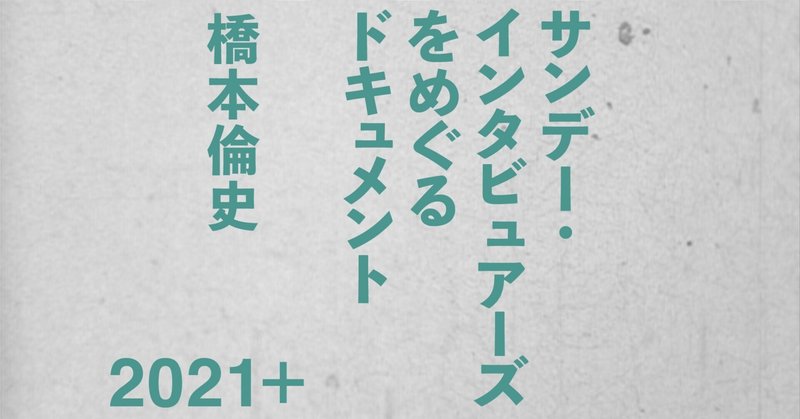
第9回「言葉が途切れたあとも余韻が響いているのかもしれない」(文=橋本倫史)
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムの映像を手がかりに、“わたしたちの現在地” をさぐるロスジェネ世代の余暇活動「サンデー・インタビュアーズ」。月に1度オンラインで集い〈みる、はなす、きく〉の3ステップに取り組みます。ライターの橋本倫史さんによる記録です。
連載第9回(全17回)
今年もまた、「サンデー・インタビュアーズ」のプロジェクトが始動する。私たちは、どんな時代を生きているのか──。サンデー・インタビュアーズは、この問いを探求するべく、月に一度オンラインで集まって活動をする。その手立てとなるのが、東京・世田谷の各戸から提供された「8ミリフィルム」だ。家族の団らん、レジャー、社員旅行などが写る、昭和のホームムービー。今とは異なる時代の風景を手がかりに、今という時代と出逢い直すのが、サンデー・インタビュアーズだ。
活動は3つのステップから成る。ステップ1は、「ひとりで “みる”」。「世田谷クロニクル1936-83」に公開されている映像を選び、気になったところをピックアップする。ステップ2の「みんなで “はなす”」では、それぞれの視点を持ち合って話し合う。最後のステップ3は「だれかに “きく”」で、それぞれの気づきや発見をさらに深めるために、誰かにインタビューしてみる、というものだ。
2019年度に立ち上がった「サンデー・インタビュアーズ」は、初年度は実際に対面で実施できていたものの、翌年度からはコロナ禍の影響でオンライン開催となった。ステップ2まではZoomで代替できたものの、どこかに出かけて行って、誰かとはなすことが難しくなった状況下では、ステップ3の「だれかに“きく”」ことのハードルが高くなってしまった。身近な誰かに話をきいてみたり、あるいは自分自身に問いかけてみたりすることで補ってきたけれど、他者と出会って話を聞くことはできずにいた。
ステップ3の「だれかに“きく”」を、もっと掘り下げてみることはできないか──。そこで立ち上がったのが、「サンデー・インタビュアーズ2021+」という企画だった。昨年度のサンデー・インタビュアーズに参加した5名が、それぞれの“きく”を掘り下げるためのプロジェクトである。まずはその準備として、今年の春からオンラインの勉強会が始まった。
第一回が開催されたのは、4月24日のこと。「だれに、なにを、どうやって〈きく〉のか」。それを考えるきっかけを作るためにも、まずはそれぞれの関心に沿っていろんな〈きく〉の事例を持ち寄って、ざっくばらんに話し合うことになった。
「“きく”というのがあえて平仮名にしているところがポイントかなと思って、“きく”ということを広く考えて資料を作ってみました」。トップバッターとして発表をする佐伯さんが切り出す。佐伯さんが画面共有で表示した資料には、“きく”の実例が「聞く」と「聴く」、それに「訊く」の三種類に分類されてある。
「それぞれの“きく”がどういう意味なのかと調べてみますと、『聞く』というのは字の成り立ちからすると、響いてくる神の声をきくというのが元になっているようです。音や声が自然に耳に入ってくる、あるいはその内容を自然に知るということで、どちらかというと受動的に入ってくる。英語で言うと“hear”ですね」
それに対して、「聴く」は耳を突き出してまっすぐな心で“きく”ことを意味し、能動的に相手を理解しようとすることを指す。もうひとつ、「訊く」という文字になると、次から次へと素早く尋ねることを指す。「聴く」は英語にすると“listen”、「訊く」は“ask”にあたるのだと、佐伯さんが教えてくれる。
「僕はちょっと前まで人事部にいたことがあって、会社でカウンセリング制度を導入することになったとき、キャリアカウンセラーの資格を取得したんです。カウンセリングの基本は、相手の話を傾聴する。相手は話をすることによって、自分自身の気持ちや思いに気づいていく。『聞く』と『聴く』と『訊く』、三つの“きく”はそれぞれ微妙に意味合いが違うんですけども、情報の流れは一方向だな、と。ただ、本来の“きく”というのは、相互にきき合うことによって相互の理解が深まっていく──流れが双方向になることがコミュニケーションの本質かなと考えました」
佐伯さんは“聞く”の実例として、「Radikoで好きな番組を聞きながら仕事をする」ことを挙げていた。佐伯さんの話を受けて、事務局の水野さんはラジオの話を切り出す。
「ラジオの文化として、“笑い屋”っていうんですか、笑い専門の人がいますよね。佐伯さんがおっしゃるように、“きく”というのはコミュニケーションだと考えると、ひとりでしゃべってるだけだと限界があって、話す人と“きく”人のコミュニケーションがあってこそ成り立つものがあるのかなと思いました」
土田さんが発表で取り上げたのは、ある書評だ。荻窪で「Title」という書店を営む辻山良雄さんは、東京新聞と中日新聞で連載中の「公開選書 あなたに贈る本」の中で、キム・ハナ著、清水知佐子訳『話すことを話す』(CCCメディアハウス)を取り上げていた。
「この書評の中に、『キムさんは意識して誰かの話し声を聴いてみるだけでも、その人の話し方は変わってくるといいます』と書かれていて、なるほどなと思ったんです。内容ではなくて、相手の話し声を意識して聴くだけでも、その人の話し方まで変わってくるというのは非常に面白いなと思いました。聴く側の態度が、話す人に影響してしまう。もしかしたら聴く側の態度によって、出てくる記憶も変わってくるのかなと思って、ちょっと紹介してみました」
これは、自分がきかれる側にまわると実感する。もしも自分がインタビューを受けるときに、相手が自分の聞き出したい情報だけを引き出したくて、それ以外のことには関心がないといった態度をとっていたら、その相手に話をする気は削がれるだろう。あるいは、こちらにさほど興味がなさそうに見えたり、話が伝わっている実感が薄かったりすると、もっと話したいことがあったとしても、途中で話を切り上げてしまうだろう。
自分がきかれる側だったらと想像すると、たとえばメモをとる仕草ひとつとっても、コミュニケーションに影響が出るのだろうなと感じる。相手がこちらには目もくれず、尋問するようにメモばかり取っていたら、あまりいい心地はしないかもしれない。ただ、話を熱心に聞きながらメモを取っているのだと感じられれば、「そんなに興味を持ってくれるのなら、もっと話をしてあげよう」という気持ちになるかもしれない。ただ、難しいなと思うのは、相手の目をちゃんと見て、「私はあなたの話を傾聴しています」という態度で接すればいいということでもない、ということ。「こうやったほうが相手は話しやすいだろう」と考えて、ちょっと芝居がかった聞き方をしてしまうと、相手がそこに白々しさを感じる場合もある。会話がコミュニケーションである以上、相手によってやりとりは変わるし、その日の気分によっても受け取り方は変わってくる。
「キム・ハナさんの本の書評を読んで思い出したのは、ある会議ファシリテーターの人のことで」。土田さんは発表を続ける。彼は、家族会議から国際会議まで、幅広い会議のファシリテーションを執り行ってきた人だ。土田さんは以前、彼が講師を務めるワークショップに参加したことがあるのだという。
「そのワークショップに、彼がどこかの国の鐘を持ってこられていたんです。『ちょっと聴いてみてください』といって、その鐘をカラーンと鳴らして、音が徐々にフェードアウトして、音が消えて余韻が残る。人が話をするのもそれと同じようなことで、話し終わったらそれで終わりっていうんじゃなくて、言葉が途切れたあとも余韻が響いているのかもしれない、と」
「その鐘って、ティンシャってやつですか?」土田さんの発表が終わったところで、やながわさんが尋ねる。
「そうですね。紐があって、チーンって鳴らすやつでした」
「もともとチベットの宗教儀式で空気を清めるみたいな感じで使われるものなんですけど、会場に良い音が響いたら良い空気になるということで、いろんな会議や対話の会で使われるもので、私もよく使ってました」
大勢の人が参加する場であれば、鐘の音を鳴らすことで場が整い、よい会になる。その一方で、会議の場に不慣れな人に話をきくのであれば、整った場所でインタビューを収録するよりも、あえて雑多な場所でラフにきいたほうが相手は話しやすいということもありうる。勉強会の様子を眺めながら、“きく”ことの奥深さを改めて考える。
文=橋本倫史(はしもと・ともふみ)
1982年広島県生まれ。2007年『en-taxi』(扶桑社)に寄稿し、ライターとして活動をはじめる。同年にリトルマガジン『HB』を創刊。以降『hb paper』『SKETCHBOOK』『月刊ドライブイン』『不忍界隈』などいくつものリトルプレスを手がける。近著に『月刊ドライブイン』(筑摩書房、2019)『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』(本の雑誌社、2019)、『東京の古本屋』(本の雑誌社、2021)、『水納島再訪』(講談社、2022)。
サンデー・インタビュアーズ
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムを手がかりに、“わたしたちの現在地” を探求するロスト・ジェネレーション世代による余暇活動。地域映像アーカイブ『世田谷クロニクル1936-83』上に公開されている84の映像を毎月ひとつずつ選んで、公募メンバー自身がメディア(媒介)となって、オンラインとオフラインをゆるやかにつなげていく3つのステップ《みる、はなす、きく》に取り組んでいます。本テキストは、オンライン上で行うワークショップ《STEP-2 みんなで“はなす”》部分で交わされた語りの記録です。サンデーインタビュアーズは「GAYA|移動する中心」*の一環として実施しています。
https://aha.ne.jp/si/
*「GAYA|移動する中心」は、昭和の世田谷をうつした8ミリフィルムのデジタルデータを活用し、映像を介した語りの場を創出するコミュニティ・アーカイブプロジェクト。映像の再生をきっかけに紡がれた個々の語りを拾い上げ、プロジェクトを共に動かす担い手づくりを目指し、東京アートポイント計画の一環として実施しています。
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]
サンデー・インタビュアーズをめぐるドキュメント2021(文=橋本倫史)
第1回「誰かが残した記録に触れることで、自分のことを語れたりするんじゃないか」
第2回「この時代の写真を見るとすれば、ベトナムの風景が多かったんです」
第3回「川の端から端まで泳ぐと級がもらえていた」
第4回「これはプライベートな映像だから、何をコメントしたらいいかわからない」
第5回「『ここがホームタウン』と感じることにはならないなと思ってしまって」
第6回「なんだか2021年に書かれた記事みたいだなと思った」
第7回「仲良く付き合える家族が近所にたまたま集まるって、幸せな奇跡というか」
第8回「子供心にいつもと違う感じがして、わくわくした」
第9回「言葉が途切れたあとも余韻が響いているのかもしれない」(本記事)
第10回「真ん中に写っているのは、おじさんが好きだった先生でしょう」
