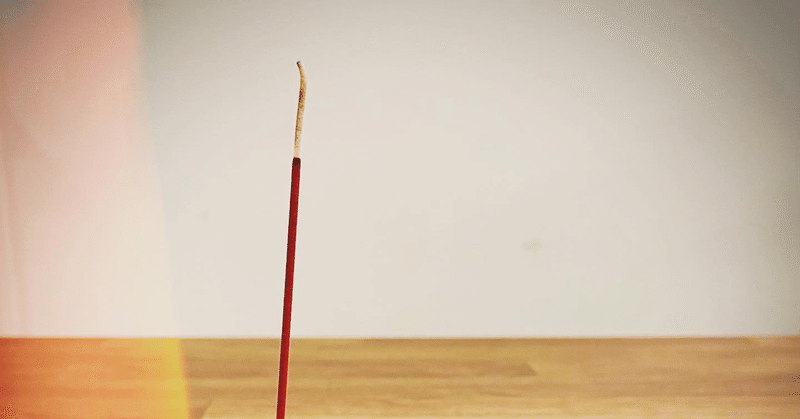
それでも、「滅び」は美しい。 第二稿
【連載】あれこれと、あーと Vol.5
田中義樹 《ウォーホル》

これは、アート/空家 二人の企画展、「NITO10」で鑑賞した作品だ。
田中 義樹 《ウォーホル》
2022年 文庫本、模型
手前に三島由紀夫著『金閣寺』の文庫本、その奥にミニチュア模型の銀閣寺がちょこんと置かれている。先にこの作品を見ていた人が、可笑しそうにくすくす笑っている。なんだろうと私も近寄ってみるが、よくわからない。
三木さんが声を掛けてくれて「文庫本、よく見てみてください」と言う。どれどれと手に取ってみると…

銀になった『金閣寺』
なんと、ボールペンの書き込みによって文庫本のタイトルが『金閣寺』から『銀閣寺』に改名されている。さらにページをめくってみると、本文中に記された「金」の字が悉く「銀」に書き換えられていた。どのページも、どのページも…。これでもかというほど執念深く金の字が銀に変わっているではないか!
あまりの徹底ぶりと謎の執念を感じるし、それがなんだか面白くて、思わずニヤっとしてしまった。「さすがにここは抜けているんじゃない?」と呟きながら奥付をチェックするも、深く刻まれるように書き換えられた「銀」の字を発見。うーん、抜かりない。
次に、文庫本の先にある模型に目を向ける。よく見るといささか厚ぼったい塗装の銀閣寺であることに気が付いた。のっぺりと灰色の塗料で覆われた銀閣寺。よく目を凝らしてみると、その内奥にかすかに金色が見え隠れしている。…どうやらこちらも、銀色に塗り替えられているようだ。
この作品で、文庫本の『金閣寺』も、模型の『金閣寺』も、田中氏の手によって丹念に銀閣へと変貌させられていた。三木さん曰く、田中氏は三島由紀夫『金閣寺』を読了し、その結末に違和感を覚えたそうだ。『金閣寺』というタイトルがこの本の内容そぐわないと感じたらしい。なぜだろうか?
三島由紀夫『金閣寺』のあらすじ
ここで、金閣寺のあらすじをご紹介しよう。(※ネタバレあり。注意です)
舞台は戦前から終戦直後の京都。主人公の溝口は、貧しい僧侶の家の生まれで、繊細で感受性の強い少年だった。父から「金閣寺ほど美しいものは地上にはない」と聞かされ続け、次第に金閣寺へ深い憧憬を抱くようになる。
吃音による劣等感や、社会での生きづらさ、人間関係の悩みなどを抱える中で、金閣寺を自らの心を癒す日々。
しかし、その存在が大きくなるにつれて、溝口は心に描く金閣と現実の金閣の狭間で苦悩していくことになる。
…美ということだけを思いつめると、人間はこの世で最も暗黒な思想にしらずしらずぶつかるのである。人間は多分そういう風に出来ているのである。
憎いほど美しい。焦がれるほど遠い。

この本の中で金閣寺は、永遠の美を内包したまま、滅ぶべき存在として描写されている。歪で不完全な肉体に囚われていた主人公にとって、金閣寺は恨めしいほど眩く、そして焦がれるほど輝かしい存在。まさに、遥か遠くに聳える「完全なる美」の象徴だった。
しかしこの深すぎる想いは少しずつ嫉妬と憎悪にすり替わってしまう。不完全な自分、醜い自分。現実世界で味わう絶望と挫折。主人公は鬱屈した日々の中で、金閣寺が戦争の最中で燃え滅びることを夢想するが、神の差配か、それも叶わない。「どんな時でも美しく悠然と佇むその姿が憎らしい…恨めしい…。」溝口は金閣寺に対して、一層の恨みを抱くようになる。そして遂に、金閣寺を自らの手で焼き殺し、共に滅びることを決意するのだった。
みにくき姿を待ちえて、何かはせん。

しかし、最後は多くの読者を裏切る結末となる。金閣寺に火をつけた後、主人公は突如として死ぬことやめたのだ。これは大きな心変わりだ。主人公は短刀とカルモチン(睡眠薬)を捨て、自死という選択を完全に放棄した。溝口はこの局面で「私は生きよう。」そう、思ったのである。
三島はここで、生きるということをかなり強調して描いている。(この辺りが、昭和25年に起こった金閣寺放火事件と違う点)金閣寺と主人公が共に滅びることによって、はじめて、物語が終焉を迎えるはずたった。けれど主人公はその道をあっけなく手放し、金閣寺のみを滅ぼしてしまった。それが、この本の結末だ。
田中氏はこの本を読み、「これじゃあ金閣寺じゃない。だったら、銀閣寺で良くない?」そう思ったのかもしれない。三島が本文中に散りばめた「金閣寺」という言葉をしらみ潰しに書き換えていく。金閣寺の模型もいささか乱暴に塗りつぶしていく。
ともすればかなり冒涜的で乱暴なアクションだ。言葉や文章でなく、文庫本に直接文字を書いたり、絵具で塗りつぶしたりする行為でアプローチしているところが「露骨」な感じで面白い。

『金閣寺』の読者も、この作品の鑑賞者も、所詮は受け手。それをどう捉えるかは自由だ。主人公の溝口もおそらくそうであったのではないか。彼が見ていたのは目の前に在る「金閣寺」ではなく、自らの心が作り上げた「金閣寺」だったのではないか。対象を美しいと思う、醜いと思う。それは受け手が勝手に思う事で、目の前に在るものは、ただ在るだけなのだ。

主人公が金閣寺を燃やしたことと、田中氏が三島由紀夫の『金閣寺』を書き換えたこと、行為者としてどこか通ずる部分を感じたのは私だけだろうか。
人はなぜ、「ただ在る」だけのものに、心を動かされるのだろう。死ぬ、老いる、衰える、寂れる、朽ち果てる、腐る、果てる、終わることに対し、ある種の特別な感情を抱くのはなぜか。この次は、「滅びの美学」という観点から、今度は土門拳の作品について記します。次の投稿へ続く!!
筆者が運営しているWEBギャラリーです。
「アートをもっと、そばに」がコンセプト。
よければ遊びに来てください。
gallery hyphen
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
