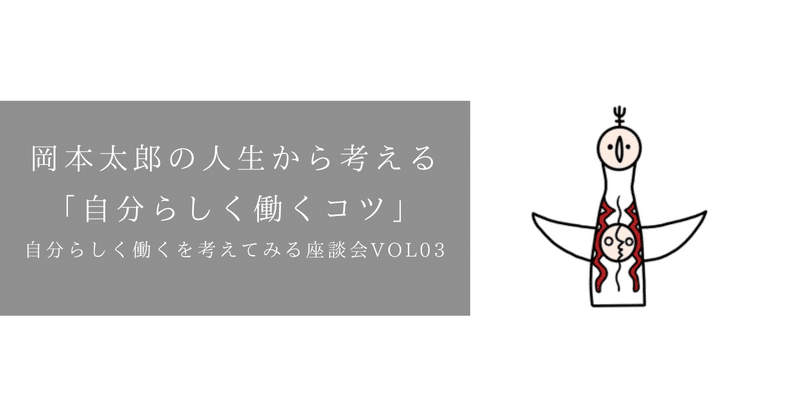
岡本太郎の人生から考える「自分らしく働くコツ」
「人の熱量を形にする」事業コンサルタントの中川です。
毎週月曜日のお昼30分を使ってTwitterのスペースで発信している
自分らしく働くを考えてみる座談会Vol03
今回の題材は、中川が好きで堪らない人である「岡本太郎さんの人生」を題材にして「自分らしく働く」とはなにか?を考えながら、ゆるく話をしてみました。
この記事は「こんな方の手助けになりたい」
・これからフリーランスを考えている方
・独立した後お金の問題と直面している方
・独立したけどモチベーションが上がらない苦しい状態なと感じる方
「自分らしく働く」を考えてみる座談会とは?
自分らしく働くって素晴らしい。
毎日楽しいと言いながら働く人が増えるといいな
という妄想により、どんな働き方・考え方が
世の中にはあるのか?考えてみる音声配信です!
ゆるっと座談会
— kazuaki hishiya 🌳WAKASHIBITO (@kazu895111) September 26, 2022
といいつつ、毎回結構学びがある面白さ
リスナーできてくれた方もありがとうございました😊
https://t.co/w5l06ic1Sx
こちらで音声は聞けるので、ただ内容をトレースする記事というよりは、中身の補填になる思ったことをこの記事では共有させてください!
今回のテーマはこの方
岡本太郎(おかもとたろう)
芸術家。1911年生まれ。29年に渡仏し、30年代のパリで抽象芸術やシュルレアリスム運動に参加。
パリ大学でマルセル・モースに民族学を学び、ジョルジュ・バタイユらと活動をともにした。
40年帰国。戦後日本で前衛芸術運動を展開し、問題作を次々と社会に送り出す。
51年に縄文土器と遭遇し、翌年「縄文土器論」を発表。
70年大阪万博で太陽の塔を制作し、国民的存在になる。
96年没。いまも若い世代に大きな影響を与え続けている。
自分の中に毒を持ては太郎さんが書いた本で一番有名なものだと思うのでぜひ手に取ってもらえたら嬉しいなと思います。
ちなみに私が好きな本は迷宮の人生という本です。
太郎さんの芸術観も書かれている内容で、どういう考えで作品と向き合っていたのかも分かる内容です。
座談会で話した内容について
①太郎さんってどんな人だった?
②太郎さんって自分らしく働いていたのだろうか?
③自分らしく働ける人って「人に依存」も出来る
④人の目や意見も気にせずに続けられる根底に「思想」があった。
太郎さんってどんな人だった?

大学生の時に読んだ読了メモがありました。
安全な道を歩く人生は、虚しい。
積み重ねてきた経験もキャリアも、自分の本音、生きる意義に値する価値を創造しているのだろうか。 自問するのは若い時だけじゃない。
いくつになっても自分自身を冷めた目で見つめながら、本質で生きれる人でありたい。
終わればいいとかそういう時間の過ごし方は勿体無いのだと思う。 太郎さんのようにならなくてもいい。ただ、人生、その瞬間•一瞬にも命を燃やし尽くしていきたい。 未来がどうなるのかなんて100%分からないんだから、 今を真剣に生きなければ。

太郎さんが「きっと自分らしく人生」を生きた人です。
それは「楽しい・心地よい」という感覚ではなく、「歯を食いしばる」ような日々を過ごしても、自分の本質に向き合った人でした。
太郎さんって自分らしく働いていたのだろうか?
自分らしく働くを考える時、「心地よい・楽」とかいう状態もイメージしてしまうかもしれない。ただそれだけが答えではないということも分かります。
自分の本質に向き合い続けるというのは、産みの苦しみも味わいながら過ごす時間でもあります。
太郎さんは「産み出す」という観点で、自分の生き甲斐・働きがいを感じて日々を過ごしていたのではないでしょうか?
どんな価値を感じて喜びを感じていたか?
太郎さんの生前のエピソードの中に、女性の話が出てきます。
内容は展示会で太郎さんの絵をマジマジと見ていた女性が、最後に「なにこの気持ち悪い絵」と言ってその場を立ち去ったという内容がある。
その時、太郎さんは「嬉しかった」と答えています。
命を表現している作品だからこそ、いいなと感じるだけではなく、苦しいと思う人もいるだろう。響くものがあったという人がいることに意義を感じて作品を制作していたのではないだろうか?
自分らしく在る「頼れる存在がいる」
太郎さんには、人生を共に歩んでくれたパートナーがいます。
岡本敏子さんです。
秘書であり、「養子」となっているものの実質的な「奥さん」だった敏子さんが、太郎さんの通訳者として社会と調整してくれたり、太郎さんの価値を届けようとしてくれていたという事実がある。
受け取る価値ではなく、表現する価値に重きを置いた太郎さんが自分らしく輝けていたのは敏子さんがいたからだと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
