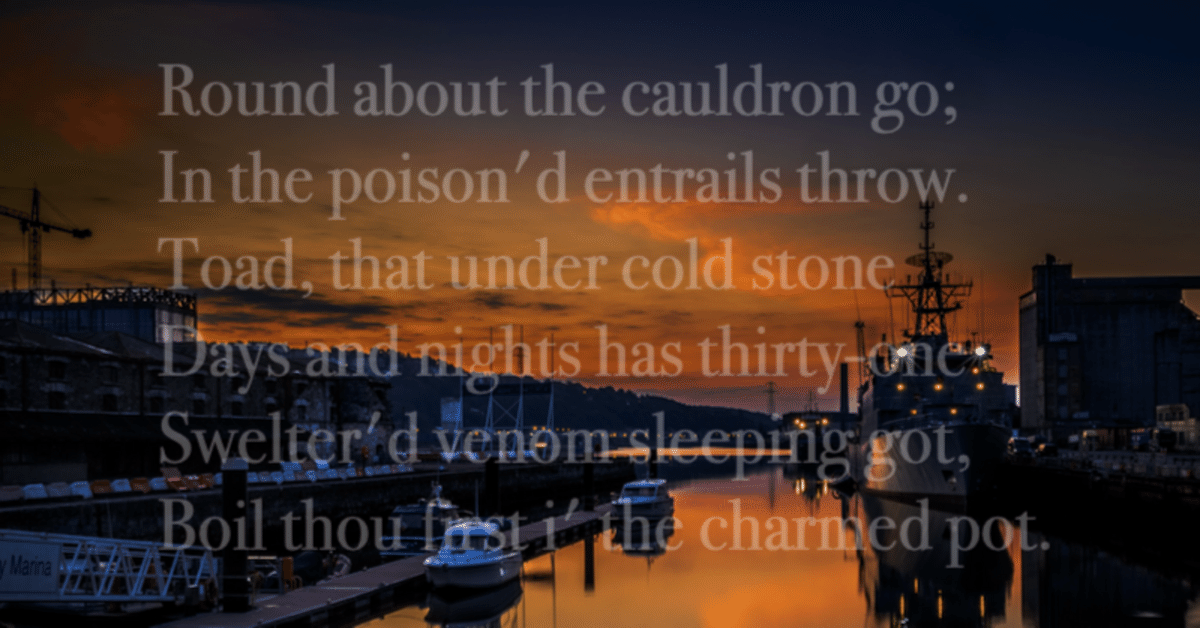
ショートショート 『セイレーンの泣く街』
古びたシビックのイグニッションをまわすと、エンジンは老人めいた音で咳き込み、すぐに停まった。
エミリー・ハーパーは小さく舌打ちをして、もう一度キーをひねった。
いかにも気が乗らないといった音を五回させた後、シビックはようやく震動しはじめた。
「頑張って、その調子よ」
エミリーは言い、車のエンジンが安定するのを待ちながら外を見た。
フロントグラスの向こうは、この季節特有の霧の朝だ。
モリーンズビーチの湾から立ち昇った霧が丘の斜面を伝い、高台に建つエミリーの家まで呑み込んでいる。小さな庭を囲む生け垣は濡れ、葉先から水滴を落としている。さほど離れていない隣家の灯りさえぼんやりと滲んでいる。
「………」
予感に、エミリーはハンドルをきつく握った。自分の腕の鳥肌を見る。
それはシビックの右側から入ってきた。
カチャカチャと皿が鳴る。話し声、女が笑う、子供がねだる。それらの音は狭い車の中に侵入し、ひとしきりさんざめいた後、向こう側から出ていった。時間にして一分弱だろうか? それでもエミリーには永遠に感じられた。
エミリーはワイパーを動かし、雨滴を弾き飛ばした。
やはり突き止めなくては。この音の正体を。
モリーンズビーチの地方史研究家、ウォルター・ジェンキンスを探すのなら、市の図書館か港近くのダイナーだった。
勘が当たって、ダイナーの奥まった席にウォルターを見つけることができた。
「やあ、先生」
少しべとつくテーブルに分厚い本を広げていたウォルターは、老眼鏡ごしにエミリーを見あげた。
「構いません?」
「………ああ、構わんよ。どうぞ」
ウォルターはメモを挟んだまま本を閉じた。古い本だ。タイトルには『島嶼地域の自然誌』とある。
「おはようございます、先生」
近づいてきたウェイトレスにコーヒーを注文すると、エミリーはため息をついた。
「どこに行っても先生、先生なのね」
「狭い街だからな」
ウォルターは言った。「若い女性の先生は注目されるもんだ」
「もう若くはないわ。まるで監視されているみたい」
休日の朝で人々の出足は遅い。他の客はスツールに座ったトラック運転手だけだ。背をかがめベーコンをつついている。
「ゴシップには気をつけることだ。こんな爺さんと昔話をしているだけなら、おかしな噂も立たないだろうが………」
ウェイトレスが湯気の立つコーヒーを置いていくのを待ち、
「幽霊話でも構いませんか?」
とエミリーは言った。
ウォルターは聞こえなかった顔でコーヒーを飲んだ。脇に寄せた皿には、トーストの屑とケチャップが残っている。
「今朝ここに来る前に、また聞きました」
「気にせんことだ。何か悪さをするわけでもあるまい」
「悪さをしない? 私の生徒のヘレンは、お母さんが自殺しました」
モリーンズビーチ特有の、海霧の頃の憂鬱に音の幽霊が関係しているのではないかと言ったのは、ウォルター自身だった。
地方史研究家たちの会合の後、安くワインが飲めるレストランに皆で繰り出した夜だ。エミリーとウォルターは偶然隣り合って座っていた。最近、おかしな音を聞くというエミリーの話に、ウォルターは冗談交じりの推理を披露してみせた。
「酔っ払いの戯言に過ぎんよ。何の根拠もない」
「この街には音の幽霊話が昔からあって、聞く力がある者を怯えさせる。ほら」
エミリーはウォルターの口調を真似、人差し指を立てた。「人を死にいざなうセイレーンのように」
「馬鹿な年寄りもいたもんだ」
「ヘレンはお祖母さんの家に引き取られていきました。とても遠い街の。彼女、行きたくないって、ひどく泣いていました」
「しかし………」
ウォルターは弱々しく反論した。「理由が分かったからと言って、あれが消えるという確証はない」
「分からないものに出くわしたなら、まずはつついてみろ。逃げ出すのはその後で良い」
エミリーは言った。
「誰の言葉かね?」
「大学院時代の恩師です」
「変人だな。………仕方あるまい」
ウォルターはため息をついた。
エミリーとウォルターは二手に分かれて調査をはじめた。
ウォルターは音の幽霊の噂をしていた年寄りたちに、その詳細を聞く。エミリーは図書館の資料や過去の新聞記事に、音の幽霊に関する情報がないかを探る。
「小学校の先生が幽霊話を聞いてまわるのは、何かと問題だろう?」
ウォルターは言った。「オカルト趣味の先生に子供を預けたいという親はそういまい」
確かにその通りだった。そしてウォルターは昔気質の研究者らしく、インターネットなど触れたこともなかった。
年金生活者であるウォルターは、ほぼフルタイムで、エミリーは定時後や休日を費やし、音の幽霊の研究を進めた。離婚をして母の遺した家があるモリーンズビーチに戻ってきて以来、仕事時間以外はすべて自分の自由に使える。あの時流産していなければ、子供のために使われたであろう時間だ。
「共通していることがある」
二回目の打ち合わせの時、ウォルターは言った。「聞いたことがある者たちの、その内容だ」
場所はいつものダイナーだった。
「何かの施設の中で、大勢の人間が集まっている。めいめいに話をしているが、内容ははっきりしない」
「大きくて立派な食堂のような感じがしました。私が聞いた時は」
エミリーは言った。「なぜそんな場所が幽霊になって動いているのか分からないけれど」
「それでも、幻聴などではないようだな」
ウォルターはうなずいた。「共通する部分が多い」
「合理性が必要ですか? 幽霊に」
ウォルターは、片方の眉をあげた。
「長年の研究家として学んだことがことがひとつある」
「教えてください」
「何かが現象として成立しているからには、始まりがあるということだ」
ウォルターは、コーヒーに砂糖を三杯入れた。
「入れすぎじゃないですか?」
ウォルターは白髪の頭を指してみせた。
「こいつを動かすには、糖分というガソリンが必要だ。さて先生、原始時代に食堂はあるかな?」
「ありません」
「と言うことは、幽霊の紳士淑女が集っている食堂を探すのなら、せいぜい百五十年前くらいからということにならないかな?」
「おっしゃる通りですね。そこは多分、このモリーンズビーチに関係がある」
その日から、エミリーは地元にあったレストランやホテルの歴史を調べはじめた。
しかし小さな街だった。歴史のあるレストランやホテルは数えるほどしかなく、その情報も表面的なものでしかなかった。
初夏の夜気は湿っていた。
インターネットで地元の図書検索サービスを使っていたエミリーは眼鏡を外し、ディスプレイの見続けで疲れた目を掌で温めた。
「………何もない」
この街にも老舗と言われたレストランやホテルはあった。今も営業している店は三軒。生前の母と行ったことのある店もあった。
………でも、引っかかるものがない。
音の幽霊として、その空間が彷徨い続けなければならないような事件めいた歴史を持つ店はなかった。
自信がなくなる。
こんなことをしていて、本当に幽霊の正体にたどり着けるんだろうか? 第一、あの朝以来、音の幽霊を聞いていない。ウォーターが口にしたように、あれは幻聴だったのではないか? 気象条件や気圧の変化が引き起こす精神の不安定ではないんだろうか。私だって、流産と離婚というふたつの出来事から立ち直っているとは言えない。不安定なのだ。
窓からの風を頬に感じる。
「帰りたい」
エミリーは椅子から立ちあがった。
声は、パーソナルコンピュータを置いた机の、すぐ横から聞こえた。息がかかるほど近くから。
「誰、何?」
エミリーはデスクライトが照らす薄暗い部屋に向かって聞いた。「あなた、誰?」
「帰りたい」
女の声だった。若い、まだ少女のような。
そして怒号が来た。
男や女が叫ぶ、何かが倒れる、皿やグラスが床に落ち、割れる。子供の金切り声、嗚咽、喚く、まるで獣のように人々が吠える………。
「やめて!」
エミリーは床に膝をつき耳をふさいだ。
これだったのだ。ヘレンのお母さんが襲われた音は。この街の、季節の病を引き起こしてきた音は。生きて正気を保っている者たちは、ここまでは聞いていないのだ。
「帰りたいの」
耳のすぐ横で、少女が囁いた。
「わたし、帰りたいのよ」
「どこによ!」
不意に、気配が消えた。少女の背後で叫んでいた声たちも。
エミリーは耳から手を離し、部屋の中を見渡した。誰もいない、もちろん。レースのカーテンが霧を含んだ夜風に揺れている。庭で虫が鳴いている。
「探すモノを間違っていた」
エミリーはつぶやいた。
「動いている」
そしてここは港の街だった。
「そういうことか」
ウォルターは言った。
場所はウォルターのアパートだった。大きな海域図やプリントアウトした新聞記事などをダイナーのテーブルに広げ人目を引くわけにもいかなかった。
驚いたことに、ウォルターの部屋には、彼と同年代くらいの女性がいた。
「先生からの連絡で、急遽、今晩のデートを中止したものでね」
ウォルターは照れたような顔で、アンナという老女を紹介した。白髪の美しい、上品な感じの女性だった。
「今回の調査で再会した、小学校のクラスメイトだ。幸か不幸か、例の音は聞いていないがね」
「小学校?」
「私にも若い頃はあった。先生同様に」
「忘れてしまいました、そんな時代」
エミリーは言った。アンナは微笑みながら歴史探偵たちの会話を聞いていた。
「歳を取れば分かる。昔のほうがリアルに感じられることもあるのがな。さて………」
ウォルターはエミリーがテーブルに積み上げた新聞記事のコピーを手に取った。「確かに、この沈没事故は聞いたことがある。私が生まれる少し前の事故だな」
古い書体で印刷された全国紙の記事は、『波の詩号、沈没』と題されていた。
「昔のことで、結局、原因は分からなかったようです」
エミリーは言った。「何かの理由で船底が大きく破損し、そこから大量の海水が入り込み、短い時間で沈んだと書いてあります。朝食の時間帯で、ほとんどの客が食堂の階にいて、逃げ遅れたと」
「助かったのは船員の数名、か」
「今から七十五年前の事故です。この地方の文芸誌に、初めて音の幽霊に関する幻想味たっぷりのポエムが載ったのが一年後ですから」
「時期は合うな。合理的だ。だが………」
ウォルターはエミリーを見た。
「『波の詩号』が沈んだのは、モリーンズビーチではない。別の海域だ。先生が声を聞いたという少女は、なぜここに帰ってきたがる?」
エミリーはうなずき、一枚のコピーを示した。
「事故の二日後の新聞です。彼女だと思います」
ここの地方紙だった。『波の詩号』の沈没事故に、モリーンズビーチの少女が巻き込まれていたのが判ったと書かれていた。モリーンズビーチは『波の詩号』の寄港地のひとつで、少女はふたつ先の港で叔母と落ち合う予定になっていた。
少女にとっては子供時代のちょっとした冒険になるはずだった。翌朝、船が沈まなければ。
「そういうことか」
「ローズ・ハミルトンよ」
それまで黙って二人のやり取りを聞いていたアンナが言った。
「知っているのか?」
ウォルターが聞いた。
「あなたもご存知でしょう? 港で倉庫業を営んでいたハミルトン家。あそこのひとり娘だったのよ。私のいちばん上の姉がクラスメイトだった。とても綺麗な娘だったのに、って聞かされたことがある。そう………」
アンナはうなずいた。「彼女は帰りたがっているのね、ここに」
「今の時期は、海流がこちらに向かう頃だ。それがモリーンズビーチの湾で渦を巻き、霧を作る」
ウォルターは言った。「元々、何か特別な力を持っていた娘なのかもしれんな。彼女は音の幽霊として、事故の時間を閉じ込めた。それが海流に乗ってモリーンズビーチに戻り、霧となる」
「ローズの悲しみを湛えた霧ね」
「君は詩人だな」
アンナは微笑んだ。
エミリーは老いた恋人たちに咳払いをした。ふたりがこちらを見る。
「何が起きているのかは分かりました。では、どうすれば音の幽霊を鎮めることができるんでしょう?」
ウォルターは頭を振った。
「残念ながら私にもアンナにも、音の幽霊を聞く能力はない。その能力があり、最も核心に近づいているのは先生、あなただ」
「心を落ち着けて会話し、言い聞かせるべきじゃないかしら?」
アンナは言った。「これ以上、巻き込まれる人を増やさないためにも」
「でも………」
エミリーは唇を噛んだ。「私、本当は苦手なんです、子供の相手って」
「頑張ることだ、先生」
ウォルターは言った。
何も準備をすることはできなかった。
七十五年前に亡くなったローズ・ハミルトンは、家族の待つこの街に帰りたいという思いの塊になっている。当時、ハミルトン家の行ったであろう葬儀も、墓も、祈りも、瞬間に凍結された時間には届いていない。
それなのに、今、自分がローズに言い聞かせ、そんなものがあるとしてだが、天国かそれ以外のどこかに向かわせることができるとも思えなかった。
それでも霧の朝を待ちエミリーが家を出たのは、これ以上、音の幽霊で苦しむ人を増やしたくないという気持ちからだった。子供は苦手だが、ヘレンのように母親を失う子供を見ることにも耐えられない。
ハミルトン家の墓がある墓地は確認していた。湾の北側、背後に森林地帯が広がる一角だ。
シビックのフォグランプに細かな霧の粒子が踊っていた。
「ちょうど良いかもしれない」
エミリーはつぶやき、エンジンを切った。車を降り、墓地を貫く歩道を歩く。霧が髪にまとわりついた。
森のほうで鳥が鳴いていた。最後を引き延ばすような声で。
「帰りたいの」
声に、エミリーは立ち止まった。それでも唇を噛み、恐怖を押し返す。
「ここはモリーンズビーチよ。あなたはもう帰ってきているの。ローズ」
「知っているの? わたしを」
ローズは戸惑ったように言った。
「知っている。これからあなたに何が起きるかも」
エミリーは言った。ローズの背後で、男が声をあげるのが聞こえる。パニック寸前といった感じで。目の前に繰り広げられる劇のようだ。
「その船は沈む。悲しいことだけれど、ほとんど人は助からない。あなたも」
「嘘よ!」
ローズが叫んだ。「こんな大きな船が沈むわけない。絶対安全だってお母さんは言っていた」
耳の奥、いやもっと深い所に少女の怒りが届き、エミリーを貫いた。よろめきそうになるのを堪え、エミリーは歩いた。
「受け容れるしかないのよ、ローズ。あなたが作った牢獄を解いて、皆を自由にしてあげなさい」
「いやよ、嘘つき女!」
霧が流れ、目に飛び込んできたのは、小さな墓だった。ローズ・ハミルトンの文字が刻まれている。
「今、ここにあなたの墓がある」
大人たちの怒号が聞こえた。落ちた皿が割れる。沈没の苦しみを七十五年再現しているのだ。彼らも犠牲者だった。
「誰か助けて! 帰りたい!」
ローズが叫ぶ。
「来なさい。こちらに」
エミリーは墓の前にひざまずいた。「私が受け止めてあげる」
なぜか涙がこぼれた。抱くことのできなかった自分の子供、名前を決め、ベッドメリーまで買っていた。布製の、ピンクの象や水色のカモメが踊る………。
「帰るの!」
パチン、と何かが割れた感覚があった。音の塊のようなものが胸に飛び込んできて、エミリーは湿った芝生に尻餅をついた。
鳥の声が聞こえた。
音は去っていた。
風向きが変わったのか、見る間に霧が晴れていく。その向こうに、たっぷりとした光を湛えた初夏の青空が見えた。
「………帰ったのね」
エミリーはつぶやいた。
胸の奥に入ってきた温かなものが薄れ、小さくなり、やがて消えていく。残念なことのようにも感じる。でもそれで良いのだ。私も私の日々を始めなくてはならないのだから。
エミリーは立ち上がり、ローズの墓に小さく手を振った。ゆっくりと墓地を去っていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
