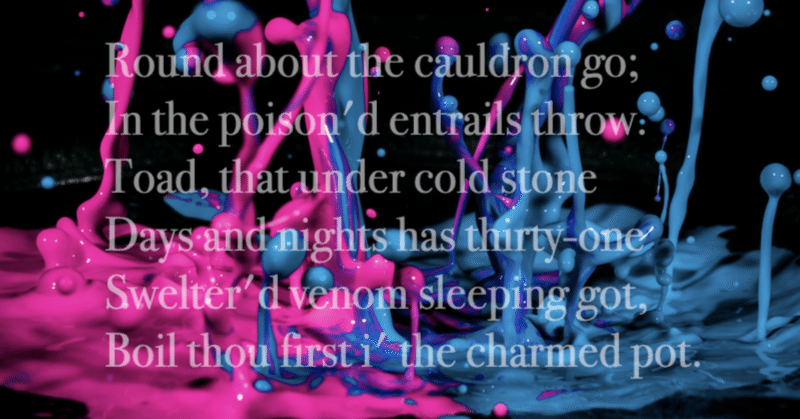
ショートショート 『さらば、肉の日々』
代替肉の臭いに、隆史は大きく開いた口を閉じた。
手の中のハンバーガーを見下ろす。ファストフードのバーガー袋が高架を吹き抜ける夜風を受け、カサカサと鳴る。
………ふざけるな。
隆史はハンバーガーを握りつぶした。
作り物めいたバンズの間で、わずかばかりのレタスとトマト、ピクルス、そして大豆製のパテが潰れ、歪んで落ちた。
こぼれたソースで両手がベトつく。ハンカチもティッシュもない。ヤケ気味に作業着のズボンにこすりつけ、それでも残ったベトつきを舌で舐めた。
ソースだけは本格的な味がした。
「やってくれたな」
隆史は自分に言った。
これで今日の晩飯は終わりだ。自室の台所にある賞味期限切れの食パンは、明日の朝に取っておかなくては、腹が空きすぎて力仕事にならない。
隆史はあてもなく周囲を見まわした。
この時刻になると、駅に直通の回廊を歩く人は少ない。下の道で酔ったサラリーマンたちが群れ騒いでいる。足元の暗がりには、ハンバーガーの残骸だけだ。
一瞬、拾えばまだ食える、と思った自分を罵り、隆史はハンバーガーを踏み潰した。二度、三度と踏んでいるうちに、それは酔っ払いがもどした反吐に似たものに変わった。
40分歩いてアパートに帰り着くと、明かりもつけずに万年床にもぐり込んだ。中学生のようなふて寝だ。
振動音。
隆史は薄闇の中で畳に放り投げていたスマートフォンをたぐり寄せた。非通知の相手だった。
「夜分すみません。………CEOですよね?」
男が言った。
「誰かな?」
懐かしすぎる呼び名に、応えに戸惑った。
「沢田です。お久しぶりです。って、もう忘れられちゃったかな?」
「いや、………覚えているが」
隆史は布団の中でうつ伏せになった。
会社が傾く前に、とっとと辞めていった若者だ。自分の成果を言い立て、結構な退職金をかっ攫っていった。それで記憶している。
「何か、用でも?」
隆史は聞いた。
もしも再雇用を求めてきたのなら、お笑い草だ。会社は社長兼CEOだった俺が潰してしまった。そう言ってやろう。いや、頭の切れる沢田が、その程度の情報を押さえていないはずはないか………。
「いえ、特に用ってことはなく、懐かしいな、なんて思ってですね。皆さんバラバラで、もう連絡もつかなくて」
「ああ、そうだな」
やはり会社が潰れたことは知っていた。しかし、その社員の「皆さん」が、仕事はできるがとことん小狡く身勝手な沢田を嫌っていたことは気づいていないようだ。灯台下暗し、って奴だ。
「連絡先に残っていたのが、CEOでして」
「もうCEOでも社長でもないが」
「そうみたいですね。でも僕にとってはCEOだな。………で、どうです?どこかで飲みませんか?昔話とか近況とか話したいな。軽く」
「………」
「もちろん、散々お世話になった僕にご馳走させてください。すみません、失礼なこと言ってますかね?」
………タダ酒か。
隆史は湿っぽい枕に顎を乗せた。
「どこで?」
「そうですね、たまには肉なんかどうです?パーッと」
隆史の迷いは消えた。
最低ラインでも混合肉だと思っていた隆史の予想は、意外な方に外れた。
肉から溶け出た脂が焼かれ、ねばついた煙となって立ち昇る店内は、白く煙っていた。懐かしい香りだ。
JR蒲田西口から出て飲み屋の連なる細い通りを斜めに入った場所にある店だった。
「しかし、大丈夫なのか?」
隆史はロースターを挟んで、ピンクのおしぼりで顔を拭いている沢田に聞いた。
品川で待ち合わせ、普通に高いだけの店なんか面白くないですよ、と沢田に連れられた店だ。奥深い構造で、間口は狭い。昔は透明だっただろうガラス戸は、ヤニで褐色に曇っている。店の看板も見当たらないが、十二畳ほどの客席は癖の強そうな客たちで、ほぼ満席状態だった。
「何がです?」
メニューを持ってきた老婆に、生と、1番から5番までを二人分ずつと雑な注文をすると、沢田は隆史を見た。
「ここはその、………闇肉屋だろう?」
「怖いですか?CEO」
沢田は聞いた。
「そのCEOはやめてくれ。嫌味を言われている気分になる」
「嫌味のつもりはありませんでしたが、………じゃあ中尾さん、で良いですか?」
「ああ、そう呼んでくれ」
「中尾さん、常識ですよ闇肉なんて。ヤミでもなければ、僕たちはこの先、死ぬまで肉なんか食えないかもしれない。敗戦後のヤミ屋やヤミ市と同じで、無能な政府がいくら駄目だって言っても、庶民はヤミに頼って生きる。そうするしかないからですよ」
「そりゃあそうだが………」
「まさか、純粋肉とか培養肉とかを食べる気でいらっしゃいました?」
大学生にしか見えない沢田に半笑いで聞かれ、さすがに隆史はムッとした。タダ酒、タダ飯だとノコノコやってきた自分の浅ましさを嘲笑われているようだ。
食肉に環境負荷税がかけられたのは四年前だ。
世界的な動きだった。
日本では、牛、豚、鶏、羊など、食用畜産の生産者はすべての個体のDNAを農林水産省畜産管理局に登録し、流通プロセスを追跡できるようにした上で、売上に対する環境負荷税を払うことになった。
それは当たり前のように消費者に転嫁された。
税率がいちばん高い牛肉は、課税以前の十倍ほどの価格となった。
代替としての豚肉や鶏肉などもあおりを受け、同程度の倍率で値上がりした。
同じ頃に、培養肉の生産技術が安定した。
培養肉には環境負荷税はかけられないが、そもそも生産コスト自体が大きいため、純粋肉と呼ばれる普通の肉よりも心もち抑えられた価格にとどまっている。世界的な培養肉生産企業がロビー活動で、環境負荷税の導入を決めさせたという噂もある。
今、肉の市場価格は、純粋肉がいちばん高価で、培養肉、穀物由来の代替肉の順となっている。培養肉と代替肉をミックスした混合肉は、素材の比率によって価格が決まる。
こうした動きの中で、必然的に成立したのが闇肉市場だった。
隆史は詳細を知らないが、畜産業者が密かに育てた牛や豚、鶏、羊、狩猟によるイノシシやシカ、その他のワニやダチョウ、鳩などがヤミで流れていると聞く。
もちろん畜産管理局も都度、監査の強化や管理対象の見直しを行い、抜け穴を塞ぐことに腐心している。官と民のいたちごっことも言えた。
「まあ、手入れがあっても、捕まるのは店側ですよ。僕らは、普通の肉が安く食べられる店だと思って来てた、って言えば良いんです」
沢田は言った。「だから、ここのメニューには、番号しか書いてないんです。ひとつ注意しておきますが、これ何の肉?って聞くのはルール違反ですから」
最後の念押しは真顔だった。
隆史はうなずいた。
分厚い肉が、網の上でチリチリと踊っていた。
それからの記憶は、穴抜け状態だ。
久々の肉とビール、焼酎、マッコリに隆史の頭は吹っ飛んだ。肉を食うことで発生するという至福ホルモンにやられたのかもしれない。
切れ切れの記憶にある会話は、バラバラになった社員たちの噂、出ていった女房と娘への恨み、この年齢では難しい就職の愚痴などだ。
気がつくと、隆史はアパートの万年床の中にいた。
開け放したままのカーテンの向こうは明るくなっていた。バイトに遅れるのは確実だ。
………あんなクソ仕事、たまには良いじゃないか。
隆史は四つん這いで壁際のテーブルにたどりつき、昨夜、どこかの自販機で買った発泡酒の缶を持ち上げた。幸運なことに半分弱は残っている。
あぐらをかき、気の抜けた酒を流し込んだ。
髪と言わず、身体中に肉の匂いがへばりついている。久々だ、悪くない。
「案外、良い奴だったな」
沢田のことだ。
散々肉を食わせ、酒を飲ませてくれた挙げ句、タクシー券まで寄越した。俺は沢田を誤解していたのかもしれない。それに最近起業した沢田は、これからも時々会って会社の運営を相談させてくれ、と頭を下げた。
隆史はだらしなく笑った。
相談ってことは、奢りってことだ。いや、的確な助言をしてやっていれば、いずれ正式な相談役として来てくれ、なんて言い出すかもしれない。そうなれば………。
幸福な夢の続きを見るため、隆史は布団に転がった。
「たまには、割り勘ってことで」
沢田が言った。
イスから腰を浮かせた格好で、隆史は動きをとめた。
「アラフィフの中尾さんに、いつも奢りますじゃあ失礼ですよね」
心なしか沢田の唇が笑っているように見えた。店の老婆から渡されたレシートを、脂でべとついたテーブルに置いた。
ちらと見て、隆史はイスに尻を戻した。
代金は、12万と読めた。
「ヤミでも、肉は肉。軽くこのくらいはするんですよねえ」
沢田は言った。「今日で五回目ですかね、ご一緒させていただくのは。割り勘、たまには良いんじゃないですか?」
「………いや、しかし」
隆史は口ごもった。「今日は、あいにく手持ちが」
「大丈夫ですよ」
沢田はレシートを隆史のほうに押しやった。「明日にでも振り込んでいただければ。ああ、LINEやってます?LINE割り勘が早いな。使い方が分からないなら、今、僕が操作してあげますよ。ここに出して」
トントン、とテーブルをつついた。
「LINEはやってない。女房が出ていったときにアカウントは消したんだ」
隆史は言った。嘘だ。バイトの連絡はLINEで来る。
「ふーん………」
沢田は隆史を見下ろした。さっきまでの軽薄な感じが失せている。「あるんですよね?」
「何が?」
「カネに決まってるでしょ。割り勘の6万円」
「………」
隆史は顔を伏せ、テーブルを見た。
同じことをした記憶がある。会社がもう駄目だと分かったときだ。債権者たちや社員、女房やその両親に向かって。
網の上に残された玉ねぎが、黒く炭化している。老婆が無愛想にジョッキや皿を片付けていく。
沢田が舌打ちをした。
「ないんですね」
「………かき集めても、2万が良いところだ」
「ダセえ」
沢田が向かいのイスに座る気配があった。「ねえ、CEO」
隆史は顔をあげた。
「良いバイトがあるんですが、やりませんか?」
「バイトなら、もうやっている」
「今やってるクソみたいな仕事じゃない」
沢田は長い脚を組んだ。「中尾さんが持っているものを売って欲しいんですよ。何度か病院に来てもらえばそれで済む」
「俺の臓器を売れとか、そんな話か?」
臓器売買の話は聞いたことがある。
「中尾さんのくたびれた腸とかに興味はないですね」
沢田は笑った。「13番の肉、うまかったですか?」
「ああ、そりゃあうまかった。あれは………」
聞きかけてやめた。ここでは、肉の種類を聞くのはタブーだ。
「ここだけの話ですけどね」
沢田がテーブルに肘を滑らせ、隆史に顔を寄せた。小声で言う。「ヒトですよ」
「何が?」
「13番の肉は、ヒトって言ってるんですよ」
隆史は沢田の顔を見た。薄い唇は笑っているが、眼が笑っていない。
「馬鹿な………」
「小役人のチェックが厳しくて、うちの業界も肉のバラエティが追いつかなくてですね。ちょっと実験的に、ヒトの培養肉ってのを試しているんですよ。………吐くなら、トイレでお願いしますよ」
隆史はテーブルの端をつかんだ。
「何も生きた人間をバラしているわけじゃない。研究所で衛生的に製造してるんですけどね。ちょっと困ったことが起きまして」
沢田は老婆を呼び、灰皿を持ってこさせた。「ちなみに、ここは僕がやってる店でしてね。良い店でしょ?」
「………そういうことか」
沢田はマイルドセブンに火をつけた。薄い煙を吐く。
「君の商売は分かった。それで、俺に何を売れと?」
「プリオン病って、知ってますか?」
話の飛び方に、隆史は戸惑った。
「詳しくは知らない。………確か、狂牛病とかに関係があったか?」
「そうですね。簡単に言えば、共食いやその他で、異常プリオンってタンパク質が、食った奴の神経系に溜まって障害が発生し、最終的に死ぬって病気です。どういうワケか、うちの培養肉で、それが頻発している」
立ち上がろうとした隆史の手を、沢田が押さえた。
「落ち着いてください。中尾さんには発生してない」
「なぜ?」
「異常プリオンに耐性のある人間、まあ遺伝情報の読み取り関係なんでしょうが、いるってことでしてね。この辺、うちの研究者の受け売りですがね。で、困りまくっている時に、ある製薬会社から共同開発のオファーがあった。もちろん超極秘にですが」
「何のために?」
「マインドがビジネス向けじゃないですね」
沢田は笑って、指で宙に絵を描いてみせた。「うちは培養肉でがっぽり儲ける。ヒトを食ってみたいって金持ち、結構いるんですよ。ゲテモノ食いのつもりかもしれませんが、下品な馬鹿です。奴らは一定の割合でプリオン病になる。その遺伝治療を開発しておけば、これまたセットで儲けることができる」
隆史は口を閉じた。奈落の底に堕ちていく感覚がある。酒のせいではない。
「だから、中尾さんの身体は大切なんですよ」
「それが理由か?」
「何のです?」
「俺を飲みに誘った理由だ」
「まあ、そうかなあ。うちのチーム全員で、異常プリオンに耐性がある人間を探しまくってたってわけです。もちろん、お話しは懐かしかったですよ。ああ、来た来た」
くもったガラス戸越しに、店の前、グレイのハイエースが停まるのが見えた。
「さあ行きましょう、CEO。悪いバイトじゃないですよ」
沢田が立ちあがり、隆史を促した。「肉だってたっぷり食える」
………俺はベジタリアンになる。
沢田の後を歩きながら、隆史は入り口のテーブルに並べられた菜箸を取った。長い、金属製の。
今どきの刑務所なら、肉など出ても大豆で作った代替肉に違いない。
沢田の、清潔で柔らかそうな襟首が、目の前にあった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
