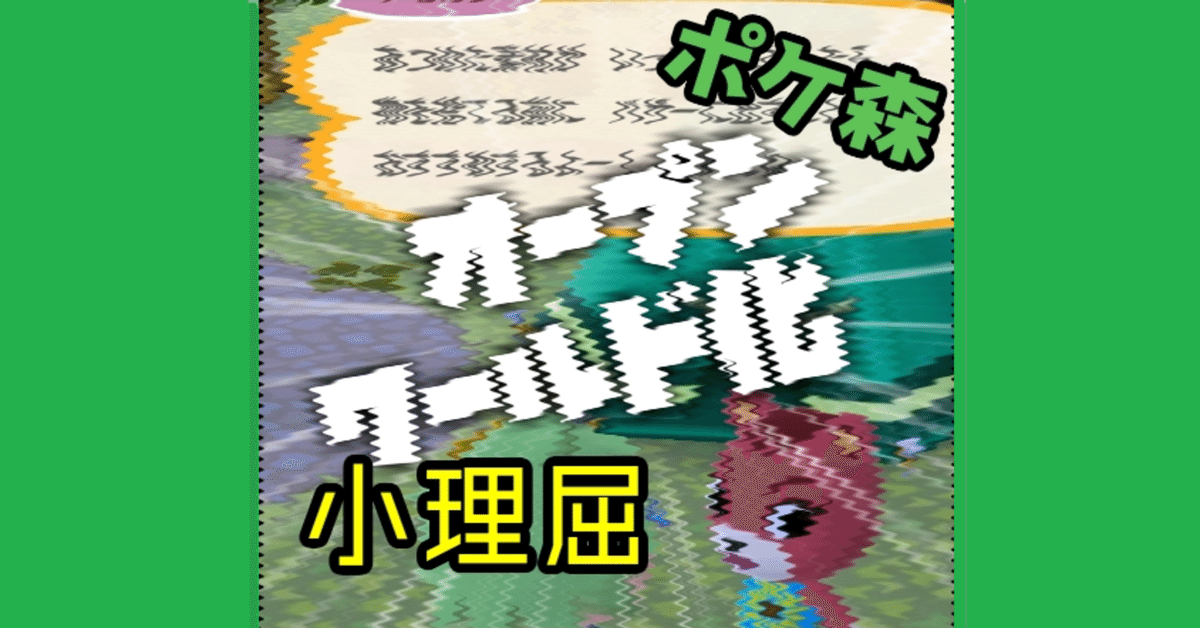
ポケ森日記3 ポケ森のelona性について(2)箱庭ゲーム・オープンワールド話
こんにちは。現在曇り空の真っ昼間です。こういう、人間として生きるには些か身動きが取りづらい日にもポケ森みたいな疑似箱庭ゲームは相性がいいと思っています。
前回は
ポケ森の、ゲームとしての「なんでもできる性」=elona性 について述べました。
elonaはなんでもできるゲームな反面、ぼくには「なんでもできるがゆえに、あるいはゲームに慣れるにつれてもっとこういうことができる/すべきという点が見えすぎてしまうがゆえに、どこかで断念してしまう」という背景がじわじわと形成され、いずれどこかで断念してしまいがちになるというケースがありました。
自由度が高すぎないこともゲームを続けるための動機たりえるのではないのだろうか、的なことも考えたりしていました。
箱庭ゲームってなんだろう
冒頭でも箱庭ゲームみたいな概念について触れましたが、ゲーム内機能として自分の手や足、果てには指先の役割すら担ってくれるシステムがあればあるほど自由度は高くなるように思います。
目や耳はゲーム画面、BGM・SEとして主人公やPC(Playing Character)と共有しているため、何らかのゲームを始めた時点ですでに五感のうち2感は没入が保証されているといえそうです。
箱庭ゲームの概念について調べてくださっている方がいらしたので引用します。
『オープンワールド』舞台となる広大な世界を自由に動き回って探索・攻略できるようなゲーム。【例】ゼルダの伝説、アサシンクリードなど
①リアルタイム進行のゲームで、プレイヤーがゲーム内の環境を操作することによって状況の変化があるゲーム。【例】シムシティ、A列車で行こう
②舞台となる広大な世界を自由に動き回って探索・攻略できるゲーム。(オープンワールドと同じ表現だそうです!)
本来、箱庭ゲームは①の内容のゲームを表す言葉だったようですね(;´・ω・)ビックリです
ちなみにゲームの進行に関わるクエスト類が存在しない、プレイヤーが自分で目的や目標を決めて遊んでいくゲームを『サンドボックスゲーム』と呼ぶそうです。【例】マインクラフトなど
オープンワールドと呼ばれているゲームの中にはこのサンドボックスゲームというのが多くありそうですね!
消去法でいえばelonaもポケ森も「世界が広大」ではないため、②には該当しなさそうです(仮に第三者から言われたら「それは屁理屈なのではないか」とか言ってしまいそうですが……)。
ただどの程度を「広大」と定義するかは人によってあまりにも自由が保証されるべき、許されて然るべきはずなので
「elonaは世界の隅から隅までとても回りきれない、だからオープンワールドだ」
「休憩時間だけじゃとてもポケ森全部の島(7つぐらいあり、移動にやたらロード時間がかかります)を回りきれない、だからポケ森だってオープンワールド」
と言ってしまう向きも別に悪くはないように思えます。上記ふたつは極端な例としてお見せするつもりでしたが、見返して思うとほぼぼくの意見です。自然とそう思っているからこそ出てきたんでしょう……
ゲームに対する自分のキャパシティを設定する
ゲームは本を読むのと同じように、一人で遊んで色々考えたりします。
つまりゲームからもたらされた結果をどのように享受するか、しないかもそのたった一人の自分に一任されるため、ゲームを遊ぶという行為自体を誰かと比べる必要も意味すらもないように思えます。
仮に比べたとて、その結果でゲームの内容が書き換わるなんていう奇跡みたいなことが起きることもないです。
ユーザとしての自らがゲームと相対するためのキャパシティ値をあらかじめ小さく設定してしまえば、途端に世界は広くなり、それだけ楽しめるようになるということなのかもしれません。
ゲームの内容が書き換わることはないですが、もちろん自らのゲーム体験と同じ体験をした人にその感想を話すなどして、意見を交換すればもしかしたらその体験を別視点から多角的に見る方法を手に入れ、そのゲームに対する感情の構え方が変わったり、見えていた世界観が大きく変わったりという影響を受けられるかもしれません。
それはもしかしたら(とてつもない綺麗事かもしれませんが)ゲームの内容を書き換えることよりも美しい体験となるかもしれない気がします。何も考えずに文を書いていましたが、少し結果的なことが言えたような気がします。
比べないことについて(余談)
そうですね。比べちゃいけない……となるといわゆる競技としてゲームに関わる層から異議を唱えられるかもしれません、が、そこまで分野・次元・文化が異なるとおそらく比べるの意味も少し違ってくるんじゃないか、違っていると良いなと思います。
こどもの頃に誰かの家に集まって、誰が一番マリオが上手いか的な……「ゲームの共有」が発生している状態が継続している環境という特殊な場といえるでしょうか。
ただそうなると、課金によるレア当てゲームをSNSとかに貼り付けて比べ合う―――――比べるという言い方は違うでしょうか―――――文化はどう説明すればいいのか答えに窮する気がしてきました。
「これだけお金を支払うぐらいそのゲームに陶酔しているんだから、それだけの結果があったことを世界中(ソーシャルネット)に報告して当然である」
「これだけお金を支払ってダメだったんだから、自分の金銭の使い方について嘆く権利がある」
と、個別に切り取ってみればぼくが今こうして書いているnoteの日記と大して変わらないように思えます。
同時に、そういった部分は「ゲーム部分」ではないとも言えるかもしれません。「お金をこういう事に使いました」という報告はゲームと関係ないといいますか、あえてそのケースに当てはめるのであれば「お金を何千円出して、マリオオデッセイというゲームを買った」という結果報告と同次元で扱われるべきと言えば適切でしょうか。
したがいまして、レア当て文化をゲーム文化と同次元で取り扱うことはあまり適さないことなのかもしれないですね。些か余談が過ぎました。
末尾
ゲームのオープンワールド性、箱庭性という部分に触れ、アナザーワールドといいますかミラーワールド、VR/ARクラウドということに話を持っていこうと思っていたのですが、案の定べつの方向に話が向いてしまいました。後ほどまた続きが書けたらなぁと思います……前回まで、そして今回もさわりだけでも目を通していただいた方がいらっしゃいましたら、ありがとうございます。おかげで楽しく続けられます。
このサイト内ではいかなる場合でも返信行為をしていません。
