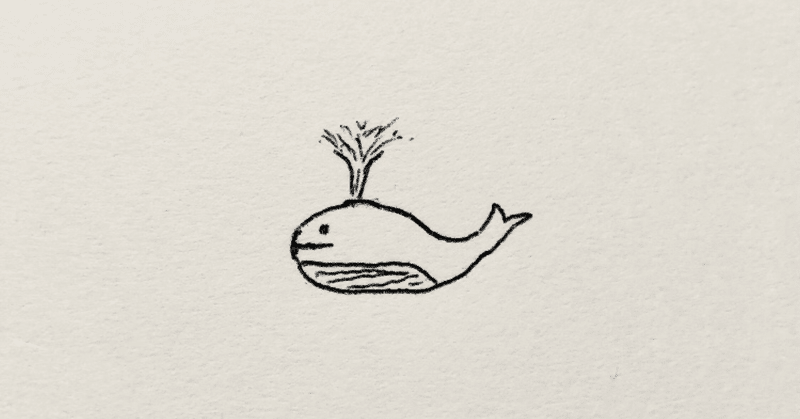
掌編小説(23)『死活問題』
「ごめん。俺、好きな人いるから」
「そうなんだ……じゃあ、仕方ない……よね」
「それに、君とは合わないと思うんだ。その——世界観が」
「なにそれ……」
唖然とした表情の女子。これ以上かける言葉もないと思って、無言で立ち去った。なるべく早く、その場から離れたかったから。
世界観が合わないというのは、別に言い訳のための抽象的表現というわけではない。
幼い頃から何故か、俺には世界が歪んで見えた。
他人の存在が世界に干渉する。ここでいう世界とは、〈俺が見て感じることのできる全て〉を指している。
あたりに草花を芽生えさせる者もいれば、不気味な化け物を生む者もいる。それこそ十人十色だ。
相手との距離が物理的に近いほど、その影響は大きい。人数が多ければある程度の調和は生じるが、人によって及ぼす影響度に強弱があるため完全に釣り合いはとれない。
だから、俺にとって〈誰をそばに置くか〉というのは死活問題といえた。
これは抽象的表現じゃないし、もちろん比喩でもない。文字通りの意味で生き死にがかかっている。
夜。読書をしていると、部屋を訪ねる者があった。
「お前、最近あまり良い話を聞かんぞ」
縁側から障子越しに父が言う。実家は寺で、父はそこで住職をつとめている。
「そう? 別に親父に——家に恥じるようなことはしてないよ」
「どうだかな。お前は他人を品定めするフシがある」
ふんと鼻を鳴らし、障子紙に映る父は母屋に向かって歩を進める。
「いつか足元を掬われるぞ」
「わかったよ。気をつける」
父が遠ざかると、部屋に充満していた香水の匂いも薄らいだ。父の足や背にすがる女達のものだろう。彼女達の金銭欲や独占欲らしきものが、屋根の上でとぐろを巻いたり、家中を這いずり回っていることを父は知らない。
あれが瘴気と呼ばれるものの正体かもしれない。いずれにせよ、母は死んだ。
「おはよう」
朝の教室。席につきながら隣席の女子に挨拶する。彼女は驚いたように目を見開き、次に眉をひそめる。
「——おはよう」
いつも肩に止まっている小鳥はおらず、腕から肩にかけて伸びる蔓に咲く、ジャスミンの花も萎れている。
「どうしたの? 元気ないね」
彼女は何も言わずに席を立ち、教室から出て行った。
入れ替わるようにして教室に入った茶髪の男子が席についた。同時に、室内にはいくつかの小さなつむじ風が発生する。マコトだ。
「見てたぜー。冷血漢」
マコトの周囲にはいつも風が吹く。こいつがそばにいると鼻につく悪臭なんかもたちまちかき消されるので、換気扇がわりに重宝していた。
「よくもまあ澄まし顔で。元気ないねはナイだろ。傷心中なんだよ、お前がフッたせいで」
「ああ、そういうことか」
「ああって。お前、毎度それじゃあ、いつかマジで刺されるぜ」
マコトは手に持った見えない刃物で俺の胸を刺す。俺は舌を出しておどけてみせた。
その方法もアリかもしれない。そう思った。
「シュウくん! 待った?」
「ううん。俺もさっき部活終わったとこ」
放課後。学校前の歩道。車止めから腰を浮かす。
「ごめん。会議は早めに終わったんだけどさ、先生から用事頼まれちゃって」
「いいよ。ユリは頼りになるから。美人だしね」
「なにそれ」
屈託のない笑顔。通り過ぎる男子の何人かが横目で彼女を盗み見る。
「でさ、甥っ子がめっちゃ可愛いんだー。ほら見て」
携帯端末の画面上で、つかまり立ちする男の子がカメラに向かって笑いかける。
「ほんと天使。ユリ、ソウタが産まれてから虐待する親とか特に許せなくってさ。ニュースとかで見るとカワイソ過ぎて涙出るもん」
「最近多いよね」
並んで歩きながら、他愛のない話を延々と続ける。
俳優の誰それが誰と結婚するだとか、女友達の恋を応援しているだとか、人を救ける仕事をするのが将来の夢であるとか。
無難な相槌を返しながら、こんなことを考えていた。
誰かを救けたいというのなら、後ろをついて歩くその醜悪な化け物どもに、俺を殺すように命じてくれと。
***
このお話は『人は自らが望む世界を見る』をテーマにして書きました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
