
私の読書遍歴
皆さんこんにちは!
趣味欄にはいつも「読書」と書きますが、最近は読むより書く方が多くなってしまっている古山大です!
それ以外にも、ラジオ、ブログ、毎日投稿…etc、手を広げ過ぎた気がします😅
まあ、練習時間外に半分趣味みたいにやってる活動なので、時間足りないのはアタリマエですけどね。
さて!そんな私ですが、先日久々に本屋に行って本を買いました。
めちゃくちゃ久しぶりです。
私は本屋に行く時、買うものはあまり決めずに行って、店内を徘徊しながら気になったものを買うので、一回にかかる時間が長くなりがちなんですよね…。
なのでまとまった時間が取れないとまず行けないので、久々に楽しかったです。で。本を選んでいたら、ふと「そもそも何で好き好んで本を読むようになったんだっけ」と疑問が浮かんできました。
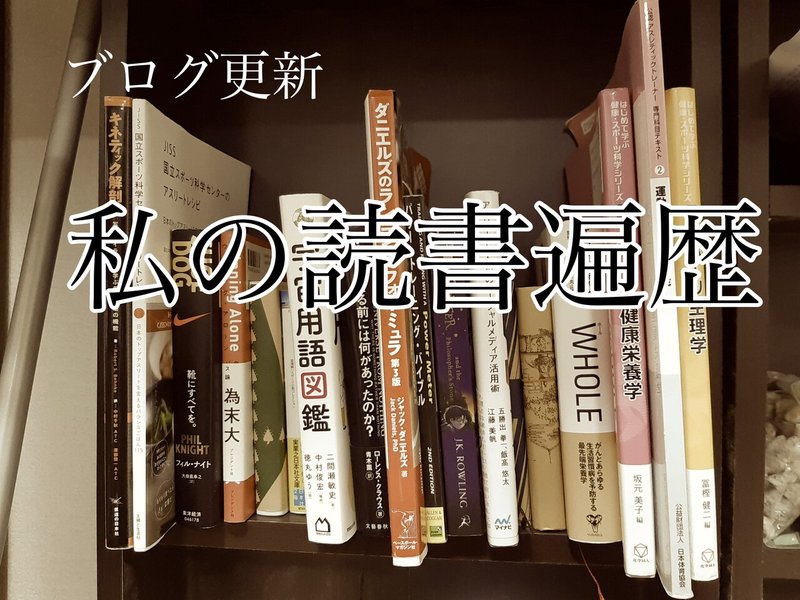
私が小学生の頃、家では毎週末に本を読む時間がありました。
その15分だか30分間は、勉強机に座って本を読む。という時間でした。(確か土曜に「勉強時間」があって日曜に「読書時間」があったハズ)
せっかくの休みなのに机に座って本を読まなきゃいけないのが私は最初苦痛で嫌いでした。これははっきり覚えてます。笑
ですが、どこかのタイミングから時間を超えても本を読み続けていた記憶があるんですよねぇ。
と思って考えてたら、記憶の隅に引っかかる本がありました。
上橋菜穂子先生の『精霊の守り人』です。
小学生の時、この本にどハマりした気がします。
この本を読み始めてからでしょうか、小学校に本を持って行って空いた時間に読み進めるようになりました。
詳しくは読んで欲しいのであまり触れないですが、主人公の用心棒が水の妖怪に取り憑かれた皇子と共に逃避行するって話だった気がします。(すいません。調べてません。記憶だけで書いてます。。)
で、上橋菜穂子先生の『守り人シリーズ』と呼ばれる、ある世界を舞台にした大河物語の一作目なのですが、この物語何がすごいって「水」の表現の感じがすごいんです!!!
ざっくり言うと、皇子が水の妖怪に取り憑かれた事はこの世界にとっては非常に重要な事なのですが、人間の言い伝えでは忌子であるとして、命を狙われます。
作中、皇子は度々水の妖怪たちと交信をするのですが、その時の文章がもう秀逸で、本当に水の匂いがする気がするくらいの文章です。
「雨上がりの命が芽吹きだした匂い」とか、「甘ったるく意識が遠のくような感覚」とか(実際にこう書かれてた訳ではありません。あくまでも「こんな感じの表現」です。実際はもっと上手な表現でした。)
そういう文字だけで、その世界に引き込んでしまう力に魅了されてから、割とファンタジーとかフィクション系の物語タイプの小説を読み漁るようになったと思います。
ちなみに宮部みゆき先生の『ブレイブストーリー』もハマりました。映画は観なかったですけどね。
『精霊の守り人』の作中には、妖怪とかもう一つの世界とか言い伝えとか、そういうファンタジックな要素が結構出てきます。
著者の上橋菜穂子先生が文化人類学を学んでいたらしく、そういった設定も、それこそ小学生であった私が理解できながらもかなり詳細に練り込まれていて、そういった部分でも『守り人シリーズ」には最後まで引き込まれました。
ちなみに『守り人シリーズ』は前述したとおり大河もので、『闇の守り人』『夢の守り人』『虚空の旅人』『神の守り人・来訪編、帰還編』『蒼路の旅人』『天と地の守り人・第一部、第二部、第三部』と続きます。
最終章の天と地の守り人は確か私が中学3年生に時に出版されたんじゃなかったかなと記憶しています。
今改めて振り返ると、私の世界観とか物の見え方考え方って結構この小説に影響されてる部分があるなぁと感じます。
「本棚を見ればその人がわかる」なんて言葉をどこかで聞いた気がしますが、その場合私の本棚にはこういう本がたくさん並ぶんでしょうね。
読む立場から、書くことも少し齧ってみて改めて物語を生み出すことの困難さを知りました。
まあ、執筆活動は競技活動のサブ程度ですが、いつか私も『守り人シリーズ」のような壮大でいて誰でも読みやすく、文字だけでその世界に引き込めるような物語を書きたい物です。
あ、題材はもちろんトライアスロンで。😁
はい。長くなりました。
書きたいことまだまだいっぱいありますが、今日はここまで。
…今度ガッツリ読書感想文とか書いたら需要ってあるのかしら。
それでは!
トライアスロンーーー!!!🏊♂️🚴♂️🏃♂️🥇
