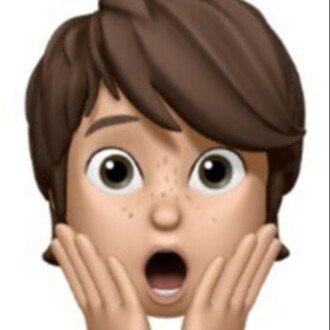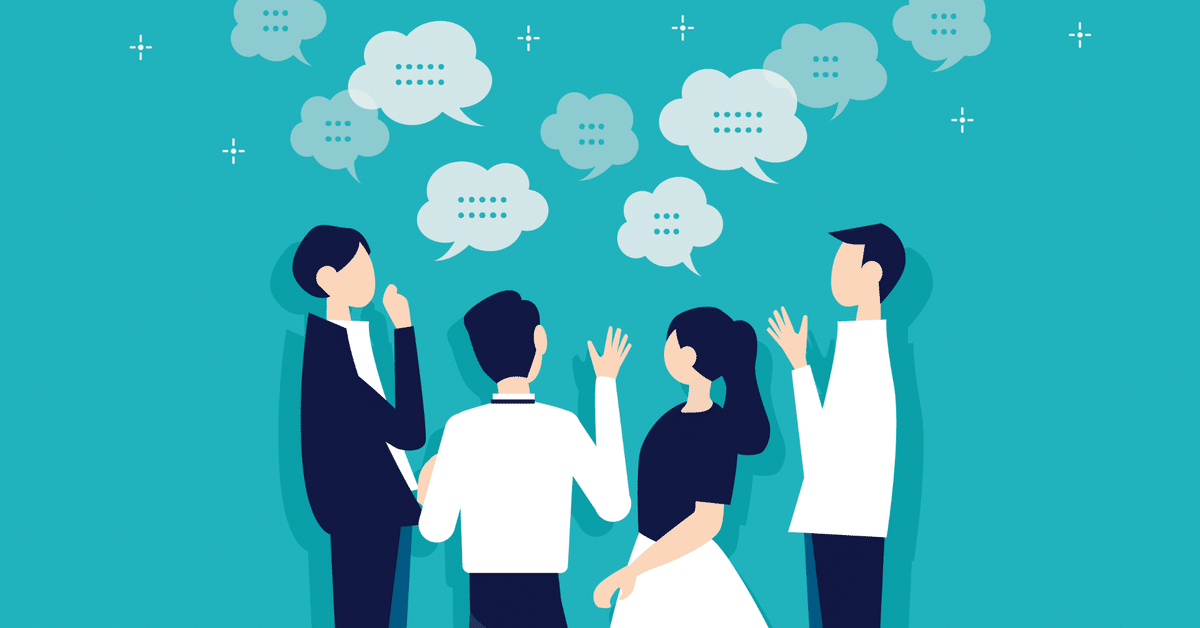
【子育て・日々悶々】国際バカロレア研究は続くよ!:文科省の「IB教育推進コンソーシアム」は使える
こんにちは。長男が無事にIBの小学校プログラムPYPのプロジェクトPYPxを終えました。
やり切った感がちょっとないところで「時間切れ」となってしまったいう大反省はあるものの、「教育(SDGsのGoal#4)」という大きなテーマにいどんが彼のプロジェクトをはじめ、1年生から知っている子どもたちが、クリエイティブにプレゼンテーションをまとめ上げたこそそのものに、感動しました。
さて、ジャーナリストの血が騒ぐ!深堀大好きな私は、今更ですが子どもたちが関わるIBについて、とことん研究しよーっというモードの今日この頃。
文部科学省が運営する「IB教育推進コンソーシアム」
改めて、文科省が運営するこの「IB教育推進コンソーシアム」には、本当にめちゃくちゃ情報が凝縮されているということに気づきました。(特に日本語で)
AirCampusで得られるディープな情報
さらに、教員に限らず、保護者や普通に関心ある人でも、AirCampusを登録すると、セミナー(ちょっと数年前のだけど)などの動画や資料にアクセスできます。日本語による情報で、日本に導入するという視点から考えるとすごく良い資料の山だと思いました。
特に「News Letters」!MYPについて書かれたニュースレターの中で書かれていた内容で目を引いたのは、
・(DPが大学入学資格が得られるのに対して)MYPではこのような大学進学に役立つ資格は取得できません
・MYP導入のメリットは、プログラムを通して身につくその力にある
・MYPで身につけたいのは「学びのお作法」
・具体的には「学びの概念的理解」と「ATL(Approaches to Learning)」
学びの概念的理解:知識を概念的に捉えて、用途や現実に合わせて使い分けるということを知り、さらに変えて使えるようになること
ATL(Approaches to Learning):MYPを通じて、学びを円滑に進めるために必要なスキル(資質や能力)を身につける。
事務局の小野さんが2020年に書かれたVol2のコラムからです。
詳しい内容は、こちらでご確認ください!
コンソーシアムの欠如している部分
ですが、このコンソーシアムの全体的な流れを見て思うのですが、
学校って結局親が何らかの判断で決めたところに子を送り込むことになると思うのですが(高校や大学になるとちょっと違うかもだけど)、IBに関わる「保護者」目線の意見や経験談などの情報って、なんだか忘れられているなぁと思いました。
先生や学生・卒業生の声はいっぱいあるんだけどね。
保護者のことについては、「質問」に答えるレベル。。。
どちらかということ、「こういう問題があって、こんな経験があった」
「こんないいことがあった」などなどの経験談の方が、Q&Aより共感できる気がするのですが。
学校によって違いすぎるのだろうか。。。んーでも家庭学習の仕方やアプローチなどは、ケースバイケースでもケースをちゃんと聞いた上で、対応を聞けたら、すごく役に立つ気がするのだけれど、、、
私は先輩ママたちにどうやって見守ったのかとか、不安はなかったのか、とかどんな風に子どもたちと関わったのかってことをもっと聞きたいと思います!
幸い、学校のママ友たちがいるので、少しずつちょっと上のお子さんのいる方から教えていただいたりしていますが、これって入学前に知っていたら、幼少期の子育て全般の判断まで変わってたんじゃない!?みたいなこともあるなぁと思うことも。
文科省さん、保護者視点の情報収集も是非ともお願いします(笑)
皆様からの経験談、ご意見、共有してください!
いいなと思ったら応援しよう!