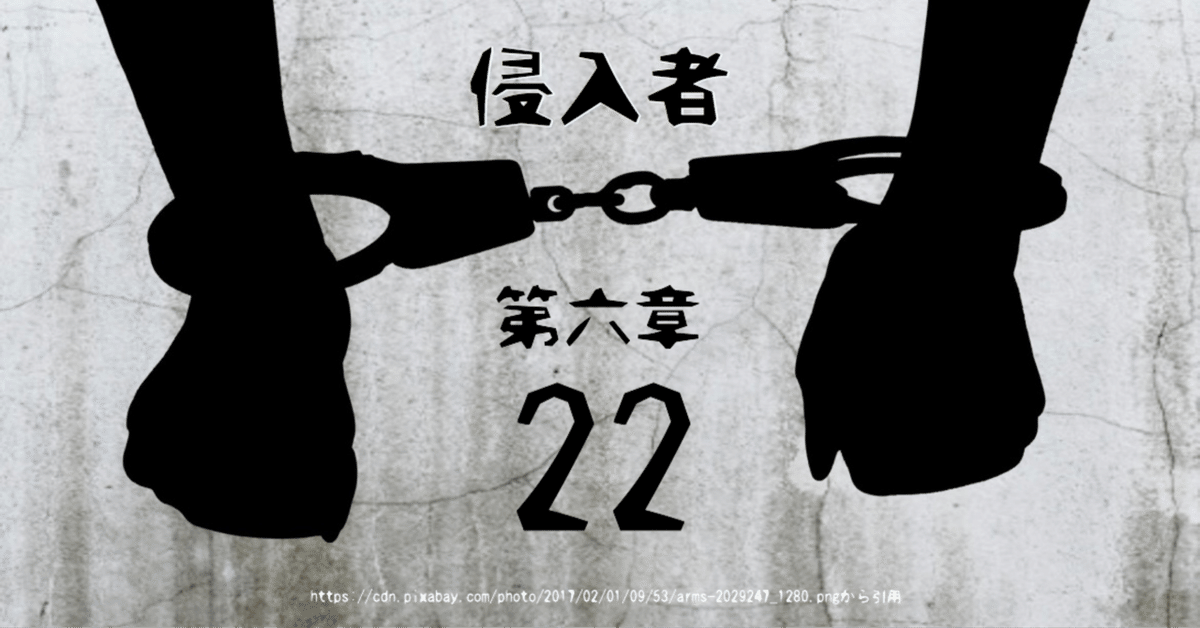
64第六章 空き部屋 22-瑛子の苦悩
「家中に、これをまいてもらえるか。終わったら、一階の応接間で待っていてほしい」
今朝、瑛子は真琴からそう命じられた。前から、それを今日やることは決まっていた。ポリタンクには、液体が入っている。ただの水ではないことは、幼い彼女でも知っていた。
「これは家族の時間を得るために必要なことなんだ。わかるね」
ポリタンクの液体を屋敷にまくこととそれが、なんの関係があるのか。齢十も超えていない瑛子では、両親の考えを全て理解なんて、できなかった。
しかし瑛子は、両親も自分と同じ思いだと信じて、両親の行いに従っていた。
——私は、あなたのお母さんよ。
三年と半年前。瑛子は神様が、この世にいないことを知った。本当にそんな存在がいるのであれば、大好きな母親と離れ離れにする訳がないのだ。
私を置いて、亡くなったお母さん。母の死は、藍田製薬の次期当主の妻としての重圧に耐えられなかったことによる自殺、外に男が別にいて駆け落ちしたなど、根も葉もない噂を飛び交い、誰もが納得している節があった。
しかし瑛子にとっては、理由など何でも良かった。
「一年の我慢よ。それで、また元の生活に戻ることができるわ」
この藍田家に来ることが決まった時の、両親の言葉。それを信じて、雛子の厳しい指導にも耐えてきた。それがこの仕打ちだなんて、あんまりではないか。
元いた場所に戻りたい。今は裕福で、大人達も彼女のことを瑛子様、お嬢様とへりくだる。欲しいものも手に入る。しかし心は痩せ細っていく一方だった。貧しくても、普通に友達と遊んで、普通に両親と過ごして。それが少女の中での、理想の生活だったのだ。
母が死に、気付けば約束の一年はあっという間に過ぎ、元の生活に戻れるなどという期待は、持つだけ無駄と思えていたある日、彼女は驚くべき事実を知ることになる。それは、冬子が亡くなって、数ヶ月後のことだった。
「…そういえば、冬子の遺体はまだ見つかってないのか」
「いきなり何?よしてよその話」
隣の空き部屋の床下の隠し通路のことを、瑛子が知ったのは本当に偶然だった。
真っ暗な階段を下った先には、また扉があった。瑛子はそれを開けようとしたところで止まった。向こう側から声が聞こえてきたのだ。雛子と、もう一人は男の声。勝治ではない。聞いたことのない声だった。
「警察に事故と処理してもらえたのは、運が良かった。でも、遺体が無いなんて、普通あり得ないだろう。…俺は時々、彼女が生きていて、俺達に復讐しようとしているんじゃないかって思うんだよ」
「あの子が生きてる?」
瑛子は耳を扉にべたりとつけた。声が少しだけ、聴き易くなる。雛子は「勘弁してよ」と笑い声を上げた。
「あの血の量、あなたも実際に見たじゃない。それにあのマンション、近くに川があったわ。駐車場のコンクリで大きく跳ね返って、川に流されたのよ。今頃海でふやけて、魚の餌になってんじゃないの」
「だと、良いんだが」
「全てうまくいってるのよ。誰も、私達がけしかけたなんて、わからないわ。あの子はこの家に馴染めなかった、プレッシャーに負けた。皆、良いふうに噂してくれてるんだもの」
会話はそこで終わった。というより、瑛子自身放心してしまったのか、その先の会話が耳に入ってこなかった。
——誰も私達がけしかけたなんて、わからないわ。
母の死は、仕組まれたものだった?
それを仕組んだ者が、祖母だった?
いや…事はそう単純ではない。雛子は男と一緒だった。それが誰なのか、瑛子は分からなかった。しかし恐らく、雛子はあの男と画策して、母を殺したのだ。
以降、瑛子は周囲の人間が信じられなくなった。何せ自分は、祖母が邪険に扱っていた母親の娘である。祖母達からしてみれば、邪魔な存在と思われているのかもしれなかった。
ちなみに、真琴はこの事実を知っているのだろうか。たとえ知らないとしても、父を頼ることはできなかった。母の死を、彼のせいと考えていた節があったこともそうだが、約束の一年が超えても何も変わらなかったことを考えると、彼に相談しようが、事態が好転するとは思えなかった。
自分の身は自分で守らなくてはならない。己を奮い立たせ、他人とできる限り、関わらないように努める生活を始めた瑛子だったが、数ヶ月後、そんな彼女を更に混乱させる出来事が訪れる。
「瑛子。新しいお母さん、志織さんだ」
真琴が彼女を連れてきた時は、瑛子は愕然としたものだった。一年も経たずに、別の女に目が行くほどに、父は冷徹な人間であったのかと。
それが思い過ごしと分かったのは、二人の結婚式を終えた数日後。志織の部屋で、彼女から自分が冬子であることを聞いた時だ。夢を見ているのではないかと、引きちぎれるくらいに頬をつねり、涙も出たものである。
しかしそれだけに、気になった。母親は何故、死んだままでいるのか。顔は、わざわざ病院で変えたと聞いた。人の顔を変えられる技術がこの世にあることにも驚きだったが、顔を変えて、別人として父と再婚する形を取ったのは、何故なのだろう。
「お母さんは今、藍田志織として、瑛子の二人目のお母さんとして、ここにいるの。でも、そのことを疑う人がいてね。もしもあなたの本当のお母さんって、その人達に知られると、瑛子と離れ離れにされちゃうかもしれないのよ。お母さんもお父さんも、それは嫌だし、瑛子もそうだと思うの。…だから瑛子、もしそういう人がいたら、お母さんとお父さんに教えてほしい。わかった?」
結局のところ、何故そうしているのかという疑問の答えは、もらえなかった。しかし瑛子は、両親の言うことに従順だった。もう、母と離れたくはなかったのだ。
しかしその従順さは、彼女が使用人の芳美を二階から突き落とす要因となってしまった。
仕方がなかったじゃないかしょうがなかったじゃないか芳美さんがお母さんの部屋でこそこそして何かしていたからお母さんのことを疑ったんじゃないか彼女が悪かったんじゃないのか——。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、頭にそれらしい理由がいくつも浮かぶも、自分の行いを正当化させることなんてできなかった。
幸いにも芳美は一命をとりとめ、自分に突き落とされたことも覚えていないようだった。ただ、両親は安心できていなかったようだ。もともと口の軽い、噂好きの女。密かに、彼女の病室に盗聴器を仕込んでいたらしいが、案の定、警察に彼女自身見聞きした情報を話していたという。
故に芳美は今日、この家まで無理やり連れてこられた。
「瑛子の行いは知られては駄目なの。あなたの、未来のためにも」
つまり、自分のせいで芳美は殺されてしまう。瑛子の胸に潜む罪悪感は、消え去ることなく今も、まだそこにいる。
口に手を当て、体育座りした両脚の膝の間で、瑛子は必死に声を堪える。
扉一枚を隔てた廊下、確かにいる。震える全身、じんわりと流れ出る冷や汗と涙。心地の悪い感覚。やめてやめてと心で願う。体は、小刻みに揺れ続ける。
足音が聞こえた。そのすぐ後に、苛立ち混じりの男の声。それは数年前、雛子と冬子の死について話していた時に聞いた声色と、同じだった。
こんな夜遅くに何故、ここにいるのだろう。彼は誰なのだろう。静寂。数秒がまるで数分、数時間、永遠とも思える程に長く感じる。怖い。怖い、怖い。
お母さんお父さん、助けて。声にならない助けを求める。しかしその声が届くことは無い。真琴と冬子は、今は二階にいるのだ。
不意に、尻から振動が全身に伝わる。近くの壁を蹴ったのだろうか。突然のことに足が前に伸び、それは扉に当たった。
冷や水をかぶったように鳥肌が立った。それは、音としては微かなもの、普段は気にならないものだっただろうが、今の状況では違った。足音がひたり、またひたりと近づいてくる。気配から分かる。来ないで。瑛子は両手を胸の前で組み合わせて目を強く閉じる。願いが叶わないことなど、分かっているのに。
がちゃ、がらら。願いも虚しく、両者を隔てる扉は開かれた。瑛子は見上げる。
——「死」が、彼女に微笑みかけていた。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
