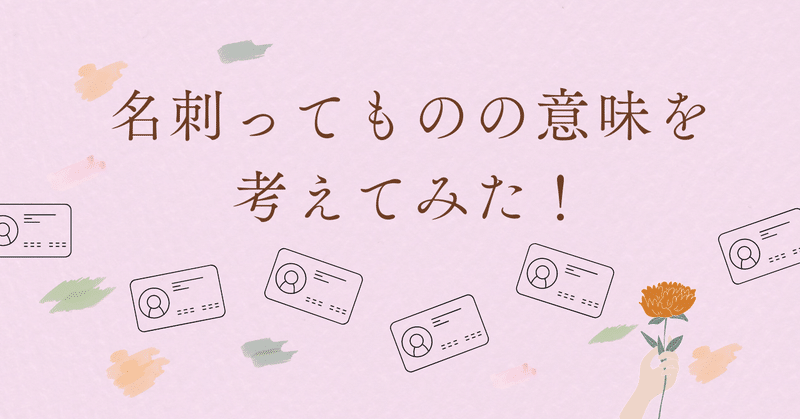
名刺ってものの意味を考えてみた!
名刺初めて物語
初めて名刺を作ったのはいつだったかな?と記憶をたどってみたら、高校2年生だったことを思い出したかえるです。今のようにオンラインでささっと名刺オーダーなんてできない時代の話ですから、当時は珍しかったかもしれません。でも、欲しかったんです。名刺ってものが!
中学生になったぐらいからだったでしょうか。両親の友人や知り合いのような大人から、「◯◯さんの娘さん」扱いでなく、あくまでも対等に一個人として扱われることを求めていた生意気なティ―ンエイジャーだったんです。高校生になると、大人に混じって学外での活動(例えばアート関係とか)にも参加してたので、必要性を感じて名刺を作ったわけです。手にした時、大人気分でうれしかったのを覚えてます。当時は、仕事をしている大人に対して、名刺を渡すということそのものが、ある種の「通過儀礼」のような感覚でした。
最近の出来事
昔話から、急にぐぐーっと時間軸を「現在」に動かしますね。ちょっと前の話ですが、知り合いから頼まれて、とあるイベントにボランティアとして参加してきました。いくつかテーマがある中で、私かえるは防災関係のカテゴリーで、来場者に説明する係を割り当てられました。もちろん、そばには専門家の方が控えているので、私のミッションはあくまでも「わかりやすく伝えること」。デモンストレーション込みでの来場者の方への説明は、3時間限定ではありましたが、なんとかやり遂げることができました。
ボランティアスタッフは、民間企業の社員はもちろん、元々行政関係に携わってた方や大学の研究者など、顔ぶれも様々なのですが、社会貢献の一環だと思うと皆が使命感に駆られて、対応も積極的でした。すると生まれてくるのが連帯感ですね。その共感から連帯感として花開くきっかけの「種」は、実はイベント準備の時間に撒かれていました。
やっぱり名刺は大切なツールだった!
その「種」とは、初対面のスタッフ同士、準備に入って顔合わせした際に始まった名刺交換です。そこはやはり普段ビジネスパーソンとして動いている面々なので、だれからともなく条件反射的に(?)そんな流れになりました。ただ、決して形式的なものではなく、あちらこちらで盛り上がるわけです。社名や団体名を見て、「あ、以前◯◯さんという方にお世話になったことがありますよ」とか、「もしかして、そちらに△△さんっていらっしゃいます?」など。
コロナ禍では、「リアルで会えない」という条件が、従来の名刺交換ができないためオンライン名刺交換といった進化を促しました。そんな時期を経て、選択肢が広がった中で、あえてまた「対面での名刺交換の機会も意味も、またぐっと増えてきたな」と、実感しています。
「2つ目の名刺」急増の背景
今の時代、例えばメインで所属する会社のほかに、起業家として活躍していたり、もうひとつの組織にも所属してパラレルキャリア的に働いていたり、プロボノ(=プロとして自分のスキルや経験を社会貢献に活かすような活動)として純粋に個人として活動する方は珍しくありません。最近名刺交換した場面を思い浮かべても、一度に名刺を2枚渡されるケースが増えたなぁという感覚です(かえる調べ)。
本格的に極める道も、振り返るとスタート時点ではお試し感覚だった、ということも往々にしてあります。「こんなふうになりたい」「こんなことしたい」という現状+α の思いが生まれたら、2つ目の名刺で自分のあり方や姿勢を示すことも選択肢のひとつですね。
今は幸い、私が高校生だった昔(笑)とは違って、「2つ目の名刺」もサクッと作れる時代です。デザインのプロでなくても自分で簡単にデータが作れてしまうのも歓迎すべき進化ですよね。自分のこだわりを形にした名刺を作ってデータをアップするだけ。いたってシンプルです。「こうだ!」という自己表現のきっかけにもなるでしょう。
そんなこんなで、「2つ目の名刺」を考えておられる方は、ぜひこちらをご覧ください。過去の私がこれを見たら、「え~?カラーでこんな値段でできるの?」って大声で叫びます!確実に!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
