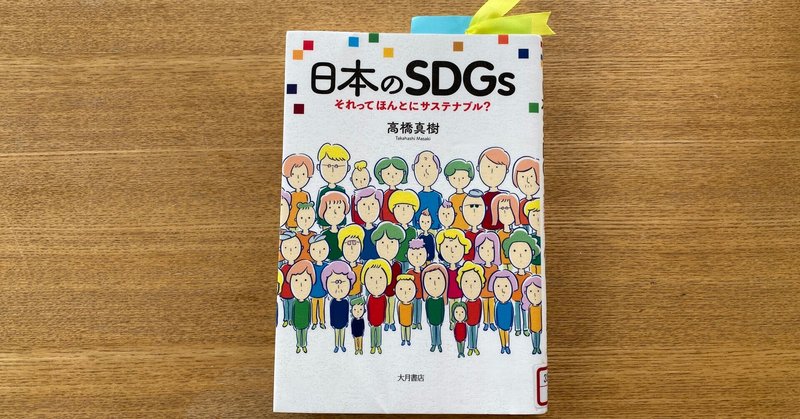
『日本のSDGs』を読んで
正直、僕はSDGsというものがいまひとつよくわかっていない。
なんというかピンとこないのだ。
恥ずかしながら、「持続可能な社会」を作るために必要な様々なことに取り組む。それくらいの認識であった。
いいことなのはなんとなくよくわかる。けれど、皆が一斉にSDGsを唱え、バッチやロゴを掲げる光景に違和感が強くあった。ひねくれているようで申し訳ないのだが、いいことをするにしても得意分野や専門性はそれぞれだし、企業の大きさや取り組みによっては方向転換は容易ではない。また、あっちを立てればこっちが立たずではないけれど、何かをするということは何かに影響を与えることだ。僕のように「良いことをするにはどうしたらいいんだろう?」と漠然とした部分がある人や「持続可能な社会の実現」のために日本は今どのような状況にあるのか?という入り口に立っている人、実際に行動を起こしていきたい人にとってはおすすめの本だ。
精神的幸福が実感しにくい社会
「世界繁栄指数2019」では、日本の総合順位は149ヵ国中19位となっている。しかし、地域社会での家族以外の人との信頼関係や結びつきを意味する「社会関係資本」が極めて低かった(149ヵ国中132位)。さらにユニセフ(国際児童基金)が実施した「子どもの幸福度調査」では、先進38ヵ国中。日本は総合20位。健康面は1位だったが、精神的幸福度については、生活満足度の低さや若者の自殺率の高さなどから最下位に近い37位だった。
こうした国際調査からわかることは、現在の日本は経済的に比較的豊かなわりに、精神的な幸福を実感しにくい社会になっていることだ。社会的なつながりやセーフティネットが希薄なため、悩みや苦しみを個人や家族だけで解決するしかない。そのため他者により厳しくなってしまうという悪循環が透けてくる。そのような課題を克服するためにも、SDGsのかかげる「トランスフォーム」や「誰一人取り残さない」といったコンセプトの実践が、日本社会においても必要になる。(P.51より引用)
それなりに豊かでそれなりに平和な国、けれど、将来に対する希望となると明るいとは言い難いのが日本の現状ではないだろうか。僕は40代なので、若い子たちが実際にどのように感じているかは分からないがそのように想像する。若い子たちにかっこいい背中を見せることのできる大人がどれだけいるだろうか?大人世代がワクワクすることができず、希望を見出せなければ下の世代はその空気を読んでああ人生はそんなものなのかも知れないと若いうちから悟ってしまう気がする。
豊かさの指標は様々だ。経済的に豊かになれたとしてもその豊かさを満喫するための余暇がなければ、豊かさとはいえない。一人一人が尊重され、尊厳を大切にされてこその人生だと思う。それがあってこそ、精神的幸福を感じることが出来るのだと思う。
バックキャスティングの発想がない
政府のSDGsアクションプランの数ある個別政策の中には、もちろん意義あるものも含まれている。しかし本質的な問題がある。まず、SDGsアクションプランでかかげている政策はどれも、すでに政府が実施していたり、導入の決まっている政策を、SDGsに合わせて並べているだけになっている。また、政府による自治体や企業の表彰も、優れた先進事例を賞賛するにとどまっている。いわば、後づけで「それらしく」SDGsに取り組むように見せているにすぎない。その意味では、木企業がホームページでSDGsロゴを「タグ付け」しているのと変わらない姿勢と言える。
さらに大きな問題は「バックキャスティング」の発想がないことだ。バックキャスティングとは、数値目標を含めて、あるべき未来の姿を明確にイメージし、達成するために逆算する考え方である。SDGs自体もバックキャスティングの発想で作られた。17ゴールが目指すべきビジョンで、具体的な方法論が169のターゲットという関係になる。(P.56~57より引用)
この問題は、SDGsに限ったことでなく、政府に限らず日本のシステムが苦手な考え方かもしれない。もしくは日本人特有の合議制と相性が悪いといった方が良いかも知れない。個々の日本人が目標を達成するにあたり、ゴールを決めて、そこに向けてミニゴールを設定し、実現に向けて努力を重ねる。これってスポーツにおけるトレーニングの考え方だ。多分、ビジネスでもそうだろう。けれど、合議制になると色々な人間関係やら入り込んでくるので個人の意思で決められない範疇が大きくなる。責任の所在も曖昧になるし、多分、そのあたりが大きく影響しているように感じる。
物事を決める際には明確なリーダーシップが必要な場合もあるが、これも合議制と相性が良くないと考える。丸く収めましょう、この辺りを落とし所にしましょうという発想と明確なゴールという考え方は相容れない。結果、既存の事例の紹介や表彰、新規の取り組みをするとなると曖昧な実践になっているのではないだろうか。
欠けている信頼関係
デンマークの政治では、何よりも公平性と透明性が重んじられ、政府と国民のあいだにしっかりとした信頼関係が築かれてきた。国民からすれば、なにかトラブルが起きても合理的に対応したり、きちんと説明責任を果たしてくれるという安心感がある。コロナ禍の対応でも、各大臣がたびたび記者会見を開き、自身の言葉で、どのような議論が行われ、なぜこの結論に至ったかというプロセスを丁寧に説明している。(P.73より引用)
デジタル化と透明性や説明責任は、セットで考える必要がある。(P.74より引用)
"日本の「デジタル化」に欠けているもの"というP.72からの章に出てくる一文。デンマークの事例と比較しながら日本の課題を上げているのだけれど、これはデジタル化に限ったことではない。
日々暮らして思うのが責任の所在を曖昧にする日本の姿勢だ。伝統的といえば伝統なのかもしれないが、責任を回避したいがために曖昧でよくわからない内容のものを作ったり、ひたすらに長く分量の多い説明で何が言いたいのかわからないケムに巻くような文章を作ったり。何から何までシンプルにする必要はないが、大切なことは時にスパッと言い切る必要があるし、責任ある立場の人は自らの言葉で語りかけ、また、その責任をきちんと行動で示す必要があると思っている。
最低賃金について
ワシントン州シータック市では2014年に全米で初めて最低賃金が時給15ドルに引き上げられた。最低賃金の上昇に反対していたホテルやレストランのオーナーは「事業が不可能になるので撤退する」と宣言した。ところが、結果的に仕事が増え、企業の収益が上がり、雇用が増えた。そしてシータック市でも20年には最低賃金が16.34ドルとさらに上昇した。(中略)
ここからわかることは、最低賃金を上げることは、経済界で一般的に思われているように経済的なリスクばかりではないということだ。格差を縮め、多くの人がお金を消費することで、場合よっては経済効果がもたらされる。逆にこのままm格差が広がり続けレバ低所得者が増加し、彼らを支えるための社会保障、つまり税消えんを使わざるを得なくなる。それは長い目で見れば地域の衰退をもたらす。(P.104より引用)
この後の文章で著者も指摘しているが、最低賃金をあげる=多くの問題が解決とはいかないだろう。地域ごとの特性を踏まえ、どの程度の賃金を上げるかは検討の余地がある。加えて、企業を支える仕組みだったり総合的な取り組むであるべきだ。
ただ、ここで大切なのは①最低賃金をあげることはリスクとは限らない。②思い込みで決めるのでなく、こうした実例を参考にして検討することだと思っている。今後日本では人口減少が進み、若年層の支えるべき高齢者の負担は増えていく。であれば、賃金上昇はもっと本格的に議論されて良いことに思えるし、豊かな暮らしを支えていく上では大切な要素だ。
スフィア基準の視点から
イタリアの災害支援はスフィア基準でもっとも大切にされていることは何か。あんどうりすさんは言う。「スフィア基準については、トイレの数や人との距離などの数字に注目が集まりがちですが、大切なのは数字ではありません。『命さえあればいい』というレベルにとどまることなく、人として尊厳を保つ避難生活をサポートしていくことです」(P.129より引用)
スフィア基準とは:国際的に被災者を支援する最低限の人権基準のこと。それに照らすと日本の避難所の環境はあまりに過酷で難民支援の基準以下だと指摘されているそうだ。(P.126より抜粋)
コロナ禍となり、人と人の間隔を保つことが求められ、度重なる災害で分散避難の推奨など改善傾向にはあるものの、そもそも避難所も足りないし、避難先がすし詰めであっては長期に滞在せざるを得なくなった際にプライバシーをはじめ耐え難い問題も出てくる。対象例として本文中で紹介されるイタリアの事例が印象的だ。仮設住宅もプレハブでなく10年住むことも出来るようなものを作るそうだ。避難生活が必ずしも短期で終わるとは限らないし、少しでも人間らしく暮らせるようにという視点に立って、実践されている。
最低賃金の話でも感じたのだが、「少しでも豊かに暮らすには?」という視点を常に持っているから結果として人の暮らしに寄り添ったアイデアが実践されているのだと思う。これは文化的背景が強いのかもしれないが、例えば、眠れれば良しとするのか、どうせ眠るなら背中が痛いと感じながらよりもぐっすりと眠りたいのは当然ではないだろうか?おもてなしとは言わないが、避難所の過ごし方でも快適に過ごせる創意工夫があっていいように思う。
最後に
この本を読んで、僕がSDGsに関して抱えるモヤモヤが少し晴れた。と同時に同じようにモヤモヤしたり違和感を感じている人がいて嬉しくなった。
僕は山を走ることを通じて、環境維持や次世代育成などに取り組んでいる。今は知っている環境を僕の子ども世代、その先の世代に残したいからだ。そのためには面白いアイデアが浮かんだら是非実現に向けてアクションを起こすし、おかしいなと思うときは「これおかしくない?」「これってどういうこと?」と、きちんと声を上げるようにしたい。
【今後の予定】
8/7(土)ランナー、トレイルランナー向けテーピング講習会 Part.2
8/28(土) Duo Espoir 20周年記念リサイタル
9/26(日)第6回NAGANO Jr TRAILRUN in 富士見高原
10/10(日)トレイルシンポジウム2021
10/17(日)第13回TOKYO Jr TRAILRUN兼-U15ジュニアトレイルランチャンピオンシップ
10/31(日)第7回YAMANASHI Jr TRAILRUN in 武田の杜
11/7(日)逗子トレイル駅伝2021兼U-12ジュニアトレイルランチャンピオンシップ
「RUNNING ZUSHI」
逗子市内池子の森自然公園内400mトラックを拠点にしたランニングチームです。
Facebookページ
instagram
最後まで僕のnoteを読んでくださりありがとうございます!!
「スキ」や「フォロー」していただけると励みになります。
過去のnote記事はこちら
最後まで読んでくださりありがとうございます。僕の経験や感じていること考えをいろいろと書いていきます。noteの記事を通じて一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです!「スキ!」や「サポート」はとても励みになりますので、宜しければ応援の気持ちも込めてよろしくお願いします!
