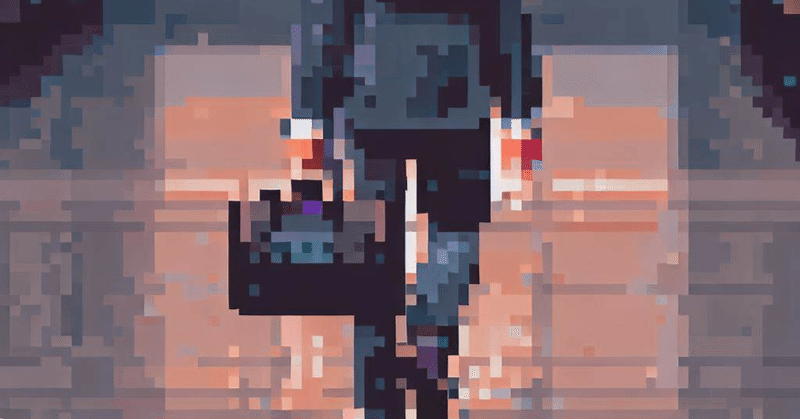
オフィス出社の意義
昨日、知人主催で各社の人事担当や専門家が集まる「人事の会」に参加していました。いろいろな話題が出た中で、どの程度テレワーク勤務を認めているかという話になりました。ほとんど認めていない会社から、いったんフルリモート勤務にした後に何割か出社を求めるハイブリッド型の会社まで様々な対応で、各社試行錯誤中だというのを感じた次第です。
リモートワークか出社かというテーマについては、過去にも何度か取り上げたことがありますが、改めてこのテーマで考えてみます。
出社に関連するテーマとして、8月26日の日経新聞で「力作オフィス、出社は求めず」というタイトルの記事が掲載されました。「どんなオフィスなら行きたくなるか」という視点でオフィスを設計するという事例を紹介しています。
同記事の一部を抜粋してみます。
ビデオ会議システム大手で、リモートワークを普及させた米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズが自社の一部従業員に週2日の出社を要請したことが明らかになった。幅広く在宅勤務を認めてきたが、リモート頼みでは生産性の向上に限界があると方向転換した。オフィスでのチーム作業の重みを再確認したといえる。
東京駅そばのリクルート本社オフィス。工事に1年4カ月かけたリニューアルが7月に完了した。セミナー室、ラウンジ、イベントスペース、食堂、カフェ……。大小さまざまな単位で従業員が対話し、つながるための施設を21ある全階にちりばめた。オフィスは集まってコミュニケーションをする場所。そう明確に位置づけた。
力作だ。投資したからにはフル活用かと思いきや、会社は従業員に出社を強要しない。あくまで選択肢のひとつだからだ。自宅とサードプレイス(サテライトオフィスなど)を加えた3つから従業員が自律的に選んで職場にする。21年から採用する考え方だ。出社率(全国)は平均4割という。
クラウド会計のフリーも人員増に伴う移転に合わせ2022年にオフィスを刷新した。やはり対面でのコミュニケーションを重視し、料理やゲーム、パーティーができる会議室などをつくった。
どんな場所なら来たいか従業員の意見を聞き反映したオフィスだが、それでも出社は絶対ではない。エンジニアは週1回以上、ビジネス系は週3回以上の出社をと呼びかけるレベルにとどまる。
ときに部署の壁を越え、従業員がオフィスで密に接することの効用はかねて指摘されてきた。ヒット作を連発した米ピクサー・アニメーション・スタジオは有名だろう。建物の入り口は1カ所にし、会議室やトイレなどを中心部に配置した。働く者同士が自然に、頻繁に顔を合わせるしかけだ。
最高経営責任者(CEO)をつとめたスティーブ・ジョブズ氏が設計した。オフィスでの交流がアイデアの発火点との思いが根っこにある。米アップルの円環型の本社ビルにも受け継がれている。
同じ空間を共有していれば五感を使って情報を伝え合えて、組織のシンクロ率は高まるはずだ。おそらく誤解や勘違いが減り、事業運営のスピードも上がる。
しかし、いまや世界中の人がリモートワークを経験し「出社せずとも何とかなる」と知った。業種・職種にもよるが、出社せよと圧力をかける企業は従業員との間に摩擦を生みやすいに違いない。
リクルートの佐野敦司ワークプレイス統括室長が言う。「オフィスもリモートも一長一短がある。いいとこ取りが一番いい。オフィスも状況に合わせて変える。永遠のプロトタイプ(試作品)だ」。事実上オフィス一択だったころほど方程式は簡単ではない。
同記事の内容も手がかりに、出社する意義について改めて、大きくは次の2つに集約されるのではないかと考えます。
・出社したほうが、生産性が高まる仕事がある。
・出社したほうが、予期せぬ偶然のコミュニケーションが起こり創造性を生みやすい。
今の技術と環境下であれば、現地に行かなくても家でもほぼ同じことが得られるものに、例えば映画やスポーツ、アーティストのライブ観賞があります。映画は、レンタルDVDや動画配信サービスなどで、基本的に家でも同じコンテンツを楽しめます(映画館のほうが最新作をいち早く見ることができるのが家とは条件が違うという点は、ここでは無視します)。ライブやスポーツも、家で同じ内容を中継で見ることができます。
しかし、「もし同じ映画を映画館でも家でも見られるなら、どちらで見たいか」と聞かれたら、多くの人が映画館を選ぶはずです。中身自体は同じながら、なぜわざわざ映画館まで行くのか。それは、映画館のほうがクオリティーが高いからでしょう。
画面の大きさ、画質、音響など映画自体の視聴環境の良さに加え、ポップコーンの香りによる雰囲気など、より満足度高く見ることができる条件が揃っています。同じ映画を見ることによって得られるものの大きさを生産性と例えると、映画館のほうが生産性が高いと言えます。
この適当な例が、出社にも当てはまるのではないかと思うわけです。家でも会社にいるのとほぼ同じ仕事はできる。しかし、作り込みの作業そのものや周囲との連携などで、細部のクオリティーをより高めてより生産性の高い仕事に仕上げるための環境が揃っている。だから出社したほうがよいというわけです。
逆に、家に最高の映画の視聴環境があれば、わざわざ映画館には行かないかもしれません。家の作業環境のほうが生産性の高い仕事ができるための環境が整っている場合、例えば理想的なデスク、椅子、プリンター、通信機器があるなどで、家のほうが早くよりよく仕事ができるならば、オフィスに行く必要はないのかもしれません。
リモートワークは、1日の予定が決まっていて、基本的に予期した流れの通りに仕事を行います。予期せぬ偶然は起こりにくい環境です。一方で、同記事で紹介されているオフィスの例は、いずれも働く人同士の自然発生的なかかわりあいを高頻度で促し、予期せぬ偶然のコミュニケーションがあちこちで起こることを意図しているように見えます。
創造的なアイデアが生まれる背景に、偶発的なコミュニケーションが起点となっていることは多いものです。ブレーンストーミングと呼ばれるアイデア出しの手法は、その典型でしょう。
逆に言うと、出社したほうが生産性が高まる仕事でもなく、予期せぬ偶然が起こるような環境や風土の会社でもない、ということなら、出社する意味はないとまとめることができるかもしれません。
上記のことは見方を変えれば、予期できる作業を固めて集中的に行なうことで効率的にやりたいというときには、リモートワークが生産的とも考えられます。しかし、毎日リモートワークだと予期せぬ偶然が起こらない。同記事中の、週2日出社や出社率4割などは、それらのバランスを考えた結果として仮の最適解ということなのかもしれないと思います。
ワークスタイルの模索は、これからも続いていきそうです。
<まとめ>
出社する主な理由は、予期せぬ偶然のコミュニケーションで創造性が高まることにあると言えるのではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
