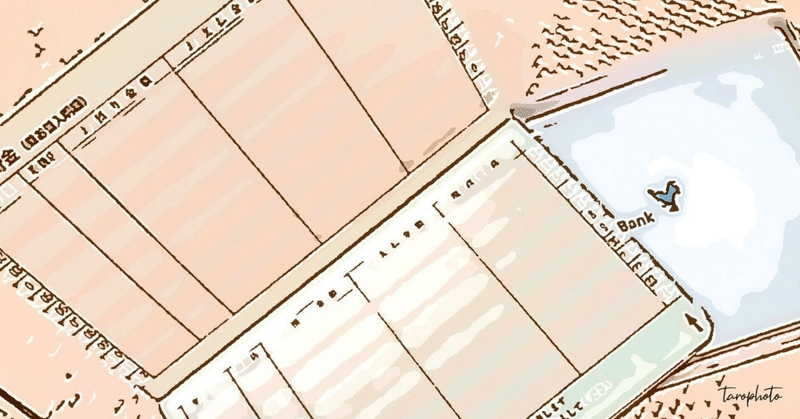
現預金の保有は現状維持への投資
国連総会出席のためニューヨークを訪問した岸田総理が、9月22日にニューヨーク証券取引所(NYSE)を訪問し講演を行いました。日本の代表者が同所で講演したということは、(各論でいろいろな意見もあるかもしれませんが)その内容に今の日本を表す社会的、経済的なポイントが、一般的、専門的な見地から統合的に織り込まれていると見るべきだと言えます。
9月24日の日経新聞から、同講演のポイントを一部抜粋してみます。
これからの課題は未来への投資を進め、新たな価値が創造される経済をつくり上げることだ。日本の5つの優先課題を紹介する。
第1に「人への投資」。デジタル化・グリーン化は経済を大きく変えた。大きな付加価値を生み出す源泉となるのは有形資産ではなく無形資産。中でも人的資本だ。
第2はイノベーションへの投資。人工知能(AI)、量子、バイオ、デジタル、脱炭素の分野の研究開発について国家戦略づくりを進めている。特に重視するのがスタートアップだ。
第3はグリーントランスフォーメーション(GX)への投資だ。2050年のカーボンニュートラル実現に向け、日本は経済、社会、産業の大変革に挑んでいる。この大変革は日本経済復活の大きなチャンスとなりブースターとなる。
第4に資産所得倍増プラン。日本には2000兆円の個人金融資産がある。現状、その1割しか株式投資に回っていない。資産所得を倍増し老後のための長期的な資産形成を可能にするためには個人向け少額投資非課税制度(NISA)の恒久化が必須だ。
第5に世界と共に成長する国づくりだ。日本は世界に開かれた貿易・投資立国であり続ける。日本は世界と人、モノ、カネの自由な往来を通して繁栄してきた。
同内容からは、大きく2つの点を感じます。投資の促進が大きな課題であるということ、そして、その中でも人への投資が最重要課題だということ、です。人への投資が1番目に触れられていることから、そのように感じられます。
産労総合研究所は、1976年以来毎年教育研修費用の実態調査を行って発表しています。企業の教育研修費総額と正社員1人当たりの教育研修費用を調査するものです。2021年度調査結果によると、2020年度の1人当たりの教育研修費用は24,841円となっています。前年に比べて10,787円減で、1人当たりの金額が3万円を切ったのは1999年以来だそうです。コロナ禍の影響が大きいことが、改めて分かります。
ただし、コロナ禍前の2018年度でも34,607円です。2010年度は36,797円。コロナ禍の影響に関係なく、以前からほとんど増えていなかったと評価できます。
社員の人材育成は、現場指導であるOJTなど他の方法もあり、教育研修のみで行われるわけではありません。また、教育研修も外部講師ではなく社内講師が行えば費用が安くなります。よって、上記だけで人材育成の規模と効果の全体を結論づけるのは無理があります。そうした点を割り引いて考える必要があるとはいえ、人材育成の取り組みの実情を示すひとつのバロメーターだと言えるはずです。
日本は他国に比べて、人材育成への投資が見劣りするということは、他の調査結果等でも言われてきていることです。アベノミクス以降、最高益を更新する企業が増え株価全体も回復するなど、企業の収益性も回復しました。その環境下で、人への投資を含めた投資活動が伸びておらず、この間投資を増やしていった他国企業との差が広がっていることが想定されます。
日銀が20日発表した2022年4~6月期の資金循環統計(速報)によると、6月末時点の家計の金融資産が前年同期比で1.3%増えて2007兆円となっています。そのうち、現預金が54.9%で最大となっています。
2番目に割合が高い保険・年金・定型保証と合わせると約82%となり、国が標榜している「貯蓄から投資へ」の動きは依然として限定的だということが見て取れます。この比率は、欧米などに比べてもたいへん高いものです。
少し視点を変えて、現預金での保有を「現状維持への投資」と捉えるとよいのではないかと考えます。
現預金を保有しようとする理由は、企業や個人が危機的状況に直面した時に対応できる余力を蓄えるためです。つまりは、現状を維持できるための状態を高めることへの投資をしていると考えることができます。コロナ禍の発生直後などの局面では、事業活動や生活基盤の存続に寄与しやすくなった面があるかもしれません。現状維持のための投資は、一定割合必要です。
しかし、投資の大半が現状維持のためという状態が永続するなら、当然経済・社会・個人の発展が限定された状態が続くことになります。企業も個人も、環境を見極めながら、投資先を現状維持と未来への開拓との間でギアチェンジさせていくべきでしょう。
このように見てみると、企業も個人も保有する現預金を未来投資に回す動きが限定的だという課題感が、冒頭の同講演にも表れていると、言えるのではないでしょうか。
<まとめ>
現預金での保有を「現状維持への投資」とみなして、未来開拓の投資活動とのバランスを考えてみる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
