
諸子百家の老子、孔子、孟子、墨子
関係、思想の違い、時代背景をお伝えします。
老子、孔子、孟子は諸子百家の方たちです。
古い順だと老子>孔子>孟子の順ですので3人については順番にまとめました。
老子 (紀元前571年,〜紀元前470年)
道教の基盤となる『道徳経』を残した。
生き方は謎で架空の人物の可能性があるが書をしたためている。
名言:優しい言葉をかければ、信頼が生まれる。相手の身になって考えれば、結びつきが生まれる。や禍は福のよる所、福は禍の伏す所なり。足るを知るは富む。
孔子(紀元前552、551年〜紀元前479年)
「儒教」の始祖と呼ばれる人物。 彼の名言をまとめた「論語」が有名、明確に本人が残した書はなし。
人を愛することを基本とする「仁(じん)」と、外見的な秩序を意味する「礼(れい)」を重視した教えが主。
名言:「知らざるを知らずとなす、これ知るなり。」「良薬は口に苦くして病に利あり。忠言は耳に逆らいて行いに利あり。」
論語収録:「吾十有五にして学に志し(志学)、三十にして立ち(而立)、四十にして惑わず(不惑)、五十にして天命を知る(知命)。 六十にして耳順い、七十にして心の欲する所に従いて矩を踰えず」
和訳:先生がいわれた。わたしは15歳で学問に志し(志学 しがく)、30になって独立した立場を持ち(而立 じりつ)、40になってあれこれと迷わず(不惑 ふわく)、50になって天命をわきまえ(知名 ちめい)、60になってひとのことばがすなおに聞かれ(耳順 じじゅん)、70になると思うままにふるまって道をはずれないようになった(従心 じゅうしん)。
四文字熟語:温故知新
孟子「亜聖」(:紀元前372年〜紀元前289年)
仁義王道による政治を説き。
名言「親に親しむは仁なり、長を敬するは義なり、他は無し、之を天下に逹するなり。」
孔子の伝道師と名乗って以前の思想のいいところどりの思想を広め、当時は政治や戦も混戦してきた頃で民衆や政治家に広く受けいれたように見えます。
老子の道教の方が平成、昭和の学校で習ったものに近いとは感じており儒教の方は社会で役立てようという働きを感じます。仁や性善説もありつつ柔軟な思想が今日のビジネスで役立ちそうなのかなと推察してます。
墨子の兼愛説もご紹介。
テキ(紀元前470年頃 - 紀元前390年頃)
利己主義や家族愛、郷土愛、国家愛などの差別的な愛を捨てて、普遍的な愛を説きました。平和主義・博愛主義です。
名言:強弓は引き絞るのが難しい。しかし、一旦矢を放てば、高い所まで届いて深く突き刺さる。駿馬は乗りこなすのが難しい。だが、一旦乗りこなせば、重い荷物を載せて遠くまで駆けていく。すぐれた人材は使いこなすのが難しい。しかし、一旦使いこなせば、君主を導いて輝かしい栄光をもたらす
上記一説、しびれます。
また道義を行うのは名誉を得るためではない。人として当然のことである。
オススメの映画紹介:同じ頃の時代を舞台にしたフィクション映画:墨攻は墨家の知略を持つアンディ・ラウ1人で一国を守った話はカッコ良すぎるので見るべき1作です。
個人的に諸子百家の中でも特に墨子好きです。兵家も法家もよいのですがオススメは墨家です。教養として儒家は必須の上でのプラスαで好きな人増えると嬉しいです。
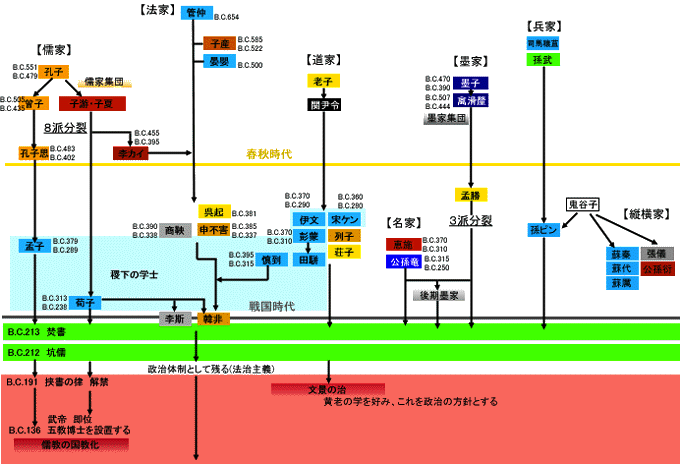
三国志で有名な三国時代前であり記録もあやふやで明確なものが少ない春秋時代は思想家が溢れた時代とも言えます。
現代で諸子百家のような方々が人気になったらアサハラのような摘発対象になりますが昔は娯楽も少なく情報ツールも口コミですのでブームになるのは必然だったことでしよう。
教え自体は現代でも通じる人生の指針になるものではありますのであしからず。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
