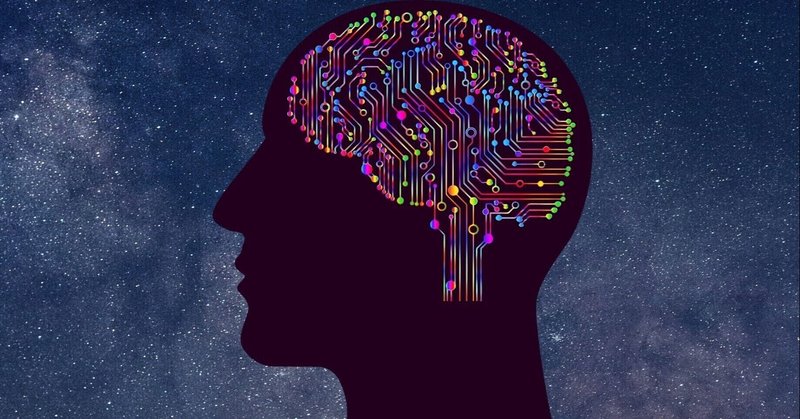
案外嫌いな自分でもない
4年前、大学の合格発表の日、こんなツイートをした。
《ゴーカクハッピョータウン》
▼あっ! 真琴の 受験番号が あらわれた!
▼真琴は どうする?
▶大学生に なる
受験生を つづける
就職先を さがす
▼やったー!人生とむきあう1461日を つかまえた!
軽い気持ちでツイートした気もするし、えも言われぬ覚悟をもってツイートした気もする。どちらにせよ、大学生活は僕にとって本当に「人生とむきあう1461日」だった。親友と出会い、専門知識を蓄え、思想をこねくり回したり子どもとわちゃわちゃしたりした、怒涛の1461日。その中で、最大の収穫だったのは「それは本当に問題か?」と問う姿勢を得たことだと思う。
◆
僕が専攻する特別支援教育は、一昔前まで障害児教育と呼ばれていた分野だ。読んで字の如く、障害のある子どもに対する教育を行うことが目的の学問。
時代の流れに応じて呼び名が変わり、対象とする障害や子どもの在り方が広がり、次々に新しい価値観が生まれている。でも何となく、核が変わっていない感じはある。「何ができないの?」「どういう問題行動を取るの?」「それは何が原因なの?」「どうしたら解決できるの?」をベースにしている、そういう感じ。
特別支援教育は主に何らかの困りごとがある子のためのもの(僕個人としては、別に困っていなくてもいいと思うけれど)だから、その発想になるのは自然だ。教育は、個人的な細かい思想はさておき、俯瞰して見れば「できなかったことを、できるようにする」という営みだと思うから。
でも、1年半前から現場に身を置くようになって、その営みに時々居心地の悪さを感じた。何らかのできなさを「問題行動」と呼ぶ空気が、その「問題行動」を取り除こうと取り組む姿勢が、僕には苦くて不味かったのだ。不登校は何も悪いことじゃないと言いながら、通学できることを目指す大人とか。多様性の尊重を謳いながら、少数者を邪険にする(あるいは、そうせざるを得ない)学校のシステムとか。障害のことだってそうだ。授業中の立ち歩き、学習の遅れ、コミュニケーションの苦手さ、困りごとは子どもの数だけある。僕だって、子ども本人が何とかしたいと望むなら全力を尽くして支えたい。でも実際の「問題行動」のうちの多くで、困っていて解決したがっているのは子ども本人じゃなく、保護者と先生のように見えた。こんな世界線で行われる教育って、一体誰のための何なの?
◆
そんな風に思っているなんて誰かに話したことはないけれど、僕の指導教員はたぶん勘づいている。先生があるエピソードを教えてくれた瞬間、僕らの中で何かが噛み合った感覚があった。
「巡回相談に行った幼稚園に、とにかく水道が好きな子がいてね。何時間でもずーっと水を流して見てるんだって。水がもったいないでしょ。でも先生が水を止めても叱ってもダメだから、何とかしてくれって言うんだよ」
ほう。
「だからさ、私はさ、たらいに水を張って、じょうろで水を流して遊んで見せたわけ。そしたらその子がこっちに来たから、じょうろをあげて、水道止めに行った」
おー、無限水道の完成ですね。
「そりゃね、根本的な解決じゃないって言われたらそれまでだよ。でもさ、あの子にとっての快の遊びってさ、そんなに悪くて奪われるべきものだったと思えないんだよね」
口には出さなかったけれど、僕が感じていたのはそういうモヤモヤだとはっきり分かった。そしてそれに共感してくれる人が目の前にいるのだと安堵した。それ以来、僕はこの姿勢を守ることにしている。
「その問題、本当に解決しなきゃいけませんか。そもそも、その問題って本当に問題ですか」
4年を経て一層面倒くさい人間になっちゃったなぁと呆れながらも、まあ決して悪い成長でもないだろうと、自分では思っていたりして。
いただいたサポートは、大学院での学費として大切に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。
