
北欧ミステリーが面白い! 独特な作品構成をひもとく。
編集部の稲川です。
『このミステリーがすごい2010年度版』(宝島社刊)で、
スウェーデン作品の『ミレニアム1~ドラゴンタトゥーの女~』(スティーグ・ラーソン著)が、海外ミステリー部門第2位になって以来、
北欧ミステリーがブームになりました。
この年の『ミレニアム』シリーズは、『ミレニアム2』が第9位、『ミレニアム3』が第10位と、3冊が同時ランクインする快挙を成し遂げました。
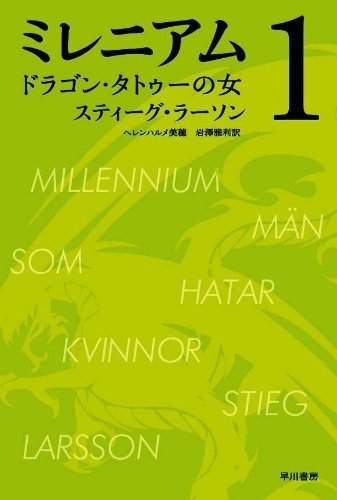
そもそも北欧ミステリーとは、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、アイスランドの5カ国で出版されたミステリーを指します。
その後、毎年のように北欧ミステリーがベスト10に顔を出しています。
【2010年度版】
『ミレニアム1~ドラゴンタトゥーの女~』スティーグ・ラーソン(スウェーデン)
『ミレニアム2~火と戯れる女~』
『ミレニアム3~眠れる女と狂卓の騎士』
【2012年度版】『背後の足跡』ヘニング・マンケル(スウェーデン)【2013年度版】『ファイヤーウォール』ヘニング・マンケル(スウェーデン)
【2014度版】『緑衣の女』アーナルデュル・インドリダソン(アイスランド)
【2015年度版】『北京から来た男』ヘニング・マンケル(スウェーデン)
【2016年度版】『声』アーナルデュル・インドリダソン(アイスランド)
【2017年度版】『熊と踊れ』アンデシュ・ルースルンド、ステファン・トゥンベリ(スウェーデン)
そして、2017年度版の『熊と踊れ』は、『このミス』の海外部門第1位となり、北欧ミステリーがついに頂点に立ちました。

私もとにかく、この北欧ミステリーにはまった1人です。
私はビジネス書の編集者ではありますが、あまりに好きすぎて、ファンの1人として、スウェーデン在住の翻訳家のお1人、久山葉子さんに連絡してしまったほどです。
久山さんが来日された際は、お忙しいお時間を頂戴して、スウェーデンの話をたくさんお聴きすることができました(ミステリーは難しいですが、いつかスウェーデンにまつわる自己啓発的な本を一緒につくりたいと思っています)。
それはさておき、なぜ北欧ミステリーは面白いのか。
ちょっと考察してみようと思います。
◆社会問題を取り上げた骨太ミステリー小説
私がよく読む北欧ミステリーはスウェーデンもの(最も日本で翻訳されている国)ですが、どの本もとにかく分厚い。

写真は12作品でちょうど30センチありました(汗)。
とにかく、文庫本で悠に500ページ以上、上下各巻500頁以上という作品も多くあります(『熊と踊れ』は上巻561ページ、下巻570ページ。これで1位を取ったのですから、すごいことです)。
なぜこんなに長い作品になってしまうのか。
もちろん、どんな海外作品も日本語にすると長くなってしまうということがあります。それにしても北欧ミステリーは破格。
しかし、それでいてその先が気になってしまうという代物ですから侮れません。
また、作家のなかにはミステリー作家というより、面白い肩書を持つ著者が多いのが特徴。
たとえば、犯罪学の教授であったり、新聞記者であったり、脚本家、シナリオライターであったり、編集者であったり、実業家や専門医であったり……。
ベリエ・ヘルストレム(『熊と踊れ』の共著者)などは元服役囚という経歴を持っています。
実はこれ、北欧ミステリー(とくにスウェーデン)の特徴と大いに関わりがあります。しかも、スウェーデンの歴史にも深く関わっているのです。
それは、北欧ミステリーが誕生する背景にあります。
スウェーデンでは、社会問題に対する意識が低かったことを問題視する時代がありました。今でこそ福祉国家として有数の国の1つとして知られていますが、個人を尊重するこの国では、社会問題も個人の問題として意識することが求められました。
そこで、どうしたら社会問題に対する国民の意識を向けられるかを考えた末、新聞記者や編集者、犯罪学の教授などが立ち上がり、ミステリー小説に社会問題を取り入れるということを始めました。
社会問題をミステリー小説にすれば、多くの人がエンターテイメントとして読み、同時に、そこで展開されるテーマ=社会問題を知ることになるからです。
つまり、小説には1つの、あるいは複数の社会問題をベースに起きる事件(殺人事件)が描かれ、読者は否が応でも事件の背景にある問題を考えざるを得なくなるのです。
ですから、社会問題の背景を描くことになりますし、そこでの警察の取り調べなどもよく記されたりしますから、作品ががぜん長くなるというわけです。
しかし、北欧ミステリーに社会問題が描かれることそこが、まさにリアルで、たんなる謎解きミステリーを超える骨太な作品になっているのです。
◆北欧ミステリーにはどんな社会問題が描かれている?
では、ある作品を取り上げて、どんな社会問題が背景に書かれているかを見てみましょう。
私が親しくさせていただいている久山葉子さんの翻訳、『海岸の女たち』(トーヴェ・アルステルダール著)を例に挙げます。
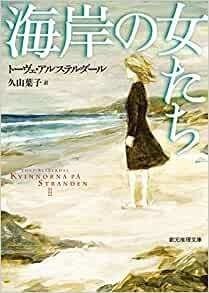
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この物語は、舞台美術家の主人公アリーナ・コーンウォールが、夫でフリージャーナリスト、パトリックの失踪をきっかけに、パリへと向かうことから事件に巻き込まれていきます。
ボストンでの劇場で美術品をあつらえていた彼女のもとに、夫からの分厚い封筒が届きます。郵送先はフランスのパリ。そして、中身は小さな黒い手帳と“写真”と記された1枚のディスク。添えられていた絵葉書には、追伸に「おれが家に戻るまで、これは劇場で保管しておいてくれ」というメッセージが。
夫は何かのネタを追いかけている……。
そう感じた彼女は、夫のネタの売り込み先の雑誌の編集者に会いに行き、夫が追いかけているネタを知ることになります。
それは「人身売買」でした。
実は、夫はアフリカから地中海を渡り、ヨーロッパへ不法に入国する黒人の人身売買の実態を暴こうとしていたのでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
と、ここからはネタバレになるので話を終えますが、この作品のテーマは「アフリカからヨーロッパへの不法移民」という社会問題。
読者は、この作品を読み進めていくうちに、ヨーロッパ社会の闇が受け皿となり不法移民を搾取しているという現実を知るのです。
久山さんのあとがきに、作者がこの作品を書こうと思ったきっかけが書かれていました。
「かつてニュースのレポーターをしていた著者アルステルダールは、地中海で溺れて亡くなるアフリカ人のニュースを現地から報道していたが、その深刻さがスウェーデンの視聴者にきちんと伝わっている実感がもてなかったそうだ。そのうちに、たった二分間のニュース報道ではなく、このことをもっとじっくり伝えたいと思うようになった。これほど大勢の人が地中海で命を落としているというのに、それが黒人だからというだけで、誰もさほど気に留めない。そんな不条理を知ってもらいたくて、人々の運命が交錯する海岸を舞台に小説を書きはじめたのだという」
こうした背景が、北欧ミステリー独特の面白さなのです。
◆北欧ミステリーを10倍楽しく読む方法
北欧ミステリーの特徴として、けっこう猟奇的な殺人事件が多かったりします。
それはそれで、エンターテイメント性を高めているのですが、それはさておき、北欧ミステリーを10倍楽しく読む方法があります。
それは、北欧という美しい街や自然を堪能しながら小説を読む方法です。
私は小説を読む前に、その舞台となる場所をグーグルアースで検索します。
ストックホルムの街並みや、田舎が舞台の美しい自然を先に頭に入れたうえで読み始めると、よりリアルに臨場感が楽しめるのです(北欧にかぎらず、海外作品を読まれる際にもオススメです)。
たとえば、『消えた少年』(アンナ・ヤンソン著、久山葉子訳)の舞台は、スウェーデンのゴッドランド島が舞台。
実は、このゴッドランド島は、あの『魔女の宅急便』でキキが暮らし始める街として知られています。

また、『ピラミッド』(ヘニング・マンケル著、柳沢由美子訳)は、マニングの有名作、ヴァーランダー刑事の若き日の事件を綴った物語ですが、その舞台はデンマーク国境にあるスコーネ地方のなかの田舎イースタという街が舞台。
バルト海に面したこの街をグーグルマップで検索すると、もうイースタの街のイメージが残り、さらにスコーネ地方を動き回るヴァーランダー刑事の活躍ぶりが目に浮かんできます。
はるかなる北欧の地を覗きながら、ミステリー小説に耽るのも、また楽しい読み方なのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
