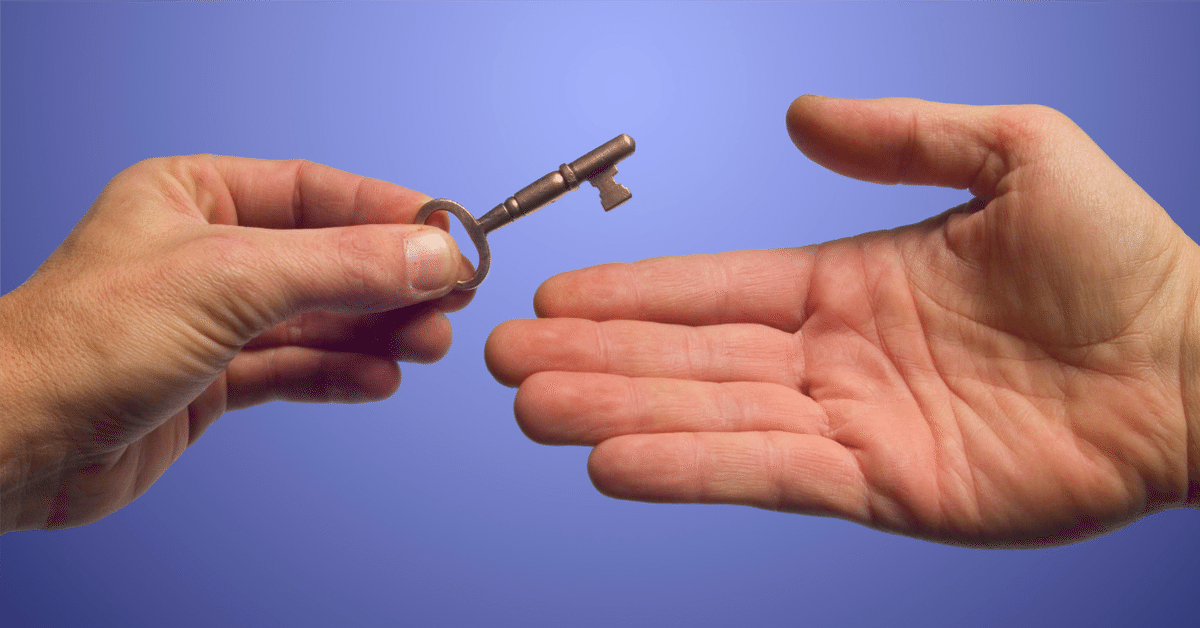
結果が出る権限委譲のコツ
こんにちは窪田です。
前回は部下にかけるべきプレッシャーについて考えてきました。上司は良質なプレッシャーを部下にかけることが健全なチームのあり方だとお伝えしました。
そして、上司が、プレッシャーと同じように部下に与えた方が良いといわれているものがもう一つあります。
なんだかわかりますか?
そう、それは
「権限」です。
今日は「権限委譲」について考えます。
権限委譲は難しい
モノの本でも何かの研修でも、管理職は部下に権限を委譲して、主体性を発揮させるべきというのが最近のマネジメントの主流です。
しかし、私も管理職経験があるのでわかりますが、自分でやった方が早いし、クオリティが高いんですよね。
任せたら任せたで、うまくいかないと納期に間に合わなかったりお客さんにご迷惑がかかったりするので、なかなか判断が難しいです。
本当に、権限委譲をしたら、チームや部下は楽になるのでしょうか?
また、どんなことに注意して委譲すれば良いのでしょうか?
米海軍に学ぶ権限委譲
様々な組織の中で、「上位下達が厳しい組織」といえば、多くの人が思い浮かべるのが「軍隊」です。
上官は頭、下士官は手足、上官の指示は絶対、下士官は奴隷、というイメージが強く、上に行くほど権力が集中し、世界で一番、権限委譲がされない組織というイメージを持っている方も少なくないのではないでしょうか。
今日は、そんな軍隊組織で最も権限委譲が効果を発揮した、アメリカ海軍の潜水艦艦長デビット・マルケの事例で権限委譲について考えてみたいと思います。
マルケが搭乗した潜水艦「サンタフェ号」はマルケ着任後にたった1年で
乗員の残留数0%から100%
本部からの評価 「平均以下」→「平均以上」
乗組員の健康状態 ワースト6→ベスト6
任務遂行能力「平均以下」→「平均以上から優秀」
の成果を上げました。。
マルケは権限委譲を上手に使い、これらの成果を上げたのですが、施策の中で最も効果があった方法の一つに「これから〜をします」と言い方を部下に徹底させたことを挙げています。
この言い方こそ、組織の支配構造を根底から破壊する強力な儀式の一つだったとマルケはのちに振り返ります。
上司に対する
「どうしましょう?」
「何をしましょう?」
という聞き方は、部下に権限やアイデアがないことを象徴していると、マルケはいいます(本当はあったとしても)。
「どうしましょう?」「何をしましょう?」と聞かれた瞬間に答えを出す権限は部下ではなく上官であるマルケに移り、指示を出すためにはマルケが答えを考えなければなりません。
つまりこの聞き方をした瞬間に、問題解決の権限が部下から上司に移ってしまっているということですね。
そこで、マルケは部下の報告に対して自分が「よろしい」の一言で終わるように報告をさせるように指導します。
マルケが「よろしい」というためには、部下はマルケが判断できるだけの情報を収集し、整理して「これから〜をしますがよろしいでしょうか?」という聞き方を使わねばなりません。
最初は「よろしい」の一言をいうために、マルケが部下に質問せざるを得ないことが山ほどあったそうです。質問されて初めて部下は、自分が提供した情報が不十分だったことに気づき、もう一度情報を集めに戻る、ということが繰り返されたそうです。
最初はこうした手戻りが発生することは、日常茶飯事でした。
しかし、続けていくうちに部下が、ことに至った経緯や合理性を完璧に説明するように変わっていきます。
それにつれて次第にチームは高次のレベルでものを考え、表現するスキルを身につけていったそうです。
サンタフェには特別なリーダー育成プログラムなどなく、特別な研修などはありませんでしたが、このコミュニケーションこそがリーダー育成プログラムそのものであったとマルケはいいます。
結果として、マルケが乗船する前と比べ、昇進した下士官の数は1年で1.6倍にも上ったそうです。
権限委譲の注意点
では、権限委譲は万能なのでしょうか?
マルケは、権限委譲に関する注意点も著書の中で述べています。
例えば、「スキル不足のメンバーに権限を与えすぎると混乱が起こる。その役割や職務に対し専門知識があり自分で決断できる状態になければ主導権を与えてはいけない。」と言っています。
誰にでも権限を与えればいいってものではなく、新入社員や異動したてのメンバーなど、スキルが未熟なメンバーは権限を与えるのに、様子を見る必要があります。
例えば、昔私が所属していた会社では、フルフレックスが適用されていましたが、新入社員は1年目は9:00-18:00で定時出勤という決まりがありました。
当時、新卒たちは先輩の働き方を見て「自分たちだけ定時は意味がわからない」とブーブー言っていましたが、基本的な仕事動作を身につけるまでは働き方の権限を付与しないのがセオリーと考えると、正しい判断なのかもしれません。(その理由を納得できるように説明できていればもっと良かったのでしょうが。。)
また、あまり時間がない中で決断を下す必要があるときはどうするのが良いでしょうか。部下に考えさせる時間を十分に取れない場合です。
この場合でもマルケは、短い時間でいいのでチーム全員の意見を募ってから決断を下すことを勧めています。期限があるので、必ずしも全員が合意する必要はないし、合意を強要する必要もないですが、そのプロセスを経ることに意味があると考えています。
また、意見を募る間もなく直ちに決断を下す必要がある時は、リーダーが決断を下します。ただし後からチームに決断の評価を確認することを忘れないように、と釘を指しています。
なぜその決断をしたのか、説明責任をリーダーは負う必要があるからですね。権限委譲は結果に責任を負います。
やり方は自由でも、結果に対しての報告や確認の責任を果たさなければならないところは、「丸投げ」と最も異なるところですね。
今日は権限委譲についてお伝えしました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
