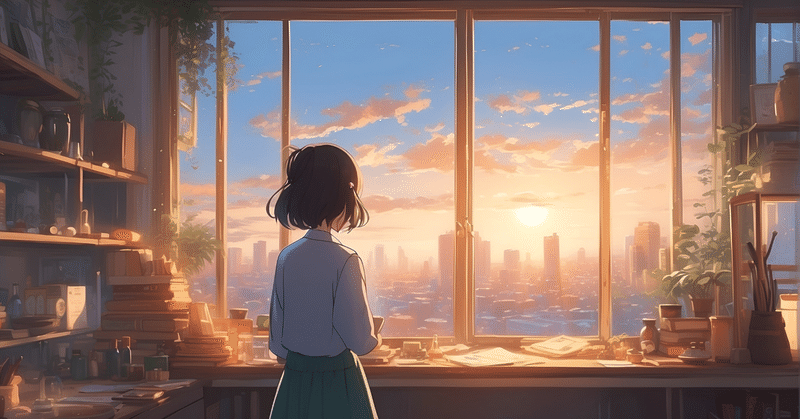
戦略的モラトリアム【大学生活編】(43)
「ごめん、行けそうにないわ……」
弱々しい声、それは電話口の向こう側から。
指導教官の声。それはとてもゆっくりと、そして申し訳なさそうな気持ちが電話口から零れ落ちそうな声で。
ぎっくり腰で起き上がれない。
指導教官に思いもよらぬ災難が降りかかったってわけだ。しかも、それはそのまま自分への災難となって頭から降りかかった。
授業どうする?
給食どうする?
学活どうする?
教頭と数名の先生が職員室のど真ん中で打ち合わせをする。
ボクはただただ、呆然とその後ろで立ち尽くすのみ。
「とりあえず授業行って」
投げやりに自分に話がきた。何が何だか分からずに教科書とラジカセ持って、教室に向かった。
あぁ、追い立てられるように授業をやりきった。
ただただ闇雲に。そして必死に声を上げ、同じことを何回も繰り返す。
そして、昼。給食当番に声をかけ、それぞれの役割を確認。教室中が美味しいにおいで満たされるころに
「いただきますっ!」
あぁ、これが教員ってやつなのか……。くたびれたリクルートスーツを脱ぎ捨て、ワイシャツにネクタイを胸ポケットに押し込んだ、だらしない教育実習生の自分が多少なりとも充実感に満たされ、牛乳を飲みほした。
そこには確かに「やりがい」にも似た達成感のようなものがあったのかもしれない。
しかし一方で、あの時……自分がこいつらの歳のときはどうだったのだろう。
荒れ果てた学校。喫煙をはじめとするあらゆる不可能が可能となった学校。
嘘みたいな出来事がホントに起こっていた学校。
そんな中で、今自分が味わったような気持ち先生にはあったのだろうか。
きっと、そこには何もない虚無の疲弊しかなかったはずだ。少なくとも自分はそう思う。そこすら喜びに変えられる人間なんているはずがないんだ。
自分はそう思い込んだ。そうだ、あの時に自分の行動は、学校に行かないと決めた行動は少なくとも間違いではなかった。そう、学校全てがこんな充実感に満たされたものであるはずがない。
自分は今の気持ちをかき消すように「すべてがこうだ」と妄信してしまうようなことはしたくなかった。それは学校というものを全肯定するものだとかんじたから。そして、あのときの自分が間違いだったと認めてしまうことが何より悔しかったから。
昼休み、職員室に戻ると
「もうプロだな。教員の顔になってるよ」
先生方からほほえましいチャチャが入った。愛想笑いをしていたが、決してこの業界に飲み込まれたわけではない。自分が20数年歩んできたことは、間違いではなかったはずだ。
今の充実感が全てではないと自分に言い聞かせながら、午後の授業準備をするのだった。
何とも滑稽でおかしな自分を心の中でほくそ笑んでいた。
福島県のどこかに住んでいます。 震災後、幾多の出会いと別れを繰り返しながら何とか生きています。最近、震災直後のことを文字として残しておこうと考えました。あのとき決して報道されることのなかった真実の出来事を。 愛読書《about a boy》
