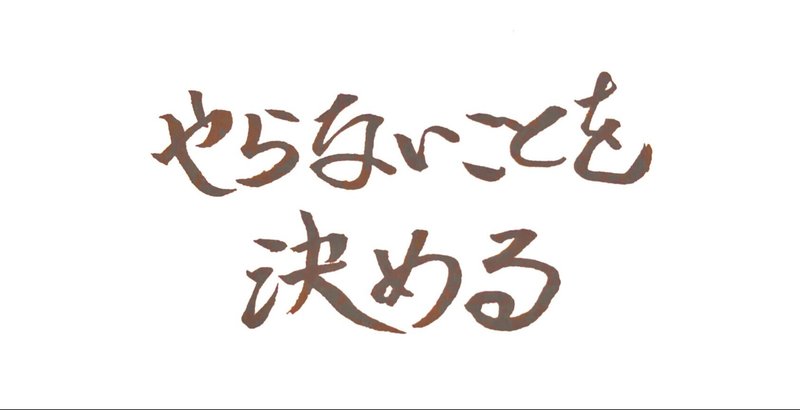
19話目 「わたしの知的生産の技術」はマジで名著ですよ、という話。
前回に引き続き、「わたしの知的生産の技術」PART1は本当に面白い本だ。
この記事でAmazonの中古本の価格は上がってしまう可能性もあるが(現在2022.2.10時点で、95円)「書きぬき」をまとめておく。(太字強調は筆者)。
・「博物館というものは、ほんとうは博情館でなければならないといわれる。あつかうのは、「物」よりむしろ「情報」なのだ。」p.6
・「必要なものは、知的生産の技術を駆使して偉大なる生産をやってやろうという、知的情熱なのである。この点は、まったく意外なことだったが、かなりひろく誤解があるようだ。」p.7
・「独創的なアイデアがひらめくということには、少なくとも情報の交錯が必要です。別の言葉でいえば、この道一筋的に同じ種類の情報ばかりを積み重ねただけでは独創は絶対に生まれてこない。(中略)俳句だけを五十年やってきましたというような人の俳句でろくなもののあったためしはない。(中略)湯川秀樹君が中間子を発見したのも、中間子と物理のことばかり考えていたから出てきたのではありません。アインシュタインらの新理論を研究するいっぽう、老子や荘子を相当熱心に勉強していたことが役にたっているのではないかと思います。」p.18
・「ただ人間の才能の可能性は生まれた時におおよそ決まっています。ただそれが十分開発されるかどうか、ここに大きな問題がある。」p.27
・「湯川秀樹君はノーベル賞をもらったが、月給においては一生かかっても桑原武夫をぬけなかった。何故か、彼のほうが二年遅く大学を出たからです。これが日本の大学制度なのです。」p.28
・「フランスのアランの言葉に、人間は幸福である義務をもつというのがあって、私はこれにひどく感銘しました。」p.30
・「これだけ地球上の無機物と有機物、あるいは生物同士がうまいこといっとるというのは、やっぱり、よそから入って来たものがおらんからだろうという気持があります。それで、隕石について来たという説をとりあげていないのです。」p.34
・「単独生活能力を身につけるということ、つまり人にも迷惑かけんし、人の世話にもならん。そういう、なにか、悪くいえば世捨人、そういう心境をひらくことが必要なのかと思いますね。」p.46
・「実験や観察、すなわち、実証を伴うことが、科学が科学であることの必要条件です。」p.58
・「これによって、科学であることの必要にして十分な条件は、 一、科学は理論と実証の統合である 二、理論とは完全理論である 三、実証とは完全な実証計画法を伴った実証である の三つであることが明らかになりました。」p.66
・「心理学では、原理的に実験は可能である→しかし、人間を対象にしての実験はできない→したがって、最も簡単なネズミからはじめる→そして、はるか人間に迫ろうとする。心理学はこのように大きな迂回と犠牲をはらってようやく科学的実験方法を獲得しました。」p.69
・「たとえていえば、碁の名人が十手先、二十手先を読めるから名人といわれるように、学問も一手、石を置いて全局を見きわめるくらいに深まらなければ本当ではありません。経済学は一般均衡論によってはじめてこの任をはたし、最先進科学の栄誉をになうことができるようになりました。」p.70
・「科学とは現象を認識するための一手段ですが、どうしても現象の一側面しかみない。さらにいえば、現象のある部分をきりとりモデルをつくって、研究者の目的に合わせた連関の上においてのみ見ようとする。だから、森羅万象をまるごと対象にして、直観的に悟るといった哲学や宗教と根本的にちがいます。」p.77
・「それは、学問間にある方法論的格差を利用するということなんです。学問というものは進んでいるものもあればおくれているものもある。それは世界歴史に似ていまして、よい仕事は未開社会にあります。」p.80
・「私の意見を申しますと、特定の個人は専門バカであってよろしい。しかし、学界全体が専門バカでは困るということです。」p.86
・「ほんとうのインターディシプリナリー(学際的)というのは、二つ以上の学問で専門家として通用しなければダメです。」p.87
・「漱石は文学論の中で自分は西洋の文学に対して、東洋の文学に対して払った以上の時間と努力を払ったけれどもよく分からないと言っています。つまり彼我のコンテクストはついに重なりをもつことができなかったということを別な言葉で言っているのです。漱石が指摘したこの深刻な問題に明治以降の日本は直面しつづけていたのです。」p.104
・「アルファ読みからベータ読みへの移行、音読から黙読への移行はどうするかというと具体的に方法は一つしかありません。文学作品を読むことです。」p.111
・「本は読んだら栄養が吸収され、毒素が出切ってしまうまでの期間、暫くはちょっとぼんやりしていないと駄目です。Aの本を読んだら息もつかせずBの本を読む。これは若い勉強家と称する人がよくやりますけれども、頭が悪くなります。朝から晩まで食いっぱなしというようなことですと、消化不良をおこすにきまっています。」p.115
・「二十回読んだという本が五冊あれば、りっぱな読書家です。(中略)しかし、そういう本にめぐり会うにはやはり、たくさんの無駄な読書をする覚悟が必要です。」p.115
・「ショーペンハウエルが読書の害を説いたのは有名で、自分で見ることをやめて、本という眼で物を見るようになっては読書は害あって益ないものであると大胆率直に述べています。」p.119
・「大工さんは新しい生木で家を建てないものです。新刊書と雑誌だけで我々の精神の家を建てると、しばらくしてひずみが出てきます。」p.120
・「日記でも手紙でも心を込めて毎日書いて、それを早い速度で書いて、それが早いなりに深みをもつようになる。そういう書き方がいいのではないかと思いますけれども、これは言うは易くして行うは難しでしょう。」p.124
・「もちろん、答えるよりも問うほうがはるかにむずかしい。(中略)根源的創造は、ものごとの本質を疑ってかかるところにおいてのみ可能である。ギリシャ人が近代の諸学問のほとんどすべての基礎を固めることができたのは、彼らが、なぜ? という問を出すことにきわめてすぐれていたからだといわれている。」p.128
・「飲んでいるだけではしかたがない。自分でもひとつ酒をつくってみよう。これだけ酒にしたしんできたのだから、見よう見まねでなんとか酒らしいものができるのではあるまいか。そんなノンキな気持で論文づくりにかかるから、ひどい目にあうのである。いくら酒を飲んでも、酒飲みは造り酒屋ではない。酒の通人だからといって、酒がつくれるわけではない。(中略)われわれとしては、「うまいカクテルよりもまずい地酒を」を旗じるしにしようではないか。」p.131
・「昔の中国の人が「三上」ということをいった。文章の妙案を得るのに好都合なところが三つある。すなわち、鞍上、枕上、厠上。」p.135
・「調査するということに、時間などの限界もありますが、やはり見るものを大切にして徹底的に調査するということは論文の勝負所です。」p.152
・「以上のべた四つの要因、関心、調査、共感、機会がそろっていれば、どんな論文でも小説でもその他の形式の文章でもおもしろいと思います。」p.157
・「論文でいちばん大切なことは、人に理解できるように書くということだと思います。これには形式がきちんとしていること。起承転結がなくてはいけないと思います。」p.160
・「しかし、取材について経験的に学んだことは、まず「なりふりかまわず誰にでも聞く」ということです。」p.172
・「この道一筋、関係ないものは、みなクズカゴに入れる――という人は、優等生の論文は書けるかもしれませんが、意外な事実の発見はできないというわけです。」p.174
・「いつか大宅さんが私に教えてくださり、いまでも守っていることがあるのですが、それは「どんなくだらないものでも、活字になったものは捨てるな」ということです。」p.176
・「私たちはしばしば散歩の楽しみを忘れてしまいがちです。用があるから歩く、用がなければ歩かない――この姿勢を捨てないかぎり、知的生産のベースは出てこないのではないでしょうか。」p.178
・「雪見、月見、花見というように、季節ごとにものを見ることが娯楽になっている文化がはたして世界中にあるだろうかと考えてみると、あまりないようです。」p.181
・「一億一千万人もの日本人全部が知的生産をやっていたのでは、世界中の怨嗟のまとになって日本はいずれ滅びるしかありません。知的生産が国民運動にまでならないように、ひたすら祈る次第です。」p.182
・「これも国立国語研究所の統計ですが、ごく日常の会話を喫茶店とか井戸端とか、人の集まるところに隠しマイクを据えつけてこっそり収録した会話を分析すると普通の会話の70パーセントは不要な言葉から成り立っていて、残りの30パーセントで意味が通じているという結果が出た。」p.239
・「文章というものは、どんなに名文を読んでもよい話を聴いても上手になれない。自分で書かなければ上達しない。」p.254
・「ところが、いざ能動的知的生活に入ろうとするならば、最低四時間以上とれない場合は、何もはじめないほうがいい。カントは四時間とれなければものを書かなかった。」p.265
・「この「目的」と「手段」という大切なことが、どうしても日本のような後進資本主義国では逆になりがちです。」p.270
・「日本の国立国会図書館は夕方五時にしまってしまうのに、外国のナショナル・ライブラリーは閉館は午後十時です。ハーバード大学の図書館などは、二十四時間やっています。(当時)夕方五時に閉館してしまう日本の図書館に、労働者はいつ行くことができるのでしょうか。」p.300
・「映画と比較してテレビは、こうした時代考証は、ほとんどなされていないといっても過言ではない。」p.304
・「溝口健二監督は、「調査は徹底的にやれ、その上で嘘をつけ」というのが口癖であったという。」p.305
・「映画で最も大事なのは企画であり、シナリオ(脚本)づくりである。」p.312
・「映画音楽家は単に作曲のみでなくて、録音技師とともに川の流れの音、鳥の鳴き声、電車の音、すべての効果音の扱いに責任を持ち、計算のできる人でなければならない。そういう選ばれた人たちは、日本には非常に少ない。」p.317
・「質問者A 映画を作るのに映画監督は実に多数のスタッフ、キャストをひっぱって行かれるわけですが、その牽引力は何ですか。
熊井 「自信」だと思います。自信を持って仕事をすることです。スタッフや俳優に、迷っている様子を見せたら動揺します。」p.321
・「多くの知的生産者に会っていちように感じることは、まず、彼等がものごとを純粋に論理によってすじみちをたてて考える訓練ができているということである。(中略)彼等のあたまの中を解剖してみると、ラック倉庫のようになっていてそれも太い幹のところと枝葉の部分に分かれていて、それぞれ仕入れた知識・情報をどの枝のどのひきだしにしまっておくか優先順位の原則がはっきりしているようだ。」p.332
・「この意味で読書は自分を発見し、育てていく過程であるといってよい。」p.334
・「つまり行動は、他人の知らないデータを手に入れる唯一の方法なのである。」p.337
・「知的生産というものは要するに目的意識があるかないかできまる。」p.340
・「私はたくさんの知的生産者とお会いしたが、この人達で麻雀をするという人に会ったことがない。(中略)知的生産者にとっていちばん貴重なものは時間であって、彼等にとって麻雀をするヒマは絶対にないと言ってよい。」p.345
・「私は知的生産者が頭脳的に強い理由は古典の多読にあるとみている。」p.351
本当にいい本です。おすすめ。
いいねとスキ!フォローをお願いいたします。
よろしければサポートお願い致します。いただいたサポートはこれからの投資のために使わせていただきます。
