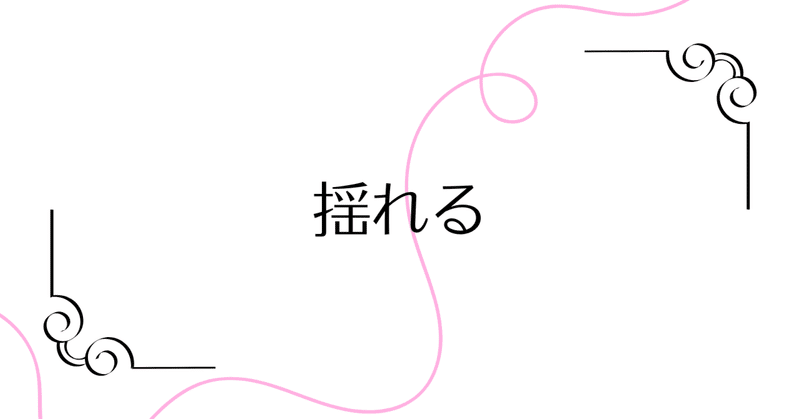
【小説】揺れる
その町への年間移住者数は数年前から僅かながら上昇の一途を辿っていた。元々特別人口の少ない地域では無かったが、役場に新設した「町おこし課」へ都会に進学した出身者のUターン採用を行ったことが功を奏したのである。山間に位置するため緑豊かな環境なのは勿論のこと、育児補助制度の充実やスローライフの確約といった魅力は現代に合ったPRの手法で巧みに拡散され、先月にはローカル番組ではあるものの特集の案件が打診される程となった。
現在、古民家の縁側で手をついて足を放り出している男もつい先日越してきたばかりである。手元には一枚両面刷りのアンケート用紙。この町への移住を決意した動機や、魅力はどこだと思うか、何でこの町のことを知ったのかといった質問が十個のQを頭に連ねられていた。
八月も中旬。風は全く鳴りを潜めている。男は額に汗粒を浮かせながら、ここに来る前の出来事を思い返していた。
「んんっ……っふぅ……」
悟が風呂から上がり背伸びをしてどこの骨かもわからない骨をぽきぽきと鳴らす頃にはとっくに日を跨いでおり、テレビではよく分からないどこかで見たことのあるような陽気な女性が宝石の加工品の宣伝をしていた。特にどこどこが痛いという訳でもなく全身に鈍い重さを抱えているものの何とはなしに腰をさすりながらリモコンのスイッチを押し電気を消すと、窓から差し込む外の街灯が部屋唯一の光源に換わる。
三浦悟は今年三十二歳を迎えた。大学最後の年、特に就きたい職業や理想があった訳でも無かった彼はなんとなく参加した会社説明会を主催していたなんとなく良いと思った企業に就職し、現在は特段感情の動くことも無い日々を過ごしている。
と言うよりも、逐一そんなものが作動していたのでは精神衛生上異常を来すと防衛本能が代わりにエネルギーを消費するようになったと言った方が適切である。
彼の就職先は転勤の多い業界に位置することもあり、現在の店舗に落ち着いたのは四年前のこと。その前に担当した三店舗では何れも人、特に上司に恵まれ、常時残業時間は長かったもののその時間も苦にならない程にチームプレーの上手く効いた明るい職場であった。
今となってはその経験が幸だったのか不幸だったのか定かではないが、その分に彼の職場への精神的苦痛が増幅したことは確かである。パワハラ、セクハラ、同僚の失踪。同じ企業内でこれほどの差があるのかと絶句しながらも店長のワンマンプレーに水を差すほどの気力は配属一週間で失せてしまっていた。俺もそろそろ店長職だぞ、といった気概などどうなったのかは言うまでもない。そうして彼は彼自身を決定づける何かを持たないままに三十台を迎えることとなった。
ただ一つ強いて特異な何かを挙げるとすれば、彼は所謂事故物件に住んでいる。
幼い頃からそういった物事に関心を寄せなかった彼は恐れる恐れない以前に霊的存在やオカルトにあまりにも疎く、安くなるなら別にいいんじゃないですかね、という理由からこれぞ節約の知恵とばかりにアパートの一室を根城に選んだ。
六畳一間の和室。海の日を見送りながら、彼は寝返りを打ってそういえばそうだったと電気からぶら下がる紐の揺れを見ていた。というのもここ数日、窓も開けていないのにいきなり紐が大きく揺れる光景を連続して目の当たりにしており、主に仕事の疲れから相手にしていなかったものの明日が休暇である余裕から今回はと脳が重い腰を上げてくれたのである。
前述の通り彼は霊的なものに疎く、よって恐怖を抱かない。久しぶりに友達がつくれるような好奇心すら秘めながら、ばかばかしいという考えを脇に嬉々として話しかけた。
「えっと、こんばんは。俺、三浦悟って言います。今年で三十二になる、えー、冴えない男です、はは」
紐の揺れは治まらず、大きく綺麗な楕円形を描きながらくるくると回っている。ただ、話しかけた瞬間だけはぴたりと物理法則を無視した位置で静止したのを彼は目視した。
久しぶりに気兼ねなく誰かと話せそうだ、と話を続ける。
「これでも小学生、中学生だった頃はサッカーとかやってて、夢はサッカー選手だ、とか言ってたんですよ。今じゃこんなんになっちゃったんですけど、はは」
絶えず紐は回転を続けている。
「俺の友達も皆聞く所だと、って直接聞いた訳じゃないんですけどね、そこそこな偉い立場になり始めてるみたいで。たまたまこの間テレビに映ってた奴なんて起業して、最近軌道に乗り始めたとか。ははっ、いやぁ、本当そう言うの聞くと俺って……」
ここまで続けて悟は口を噤む。この先まで言おうと言わなかろうと何が変わる訳でも無いことは重々承知の上で、声として形作ることになんとなく抵抗を覚えた。とうとう俺もこういうのに縋るようになっちまったかぁ、いやいや途中で我に帰れて良かった良かった。即席の理由で口を閉ざしたことを誤魔化して、悟はぐったりと床に伏した。
翌日、悟が目を覚ますとオレンジ色に輝く雲が窓越しに見え、もう朝かと思いテレビを点けると左上には夕方の時刻が表示されていた。はは、と乾いた笑みを浮かべてどうせなら夜まで眠ろうかと思うと、頭にゴミが付いた感覚がある。腕を伸ばして取ろうとすると、それはゴミではなく例の紐だと確認できた。やはり風は吹いていないし、何か外部的な力が加わらなければ有り得ない程に紐はぴんと張っている。こうなってしまっては流石に頭がおかしいとかそういうのではなく、物件が本領を発揮してきたのだと認めざるを得ない。そう考えつつも相変わらず恐怖は全く感じていなかった。
昨晩同様、悟は声を掛ける。
「おはようございます。あ、いやもう、こんばんはですかね。いやぁ、折角の休日だったんですけど、いつも結局こんな感じになって寝るだけなんですよねぇ。はは」
紐は頭を離れると直ぐに、例によって楕円形の弧を描き始めた。
「そういえば昨日から俺が話しっぱなしですけど、あなたについて何も聞いてなかったんでしたね。まぁ、話してもらうって言うのも、難しいんでしょうけど。はは」
すると紐は悟の予想に反してぴたりと動きを止め、しばらく人で言えば考えるようにしてから、部屋の隅に置いてあるビジネスバッグの方に先程同様ぴんと張り詰めた。
「バッグ……ですか? 生前は営業職とかに勤められていたんですかね。ここの紹介してもらう時に不動産の人もなんか話していたんですけど、ちゃんと聞いてればよかったな、はは痛っ」
ぴしりとおでこを打って、もう一度同じ方向にぴんと紐が伸びる。咄嗟に痛っとは発したものの特に痛みは感じていなかった。そういうことではない、という明確な意思が伝わる。
「すいません、疎くて。えっと、じゃあとりあえずバッグをお持ちしますね」
紐の届く所まで抱える形でバッグを移動させると、シュルシュルと器用にチャックを開けてから、中から二本のペンを取り出した。お気に召さなかったのか、会社のロゴが入っていたボールペンは投げるようにバッグの底に返却される。
「ペン、ああもしかしてそれで書いて、筆談ってことですかね! 紙、印刷用紙とかそこら辺にあったと思うんで、ちょっと待って……あ、あったあった。これもあった方がいいか。これでどうですか?」
下敷きとA4のコピー用紙を紐の書きやすいであろう位置まで悟が掲げると、そうそう、とでも言うかのように紐はすらすらとペンを動かし始めた。悟は内心興奮気味であり、紐が書き終わると早速用紙を見る。
「えぇと、私は樹里と申し、えぇっ! 女性の方だったんですね。すいません、てっきり私、男友達と話すみたいに話してて、いやぁ、お恥ずかしい。あ、ええっと。お仕事大変ですね、毎日お疲れ様です、でも誰かの為に一生懸命頑張るあなたは……いやぁ、んはは……あっ、すいませんね、本当、すいません」
久しぶりに悟は喉元に熱い詰まりを覚えて、すぐに頬骨の上を涙が流れた。
「いやぁ、なんか、こういうの仕事の他で言ってもらったのって久しぶりで。なんか、良いですね。自分ちだから気抜けちゃったのかなぁ。あ、あなたの家でもあったんですね。仕事場でも別に、言ってもらえる人っていないんですけど、ははっ」
紐は迷ったように揺れた後、彼の頭に何度かぽすんぽすんと自身をうちつける。悟はきっと慰めてくれているのだろうと感じた。
「まさか、はは、三十にもなってこんな、ね。両親にも仕事はうまくいってるよ、なんて言ってるもんですから、中々。後輩にも前、懐いてくれてる子がいたんですけどね。俺を庇って店長と喧嘩しちゃって、そのまま手紙だけ置いてどっか行っちゃったんです。だからどっか、自分さえ我慢してれば、って思ってたんですけどね……」
紐が頭に巻き付く。長さが足りないから腰までは届かないけれど、という優しさを悟は確かに受け取った。孫悟空のあれみたいですね、と泣き笑うとぴしりとまた叩かれる。
「はは、いや、俺は元々こんな感じでとぼけるのが好きなんです。すいません。でもなんか、こういうの久しぶりです。本当に……」
悟はこの夜、即席麺をすすって風呂に入るとすぐに寝た。いつもよりもずっと寝つきが良く、それを見た紐は誰にも知られずに嬉しげに揺れた。
それからは悟にとってしばらくぶりの楽しい日々となった。帰れば話し相手が待っているのだ。どんな趣味があった、どんな食べ物が好きだった、勤め先では今日どんなことがあった。クレーマー対処の事例ですら話題の一つとなる。
反面、当然とも言えるが暗い雰囲気も合間合間に差し込まれることがあった。今がどうであれここは事故物件。樹里と名乗った女性がここにいる事実は彼女が地縛霊化してしまっているということでもある。彼女が話しにくそうにしているのを無理に追及するほど悟には度胸が無かったが、話の中でそれとなく彼女について察していくことも多かった。子どもはいなかったこと、好きだった仕事は結婚相手に辞めさせられたこと、その相手は頻繁にDVを繰り返していたこと。時折見せる身の引き方が、長年のストレスと恐怖によって出来上がった忌むべき代物であるのだろう。憶測には過ぎないそういった様々な情報に確信を持ちつつ、彼は避けるべき話題を一つ一つ見つけていった。
そんな共同生活の中で、悟にとって一番の驚きとなったのは料理だった。発端は悟の一言。
「この紐、もうちょっと長かったらなんか、できることとか増えますかね。俺出勤してる時とか暇だったらテレビとか見れるかもですし。あ、でも紐変えると問題とか……」
言った後に余計なことを持ち掛けたか、と悟は後悔した。それは彼女が紐に憑いている理由を察していたからである。所々気にならない程度ではあるものの畳や壁が傷んでいる中で、電気の紐だけは異様に新しかった。
とはいえ、彼の気遣いは杞憂に終わる。彼女の同意後あっけなく紐が取り外されると、今度は床に垂れ下がる程の紐へと問題なく寄生木を移した。
物を変えても取り憑く先が変わらなかったことにほんの少し悟は寂しさを覚えたが、そんな思いは一瞬で樹里に吹き飛ばされることになる。紐を変えて直ぐに彼女はピュンと小さな台所へ飛ぶと庖丁を巻きつけて戻ってきたのだ。これには悟もひぇっという情けない声が出したが、意図を察してほんの少し照れた。
「えっ、いやその、本当にいいんですか? 俺なんてそんな大した痛っ」
柄で叩かれて頬を抑えているとその間にペンに持ち替えていた樹里は、いいからこの錆びた庖丁の代わりと食材明日買ってきてください、と紙に書いていた。わかりましたと言いつつ悟は、隣の部屋が空いていて良かった、と頭に浮かべていた。冷静に考えて誰もいない部屋で調理の音が聞こえたら多くの人は怖いのだろう、と考えた為である。
「うわぁ、おいしい! なんか、しばらくぶりに人の手がかかった料理食べました。煮物なんて本当久しぶりで……子どもの頃ババ臭いとか言って好きじゃなかったんですけど、いやぁ、俺もおじさんになってきてるんですかね、はは。本当……おいしいです」
樹里は照れ隠しのように悟が口を付けるまでテレビを見ていたようであるが、初めての彼女の手料理に悟がそんなことを言っていると、しゅるしゅると近付いてきて体にそっと巻き付いた。悟にはそれが喜んでいるようにも泣いているようにも見えた。きっとどちらもなのだろうと思ったのでもう一度、おいしい、と言った。
そうして二週間が過ぎた日の夜。彼が帰るとテーブルには以前好きだと話したオムライスをメインに、サラダやオレンジジュースなどが並んでいた。早速部屋着に着替えてあぐらを組み、いただきます、と手を合わせる。
「いつも本当に料理お上手だと思いますけど、今日は前に好きだって言ってたの作ってくれたんですね。いやぁ、なんか好きだって言ったのは俺なんですけど、ちょっと子どもっぽい感じで恥ずかしいですね、ははは」
オムライスの中央にはつまようじとコピー用紙で作った旗が立っていた。中央には赤のボールペンで書かれたハートマーク。紐はいつも通りに床にだらと垂れ下がっている。何となく元気が感じられないな、と思ったものの特に追及はしなかった。
「じゃあ、いただきます!」
食べ進めながら、悟はいつもよりも特に美味しく感じていた。好物を食べていることを差し引いても、所謂愛情が籠っているとかテレビで聞く、体内があたたかさで満たされる感覚。
胸の温度が上がっていくような思いを抱きながら完食すると、ごちそうさまでした、と言うのと同時に彼は意識を失った。
気を取り戻した時に先ず初め、彼の視界に入ったのは立派な梁と天井。どこか知らない片田舎の古民家であることは周囲ののどかな景色と空気感も含めて分かったが、それ以外のことは自分が何故ここにいるのかも含めて何一つ分からない。ただ、自身の体がひたすらにだるさを帯びていることだけは確かだった。
一息ついて三分も経たない内にドキリとして時計を探す。部屋を見回してもカレンダーしか見つからなかったが、気を失った日から二週間が経過していることは分かった。一体どれ程の悪態を吐かれるのだろう。それでもきっと辞めさせられることは無い。彼は体の芯をすっと冷やし、とにかく連絡だとスマートフォンが入っているらしいポケットに手を伸ばして手帳型のケースを開く。
すると中には二枚の紙が挟まっていた。一枚は両面びっしりと文字が書かれたもの。もう一枚は何かが包まれたもの。その紙はどこかあたたかく、さみしく、書き手を直感させる。
彼の察した通り、その字は何度も見た樹里のものだった。
<悟君へ
はじめに、ごめんなさい。私は君に相談もせず、私情だけで勝手なことをしてしまいました。本当にごめんなさい。これから君が気を失っている間に私がしたことを記します。何か不可解な連絡などが届いたら、恐らくそれは全て私のせいです。
まず私は君の思っている通り、夫のDVが苦痛であの場所に縛られることとなってしまいました。君はとても優しいから私の辛いと思うような話は避けてくれていたんだよね。きっと、その憶測は全て当たっているのだと思います。ただ、夫の正体については気付いていなかったのでしょう。
その相手は正に君が働いている先の店長をしている男です。どんな人かは君が良く知っている通りです。私は君が話しかけてくれる前からも、いつかこの住人を利用してあの男へ報復してやろう、と考えていたのです。本当にごめんなさい。でも結果的にそうなってしまいました。
私はあの家で紐に取り憑く形になったけど(その理由もおそらく気付いていたと思います)、君はペンや庖丁を私に与えてくれましたね。私も初めは使えるかどうか分からなかったけど、文字が書けて以来私は紐に触れた物は寄生先にできることを知りました。あなたとの生活はとても楽しかったけど、心の底では調理後に料理に取り憑けばそれを伝ってあなたも操れるのではないかと庖丁に触れたその日から考えていました。君が料理を食べて直ぐに倒れたのはそれが成功したということです。
次の日に私は早速、私を縛り付けた元凶に会いに行く決意をしました。家を出られるかは不安でしたが、寄生主が君だったからか未練を絶ちに行くからか、特に問題はありませんでした。
そして生前の記憶を頼りに店を訪れた私は、奴の姿を見るや否や殴りつけて、君から聞いていた君の愚痴を喚き散らしました。生前出来なかったことも、あなたの鬱憤を晴らすためだと思うと何の躊躇も無く吐き出すことができました。止まりませんでした。警察沙汰になりかけもしましたが、電話をする直前に私の名前を出すと奴は狼狽えておとなしくなりました。奴は戦意を喪失したはずですが、もし今後何かがあったら申し訳ありません。
ただ、ここからが誤算でした。私は私の後悔を晴らすことができたら自然と君の体から出ていくことができると思っていたのですが、どうやらそういう訳にもいきませんでした。そこで私は君のこの先のことを勝手に心配してしまっているからだと気付きました。君の言う店長がどんな人間かは私がよく知っています。そんな奴の下にやさしい君を置いておきたくなかった。未だ狼狽えている奴に私は退職に必要な一式をその場で作成して突きつけることにしました。実はそういった作業は得意だったんです。働いていた頃はこれでも優秀だったんですよ。
それから私は引っ越すことにしました。君も私も、住んでいたあの場所にいたのでは何からも解放されないのだとまた勝手に考えて、少し不便かもしれませんが緑豊かな地域へと住む場所を移させてもらいました。私は今その町でこの手紙を書いています。
これが君が気を失っている時にさせてもらったことです。
改めて、本当にごめんなさい。でも私は本当に勝手だけど、すごく、すっきりしています。きっと手紙を書き終えたら霊としてもいなくなるのかな、と思っています。
君との生活は本当に楽しかったです。ごはん、おいしいって言ってもらえたこと、本当に嬉しかった。名残惜しいけど、君とはこれでお別れになります。悟君が元気でいられることを見守っています。
樹里より>
少し困惑して、そして直ぐに泣きそうになったので、悟は鼻の奥にぐっと力を込めて涙を抑えるようにした。ただ、もう一枚の紙を開くと、結局その行動は意味をなさなかった。
包みの内側にはありがとうと大きく書かれていて、卵黄のシミの付いた紐が入っていた。
額の汗粒はまとまって、頬を伝って顎を垂れる。半袖Tシャツの袖口でぐいと拭いながら、彼は古めかしいちゃぶ台の上でカリカリとアンケートに回答していく。移住動機の元に緑が豊かだったからと書いて、すぐに樹里さんはこの町出身だったのではないかとふと思った。
記入を終えて縁側に横になりながら、ぼんやりと今後のことを考える。三十二かぁ、まだ何でもできる年だよなぁ、と呟きながら、自分の将来なんて久しぶりに考えたな、と悟は思った。少しはは、と笑う。笑みは乾いていなかった。
視界の先で、風鈴の短冊が揺れる。
創作の原動力になります。 何か私の作品に心動かされるものがございましたら、宜しくお願いします。
