
RPGの中の自分
もうだいぶ前の話になりますが、noteを拝見していたら、ともやさんという方が書かれた面白い記事を見つけました。
今回はこちらの記事をリスペクトしてみたいと思います。今日はたくさん書きますよ!
4種類の人のタイプ
人間を4種類のタイプに大別できるというお話でした。
それは「リーダー」「クリエイター」「パフォーマー」「サポーター」となっていました。それらが示す行動を取っているときに、1番疲れなくて喜びを感じそうなのが自分のタイプなのでしょうか?
あなたはどうでしょうか?
えんじろうは「リーダー」が最も遠い存在のように思いますが、音楽作ったりするしやっぱり「クリエーター」タイプなのかなと思いました。
ところがその先の文を読んでいくと、あれっもしかして違うかもと思えてきたのです。
ゲームで例える
ともやさんはそれをゲームのRPGのキャラクターに例えておられたのですね。それを見たら急に親近感を覚えて、自分はどれに当てはまるのかが気になりました。
というわけで列挙しますが、ここはやっぱりえんじろうが親しんでいたファミコンに合わせて「ひらがな」で書きます!
ゆうしゃ
リーダータイプはRPGの主役である勇者に当てはまり、目的を定めて仲間を集めまとめ上げるのが得意。
まほうつかい
クリエーターはRPGの世界では魔法使いとなり、存在していないものを具現化する力を持つのだそうです。僕は無から作るというよりも、要素同士をかけ合わせて力のある状態を作るというイメージですね。
せんし
パフォーマーはRPGだと戦士に該当し、前線に立ちその武芸で道を切り開く者だそうです。現実世界なら人前で何らかの能力(芸当)を発揮する者ということになるでしょうか?
そうりょ
サポーターはRPGならば僧侶で、仲間を癒す他に支援魔法を駆使して間接的に力を貸すという立場のようです。
さあ、あなたはこれらを自分に当てはめたときに、どれがしっくりきますか?多分恥ずかしさはあってもその役割を果たすときに1番落ち着いていられそうなのが該当職ということなのではないかと思います。
えんじろうの答え
これらを想像すると、結構どの要素も多少は持っているのだということに気が付きます。えんじろうの場合は、要素を全く含まないと感じた職はありませんでした。
ゆうしゃ ★★☆☆☆
まほうつかい ★★★☆☆
せんし ★★★★☆
そうりょ ★☆☆☆☆
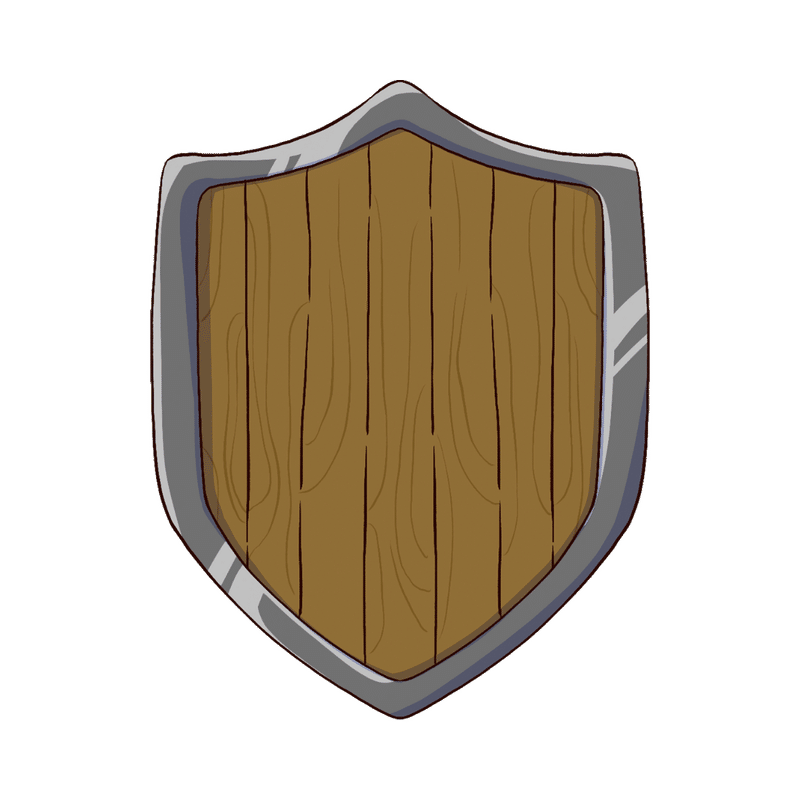
癒やしのそうりょじゃない
意外と平均的に見えますが、僧侶の要素は以外にも少ないように思います。癒やしの楽器オカリナと言われるのに、えんじろうそのものには他の人を癒やしたりサポートしたりする能力(その気持ち)が特別強いわけではない。
つまり演奏に癒やし効果があるとしたら、それはオカリナ自体が持っている能力なのです。
RPGには武器や防具に「つかう」と魔法効果が発揮されるものがあったりします。有名どころのドラクエだと「ちからのたて」などは、使うと回復効果があるんです。オカリナはきっとそういうもので、えんじろうはそれを使うおかげであたかもえんじろう自身が癒やし魔法を使ったように感じてもらえるのでしょう。
さらに言えば「ちからのたて」はドラクエ4だと自分のみ回復させられるものです。オカリナも楽器に最も近い自分が癒やし効果を最大限受けます。周りを直接癒やすというよりも、オカリナを吹き癒やされるえんじろうの姿を見た人が、温かい心になるという構図に思えるんです。
えんじろうのオカリナを聴いた人が、自分もオカリナという「ちからのたて」がほしいなと思ってくれたら、それで良いかなって思っています。
なぜ武芸なの?
最もしっくりきたのは戦士でした。そして自分でそう感じておいて「なんで戦士なんだよ」と思っているわけです。
ただやはり最もしっくりくる気がします。何も考えずに剣を振り回していたいのかな?
オカリナも武芸も日頃の蓄積。それはただ時間をかけりゃいいって話じゃないのですが、動きのコツを掴むと無駄がなくなって自然体でいられるようになるんですよね。
えんじろうはオカリナを「今からすごいことをします!」という気持ちで吹くのが嫌です。心から安心しながら吹いていたいのです。多分それが「つかう」という状態で、先程の話のように使うと自分が癒やされる魔法効果が得られるわけですよ。
うーんでもそれだと、戦士の特徴の「人前に」の部分があまり機能していないのかな?戦士でもないのかな?ちょっとわからなくなってきますね。
憧れの魔法
魔法は昔は「無から有を作り出す技」に見えていましたが、最近は自然界の要素を絡み合わせて「意味を持たないものに意味と力を与える」行為だと思うようになりました。
音楽も「ファ」とか「ド」はただの高さが一定の音という1要素に過ぎません。そこに前後のつながりという組み合わせが起こると、たちまち「ファソラファドー」といった意味と力を持った「旋律」というものが現れます。そういった基本魔法を組み合わせてAメロやBメロといった流れを紡ぎ、その変化を順序付けて曲という大魔法が誕生するというイメージでしょうか?
えんじろうはそれができないわけじゃないですが、得意というほどでもない。だから毎日湯水のように曲が湧くということもないわけです。
それを行うときには少しでも妨げになる要素を減らすという努力が必要なんです。つまり「また今度にしよ」と思いたくなる切っ掛けを排除しまくるんです。
魔法詠唱の妨げになりそうなものを取っ払う環境をしっかり作れたときに、詠唱に集中できるようになるという感じ。本当に素質のある魔法使いなら、きっと詠唱することが楽しくて仕方ないから、環境も何も関係なく詠唱できるのでしょう。
そんなところからも「ちからのたて」のような魔法道具になるものに頼りたくなるのがえんじろうのように思います。
だからえんじろうの職はこうなりました。

魔法使いに憧れる戦士
なーんかなあという気持ちでもあるのですが、それが今の自分のように思うと納得できてしまうことも多いです。
ゆうしゃ要素浮上中
ただ今年になり、またいろんな仲間と演奏をご一緒するようになると、少しだけ「ゆうしゃ」の特性が浮上したようにも思いました。こうしたら更に良いかもと感じたときに、それを伝えられるようになってきたからです。伝えるのが上手でないので、そのままうまく伝わらないこともありますが、伝えようという気持ちが「疲れるし緊張するからやめておこう」を超えることが増えました。
せんしからまほうつかいへ
それから憧れ通り戦士の特性が少し減って、魔法使いの喜びがほんの少し上昇したように思います。久しぶりのCDが完成させられたことも影響しているのかもしれませんが、ちょっと嬉しいです。
そうりょはレッスンで
またレッスン活動を通して最底辺だったそうりょ要素もほんのちょっと磨かれています。それは生徒さんが「コツを掴めた」という素振りを見せたときの自分の嬉しさでわかりました。
今までは「なんとか伝えられてよかった」程度だったのですが、最近は「自分ができるようになったときの嬉しさ」がフラッシュバックするくらいに喜べるようになってきたのです。
まとまらないまとめ
非常に長い文章になってしまいましたが、ともやさんのお陰で面白い思考に浸ることができました。ありがとうございます。
結局どのタイプ化で割り切れるものじゃないし、別に割り切らなくても良いんだと思いました。それぞれの要素が成長する中で、今4つの中で1番強い要素はこれかなといったことなのでしょう。
えんじろうは魔法も自然体で使える戦士になれるのでしょうか?そしてまあ、癒やしはオカリナという「ちからのたて」におまかせしようと思います(笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
