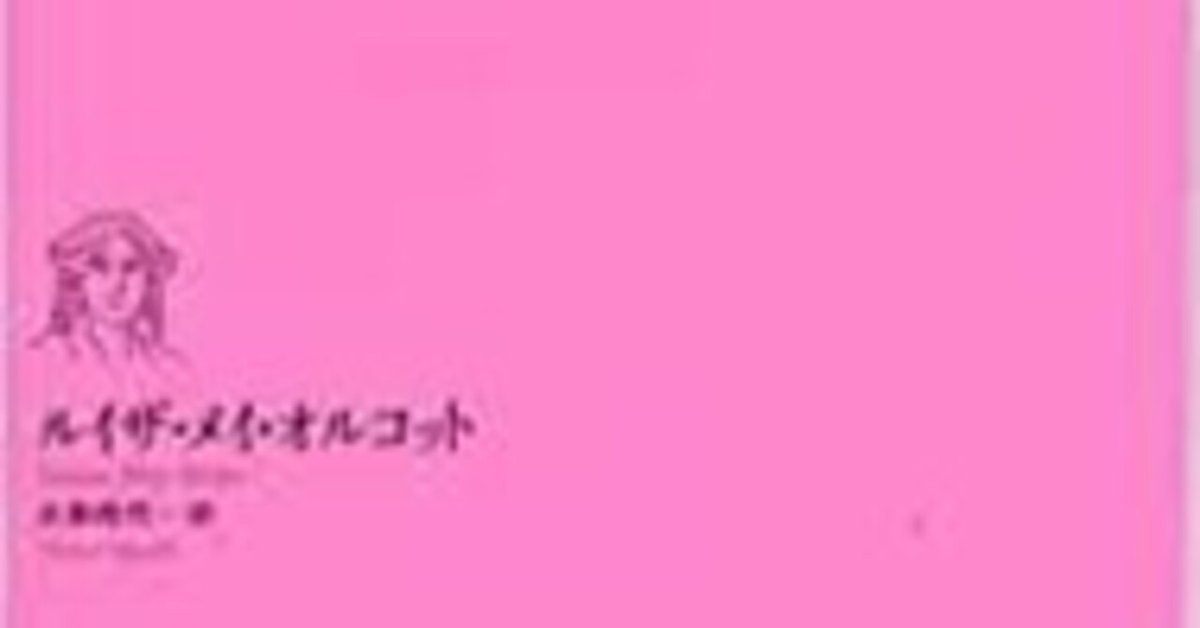
毎日読書メモ(227)煽情小説! ルイザ・メイ・オルコット『仮面の陰に あるいは女の力』
ルイザ・メイ・オルコットといえば、少女小説『若草物語』の著者として有名なアメリカの女性作家である。約1か月前に読んだ、斎藤美奈子『挑発する少女小説』(河出新書)(感想ここ)の中でも取り上げられていて、1868年に発表された『若草物語』こそが少女小説・家庭小説の嚆矢であり、南北戦争で疲弊したアメリカ社会をいやす平和な家庭の情景を描く物語でありながら、男の子になりたかった次女ジョーが主役の、ちょっと不思議な物語であった。
ルイザ・メイ・オルコット自身も、四人姉妹の次女であり、理想を追い求める教育者の父の希望に振り回され、転居を繰り返し、経済的に苦境にたつ時期の多い少女時代を送り、生計を助けるために小説を書くようになった(ジョーと一緒)。1866年に発表された『仮面の陰に あるいは女の力』(大串尚代訳、幻戯書房 ルリユール新書)は、『若草物語』で一気に有名作家となったオルコットがそれまでに書いていた、売文目的の煽情小説のうちの一作である。
煽情小説! なんじゃそりゃ! 英語ではSensational Storiesというらしい。センセーショナル、というのは、ずっと、「驚くべき」とか「世間をあっと言わせる」といった意味だと思っていたのだが、辞書を見ると確かに二義として、「〈侮蔑的〉〔新聞記事・事件などが〕人騒がせな、扇情的な」と書かれている。オルコット自身は、煽情小説のことを「血と雷の物語」と呼び、その書きやすさと原稿料の高さを意識して執筆していたらしい。『続若草物語』で、ジョーが、煽情小説を書いて原稿料を得て、自己嫌悪に陥りつつ書くことにのめりこむシーンがあるが、これはオルコット自身の姿を投影しているのかもしれない。しかし、オルコット自身は『若草物語』を執筆しながら「こつこつ書いてはいるけれど、こういう作品は楽しくない」と日記に書いているらしい。血と雷の物語の方が楽しいか! とはいえ、煽情小説は別のペンネームを用いて発表されていて、オルコットがそれらの作品の作者であることが判明したのは20世紀中盤だったという。
そんな、煽情小説、A.M.バーナード名義で発表されていたスリラー小説『仮面の陰にーあるいは女の力』(Behind a Mask, or a Woman's Power)は、上流階級の男を手玉に取って妻の座を手に入れようとする悪女の物語である。舞台はイギリス。一度、正体を見破られて婚約寸前で糾弾され追われた主人公ジーン・ミュアは、その前歴が見破られないようにうまく履歴を糊塗しながら、ガヴァネス(上流階級の家に住み込む家庭教師、イメージとしてはジェーン・エアみたいな立場)として、コヴェントリー家にやってくる。音楽とフランス語、素描を教えられる教師として、また献身的な看護婦的な技能も兼ね備えたジーンはあっという間に家族の殆どに歓待され、信頼を勝ち得る。コヴェントリー家の次男はあっという間に恋に落ち、うさん臭さを感じた長男によって家から離れて軍務につくように仕向けられるが、その長男もまた彼女に篭絡される。しかしジーンの真の目的はこの二人ではなかった。巧みにコヴェントリー家の人々を翻弄しつつ、前の家で彼女の正体を暴いたシドニーからの情報がコヴェントリー家に到達する前に、彼女は所期の目標を果たすべく陰謀をめぐらす...。
コヴェントリー家の長男ジェラルドも、最初はジーンをうさん臭く思い、疑心暗鬼の眼で一挙手一投足に難癖をつけているが、ジーンの方が上手で、それがくるっとひっくり返される過程が実に面白い。そして、家を出された次男ネッドがシドニーから情報を得て、急ぎ家に帰ってきて、ジーンの不実の証拠を提示するクライマックスは手に汗を握る面白さ。ジーンの高笑いが聞こえるようなエンディング。この先のコヴェントリー家の物語を見てみたいような見てみたくないような。
この本の存在を知ったのは、朝日新聞の書評欄。大矢博子さんの評が面白く、読んでみたいと思った。
これまで、オルコットといえば『若草物語』と『八人のいとこ』しか読んだことがなかったのだが、19世紀中盤に自ら生計をたてようとする女性が選んだ書くという手段の別の姿の結実を興味深く読んだ。
#読書 #読書感想文 #ルイザ・メイ・オルコット #仮面の陰にあるいは女の力 #大串尚代 #幻戯書房 #ルリユール新書 #若草物語 #煽情小説
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
