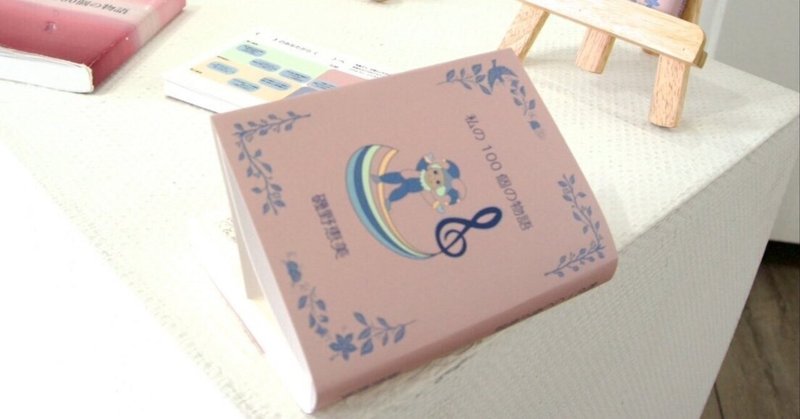
音楽家のオートエスノグラフィー私の100の物語から日常のふるまいをとらえなおす
オートエスノグラフィー「私の100 個の物語」の執筆をきっかけに、再帰的に自己をふりかえり、音楽家としての日常のふるまいをとらえなおす、二年間の再帰的自己プロジェクトの実践の記録です。
オートエスノグラフィーとは
オートエスノグラフィー(autoethnography:以下AE)は、文化というレンズを通して語られた自己の/自己についての物語である。AEは、個人的で文化的体験を社会の中にどのように位置付け、名づけ、解釈するようなったのかを、芸術的・分析的に表現する方法であり、研究者個人の文化的な「信念」「実践」「経験」を詳細に記述し、自己と社会、特殊と一般、個人的と政治的など、交差させながら、深く自己省察を行うものです。
オートエスノグラフィー : 質的研究を再考し、表現するための実践ガイド. 東京, 新曜社, 2022.
《音楽家》から〈音楽家〉へ
わたしは、華やかな舞台に憧れて音楽家になった。
表舞台のわたしは、社会に求められる様々な役割を日々滑らかに演じていた。しかし、社会から求められることは嬉しいと思う反面、期待に応えようと思えば思うほど、まるでわたしはあやつり人形のように感じていた。
音楽することが誰かに笑顔をもたらし、思わぬところで涙を誘い、誰かの祈りになる。そんな聴衆との関係で生まれる複雑な感情に触れ合うことがわたしの原動力だったはずだ。
音楽がまるで「モノ」のように消費されてくことに耐えられなくなり、涙が止まらなくなった。
わたしは、伝統的なクラシック《音楽家》から、音楽を行為としてとらえる〈音楽家〉でありたいと心から思っていた。3 歳のころちゃぶ台コンサートで歌っていたわたしは、今のわたしに必死にそのことを訴えようとしていた。
音楽家に限らず、様々な表現者や、職業、役割を《二重括弧》から〈一重括弧〉に自らのふるまいをとらえなおすことで、人々の行為を関係の中に引き戻し、伝統に縛られず、柔軟に境界線を引こうとする変幻自在な姿が見えてきます。様々な表現者、職業、役割を持つ人に、自らのふるまいをとらえなおすヒントになるかもしれません。
1年目の取り組み 物語を書く
これまで文章を書いてこなかったわたしでも、約10万字の文庫本を作ることができる。表現者として相手の要望に応えることに必死だったわたしは、自分の言葉をいつも後回しにしていた。未熟で拙い文章でも、他者にひらくと反応がある。自分に見えている世界を自分の言葉で書くことは、とても幸せなことだと気づいた。出来事をふりかえり、感情に迫ろうとする行為は、これまで見ずに済んでいたこと知らなかったことに気づかせてくれた。書くことによって、わたしの狭かった世界は確実に広がっていた。
研究室の個室に篭り、ほとんどの文章を書いた。現場から離れて、誰からも邪魔されることなく、時間を忘れて、ひたすら書いた。

2年目の取り組み 循環する再帰的自己
物語の執筆のあと、これまで忙しさのあまり悩む暇すらなかった私は、日記をつける癖がついた。日々のジャーナルをとおして、自らの感情に正直に迫ることを心がけるようになった。


1年目に仕上げた物語をじぶんで何度も読みなおしながら、物語について、9名の他者と対話をした。そして、音楽の現場にも戻り、またそのときのふるまいをジャーナルでふりかえる。現場、ジャーナル、私の物語、他者との対話を繰り返すことによって、これまで見えていなかったことや、物語に新たな洞察が加わり、5つの感情のブロックに直面した。
①パラレルワーカーの裏側に隠されていた《音楽家》としての自信のなさへの気づき
②音楽を行為としてとらえる〈音楽家〉のコンセプトの発見
③伝統的なクラシック音楽の《音楽家》の呪縛に気づく
④このプロジェクトを語ることへの戸惑い
⑤感情を止めずに物語を語る
物語の推敲
対話を終えて、もう一度全ての物語を推敲した。

右 物語の校正
左側の物語の推敲要点まとめシートは、7名の他者との対話を経て、私の物語にどのような洞察が加わったかを影響を明確にするために作成した。上からタイトルを新旧で並べ、その下に、AE にどのような洞察が加わったかを記述した。次に、誰のどの対話が、影響したか対話を抜粋し、のちに行う、KJ 法の分析に向けて、生タグの作成をした。生タグの作成では、できる限りトップダウンに関係性を意識しないように、私の生の感覚に迫ることを意識し、手触りのある言葉を残すことを心がけ、微調整を繰り返した。分析はKJ法を採用した。
物語の公開はnoteでするか、、出版社を探しております。誰か・・

音楽を行為としてとらえるわたしの11の新しいふるまい
分析の結果、音楽を行為としてとらえたいわたしの11個のふるまいが生成されました。
結果は、長いので、こちらから⇩
まとめ
このプロジェクトでは、著述したAE を複数の他者にひらき、推敲、分析することで、自己を再帰的にとらえるプロセスを記録し、再帰的自己プロジェクトの実践的な手法の提案をし、オートエスノグラフィーと向き合うための態度を検討しました。
伝統的なクラシック音楽家の教育を受けてきた私が主題になり、伝統的なクラシック音楽としての《音楽家》と音楽を行為としてとらえる〈音楽家〉の2つが対比され音楽を行為としてとらえる〈音楽家〉でありたい私が強調されています。
《音楽家》は、誰かに規定されてなるものではないと思います。自らの音楽家としての自己を常に、再帰的自己に問い続けるしかないのです。
《音楽家》が《音楽家》であるためには、伝統を隔てる境界が必要で、《音楽家》が〈音楽家〉であるためには、伝統を隔てる境界を揺るがす必要がある。どちらかに固執することなく、柔軟な境界線を引くことが重要だと考えます。
このことは伝統の中にいるだけでは語りえなかったことであって、私が伝統の中で、もっとこうだったらいいのにと、願い続けてきたことの一部でもあります。混沌とした現代社会の、漠然とした悩みを抱える人にこのプロジェクトを届けたいと思うとともに、音楽を行為としてとらえることがすっかりと消されてしまっていることにとても違和感を覚えました。
今後は、音楽を行為としてとらえたい私のこだわりを出発点に、音楽行為を記述する試みを続けていきたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
