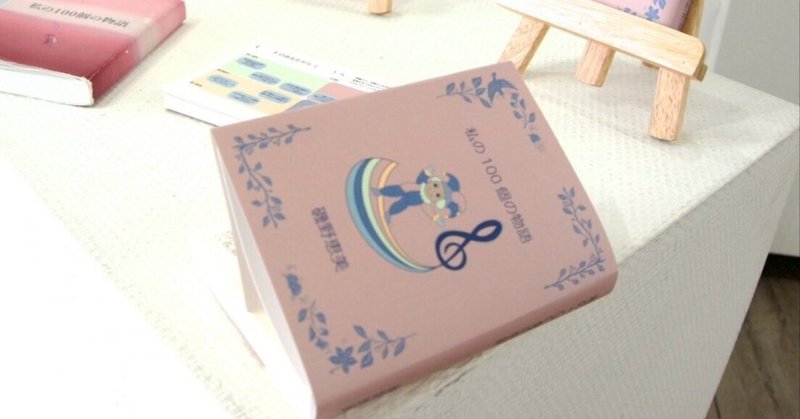
《音楽家》から〈音楽家〉へ、音楽を行為としてとらえたい、わたしのふるまいの方針

音楽を行為としてとらえたい私のふるまいの方針を紹介します。
ここまでどうやってたどりついたか、プロジェクトのプロセスは⇩から。
縦軸には、伝統と自由、(建前と本音と読み替えてもよいかもしれません)横軸には、境界線の強弱がうかびあがり、伝統に決別するのではなく、伝統とその外側を柔軟に行き来し、人々との関係の中で音楽をしようとするふるまいが現れています。
それでは!象限ごとに解説していきます。
第一象限 伝統×境界線強い
王道にいながら、王道じゃないふるまいをして、ズレた存在でいる
私は王道のクラシック業界に近いところにいるが、王道の音楽家像にこだわらないオリジナルな姿を極めたい。アクセス権が限られた人しか近づけない、みんなと違う、好奇心がそそられる場所が好きだ。目の前に見えている物事には、全力でワクワクしたい。全力で走ったり、ジャンプしたり、ダメって言われるまで全力でやる。
王道にいるけれど、ちょっとだけ他の視点ものぞいてみたい。王道にいながら、メインストリームは目指さない。B 面的なサブチャンネルで、ほら面白いでしょ、思わせるような立ち位置を取りたい。価値がわからなさそうなことに全力で取り組み、王道からB 面世界へと誘い出す道化のように。
ほらほらおいでいいでしょって誘い出す。わざとズレた存在で、ふるまう。仕事を受ける側から、作る側になり、あちこちを飛び回り、道化のようにふるまう。
この言葉からは、伝統に参加しながらも、私がどこかそうではない姿をふるまいとして見せることで伝統の中にいる人々を伝統の外へと誘い出すようなふるまいの方針がみられた。これまでの私は、定式化された伝統の中に居続けることで、自分の音楽の現場が、消費の対象として見えてしまい、褒められることにも喜べなくなっていた。伝統に縛られることなく、好奇心が向く方へ全力で向かいたい衝動を、伝統との決別として表現するのではなく、王道の中にいながらもどこか異質な存在としてふるまうことで、自分の存在を示そうとしている。
音楽よりも前に暮らしがあることを忘れない
ケアされない舞台裏。表舞台はキラキラと輝かしい。そのステージを成り立たせるために、ありったけのエネルギーを使う。エネルギーは無限ではない。音楽は、暮らしの中にあって、練習のために日常の経験を犠牲にしてしまったり、楽器を吹かないことに罪悪感を持ったり、もう競争はしなくていい。のびのび思ったように演奏すればよい。そして気が向いたらまたコンクールでも受けてみればよい。
練習で終わる人生は嫌だ。自分のよい状態をキープするには、生活のリズムを超えた本番は引き受けてはいけない。好きなことをやっているのだから、と自己責任と言われるが、表舞台を成り立たせるために、グッと堪えて我慢していることだってある。売れっ子の悩みは誰も聞いてくれない。自分を自分で助けるしかないのだ。音楽の前にちゃんと暮らすこと。
実体のない、世間が考える幻想からは距離をおく
思考停止の大人が苦手だ。伝統の中で権威を押し付けられるような、ナルシスティックな語りが嫌だ。自分たちの奏でる音楽は、よいものだと決めつけて、周りを見ずにいつまでも浮世離れしていることが嫌だ。自由な音楽を一緒にやろうと思っても顔が、不協和音ですねといったりする。表情と言葉の矛盾。無意識に良し悪しを顔の表情でが物語っていることに気づいてしまう。
《音楽家》は自らが《音楽家》であることを表明するために伝統を着る。長々としたプロフィールにはみんな黙ってしまう。《音楽家》は、《音楽家》と自己紹介したら、そのさき会話は広がらない。《音楽家》はいつも偉そうだ。私は、トップダウン的な教育の中には喜びを全く見出せなかった。みんなが同じように笑ったり泣いたり、同じ場所で感動したり予定調和的に感情を動かされていくことに激しく抵抗した。会社も同じだ、実体のない幻想を盲信している。それは全部社会が創った幻想なのに。そんな滑稽な大人からは、積極的に距離をとる。
この言葉からは、実体のない世間が考える幻想や、同質性を求められることや、権威によってトップダウンに物事が回収されてしまうことへの抵抗を示している。社会が作り出した幻想に乗り続けることは、考えなくて済むことだと私は感じていた。自分たちのよいと思うことに、盲目的になり、浮世離れして、人を寄せ付けない態度をみていることが耐えられなかった。また、世間から求められる印象に個性が埋没してしまい、個としての姿が見えなくなってしまうことを悲しいと思っていた。今目の前に起きているそのことに感情を動かされたいのに、外からの解釈を押し付けられたり、わかりやすい言葉で回収されてしまうことで、本来感じていたことが覆い隠されてしまうことにも抵抗したかった。実体のない世間が考える幻想とは逃れられるものではないが、少し距離を置いて付き合いたい。
第二象限 伝統×境界線弱い
手に届く範囲の関係性で、いいなと思う関係性の音楽を追求する
手に届く範囲の関係性で、一緒にいたいと思う人、好きな物事を一緒に共有できる人たちと、いいなと思える時間をたくさん過ごしたい。普段会えない、お世話になった人や身近な人からもらった言葉がいつもポケットに入っていて、私の宝物だ。身近な人の言動や、ふるまいにはいつも影響されている。守備範囲は広くないが、手に届く範囲の親密な人間関係を大事にしたい。
この言葉からは、他者との関係性をふりかえることができる。私が、これからどんな人間関係を築いていきたいかとてもよく現れている。私は、身近にいる人から影響を受けやすい。人から言われた言葉は、いつも自分のポケットにしまって大切にとってある。誰とでも仲良くできるわけでもなく、自分の対応できる範囲が狭いことも自覚した。手に届く範囲内で、一緒にいたいと思う人たちと一緒に、心地よく過ごせる人間関係を大切にして、その人たちにきちんと感謝を伝えて行けるようなふるまいをしたいことが現れている。
リアルに感じられる、雰囲気や情緒とのつながりが作る音楽の場をつくる
リアルに感じられる雰囲気や情緒との繋がりが作る音楽の場を作る。私の音楽的こだわりは、即興的に湧き上がる、他者とのやり取りの物語を聴くこと、音楽は出来事だ。それから、瞬間的に感じられる印象作りにこだわること。日常と非日常の交わる瞬間、最初の、その一瞬の演奏に感情を凝縮すること、アンサンブルで、ピタッと音が合う瞬間、その瞬間の印象にこだわっている。音楽や感情は身体で感じていたい。自分の奏でる音が身体と繋がっていて欲しいこと、外から入ってくる光のあたたかさを音楽の中で表現したいと思うこと。人はリアルに感じていたいから、接続過剰にならないこと。出来事に紐づいている雰囲気や情緒を大切にする。今、ここの雰囲気が一番大事。
この言葉からは、私が音楽を行為としてとらえる、要素が色濃く現れていた。KJ 法の分析の第二階層では、私が思う音楽を行為としてとらえる〈音楽家〉としての態度が確認できる。生タグではその詳細の要素を一つ一つ確認することができた。とらえかたの方向性をまとめると、以下のようになる。
【私が音楽を行為としてとらえる6つの視点】
1.音楽を物語としてとらえる視点
2.その場から立ち上がる即興的なふるまいを見ようとする視点
3.リアクションによる相互作用に着目しようとする視点
4.瞬間的に生まれる感情にこだわる視点
5.気持ちとタイミングがピタッとはまるような瞬間をとらえようとする視点
6.パフォーマンスそのものよりも、そこに流れる空気感に着目しようとする視点
【私が音楽を行為としてとらえる場づくりの手掛かりとなる感覚】
・出来事に紐づいている、温度や手触りに敏感である
・雰囲気や情緒を感じられる時間を重視する
・奏でる音と身体感覚との繋がりを重視する
【私の感情を喚起させる感覚】
・光に感情を感じる
・心のざわめきに素直に感じようとする
・音楽を行為としてとらえたときの展開可能性
・音楽から感じる感情を別の感覚へと翻訳しようとする。またその逆
これらの要素は、決して伝統的な音楽教育の場では思っていたとしても、ほとんど語ることのない、まさに、音楽を行為としてとらえようとする態度であり、これらの視点を持って、音楽に還元することは、これまでとは全く違った解釈としてとらえようとするエッセンスになる。これらの項目は、直接的にこの話をしていなくとも、私が、強く感じていたことが反映されている。生タグの集まってくる枚数が、他の話と比べて多く、私がこの項目に異様にこだわりがあることもわかった。
偶然や直感的に出会う出来事や関係性を重要視する。出会った感動は人生のおまけと考える
偶然や直感的に出会うものに触れていたい。興味のある人について行ったり、危なくない範囲で近づいてみたり、えっ?と思うことにも出会ってみたい。偶然や直感的な出会いが私の人生を面白くしている。音楽とはゆっくり出会いたい。サブスクみたいに、すぐ聞けて便利なサービスはたくさんあるけれど、曲を聞かずに、CDのジャケットでフィーリングを確かめて、家に帰ってコンポで聴くくらいのテンポ感。楽譜も印刷して、製本して、それで演奏するくらいのテンポ感。その一手間が音楽との出会いを豊かにしている。そんな、なんでもない、お茶飲んでゆっくり過ごすような、時間の中に、ときたま現れるミラクルな感動は人生のおまけにしておく。舞台の上の喜びは麻薬だ。全部ラッキーだったと思うことにする。そうすれば、お茶飲んでゆっくりしているだけで多分幸せ。
この言葉からは、偶然や、直感をしようとする態度が生成された。これまでも、偶然や直感で選んだことに人生を面白い方向へ導かれている。その偶然や直感は、余白の時間から生まれることを自覚している。新しい音楽との出会いも、アルゴリズムのおすすめで上がってくるようなものではなく、自分で選んだ感覚を持ちたいと思っている。偶然や直感にで会えるようなひらかれたふるまいを大切にするが、その偶然や直感から生まれる喜びは、麻薬的な享楽でもある。その麻薬的享楽を幸せの基準としてしまうことなく、たまたまだった。
ラッキーだったと人生のおまけにしておくことでその享楽を楽しむことができるのではないか。直感で行動して見ることは、対話の中よりも、もとから自分のなかに抱えていたコンセプトだった。対話では、どちらかというと、偶然や直感的なことに遭遇するための余白の時間や、無鉄砲になんでも取り組んでみるところに対話の焦点が当たっていた。
第三象限 自由×境界線強い
愛嬌を武器に、立場を固定せず、できるだけ多くの可能性に触れ続ける。
いつも割り切ることができなくて、決められない。定まらない日々を過ごしている。遊んでいるのか働いているのかよくわからないし、一年先のスケジュール押さえちゃっていいのかな?と未来が確定することすら怖い。決めてしまうのではなく、できるだけギリギリまで色んな選択肢を抱えていたい。ずるいと言われてもちゃっかり持っておく。いつも関係調整のために、周りを見ている。評価したり、判断したりはしないけれど、中立でありながらちゃっかりしていることを悪く思わない。そうか、私の中にもまだちゃっかりなんて言葉があったのか。と思うことにする。
この言葉からは、自分の態度を統一的なものにしてしまわずに、あらゆる可能性にひらいておこうとする態度が生成された。私は他者との関係の中で、自分の立ち位置をよく観察しようとしている。そのかわり、これだと自分で決めることがあまり得意でない。あらゆる可能性を持ったまま割り切れなさをいつもそのままにしている不器用さがある。しかし、それをよいふるまいだと思っていることが発見だった。愛嬌を武器に、ちゃっかり中立な立場で、社会をドライブしようとする態度がここから感じられた。
ファンタジーを描き、表現し続ける人
私は、幼少期にたくさんの音楽や物語に出会い、そのファンタジーの儚さにいつも心奪われ、いつか物語の中の主人公のように舞台に上がりたいと思うようになった。ドラマの中で心惹かれる登場人物たちは、セーラームーンに、スイミー、優しいマッチ売りの少女、本当は心優しい悪役は、私の生きる指針にしたいと思うキャラクターたちだ。そのキャラクターからそれないように、こうだったらいいな、という妄想を頭の中で広げて、物語を書いたりする。キラキラした場所はいつまでも憧れの場所にしておきたい。私が大人たちにたくさん夢を見せてもらったように、子どもたちの純粋なまなざしを守りたい。いつまでも妄想で作り上げたファンタジーを信じて感動できる人でいたい。
この言葉からは、音楽家として、舞台人としての虚構の世界への向き合い方が色濃く生成された。私は表現者であり続けたい。その表現者としての私を支える、虚構の場所の作り込み方と、その虚構と向き合うための心構えや、表現のポイントをまとめる。
【表現者としてのわたしを支える虚構への向き合い方】
・なりきりや憧れを本物にする
・物語の登場人物の性格に自分を投影してふるまう
・キラキラしたファンタジーにいつまでも感動できる人でいたい
・妄想を広げてこうだったらいいのにを発展させる
・伝統への参加はワクワクするものである
・自分の手で作ったものは自分成果だと主張する
・消えてしまう儚い瞬間を他者に記述で伝えられるようになりたい
・自己をふりかえるための逸話を残していきたい
第四象限 自由×境界線弱い
自分を犠牲にしない範囲で、柔軟に他者との境界線を引く
私は、そこまでたくさん練習しないのに、音楽を言い訳に、他者との関係性や自分の感情を置いてきぼりにしてきた。周りの期待に応えようと、必死になって走るあまり、悩む暇すらなく、とにかく合理的な判断を下して自分の気持ちをギュッと堪えてきた。感情を押し殺すほど、合理的になってはならない。誰かと会ったり、食事に行ったり、遊びに行くことを犠牲にしなくていい。音楽、練習が全ての人生ではない。
私は、時々他者との境界線が緩くなるときがある。表現者として、わざとその感性のアンテナを緩くして、他者に入り込もうとすることもある。しかし、普段使いしてしまうと、見なくてもいいものを見てしまい、考えなくてもいいことを考えてしまったり、他者の生き様に幻滅して偏屈になったりする。できるものならば、寛容でありたい。全ては無理でも、私が思った通りにしか思えないことも知っておきたい。無理に考えを捻り出したり、あんまり思ってもいないこと、無理に喋ろうとしなくていい。解像度のメガネを上手に掛け直したい。
この言葉からは、他者との関係性と自己と他者とを分ける境界線への向き合い方が生成された。私は、他人の期待に答えようとしすぎるあまり、自分の気持ちをいつも置き去りにして頑張ってしまう傾向にあった。そういったふるまいが、私の中の自分を商品としてみてしまう虚無感や自分の周りで期待が膨らみすぎていることへの不安に繋がっていた。
また、音楽家、表現者としては、感情の境界線を繊細なまま感じようとしたり、相手境界線のギリギリまで近づいていって、見なくてもいいこと、私にはどうしようもできないことまでに思いを馳せてしまうなど、境界線の引き方が曖昧になっていた。境界線が曖昧なことが全てネガティブなわけではなく、表現者としては、必要な完成であると同時に、自分の境界線を守るためのふるまいの態度が生成された。
【自分で境界線を守るための態度】
・期待に答えようとして、自分の感性まで殺さないようにする
・私が思わないことについては、無理やり言葉を紡がない
・解像度のメガネをかけかえる
・自分の力の及ぶ範囲の限界を意識する
・他者の生き様に寛容になる
・芸術のためなら安全な範囲で境界線を緩くする
・全てのことに合理的になりすぎないようにする
人生の生き様のリアルな感情を、音楽で表現することで人を動かすと信じる
リアルな感情を口から心臓から出す。私がそうやってむき出しの感情を音にぶつけることが誰かを動かす。嫉妬や妬みもエネルギーになる。特段、何ができるわけでもない。演奏だって普通に演奏できるだけだ。それでも、私が音楽をすることが、状況と、その人の感情の状態によって、すっと影響を与えてしまうかもしれない可能性をいつも含んでいる。出会う人々の中に、すっと入っていって、すっと消える。よい雰囲気だけ残していく。私の生き様とリアルなむきだしの感情表現が人を動かしていくと信じたい。
この言葉からは、私が感情を取り扱う音楽家として、表現者として私が無意識に与えてしまう可能性と、自分自身を動かすドライブになる感情についての項目が生成された。私は表現者として、人前で感情を出すことが仕事でもある。音楽をとおして伝えたいメッセージを私が組み立てたとしても、音楽であれ、芝居であれ、考えたとおりに伝わるわけではない。私にある文脈と他者の文脈がたまたま交わることで何かしらの感情が生まれる。どこでどんな影響を与えてしまうか、全く予測不可能であり、再現性がないことだ。しかし、それができてしまう可能性だけは、信じて口から心臓を出し続けて表現することが、メディアになる。表に出れば出るほど、嫉妬や妬みも増える。しかし、その感情さえも私のエネルギーになる。
誰でもない私として、人々の暮らしの中にある音楽との出会いを大切にする
ふつうの人になりたい。〈音楽家〉である前にふつうの人になりたい。〈音楽家〉を名乗ると伝統に個性が埋没してそれ以上に話せなくなる。長年背負ってきた《音楽家》の看板は重い。音楽で競うことは、私に《音楽家》の呪いをかけた。夢ばかり見せ狭い人間関係へと閉じていく伝統的な教育。《音楽家》の権威を守るためにわざわざ《音楽家》であることを名乗る。《音楽家》をしている私にはならない。音楽をするためにいるのだから。伝統的な音楽も嫌いではない、でも最も好きなのは、人々の暮らしの中に根付いている音楽を感じることだ。ないもの探しをよりあるもの探し。見知らぬ土地で、出会った人を《音楽家》であることを名乗らずに〈音楽家〉する時間。音楽家の看板はもう必要ないと言いたい。
この言葉からは、《音楽家》でも〈音楽家〉でもない私が、音楽と出会うことの重要性に気付かされると同時に、私の音楽の世界観を表現するような言葉が生成された。《音楽家》の看板はそう、名乗ってしまった瞬間に、私の個性を伝統の中に閉じ込めてしまう。肩書は便利な一方で、その便利さに甘えて、周りに何も言わせない権威の強さを持ち合わせている。《音楽家》は《音楽家》であろうとするために、《音楽家》を名乗る。しかしそれは、伝統の外にある音楽と出会うチャンスを感じる機会を逃してしまうことにも繋がっている。私の思う音楽観は、クラシック音楽の中だけにあるわけではない。人々の文化や暮らしの中にあるローカルに共有されている音楽に心を奪われる。その音楽に出会うために、日常をエスケープしようとする。
おわりに
私は伝統的なクラシック音楽家としての《音楽家》と音楽を行為としてとらえる〈音楽家〉2つの音楽家としてのアイデンティティをAE の中で彷徨いながら、〈音楽家〉としての、私らしい11 個のふるまいの方針を見出すことができた。
生成された11 個のふるまいからは、伝統的なアプローチから音楽を語らない、〈音楽家〉として、柔軟な態度をとろうとする私の姿が浮かび上がってきた。さらに、伝統を拒絶するつもりもなく、むしろ柔軟にその伝統を受け入れつつ、新たな視点を探そうと、伝統の境界を探り、様々な取り組みを模索しながら、今までどおり音楽を続けたいと思う《音楽家》としての私もそこにいることに気づいた。
初心に還りバッハのソナタの楽譜を開いてみたら、そこから聴こえてきたのは、音楽が動く情のようなものだった。少し前までの私が感じたくても感じられなかった感覚だ。論文の執筆期間、ほとんど楽器を触らずに過ごし、楽器をはじめてからおそらく一番のブランクとなった。実力は落ちているかもしれないが、音楽を感じる心は回復の兆しに向かっていると思えた。
これまでの私は、それなりに《音楽家》として活動ができているのに、なぜこんなにも音楽がつまらない「モノ」になってしまったのだろう、素直に音楽することに全く喜びを見出せずに、練習も楽しいと思えていなかった。きっとこのまま楽器を続けていたら、きっとどこかで心が折れて、楽器すら触りたくなくなってしまっていたかもしれない。しかしその気持ちはまた裏舞台に埋没していくばかりだ。私は、AE の著述過程で、《音楽家》の呪縛発見によって自分に呪いをかけていたことに気づいた。
呪縛の根本的解決にはまだ至ってないが、きっと発見されなければ解
決に向けて考えることもできなかっただろう。これまでの《音楽家》的生き方私は、中学校のとき、コンクールで一位をとってから、競争の海に巻き込まれ、《音楽家》であらねばならぬと、必死になっていた。運よく大学を出てすぐに、活動を軌道に載せることができたが、仕事は増える一方で、音楽をする気持ちは衰退していた。〈音楽家〉的生き方では、音楽を行為としてとらえる。ちゃぶ台でコンサートをしたときのように、音楽することは、日々の暮らしの中にある。それはいまのところ脅かされそうなことはない。音楽することのラインを生活の中に、引き戻すことによって、ステージはまた憧れの場所になり輝きを戻したように感じる。
《 》のあなたから、〈 〉のあなたへ
これまでの項目は、わたし特有のものであったが、音楽家以外にも、さまざまな社会的役割、職業、表現活動に共通するところがあるのではないかと思い、少し言葉を一般化してみました。
なんだか、名前に囚われて、そうゆうことじゃないんだよ、と思っている人多いのではないかなと思います。細かなふるまいについて考えて見ることはとてつもなく面倒なことにように思うかもしれませんが、私は、それが大事なのだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
