
『Jazz The New Chapter 5』の作り方: 新しいジャズとジャズの歴史を編集するための試行錯誤 - インタビュー 柳樂光隆(取材:伏見瞬 @shunnnn002 )
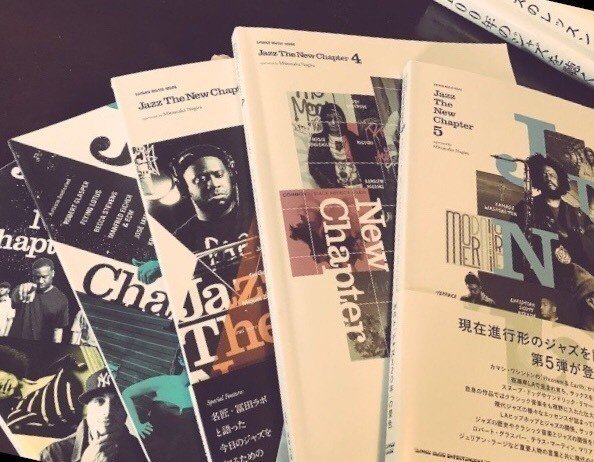
『Jazz The New Chapter』は現代のジャズの動向を伝えることで、日本の音楽ファンの生活に大きな影響を及ぼした。この本がなければ、ロバート・グラスパーやカマシ・ワシントンの名前が今ほど広く知られることはなかった。現在まで5冊を数える『Jazz The New Chapter』シリーズについて、監修人である柳樂光隆はそれぞれをあくまで一冊の「本」として読んでもらいたいと語る。その真意はどこにあるのか。ジャズメンの言葉を伝えるメッセンジャーの役回りが多い柳樂に、今回は自分の言葉で、歴史に対する姿勢やインタビューの方法論などについて大いに語ってもらった。
(取材・執筆・編集:伏見瞬 @shunnnn002 )
コントラストを際立たせるためには、ある種の網羅性は失われる
――柳樂さんは『Jazz The New Chapter』(以下JTNC)シリーズが「本」として読まれたいってことを強調してますよね?
一つのパッケージとして扱われたい気持ちがあるんですよね。JTNCには章立てがあって、章ごとにテーマを設けているけど、大きく一つの本として章を超えたテーマや共通性もあって、一冊全体がゆるく繋がるようにしているんです。つまり全て読むと、「今起きていることの大きい傾向」が見えたり、「ジャズがそもそもどういう音楽なのか」とか、「現代の演奏家がどんなことを考えてるのか」とかが掴めたりする。だから、全体を読んで何かを捉えるって読み方をされると嬉しいって思うんですよね。
――なるほど
あと、トレンド的に消費されたくないってことは結構考えてましたね。「最近、ジャズ流行ってますね。」みたいなの嫌だし。だから、あるジャンルを網羅したお買い物ガイド的なものにはしたくないと思ったし、読んだ人がコンテクストを読み取ってジャズを長く楽しんでもらえるような作りになるようにしようとしてます。でも、そうやって自分が伝えたいと思うコンテクストを際立たせるためにはなんらかのコントラストをつけなきゃダメで、そうなるとある種の網羅性は失われるはずなんですよ。だから、制作中に多少話題になっているけど、本のコンセプトに合わないから取り上げないトピックも出てくる。『JTNC5』だったらUKジャズには触れていないんですよね。載せるかどうかは流行ってるとかじゃなくてすべては文脈次第なんです。
―― 一冊の本として読まれるって単独性と、何号も刊行していく連続性とのバランスはどのように考えていますか?
僕の興味は繋がってるから自然に連続性が生じているとは思うんですよね。でも、それが強く出てきたのは『JTNC4』とその前のマイルス・デイビスを扱った『MILES:Reimagined』からですね。それまでも繋がってるけど、明確に特に上手く繋がるようになった実感があるのはマイルスの本から。
――たしかに、『JTNC4』以降から特に各号のキャラ立ちは感じますね。柳樂さんの(インタビュー記事ではない)書き原稿が増えてきたことも関係しているんですか?特に『5』では沢山書いていますよね。
それは意図的に増やしたんですよ。マイルス本でかなりの分量を自分でやって、『4』でも取材はほぼ全部自分でやったんですけど、それ以来、大きなひとつのテーマを定めて、そこに合わせて全体を考えるってやり方が機能するようになってきたんです。ひとつの大きなテーマが見えると、それが個々のインタビューにも反映されていくし、そのテーマに即したもので何が必要かを考えながら自分の書き記事を入れると全体がより繋がっていく。
あと、「生演奏と機械」ってテーマは『1』からずっとあって、それは『5』のテラス・マーティンやマシュー・スティーヴンスのインタビューで出てきたりもして。そうやって僕が同じテーマを何年も追い続けてることで自然に出てる連続性もあると思います。
正直言うと『3』まではシーンの全体像が見えてなかったんですよ。まずは基本情報から集めないといけなかった。だから最初は紹介レベルに留まらざるをえなくて、テーマはぼんやりとあっても、あまり踏み込めなかった。でも、3冊積み上げてきたことで紹介の段階が終わったし、それがリスナーやメディアにも浸透した気もしてて。その意識があったから『Miles Reimagined』ではチャレンジができて、『4』からは次の段階に進んだとも言える気がします。
――『5』ではカマシ・ワシントンだったりケーシー・ベンジャミンだったり、一人のインタビューが特集によって二つに分かれていますよね。サックスの話と、新譜の話が別の記事になっている。あれはひとつのインタビューを編集で分けているんですか?
そうそう。『4』でもグラスパーのインタビューを二つに分けたんだけど、それは分けたほうが内容が入ってくると判断したからですね。普通の雑誌だったら1アーティストにつき1インタビュー記事ですよね?一人のインタビューが二つの記事になっているってのは珍しいし、常識的にはあまりやらないことですよね。

――しかもページが飛んで掲載されてる。
そういうことをするようになったのは一冊の本の設計図が描けるようになったからですね。逆に設計図がはっきりしてる分、思うような話が聞けなかったインタビューは浮くから載せどころに困るみたいなこともあるけど(笑)
だから、記事の内容次第では最終的に台割を変更して記事の位置を変えたりもしてるんですよ。『5』で言えばクリスチャン・スコットのインタビューは当初は巻頭のカラーページにしようと思ってたんだけど、話を聞いたら《What Is Jazz?》特集にふさわしい内容だったから、場所は後ろになるけど、その特集に入れたほうがいいと判断して。

――本の後ろの方が内容濃い時もありますよね。
それもJTNCの特徴だと思う。マリア・シュナイダーとか知名度のある人を普通は前に載せたがるけど、本のテーマやコンセプトに沿ってふさわしい場所に置いて、その発言の内容がより読者に入ってくるほうが重要だって考えてるからですね。『4』でも一番後ろのジャズピアノとオルガンのに関する特集が個人的にはかなり重要だと思ってます。すごく後ろにグラスパーのインタビューが載ってるのも贅沢だし。それが『5』の巻頭のグラスパーのインタビューと繋がってたり。

――記事の順番の話が出ましたけど、『5』はリヴァイブ・ミュージックなど、ジャズのメディアに関する記事が前に来てたじゃないですか。あそこにはなにかメッセージみたいなものが込められているんですか?
まず、リヴァイブはポスターとかのデザインが優れていたのでカラーで載せたかったという雑誌のデザイン上の理由がひとつ。それとジャズのメディアが別のジャズ・メディアを紙面で扱うってことが面白いかなってのを推したかったのもありますね。『4』でブルーノートの特集をやって、社長のドン・ウォズとA&Rのイーライ・ウルフのインタビューをがっつり載せたんですけど、もともと今のジャズシーンに貢献している音楽業界人たちを紹介したい気持ちがあったんですよね。そのほうがUSのジャズ・シーンを立体的に把握できるようになる気がして。でも、『4』では記事を後ろの方にしか置けなかった。だから、『5』ではもっと目立つ形でやろうと。
リヴァイブ・ミュージックのボスのメイガン・ステイブルズがたまたまブランディー・ヤンガーってアーティストのマネージャーとして、日本に来てて、その「たまたま」に迅速に対応にしたからできた記事でもあるんですよ。ちなみに来日を教えてくれたのはBIGYUKIだったので、これも今までやってきたことのつながりで実現した記事ですね。

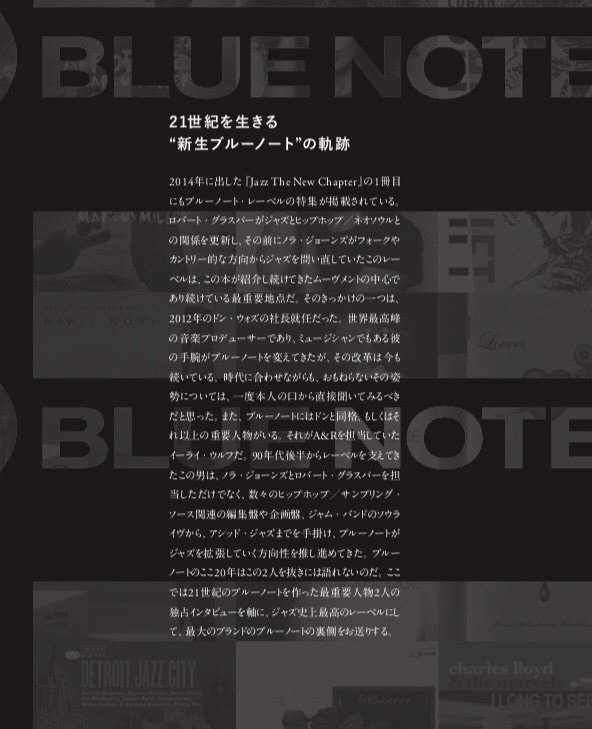
ジャズの言葉や語り口を使わない
――基本的にはジャズが好きな人が読者層だと思うんですけど、読者を広げるために考えていることはありますか?
実はそう思ってなくて。海外のアーティストに取材する際は「この本はジャズに興味があるジャズリスナーじゃなくて、ジャズ・ミュージシャンがやってる新しいことに興味がある音楽リスナーが読者です。」って説明してます。なので、『1』の時から継続してやっているのは、ジャズの言葉とかジャズ雑誌っぽい語り口をしすぎないってこと。あとはジャズミュージシャンにジャズ以外の音楽について語ってもらう、またはその逆。それは射程範囲を広く取りたいからですね。《ジャズ本》っていう設定は一応あるんだけど、その中でどう《ジャズ》だけじゃなくて、《音楽》を語っていくかを考えてます。でも《ジャズの本》って建てつけには必ず合わせることにもこだわってるので、ジャズっぽいけど本質的にはジャズと関係が薄いなって思うものは外してるんですよ。「ジャズをサンプリングしてます」とか、モダンジャズのコスプレっぽい感じのは入れてないですね。だから、流行ってても取り上げないものも多いし、縛りはかなりある本だと思いますよ。
あと、途中から変えたジャンルのことでいえば、ワールドミュージックって括りや考え方をやめようかなとか。
――確かにワールド感は少なくなってますね。
例えば、《ブラジル人の音楽》を《ブラジルの音楽》ってやり方で語ると、《ブラジル音楽》が好きな人しか読まないじゃないですか。だから、『4』でブラジル特集をやったんだけど、ブラジル人が作った音楽をブラジル音楽の枠じゃなくて、ジャズって枠でもできるかもと思ってやってみた特集なんですよ。ジャズのリスナーとか、ブラジル好き以外にも届かないかなって思って。
『5』ではもっと違うやり方にしたいなと思って、カリブとか中南米とかアフリカの話がたくさん出てるんですけど、そこでもワールドミュージックとして扱ってはいないんですね。(アルメニアがルーツの)ティグラン・ハマシアンの話も出てくるけど、アルメニアに寄せてなくて、違う文脈で出てきますよね。

――なるほど
『5』は世界の音楽が繋がってるって話をしてるんですけど、アメリカの音楽の中には世界各地の音楽が入っていて、それが現代のアメリカ音楽でもある現代ジャズに反映されてて、アメリカの音楽がある種のコスモポリタンみたいなものだというのが大きなテーマになっているんです。クリスチャン・スコットが以前から自分のことも自分の音楽も《World Citizen(世界市民)》的なものだって言ってて、その感覚を本で表現できないかなと思ったのもあります。この本ではワールドミュージックとして世界中の音楽を陳列して紹介するんじゃなくて、アメリカ音楽の中で重要な役割を果たしている世界各地の音楽の要素を抽出していくことで、それらのアメリカ以外の音楽にも関心を持ってもらえるようにするって言うか。ディスクガイドページも国や地域で分けない配置になってます。
――ベッカ・スティーブンスなどのU.S.フォーク寄りのアーティストを、JTNCでは大きく扱っています。ジャズというよりアメリカ音楽全般に視野が向いてる傾向はありますか?
そうですね。アメリカの音楽のことがわかればジャズがわかるようになるし、ジャズのことがわかってきたらアメリカの音楽のことがよりわかるかもって意図はあります。あと、もともと、アメリカのいわゆるフォークロックとかスワンプロックとかが好きだったんですよ。それらは渋谷系やギターポップの元ネタになってたりもするし。
――ジャズもその延長で聴きだした?
いや、ジャズは世代的にもともとレアグルーヴとかクラブジャズとかあったので。あと、ONJQやDCPRG。他にはメデスキ・マーティン&ウッドとかジャムバンドとかもありましたよね。
そうそう、さっきのフォークとかの話で言えば、カントリー系のシンガーのグレン・キャンベルで有名な「ウィチタ・ラインマン」って名曲があって、色んなジャンルの人にカバーされてるんだけど、もともとはフィフス・ディメンションに曲を提供していたジミー・ウェッブが作曲しているんですよ。で、そのジミー・ウェブはマリア・シュナイダーに影響を与えていたり。僕はソフトロックが好きだったからジミー・ウェブもフィフス・ディメンションも好きだったし、ミーターズやセルジオ・メンデスやカサンドラ・ウィルソンがカヴァーしてる「ウィチタ・ラインマン」も超好きだったんですけど、そういう元々好きだったアメリカのポップスやフォークの曲を近年ジャズの人が演奏していたんですよ。そういうことが何度かあってのことなので、ジャズが必ずしもスタート地点ではないんですよね。
――なるほど
だから、そもそも自分が扱いたいのは、ジャズじゃなくても好きな音楽ならなんでもいいって意識があるんですよ。ロバート・グラスパーも、最初の頃「これはヒップホップとしてどうなの?」とか「ジャズとしてどうなの?」とか言われたけど、両方入ってるんだからどちらかの視点だけで語ってもしょうがないわけだし、僕はそういう中間具合が好きだったし。
逆にジャズっぽいものが好きってわけじゃなくて、ただジャズっぽいことやってるものには全然興味ないんですよ。ウッドベースでスウィングしてるいかにもなジャズアレンジのJポップスみたいなのは心底どうでもいい。《ジャズミュージシャンが参加することで新しくなっているもの》が好きなんですよ。『ラ・ラ・ランド」のサントラが好きかって言われると、それは違うっていうか。
――ジャズ風味なものが好きなわけじゃない。
そうそう。これは取材時に何度もいろんなミュージシャンに言ってるんですけど、僕が追ってる人たちはジャズがやりたいわけじゃなくて、音楽がやりたい人なんですよ。
今年はceroやダーティー・プロジェクターズやくるりや小袋成彬のインタビューをやったんですけど、彼らはもちろんジャズじゃないけど、彼らの音楽はJTNCで取り上げてることと繋がるなって。それは新しいことやろうとしている人の音楽から抜き出したエッセンスにはジャンルを超えて共通するものが多いからなんですよね。要素としては新しいジャズと同じ新しさが入ってると。だから、ジャンルは関係ないんですよ。
『1』を出し始た頃に菊地成孔さんに言われたのは、グラスパーとティグランを分けたほうがいいってことで。ヒップホップやR&Bやビートミュージックっぽいところだけを抽出したらもっと売れたのにって。最近だと、ジャズファンの方にジェイソン・モランはJTNC枠じゃないよみたいなことをSNSで書かれたこともあったんだけど。まぁ、言い分はわかりますよ。でも、僕にとっては全部繋がってるんですよね。たしかにシーンや地域や既存のカテゴリー分類では違うかもしれないけど、同じ要素だったり時代性だったりは感じるから。クリスチャン・スコットとマリア・シュナイダーとジュリアン・ラージとカマシ・ワシントンは違う場所にいると思うけど、その4人には共通しているものがあると思う。それはジャズだから一緒って話ではなくて、理論とか手法とか考え方とか何かを共有しているってことですね。ティグラン・ハマシアンとゴーゴー・ペンギンとクリス・デイヴィスは表面的には違うけど、それぞれがリゲティの話をするんですよ。そうやって繋がってる。もちろん分けたい人もいるだろうし、わかりやすく分けた方が売れるかもだけど、僕は同じ地平の話だって考えたほうが面白いかなって思うので。
そういう感じで、ジャズの視点だけでもなく、シーンの見取り図でもなく、今起きてる「音楽」の話になったのがこの本のいいところな気がしますね。
歴史はいくらでも書き換えられる。それが当たり前。
――元々レアグルーヴの無歴史性みたいなところからジャズに入って。ただ、JTNCは「コンテクストとか歴史性とかに通じることでもっと音楽面白くなるよ」ってことを教える本だと思うんですよ。それって真逆の態度かなとも思うんですけど。
レアグルーヴって歴史性とかを無効にしようっていうか、ある意味では逆張り的とも言えるというか。一旦出来上がったヒエラルキーを無視したり壊したりするムーブメントって部分もあって、パンク的でもあると言えると思うんですよね。だからこそ、そこに世代間の対立もあって、我々の新しい感性こそがピュアで正義だっていうやり方がかっこよかった部分はあると思う。踊るって根源的な行為に導くって部分のピュアさもあるし。クラブジャズとかもそういうことだと思うんですよ。
――たしかに。
ただ、僕は大学に入ったの98年で、その頃にはレアグルーヴとかもかなり時間が経っていた。ヒップホップが登場したのって70年代末じゃないですか?もうそこに新しいヒエラルキーや歴史ができてたんですよ。「ファラオ・サンダースは聴かなきゃいけない」とか、「ボブ・ジェイムスは知っとかなきゃ」みたいな。まぁ、どう壊してもある種の権威性は生まれちゃうわけで。ジャズも同じで、ジャズ評論が作ってきたのとは別のクラブやDJ経由のもう一つの権威が確立してたんですね。ヨーロッパのジャズや和ジャズのレコードがものすごく高騰したり。その面白さに惹かれつつも、同時にそこに疑問を持つようになっちゃって、オルタナティブって言ってるけど、一回確立しちゃってヒエラルキーができちゃったら、もはや敵視してきた以前の価値観の側とやってることは同じなんじゃない?って。だから、反抗したり、逆張りしてても、しょうがないなって思って。だったら、DJカルチャーの知識も感覚も持ったうえで丁寧にジャズの《歴史》を聴いて、両方を視野に入れたほうが面白そうだなって思ったんですよ。丁寧に検証するように聴いていった方が刺激があるかなって。
――なるほど。
あと、《躍らせる》って概念で切るのは改めて考えるとすごいことなんですよ。色んな価値観があったのが「今日から足が速いやつが勝ちね」みたいなことで。それはそれですごいハードコアで刺激的なことなんだけど、一方で、踊れるかどうかって縛りが強すぎて、踊りづらいリズムとかだとどんなに素晴らしくても、そこ価値観の中では評価されないわけで。だから、自分はそこから漏れるものも丁寧に聴いてこうと思ったんですよ。そこで、カート・ローゼンウィンケルとかジョシュア・レッドマンとかマーク・ターナーとかのクラブ好きにもジャズ喫茶的な人からも評価されないけど、アメリカのジャズの歴史的には確実に繋がっていて、確実に新しいことをしていた人たちの音楽を聴いてみたら、ジミー・ジュフリーやポール・ブレイやレニー・トリスターノに辿り着いたりして刺激的だったんです。その辺は『100年のジャズを聴く』って本でいろいろ語ってます。まぁ、そこには僕が教育大学出身で、そこで歴史学専攻だったというのも関係しているとは思うんだけど。
――そもそもなんで教育の大学入ったんですか?
元々は先生になろうと思ってたから。大学で歴史学を学んでわかったのは、「歴史はどんどん書き換えられる」ということですよね。鎌倉幕府成立の年が「いい国(1192)」じゃなくて「いい箱(1185)」になったり、聖徳太子が実はいませんでしたって話になるわけじゃないですか。それは研究の現場では当たり前に起こってることで、今、表面的に出ていて、定説になっているものがその後の研究によって180度ひっくりかえるなんて普通にあること。だから、「ウィントン・マルサリスなんかクソだろ」「スティーブ・コールマンって一瞬だけ流行ったよね」と日本のジャズ評論家やジャズリスナーが思ってても、誰かの検証次第で明日からそうじゃなくなる可能性はいくらでもある。ただ、歴史として記されたものはそれはそれで残るし、その時どう評価されてたかってのが残るのも歴史の面白さだと思ってて、その評価のされ方の変遷が残っていくのも大事だと思うんですよ。だから、どんどん書き換えたいし、どんどん書き換えられたいし、それが記録されたらいいですよね。
あと、コンテクストや歴史を重視するのはレコード屋を長年やってた影響もありますよ。古いものや評価されてないものの中から、今の視点で聴けるものを探して、お客さんに提案するっていうことをひたすら続ける仕事だったから。今まで安かったレコードが、再評価で値段が跳ね上がるとか、日常茶飯事だったから。歴史が書き換えられると評価や人気が変わって値段も変わるみたいな。だから、レコード屋って批評的な仕事でもあるんですよ。そこはレアグルーヴやクラブジャズから学んだこととも言えますね。
そうやって「今を書くこと」と「歴史を書くこと」をどう共存させるかはずっとテーマとしてあります。
インタビューは批評
――ひとつ前の歴史を否定して、そのさらに前を肯定するアティチュードって、特にロックとかだと強くあるじゃないですか?親父は嫌いだけどおじいちゃんは好きみたいな。『5』にはそれがないんですよね。普通に父親からの教えを素直に守ってて受け継いでる話が多い。その違いについてどのように考えますか?
そうですね。でも、普通に考えて、楽器の奏法や理論って、連綿と更新され続けてるんで、みんな自分の父や兄の新しさを知ってるし、リスペクトしてるのは当然なんですよ。エスペランサ・スポルディングが20歳でバークリーの講師やってた話(※エスペランサがバークリーの講師の最年少記録で、その前の最年少はパット・メセニー)もあるくらいなので、教育の現場も現役感が重視されてて、講師も若いし。だから、ジャズの世界では当たり前のことをそのまま反映してるだけとも言えますね。
あと、僕は歴史の積み重ねを見せたいんですよ。例えば、変拍子だったりしたら「そんなのザッパがやってる」とか、変なシンセが入ってたら「サン・ラがもうやってる」とかすぐ言われるわけですよ。でも、色んな人がやってきたものが積み重なって、ある時にそれが商品として高い価値を持って、売れて社会的価値を持ったときになにかが変わるってことがあるし、共有可能な形にまで洗練されたときにどっと広がることもある。多分(グラスパーの)『ブラック・レディオ』はそういう大きな契機になった作品ですけど、その前にシーンの中でいろんな積み重ねがあって、その蓄積を経ての成功なんですよ。なので、大きな転換点だけじゃなくて、そのいろんな人がやってきた積み重ねが見えると豊かになると僕は思うんです。JTNCは現代のジャズの本なので、今から遡る形で、今と近い時代の積み重ねを丁寧に聞き出したいと思ってやってます。今のミュージシャンは前の世代の人からの影響をすごく話したがるんですよ。しかも、すごくマイナーな人とか「誰だよそれ?」って名前がばんばん出てくる。
――『5』に載ってる、クリス・デイヴが出身地ヒューストンの盲目のドラマー(セバスチャン・ウィテカー)から影響受けた話はすごくいいですよね。
僕もそんな人は全然知らなかったわけですよ。トニー・ウィリアムズとかジャック・ディジョネットとかの影響は音源を聴けばわかるけど、そういう人のことは話を聞かなきゃわからない。しかも、そういう直接教わってた先生の影響はかなり血肉化してるから、かなり重要なわけで。そういうのがわかるとワクワクするよね。
ーー柳樂さんはインタビューにはかなりこだわりを持ってますよね。
ですね。僕はインタビューはインタビュー記事だとは思ってなくて、「批評」として考えているんですよ。この人はどういう人で、どういう風に音楽を考えてて、っていうのをかなり深く批評的に捉えてないとできないとインタビューは面白くならないと思うし、そういう記事を作りたいと思ってます。逆にそれさえわかってたら他の細かい情報はいらないとさえ思うし、その音楽家の核がつかめれば、細かい話は勝手に付随してくることも多いので。だから、インタビューをインタビューだとは思わないようにしてて、書き記事みたいな読み口のものにしようとも思ってるんですよ。『5』のカマシ・ワシントンのインタビューが他と違うのはそういうところだと思うんですよ。核をつかんでないと「あなたの音楽にはジャズもヒップホップも両方入ってますよね?」「俺もそう思ってる」みたいな「あぁ、よくある問答…」って感じになりかねないけど、そうなってないので。
――そうですよね。
例えば『JTNC5』の挾間美帆のクラシック音楽に関するインタビューを読んだ人が思うことは二つあると思うんですよ。ひとつは「ジャズとクラシックはこんな関係あるんだ」ってことで、もうひとつは「挾間美帆ってこんなクラシックを語れるんだ」ってことかなと。あそこですごく明晰にジャズとクラシックの関係を語ってる挾間さんの語り口って驚異的なことだと思うんですよ。でも、それは彼女の音楽を聴いてればわかることでもある。そういう彼女の中にあるまだ見えていない核の部分をうまく表に出すために、「挾間美帆にクラシックについて聞く」ってテーマを決めてるんです。あれは表向きはクラシックとジャズの関係を説明するためですけど、裏のテーマは挾間美帆がどんな音楽家なのかを炙り出すため。まぁ、あの時期、挾間美帆はセロニアス・モンクのカヴァーのアルバム出してたからほんとはそのアルバムの話しないと怒られるんだけどね(笑)

――でも、新譜の話をしなくても、そのインタビューが面白ければ読む人の興味が湧いて宣伝にもなりますよね。
そうなんですよ。それに挾間美帆が語ってたラヴェルやストラヴィンスキーの特徴を知ってから彼女の作品を聴く方が絶対おもしろいはずだし。『Miles Reimagined』あたりから、どういう質問したらどれだけその取材対象のことが見えてくるかを考えているんですよ。例えば、類家心平や黒田卓也にマイルス・デイビスの話してもらうと、自然と同じトランぺッターとしての自分との差異について語ってくれるわけで。それってある意味ではマイルスを通して自分を語っているとも言えるんですよね。そうやってマイルスって一つのフィルターを挟むことで類家さんや黒田さんの本質も見えてくる。そこで話のスケールが一つ大きくなるし、深くもなるんですよね。そういう考え方で企画をたててます。
――自分のことは自分でわかってなかったりしますしね。
そうそう。多くのアーティストは自覚的ですけど、意外と自覚なしでやってるアーティストもいるので、ただその人のことや作品の話を聞いても仕方ないこともあるんですよ。自覚のない人のコアにどうやって迫るか、もしくは無自覚の中にある核の部分をどう引き出すかこそが大事って言うか。なので、インタビューってただ話を聞いてるってよりは、その前にその取材対象を批評的に捉えて、それをもとに対話をしていくってプロセスが大事だと思ってますね。
原稿では割と削ってますけど、僕は取材中に自分の意見をよくぶつけるんですよ。「ここってこういうサウンドに聴こえます。」「これってこういう音になっているのはこういう意図があったりしますか?」って。それに対し賛成でも反対でもリアクションがある。そうやって意見を言うからたくさん「違う」って言われることもあるわけですが(笑) でも「違う」から広がるものが大事なんですよ、「じゃ、それってどういうことですか?」ってそこから始まることもあるから。僕が作品をどう聴いてるのかがわからないとア―ティスとも話しようがないこともあるので。
だからインビューは面白いんですよ。自分が知らないことがその場でどんどん出てくるし、自分の見立てよりもはるかに面白い作品だってことがどんどんわかっていったりするので。でも、そのためにはその人を自分なりに一度捉えておくってことが大事だと思う。だから、インタビューってレビューや論考を書くのと同じことの先にあるものだと思うし、つまりそれって批評だと思うんですよね。■
ーーーーーーーーーーーーーーー
◆Writer Profile
伏見 瞬
1985年東京都八王子市生まれ。ゲンロン批評再生塾第3期生(東浩紀審査員賞)。主に音楽や演劇の批評書いてますが、たまに曲作って歌ったりもします。 ☞ Twitter @shunnnn002
※1 2018/10/21に名古屋でJTNC5の読書会やります
※2 dublabでJTNC5について原雅明さんと2人で喋ったときの録音がこちらで聴けます。
※この後、テキストは何も書いてませんが、このテキストに100円の価値があると思ったら、投げ銭をお願いします。JTNCの制作費にします。
ここから先は
¥ 100
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
