
interview SYLVIO FRAGA:現代アフロブラジレイロ・ジャズの気鋭レーベルを率いる奇才が語るホシナンチとレチエレス
これまで歴史は欧米の白人中心の視点や価値観で書かれてきた。それをアフリカ系やアジア系も含めたあらゆる人々の視点も考慮した上で、再び編み直そうという試みが世界中で増えていることは多くの人が感じていることだろう。それは音楽においてもかなり顕著で、過小評価されてきたり、失われていたヘリテージ(文化遺産)の価値を引き上げ、ふさわしい評価を与えようとする流れは年を追うごとに強まっている。アメリカの状況を追っていると、アフリカ系アメリカ人によるヘリテージの価値を見直す動きは日々行われている。
それはブラジルにおいても例外ではない。近年、アフリカ系ブラジル人=アフロブラジレイロたちの音楽が脚光を浴びているのにはそんな流れがある。その中心にいたのが管楽器奏者で作編曲家のレチエレス・レイチだった。ブラジルの中でも特にアフリカ系人口が多く、アフリカ由来の民間信仰カンドンブレの文化が根付いている北東部バイーアの文化の重要性を自身の音楽により訴え続けてきた。その音楽はカエターノ・ヴェローゾやマリア・ベターニアをはじめ、多くのアーティストを魅了してきた。惜しくもレチエレスは2021年、新型コロナウィルスの合併症により亡くなってしまったが、没後もその功績を讃える声がどんどん大きくなっている。
そのレチエレスは晩年、リオを拠点にするホシナンチ(Rocinante)というレーベルでの活動が増えていた。ホシナンチはリオデジャネイロ出身の詩人でシンガー・ソングライターのシルヴィオ・フラーガが運営しているレーベルだ。ホシナンチはレチエレスを迎え入れただけでなく、アフロブラジレイロの音楽に対して理解と尊敬を持って、レチエレス門下の重要人物の作品をリリースしたり、レチエレス人脈とのコラボを進めたことで、アフロブラジレイロのミュージシャンたちが自身の文化や背景を尊重された環境で、新たなチャレンジをするようになってきた。ホシナンチの登場はブラジル音楽にとって大きな出来事だったと僕は考えている。
本作『Canção da Cabra』(2019) はホシナンチにおける重要作だ。なぜなら、レチエレス・レイチがシルヴィオ・フラーガと初めてコラボレーションを行った作品であり、レチエレスが最初にホシナンチの録音に参加した作品でもあるからだ。全てはこの『Canção da Cabra』から始まったのだ。
シルヴィオは本作で手応えを感じ、それはホシナンチのベクトルをも変えることになり、レチエレス門下のアフロブラジレイロのミュージシャンたちを一気にレーベルに加えていくことになる。自身の次作『Robalo Nenhum』(2022)ではレチエレスの右腕ピアニストのマルセロ・ガルテル、アタバキ奏者のルイジーニョ・ド・ジェージ、ヘイナルド・ボアヴェントゥーラを起用し、リズム面からも本格的にカンドンブレ由来の音楽に向き合っているし、レチエレスの遺作であり重要作のオルケストラ・フンピレズ『Moacir de todos os santos』(2022)もホシナンチからリリースしている。
だからこそ、現在ブラジルのみならず世界的にも最も刺激的なレーベルのホシナンチが、その方向性を定めたきっかけでもある『Canção da cabra』は、重要作として記録されるべき傑作なのだ。
◉ホシナンチ・レーベルについて
――まずあなたのレーベル、ホシナンチについて教えてください。どんな経緯で始まったのでしょうか?
着想を得るきっかけは6年ぐらい前にさかのぼります。一番の目的は友人たちのアルバムを作りたいということです。才能があるにもかかわらず、金銭的な問題などでレコード制作には至らなかった多彩なアーティストが私の周りにいたからです。どうしても彼らを助けたいというのが、レーベル設立のきっかけです。ただ、いきなりレーベルを設立したわけではなく、まずはチアゴ・アムーヂ(Thiago Amud)のアルバムを私がサポートするという形から話が始まりました。
チアゴの『O Cinema que o sol não apaga』(2018)というアルバムを作るにあたって、エンジニアのペペ・モンネラト(Pepe Monnerat)と協力してどんどん話を進めていくなかで、ヴァイナルを作ったらいいのではないかという話が出てきました。そしてヴァイナルを作るんだったら、何かしらの哲学やビジネスモデルみたいなものがあったら、もっといい形でレーベルを運営できるんじゃないかなと思うようになりました。そこで浮かんだのが、アーティストがやりたいことをするレーベルということです。そのレコードをリリースすることで利益が出るとか、有名になるとか、世界的な名誉につながるとかそういったことを考えず、アーティストがやりたいことを第一に優先するというコンセプトからこのレーベルが生まれました。
徐々にレーベルが軌道に乗ってきて、今ではある種、成功しているとも言える規模になってきました。このビジネスモデルが成功に近づいているのを感じています。
――あなたはリオ出身で、ホシナンチのスタジオもリオにあります。もともとブラジルのどんなシーンと交流があり、どんなミュージシャンたちと活動をしていたのでしょうか?
ホシナンチを開設する以前、私の人脈はそんなに広いわけではありませんでした。ホシナンチを始めてレチエレス・レイチが自分の人脈の幅を広げてくれたのが大きかったです。例えばルイジーニョ・ド・ジェジ(Luizinho do Jêje)というパーカッショニスト。彼はレチエレス・レイチのキンテートをはじめ、様々なホシナンチのプロジェクトで演奏しています。レーベルの中におけるコレクティブ性、みんなで協力する姿勢やどこかで繋がりがあることがレーベルの特徴だと思っています。

◉レチエレス・レイチとの出会い
――レチエレスとはどういう経緯で知り合ったのでしょうか?
きっかけは『Canção da Cabra』です。ニューアルバムの準備を進めていく中でどうしても管楽器と弦楽器を入れたい思いがあって、アレンジャーを探していました。そこでレチエレス・レイチの作品に出会ったのです。レチエレスがオルケストラ・フンピレズを率いてリリースした『A Saga da Travessia』(2016)を聴いて、今までブラジルのアレンジャーにはなかったリズム感にとても感銘を受けました。レチエレスのアレンジは、ブラジルの打楽器が持つ独特のリズム感を管楽器や弦楽器が表現する、そういうある種“パーカッションから管楽器や弦楽器に翻訳”するような作業がすごく巧みで、それが私のバンドの音楽性に一番合っているのではないかと感じたのです。
そこでダメもとでメールを送ったら、まずは音源を送って欲しいと言われました。送ったところ返事が来て、実際にライブでも見てみないとわからないから、リハでもライブでもいいけどリオに行った際に演奏を見て決めたいと返事をもらったんです。その後、レチエレスがリオにきた際にリハを見てもらったところ、すごく気に入ってくれて“絶対に私がアレンジを書く”と言ってくれました。それ以来、リオにレチエレスがどんどん遊びに来るようになって、私のキンテートのリハにも参加してくれるようになり、一緒に全体的なディレクションし、時にはアドバイスをくれるようになり、結果として『Canção da Cabra』を連名でリリースすることになりました。
◉『Canção da Cabra』について
――『Canção da Cabra』のコンセプトを聞かせてください。
実はコンセプトがあってアルバムにしようとなったわけではなくて、一曲一曲を作っていったら結果的にアルバムになったという流れです。そのそれぞれ分かれているように見える曲たちをつなぐひとつのキーワードになるのが、ブラジル北東部=ノルデスチの文化である文学や詩からの影響です。
具体的な作家の例を挙げると、ジョアン・カブラル・ヂ・メロ・ネト(João Cabral de Melo Neto)というブラジルの偉大な詩人がいます。彼の『Poema(s) da Cabra』という詩があって、「ヤギの詩(たち)」という意味なんですけども、そこから着想を得て自分のアルバムに「Canção da cabra」、つまり「ヤギの歌」というタイトルを付けました。
もう一人の作家を挙げるとエウクリーデス・ダ・クーニャ(Euclides da Cunha)。彼は『Os Sertões』という著作で、ブラジルという国が生まれるまでの過程を本にした作家です。ブラジルという国がどのようにして帝国から共和国になっていくのか、そのブラジル誕生の背景をノルデスチ文化の影響と混ぜて彼は書いています。その影響もすごく大きいですね。
――ブラジルの国の成り立ちを書いた作家という話が出ましたけど、それはインディオやアフロブラジレイロの話がかなり出てくるような小説なんでしょうか?
いろいろな人種的な影響もあったのですが、どちらかというと全て入り交じっていく、そういうミックスの影響がブラジルの誕生には大きいと思います。ざっと歴史を話すと、ブラジルは1500年にポルトガルから発見される形で1500年に一応誕生したことになっています。その後、1800年に独立して、ある種の帝国的な形を取り始め、その後1899年には共和国になります。『Canção da Cabra』に影響を与えた『Os Sertões』という本のタイトルは複数形で「東北地方(たち)」という意味なのですが、これは1800年の独立から1899年の共和国になるまでの経緯を綴ったと読めるものです。
『Os Sertões』の内容について簡単に話すと、アントニオ・コンセリェイロ(Antônio Conselheiro)という当時のノルデスチにおける貧困層から絶大的な支持を得ていた宗教指導者がいたのですが、彼は「カヌードス共同体」というものを形成し、また様々な理由で共和制に反対して抵抗していました。共和国側は彼のまとめるグループを撲滅しようとしていたのですが、コンセリェイロの持つ勢力や人脈はとても強固で、国の力をもってしてもなかなか倒せませんでした。面子をつぶされた共和国側が4回目の討伐で大軍を派遣し、カヌードス軍は壊滅し、共和国の完成に至ったというのがこの本の話です。この本に出てくるノルデスチの持つ雰囲気とか佇まいが、今回の作品における大きな影響になっていますね。
また私は文学者/小説家としての一面も持っていて、本を出版しています。音楽を作るうえで重要にしていることに文学的な手法やどうやって言葉が使われているか、どういう風にイメージを連想できるのかみたいな言葉遊び的な要素があります。なので、私にとって文学と音楽は分離不可能だと思います。
カヌードスの戦い https://latin-america.jp/archives/30316
――アントニオ・コンセリェイロがインスピレーションになっているのは5曲目「Romaria de Jagunço」ですよね?
そうですね。まさに5曲目は本のイメージをそのまま曲にしたような歌詞になっています。ホマリーア(Romaria)は (聖地)巡礼という意味です。ジャグンソ(Jagunço)というのはブラジルの政治家や大地主に雇われていた当時の用心棒なのですが、どちらかというと貧しい階級にいた人たちのことです。当時、彼らが行った反抗的な意味を持つ巡礼が、経済や食料危機が再び訪れている今のノルデスチ、さらには現代のブラジルが直面している問題とすごく繋がる部分があると感じたので、本の内容をイメージするままに詞にしたんです。洞窟に入ったらキリスト像が見えてその前で拳銃を置いたり、歌詞の中に散りばめている全てのワードは本からの直接的なイメージから来ています。
◉シルヴィオが影響を受けた作曲家・作詞家
――あなたの曲には独特の雰囲気や構造があると思います。あなたは作曲家であり、ギタリストであり、シンガーですが、それと同時に詩人でもあります。あなたの作曲と作詞の関係について聞かせてください。
私は詩人としての自分と作曲家としての自分は完璧に全く別のものとして扱っています。音楽の詩ではなく純粋に詩を書く時は言葉は静かなものだと捉えていて、本当に純粋な言葉にだけフォーカスします。反対に音楽の詩を書くときは音楽的な詩について考えて書くので、どちらかというと静かなものとは一緒になりません。詩が影響して曲が生まれて、曲が生まれて詩が生まれてくるような、そういった相互関係みたいなものは結果的には出てきますが、自分の中ではふたつに分けるようにしています。
音楽に対しての詩(歌詞)を書く人は、必ずしも純粋な詩人だとは思いません。例えばチアゴ・アムーヂはどちらかと言うと純粋に詩を書くタイプではなくて、音楽に対しての歌詞を書くタイプの詩人です。とはいえチアゴは詩の愛好家でブラジルの詩や文学に造詣が深いので、そういう面で共感する部分が多いです。ブラジルの歌詞を書く人は必ずしもブラジルの純粋な詩人ではないことも多いです。とはいえ私の好きなアーティスト、例えばシコ・ブアルキとかアルヂール・ブランキ、ドリヴァル・カイミ、トム・ジョビンなどは、やはりブラジルの詩がもともとすごく好きな人だったので、そういう部分は共感ができるのですが、歌詞を書く人と詩を書く人は別のものだと思います。
――その中で自分が 影響を受けた、曲と詩のコンビネーションを作れる作詞家・作曲家は誰ですか?
やはりチアゴ・アムーヂには間違いなく大きな影響を受けていますね。彼は詩人としても作曲家としても本当に優れていて、すごくいい影響をもらっています。もう一人挙げるとしたらヴィニシウス・ヂ・モライスでしょうか。彼は偉大な詩人でかつ曲も作っていて、すごく影響を受けているのではないかと思います。
◉『Canção da Cabra』でのレチエレスとの共同作業
――あなたはこのアルバムのために曲や詩を書く際にレチエレスがアレンジすることを想定していましたか?それとも普段通りに書いたものにレチエレスがアレンジを加えたのでしょうか?
レチエレスの存在を知る前に曲は全て作っていました。曲の形はすでにできていて、ここからは先ほどの話と少しと被るのですが、完璧な管楽器と弦楽器のアレンジを探していたときにレチエレスのオルケストラ・フンピレスを知って、非常に感銘を受け、彼をに依頼するに至りました。私はリオに住んでいて、レチエレスはバイーアに住んでいましたが、我々を繋いだのはリズムのレイヤーの作り方が非常に似ていた部分でした。私は以前からリズムへの関心が強く、自分のバンドではポリリズムを使っていました。だから、オルケストラ・フンピレスを聴いた時、彼らがやっていることは私がやりたかったことそのものだと感じたんです。レチエレスと会った時も音楽を通じてすぐに打ち解けて、お互い同じことをやろうとしてることがすぐにわかり、友情が一気に加速していきました。彼と出会ったことで彼から学ぶことが多かったですし、レチエレスの周りの人を通じて学ぶことも多かった。そうやって友情の輪が加速度的に大きくなっていきました。

――学んだ事って例えばどういうことですか?
レチエレスと一緒に生活してく中で学んだことについて全てを通じて言えるのは、ブラジル音楽が持っているリズム感やリズムの起源はアフリカ発祥であるということ、そして、それはとてもよく考えられたカチッとした形で、全て体系的に決まっていることです。それはブラジル音楽にとって絶大な影響を及ぼしています。レチエレスはブラジル音楽のリズムの起源であるアフリカのあらゆるリズムを研究していました。ブラジルでは“サンバは2/4拍子なのか4/4拍子なのか”という議論がよく行われます。でも、レチエレスはリズムを楽譜に書いてそれが何拍子かという発想そのものが西洋的な考えに過ぎないと考えていました。もともとアフリカの人たちは楽譜で考えていたわけではなかったし、そもそも西洋的な考えで音楽を捉えているわけではありません。つまりサンバは2/4でも4/4でもどちらでもいいということです。レチエレスはリズムをある種のサイクルとして捉えていました。延々とぐるぐる回っているものであるとの思想を持っていて、そちらを重視していたのです。
つまり、ブラジル音楽が西洋的な考え方からの強い影響を受けていることに対し、それが全てではないことをいつも示そうとしていました。そして、そういった音楽の捉え方が反レイシズムにも通じると考えていました。レチエレスが反レイシズムを信条としていて、差別的なものには絶対的に反対していたことも重要なポイントです。
――それってレチエレスの音楽に含まれている反差別、反植民地的な側面のことですよね。近年レチエレスとコラボする若いアーティストが増えていましたが、彼が求められていたのは彼の活動が持ってる社会的な意味も関係があるんじゃないかと思ったんですが、いかがですか?
確実にその思想的な部分も関係はしているでしょう。彼の作る音楽とブラジルの歴史は切っても切り離せない関係です。つまりブラジルの歴史とレチエレスの持っている政治的・社会的思想は切っても切り離せない関係だったと思います。基本的に彼の周りにいる人はレチエレスの存在とその思想的な部分も含めて、その存在全てに対して尊敬の念や愛情をもっていたからこそ一緒にいた人が多いのではないでしょうか。
――なるほど。
私にとってレチエレスは本当に数少ないマスターと言うか師匠と呼べる存在なんです。彼は人柄もとても謙虚な人だったんですよね。例えば彼のグループでメンバーのひとりが弾けないフレーズがあったり、行き詰っている箇所があった時に、普通のバンドリーダーならそのメンバーを変えることもあると思います。でも、レチエレスは絶対にそうしないんです。まずその人のことをハグして、どうしてできないのかとちゃんと教えて、一緒にどうやったら上手くなるようになるのかを考えて、常にヘルプして本当にその人に寄り添って助けていくという姿勢は絶対を貫く人でした。音楽的な面でも人間的な面でもとても謙虚な人で、私は心の底から尊敬しています。
――レチエレスは人格者であったと。
もうひとつ思い出したのですが、あるときスタジオに行ったらマルセロ・ガルテル(Marcelo Galter)がピアノを弾いていました。ピアノは下のスタジオにあったので、私とレチエレスは上の階でモニターしながらそれを聞いていました。その時にレチエレスが「ちょっと聴いてみて、マルセロが今ピアノでやっていることは凄い事なんだよ。ハーモニーを崩してこのリズムをこうして…。彼はリズム的にすごいことをやっているんだ」と本当にワクワクしながら語っていたんです。その後、レチエレスはマルセロを質問攻めにしていました。マルセロの独特のリズム感について、そして、マルセロがどんな風に音楽を理解し、それはどうやって身に着けてきたのか、について尋ねていたのを覚えています。彼は常に探求や研究し続けていた人だったんですよ。
――アルバムの制作にあたって、あなたはレチエレスとどんなやり取りをしていたのでしょうか?
彼はリオに来てバンドにアドバイスをしてくれたり、リハにも来てくれたり、録音にも来て全て一緒にやってくれました。例えばリハで演奏したバンドの録音を二人で一緒に家のモニタースピーカーで聞きながら、チェロとオーボエを細かく入れるために二人でやり取りをしました。「じゃ、Aの部分は無しにして、ここでBから楽器を入れていこう」みたいな感じで。ストラヴィンスキーの影響がある曲に関しては「ストラヴィンスキーがどういう風に楽器使っているのか音色を研究してから、我々の弦の使い方を考えよう」って彼は提案してくれました。実際に楽譜に起こす作業はレチエレスが一人で行っていたんですけど、そうやってふたりで一緒に考えて、ともに作り上げた作品という感覚ですね。
――なるほど、だから2人の名義になっていると。
また、レチエレスは即興に関しての意識がすごく強い人でしたね。それは音楽的な即興だけでなく、その瞬間瞬間を生きるという人物性と言ったらいいでしょうか。例えば3曲目「O lagarto e o gato lagardo」をリハでやった時に二人ともアイデアが次々に沸き出てきて、レチエレスが「もうこの曲は固まった」と言って、すぐホテルに帰ってその日にはアレンジを書いていました。レチエレスはアイデアが出来たらその場でばーっと書くんです。本当にその時その時に身を任せて生きていくというか、アイデアが浮かんだら飛行機の中でアレンジをすると聞いたことがあるくらい、瞬間瞬間を大事にする、ある種即興的な人物でした。
◉ホシナンチとストラヴィンスキー
――さっきストラヴィンスキーの名前が出ました。ジョゼ・アリマテア(José Arimatéa)の「Três peças para clarineta solo」、エリカ・ヒベイロ(Erika Ribeiro)のアルバムなど、ホシナンチではストラヴィンスキーの曲を取り上げたり、参照している作品がいくつかあります。あなたはホシナンチの音楽とストラヴィンスキーの音楽になにか関連性や共通点を感じているのでしょうか?
ストラヴィンスキーについていえば、単純に私がすごく大好きな作曲家という事が一つ挙げられます。偶然なのですが、レチエレスもストラヴィンスキーのことが大好きで、マルセロも大好きだそうです。レチエレスと一緒にソファに座って「火の鳥」を聞いて、これいいよねなんて話をした思い出もありますね。ストラヴィンスキーになぜ惹かれるかというと、無調つまり長調か短調か決めないでキーが確定してない中でも、印象的なメロディーと言うか絶対に注意を引くようなメロディーラインだったりボイシングのラインだったり、何かしら完全に無調じゃない部分も感じられる点です。そのリミットや境界線の部分をうまくはしごして渡っていく手法が、すごく上手いですよね。ストラヴィンスキーだけでなくてもちろんドビュッシーやショパンも大好きなのですが、ここしばらくはずっとストラヴィンスキーが好きなので、その影響が出ていますが、これから新しい好きな作曲家が出てきたら、またその影響が作品に反映されるような日も来るんじゃないかと思います。
エリカ・ヒベイロやジョゼ・アリマテアのアルバムについて話すと、その中でストラヴィンスキーを取り上げたのは、レーベルのオーナーという姿勢を取るだけでなく、やはり監修的な姿勢、ある種のプロデューサーとしての視点も常に持つようにしていて、自分の中でこれが合うなと思ったらいろいろ提案をしています。
◉ジョゼ・アリマテア『Brejo das Almas』について
カルロス・ドゥルモンド・ヂ・アンドラーヂ(Carlos Drummond de Andrade)というブラジルの有名な作家の書いた、ミナスジェライス州のある街の名前を冠した『Brejo das Almas』という本があるのですが、ジョゼ・アリマテアのアルバムではそこからアルバムのタイトルを提案しました。音楽的な面だけでなくコンセプト面などでも一緒に作り上げていく姿勢は常に持つようにしていますね。ドゥルモンドはモダン派のブラジルの詩人です。私が最も惹かれたのが『Brejo das Almas』でした。これは「魂たちの湿地」みたいな意味になりますが、その「湿地」という言葉の持つニュアンスがアリマテアの持っている音楽性とすごく重なる部分があると感じて、この名前を提案しました。湿地は自然が豊かで、さまざまな生物が共存しています。小さい視点で言えばバクテリアも多くて、命が豊かでイキイキとした様を思わせる響きが彼の音楽性にすごく合っているのではないかと思ったんです。
――なるほど。
アリマテアに関して言うと、彼はサンバ・ジャズのジャンルで広く知られているトランペッターです。でも、私としてはもっと自由な部分を引き出せると思っていました。レチエレス・レイチのグループに彼を呼ぶことでサンバ・ジャズというジャンルに囚われずにアリマテアの良い部分を引き出すことができたのではないかと思っています。ちなみにレチエレス・レイチも実はアリマテアの大ファンで、リオに行く度にアリマテアの演奏を見に行っていたんですよ。
『Brejo das Almas』に関して言うと、アリマテアがアリマテアでいるためのアルバムというか、本当に色んな奇跡が重なって生まれた幻のアルバムとも言ってもいいんじゃないかというくらい、とても良いアルバムだと感じています。マルセロとアリマテアが一緒に作り上げていく様子、ふたりで同じ空間の中で切磋琢磨する雰囲気は特別なものでした。アリマテア達の関係性はカルロス・ドゥルモンドにも重なる部分があります。二人とも大人しくてちょっとシャイですけど、人として生きる喜びみたいなものを常に感じている人たちなんです。私が『Brejo das Almas』というタイトルを提案したのはそういう人間的な部分とドゥルモンドの作品のイメージが一致したからですね。
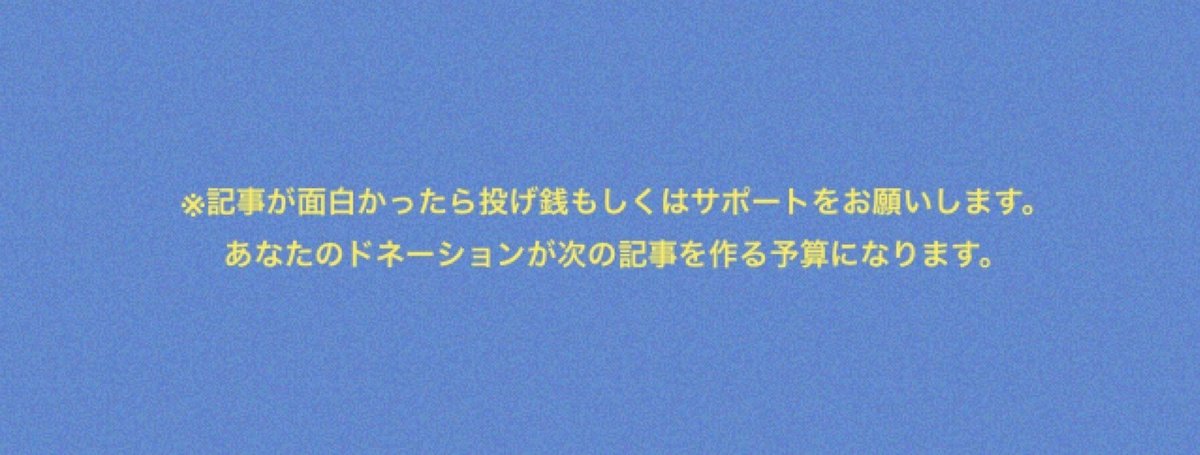
ここから先は
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
