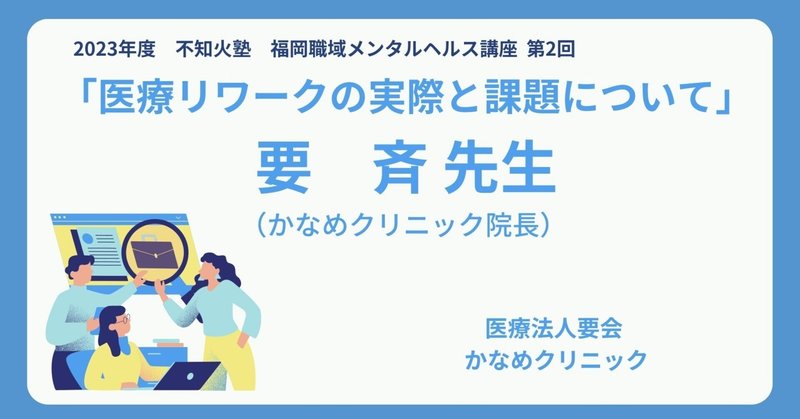
リワークとは-リワークがもたらす変容とクリニックの舞台裏-
不知火塾 第2回目は かなめクリニック 要 斉 院長による「医療リワークの実際と課題について」を事例を交えながら、お話をいただきました。
不知火塾についての詳細はこちら
次回の講座は不知火病院理事長 徳永雄一郎先生による
「再発防止を目的としたうつ病治療」です。
次回案内はこちら
かなめクリニック様は2009年よりSAD(社交不安障害)プログラムを、2011年よりリワークプログラムを開始されております。
メンタルヘルス不調による休職者の再発率(再休職率)は50%以上になり、リワークの必要性がますます高まっている昨今。
リワークの基本を知りたい、リワークの理解を深めたい、クリニックの具体例を知りたい方はぜひ、ご覧ください。
リワークの概要
復職が難しいのは、主治医が復職可能と判断する、病状が安定した状態と、仕事が出来る状態の間に乖離があるからです。その乖離を埋めるために有効なのは、リワークプログラムです。
充分にリハビリできずに復職すると、症状が再燃し再休職になる方もいらっしゃいます。その結果、慢性化に繋がる可能性も。リワークでは生活リズムの安定をはかり、復職準備性を整え、職場へのソフトランディングを目指します。
要先生のお話によると、第一期~第三期の三つの期に分けてリワークを行うのが、日本うつ病リワーク協会の標準とのこと。かなめクリニック様では導入基準や中断基準を設けていらっしゃいます。
リワークの実際のケース
リワークの具体的なケースとして、Xさんの事例をご紹介いただきました。
Xさんは多重業務やプレッシャーによってパニック状態に陥り、コミュニケーションや信頼の構築に苦労していたそう。
その後、Xさんが実施した取り組みと変容についての具体的なお話がありました。
個人の特性を把握し、個別性に合わせた取り組みをリワークで実施することが、変容に繋がると気付かされた事例でした。
リワークの場の安全を守る
プログラム自体も大事ですが、リワークの環境も大事とのこと。かなめクリニック様では、過去にグループの機能不全が起きており、その要因を踏まえてデイケアの場を安全にするための工夫を取り入れていました。
【機能不全の考察】
かなめクリニック様ではリワークグループが20名以上に拡大し、一体感の希薄化、緊張感の低下、疎外感、安心感の欠如、強制感の増加が現れるように。
オフ会「原則」禁止ルールがあるにも関わらず、水面下で連絡先の交換、男女の交際などが発覚。オフィスワークがゲーム交流の時間になり、スタッフの注意に悪びれる様子もなかったそうです。
主導力のある方が前面に出て、そうでない方の存在や意見は抑圧されグループは、まるで学級崩壊のように。スタッフへの依存も大きくなり、スタッフの疲弊も蓄積したと伺いました。
当時かなめクリニック様では、リワークと精神科デイケアの空間に仕切りがなく自由に往来することが可能な状態でした。
スタッフはローテーションし、スポーツプログラムではデイケアとリワークの利用者が交流をしたり、リワーク利用者がデイケアエリアで休息をとったりすることも。
【リワークプログラムの改革と変化】
かなめクリニック様で実施された改革の一部を、以下にご紹介します。
・エリアごとに壁を設け、トイレや水場を独立させる。
・1グループを利害関係のない約15名で選別。
・3グループに分け、グループ間の関わりを減らす。
・スタッフ2名を各グループに固定。
・オフ会「原則」禁止からオフ会「絶対」禁止へルール変更し、徹底。
本音トークと弱さの情報開示を目指し、各自のペースで取り組もうと改革を進めていかれます。
すると、スタッフからはグループの凝集性が高まった、発言を遠慮していた人が言えるようになった、グループのメンバー間交流が増え、スタッフへの依存が減った、主体性がアップしたなどの意見が挙がったそうです。
そして、自己開示による本音トークはより活性化し、グループ効果のアップに成功されます。
その事例として、Aさんのケースが紹介され、自己開示や意見交換を通じて受け入れや変容が生じたことが述べられました。
グループ効果が機能することで、利用者は自己開示しやすくなります。
機能不全のままだと、きっと意見も出しにくかったはず。グループが正しく機能する意義を感じました。
かなめクリニック様のリワーク効果研究結果

効果研究では、データをもとに具体的な課題を提示いただきました。考察のみご紹介します。
【考察】
北九州にあるため、利用者は学歴が高卒以下の工場労働者が主で、首都圏と属性は異なるが、就労継続は類似の結果となっていた。
リワーク主治医と他院主治医の違いによる就労継続への影響は示されず。他院主治医でも同等に機能していた。
20代は特に社会的経験が未熟なために就労継続に不利であり、他の世代と違う特別な課題がある。
治療上取り扱う必要のある発達障害要素、双極性障害要素は就労継続に不利であり、早期のアセスメントと特化したサポートが必要。
属性や主治医による違いは認められず、就労継続のためには、利用者の年代や治療上の要素を考慮し、個別化されたサポートが重要だと理解しました。
要 斉先生のお話は、看護師にとってもですが、企業関係者から医療専門家といった幅広い参加者層にとって、課題解決に至るまでのプロセスが非常に明確かつ実践的な内容でした。
貴重なお話をありがとうございました。
特に、利用者の事例紹介が行われたことで、リワークがもたらす変容が具体的にわかり、私にとって大きな収穫となりました。
不知火塾についての詳細はこちら
次回の講座は不知火病院理事長 徳永雄一郎先生による
「再発防止を目的としたうつ病治療」です。
次回案内はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
